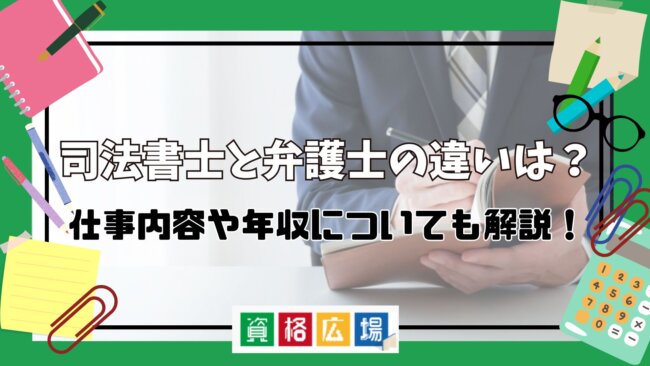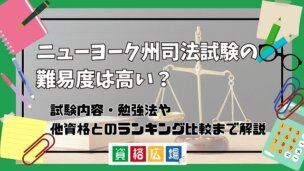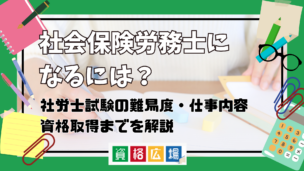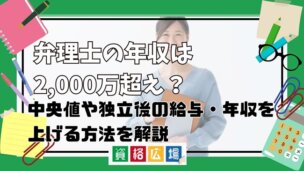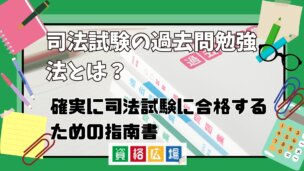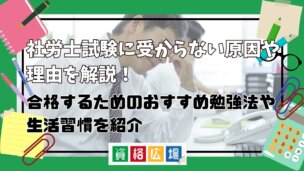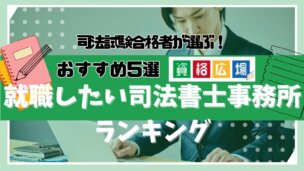皆さんは、司法書士という職業が法律家のひとつであることをご存知でしたか?
司法書士と言えば、各種の登記を請け負っているほか、裁判所に提出しなければならない訴状や答弁書など書類の作成や、相続に関する業務も行なっているのです。
その司法書士と弁護士では、一体どのような違いがあるのでしょうか?仕事内容や年収についても解説してまいります!
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
司法書士とは?
司法書士という職業が法律家のひとつだと、皆さんはご存知でしたか?
皆さんが法律家のイメージとして、最も強く思い起こされる職業は弁護士だと思われます。他にも検察官や裁判官、社会保険労務士、弁理士、行政書士なども法律家です。
実際に司法書士は、私たちが生活する上でもお世話になることがあります。
司法書士の仕事の内容について見ていきましょう。
司法書士の仕事内容とは?
司法書士は、私たちにとってとても身近な法律の問題に携わっています。
司法書士の仕事として、『登記』に関することがとくにポピュラーなものとして挙げられます。
登記とは土地や建物を所有している人の氏名や権利のことや、会社の名称や個人が持っている資格のことまでありとあらゆる情報を、国が保証することにしたもののことを言います。
他にも土地の売買を行なったり、子供や孫などに金品等を贈与した時や親が亡くなったあとに不動産を相続した場合の所有権の移転登記も行ないます。
また、個人の住所や氏名が変わったとなれば変更登記を行なうなど、司法書士は登記の内容をしっかりと把握し、間違いがないように書類を作成して登記の申請をするのです。信頼問題に関わる重大な仕事のひとつですね。
成年後見に関する制度も支援する
司法書士は、成年後見に関する制度についても全般にわたって支援しています。
例えば、認知症を発症したり、本人に精神的な障害や知的障害があったとします。
そうした場合、判断能力が十分になく、自分の意志や考えで介護施設や福祉施設、グループホームなどへ入所する際に手続きが困難となる時があります。
加えて貯金の管理なども難しくなってくるので、そのような時のために”成年後見制度”はあります。
当事者に支えが必要となった時、大切な財産を保護し、支援してくれる支援者も選びます。
司法書士本人が後見人となることも、決して珍しいことではありません。
弁護士とは
弁護士は、離婚、相続、労働問題、金銭に関するトラブルなど、日常生活における多様な問題に対して交渉を行う専門家です。
法律に関する業務全般を取り扱うことができ、業務に制限はありません。
たとえば個人顧客に対しては、金銭問題や相続、交通事故などのトラブル解決を行います。
さらに法人顧客に対しては、契約書の作成、労務管理、債務整理などを通じて企業の課題を解決します。
弁護士資格を取得するためにはまず法科大学院を修了し、次に司法試験に合格しなければいけません。
司法試験は受験資格に制限があり、合格率は約30%と高めです。
司法試験は公認会計士や不動産鑑定士と並ぶ三大国家資格の一つとされ、国内でも非常に高い難易度を誇ります。
弁護士になるには司法試験の合格が必要!大学受験から弁護士として事務所採用・業務開始するまでの流れ
司法書士と弁護士との違い

ここでは、司法書士と弁護士の違いについて紹介します。
仕事内容
弁護士は主に紛争解決に関連する法律業務を行うのに対し、司法書士は主に登記業務を担当しています。
司法書士には認定司法書士と呼ばれる資格があり、司法書士資格を有する者が特定の研修を受け、その研修の成果を測る試験に合格することで認定を受けるものです。
上記の認定を得ることで業務の範囲が拡大し、簡易裁判所において140万円までの民事事件に関する相談や和解交渉、裁判の代理を行うことができるようになります。
ただし、取り扱う金額が140万円を超える場合には、司法書士はその業務を行うことができず、弁護士に業務を引き継ぐ必要があります。
弁護士であれば、金額といった制限を気にすることがないことから仕事の幅はかなり広いといえます。
働き方
司法書士として働く際には、一般的に司法書士事務所に就職することがほとんどです。
さらに司法書士としての勤務を通じて一定の経験を得た後、多くの人々が独立を目指す傾向にあります。
一方弁護士資格を取得した後も通常は弁護士事務所に就職することが一般的です。
司法書士と同様に、一定の経験を積んだ後に独立して自身の法律事務所を設立する方も多く、ほかにも国や地方自治体、国際機関などで職員として働く人もいます。
試験の違い
弁護士になるには司法試験と呼ばれる国家試験に合格しなければなりません。
司法試験とは法科大学院を修了した者や司法試験予備試験に合格した者を対象に実施さるものです。
法律系資格の最高峰であり、合格後は司法修習と呼ばれる1年間の研修を受け、その後の最終試験(通称二回試験)に合格することで、裁判官、検察官、弁護士としての職務を遂行できるようになります。
司法試験の受験資格は永続的ではなく、法科大学院を修了した後、または予備試験に合格した後、5年が経過すると失効するので注意が必要です。
つまり受験資格を得た後は5年以内に、または5回以内に司法試験に合格する必要があります。
司法試験の受験科目は、短答試験で憲法、民法、刑法の3科目、論文試験では商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法、選択科目を加えた合計8科目となります。
一方、司法書士試験では出題科目が11科目と多く、科目数において司法試験とは異なります。
司法書士試験は筆記試験と口述試験に分かれており、筆記試験に合格すると、口述試験と呼ばれる面接形式の試験を受けることができます。
この筆記試験と口述試験はそれぞれ1日で終了するため、司法試験のように長期間の予定を確保する必要がない点も異なります。
さらに、司法書士試験には特に受験資格の制限が設けられていないことも特徴的です。
試験の難易度
弁護士を目指すための司法試験は、合格率が約45%と高いように見えますが、誰もが受験できるわけではありません。
司法試験では、幅広い法律知識が求められるだけでなく、法科大学院を卒業するか、予備試験に合格することが受験資格として必要だからです。
ちなみに予備試験の合格率は4%とかなり低く、司法試験よりも難しいともいわれています。
一方で司法書士試験の合格率は4~5%と非常に低いですが、試験範囲が弁護士試験に比べてやや狭いため、受験しやすいと考えられます。
ちなみに他の法律関連資格の合格率を見てみると、行政書士試験は8~15%、宅建試験は15~18%程度となっています。
また勉強時間の目安としては、司法試験の合格には約3,000~8,000時間の学習が必要とされる一方、司法書士試験では約1,000時間が合格の基準とされています。
以上の理由から、弁護士になるための司法試験は司法書士試験よりも難易度が高いと考えられます。
しかし、どちらの試験も非常に厳しく、合格するためには相当な努力と準備が求められます。
平均年収
令和5年度の厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、司法書士の平均年収は約1,122万円といわれています。
ただし、この金額は勤務形態や地域によって異なるため、独立開業した場合はこの金額よりも高くなる可能性があり、企業や司法書士事務所に勤務する場合には低くなることも考えられます。
一方、弁護士の平均年収は令和5年度の日本弁護士会連合会の調査によると約2,083万円であり、司法書士の約2倍に相当し、一般的な平均年収の5倍以上という高い数値です。
さらに独立すれば上記よりも多くの収入を得られることもあります。
司法書士と弁護士の年収に差がある理由としては、その主な要因は職務内容と業務範囲の違いが挙げられます。
司法書士は主に登記や供託業務に特化しているのに対し、弁護士は民事事件、刑事事件、企業法務など多岐にわたる法的業務を扱っています。
幅広い法的業務を通じてキャリアを築きたい方は弁護士がおすすめです。
行政書士・司法書士・社労士の違いとは?資格取得の難易度も比較
司法書士から弁護士になる方法
現在司法書士をしている方のなかにも、キャリアアップを目指して弁護士の資格を取得しようと考えている方もいるでしょう。
弁護士になるためには司法試験に合格する必要がありますが、司法試験は誰でも受験できる試験ではありません。
ここでは、司法書士から弁護士になるルートについてご紹介します。
法科大学院ルート
弁護士になるための方法としてまず法科大学院に入学し、学びを深めた後に司法試験を受けて合格することが挙げられます。
法科大学院には既修者コースが2年間、未修者コースが3年間の学習期間が必要ですが、既修者コースを選択するのが一般的です。
なお、大学を卒業していない場合は法科大学院への進学ができないので注意が必要です。
司法書士としての業務を続けながら法科大学院に通うことはかなりハードですが、夜間のプログラムを利用すれば両立することができます。
もしくは仕事を一時的に休止し、学業に専念することもひとつです。
しかし学習に集中できるメリットはありつつも、その間の収入が途絶えることや学費の負担があるため、慎重に判断するようにしましょう。
予備試験ルート
司法書士から弁護士になる方法として予備試験に合格し、その後司法試験を受験して合格することが挙げられます。
予備試験は、大学を卒業していない方でも受験できます。
予備試験では5月に行われる短答式試験、7月の論文式試験、10月の口述式試験のすべてに合格しなければ、司法試験の受験資格を得ることができません。
予備試験の最終合格率は約3~4%と非常に厳しいですが、合格率が一桁の司法書士試験に合格するだけの学力を持つ方であれば、挑戦する価値は十分にあるでしょう。
法科大学院とは異なり、通学の必要がないため、働きながら司法試験を目指す方にとっては、時間的な制約が少ない点が魅力的です。
予備試験対策は独学だとかなり難しく、通信講座や予備校に通うのが一般的です。
司法書士から弁護士を目指すメリット
司法書士から弁護士を目指すメリットには以下のものが挙げられます。
これまでの知識や経験を活かせる
司法書士としての職務においては、これまでに習得した法律知識や実務経験を活かすことができるというメリットがあります。
例えば、民法や商法などの試験科目が重複している場合、法律に関する基礎知識は司法書士の試験や仕事によって既に身についています。
また、行政法や刑事訴訟法など新たに学ぶ必要がある科目についても、初学者に比べて比較的スムーズに学習を進めることができます。
さらに、司法書士としての実務経験は、弁護士としての活動にも必ず役立つでしょう。
書類作成や各種行政機関への対応、依頼者との信頼関係の構築やコミュニケーションの取り方など、司法書士の業務と重なる部分も多くあります。
法律に関連する職業での経験を活かしつつ、より広範な分野に対応したいと考える場合、弁護士になることも一つの選択肢としておすすめです。
仕事の幅が広がる
弁護士は司法書士よりも仕事の幅が広く、さまざまな経験を積みたい方におすすめです。
弁護士は法律関連の資格の中で取り扱える業務の幅広さにおいて最も汎用性の高い資格であり、司法書士では対応できない高額な訴訟や刑事事件を担当できます。
一方、司法書士は認定試験に合格することで簡易裁判所において140万円以下の訴訟に対応することができますが、先にも述べたように140万円を超える訴訟や簡易裁判所以外の裁判には関与できません。
したがって、より本格的な訴訟に関与したいと考える人にとって、弁護士の職務は非常に魅力的なものだといえるでしょう。
キャリアアップ・年収アップにつながる
司法書士としての知識や経験を基盤に、法曹界における広範な知識や見識を習得することでより高い専門性を獲得し、自身のキャリアアップ・年収アップにつながるメリットがあります。
先にも述べたように、弁護士は業務の幅が広いことから司法書士よりも年収が高い傾向にあります。
司法書士としての実績を活かし、弁護士にはない独自の知識を活かせる場面も多いのでチャレンジしてみるのもいいでしょう。
将来的な目標を明確にし、目指すべき具体駅なキャリアビジョンを持つことが大切です。
司法書士の年収が低いのは本当?平均年収と独立開業の場合を徹底調査
司法書士と弁護士の違いについてのまとめ
今回は司法書士と弁護士の違いについて解説してきました。
司法書士と弁護士では、業務内容や収入面などにおいて大きな違いがあります。
司法書士は基本的に登記の制度に関するエキスパートとして働いているものに対して、弁護士は法律にまつわる様々なトラブルを解決するなど業務内容や範囲に違いが見られます。
業務範囲の違いによって給与も異なり、一般的には弁護士よりも司法書士の方が高い傾向にあります。
司法書士と弁護士のどちらを目指すべきか悩んでいるのであれば、途中でシフトチェンジすることも可能なため、まずは司法試験の勉強を始めるのがおすすめです。
司法試験の内容の方が広く、司法書士試験の内容と重複するところがあるからです。
試験の難易度や内容も異なり、どちらも難易度が高い試験であることは変わりないので、通信講座や予備校などを利用するのがおすすめです。