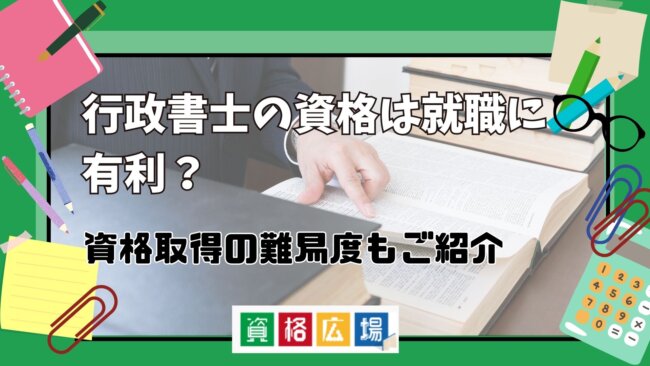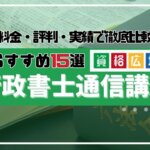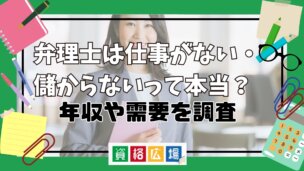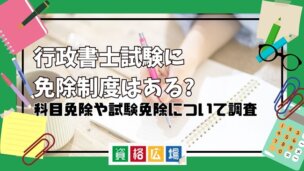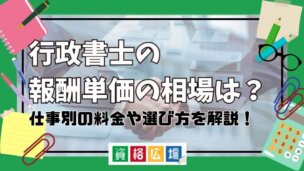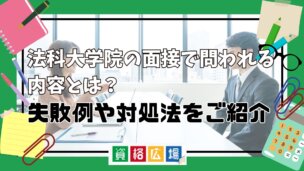行政書士は弁護士などと同じように法曹界で非常に重要な役割を担っており、業界内でも注目を集めている職業の一つです。
未経験の方でも将来資格を取得し就職や転職を考えている方もいると思います。
そこで、行政書士の資格取得難易度や行政書士の資格は就職の際に有利になるかということも含め、行政書士の就職事情について紹介します。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
行政書士講座ならアガルート!

行政書士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
令和6年度は全国平均の3.63倍の56.11%と高い合格率が出ています。
通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。
行政書士とは
そもそも行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格の一つであり、法律関連業務において必要な書類作成や相談業務を行う法律のプロフェッショナルです。
行政書士は基本的に法律事務所や弁護士事務所において、弁護士や司法書士など方関連の職業の方と連携して業務を行いますが、行政書士として独立し自ら事務所を立ち上げることできます。
つまり、行政書士の資格を持っている者は活躍できる場がたくさんあります。
行政書士の仕事内容
行政書士の主な仕事内容は、①各官公庁への必要書類作成及び申請代行業務、②書類作成に関する相談業務、③各契約書の作成代行業務の3つとなります。
①・②に関して、新しい事業を始める際には各役所に提出するための開業届や認可などの書類が必要となります。
素人にとって必要書類の作成は難しい箇所もあるため、行政書士と相談を行いながらそれらの作成・申請代行してサポートします。
③に関して、遺産相続や不動産取引などを行う際には必ずそれぞれ法的内容に従った契約書を作成するこが義務付けられています。
その際に行政書士はクライアントの意向をしっかりと考慮した上で適切な契約書を作成します。
行政書士の資格取得方法や難易度
行政書士の資格は毎年一度行われている行政書士国家試験に合格することで習得することができます。
受験資格は特に設けられていないため未経験の方でも受験することはできますが、行政書士の資格は国家資格の中でも司法試験などに次ぐ非常に難易度の高い試験となっているため一筋縄では合格は難しいです。
試験では法律関連の書類作成や申請業務における実践的な知識に加え、普段私達が生活している上でめったに耳にしない民法やその他法律に関する専門的知識が問われます。
そのため、行政書士を目指す方は大学や専門学校、また資格学校等で法律に関する専門知識を身に着け資格取得を目指す方がほとんどです。
行政書士の平均年収
行政書士は、法律系の国家資格の中でも代表的なもののひとつです。
年齢や勤務年数によって異なるものの、行政書士の多くは年収500万円以下であり、一般的な会社員の平均年収と大きな差はないのが現状です。
また、一般企業の法務部や総務部での給与は年収400万円から700万円程度とされています。
さらに独立して開業している人の中には年収1000万円を超える人もいますが、それはごく一部に限られるでしょう。
一般的に幅広い業務を行うよりも、特定の業務に特化し、ターゲットを明確に設定している人の方が収入が高くなる傾向があります。
行政書士試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!
行政書士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。
合格者には受講費全額返金orお祝い金5万円の特典もあるのでモチベーションの維持も期待できます!
最短ルートで合格が目指せる!
アガルート公式HPはこちら
行政書士資格を取得するメリット
行政書士資格を取得するメリットには以下のものが挙げられます。
- 受験資格なしで受かりやすい
- 独立・開業がしやすくなる
- 法律の知識が身に付く
- 就職・転職に有利
- 他資格取得時にチャレンジしやすい
受験資格なしで受かりやすい
行政書士試験には受験資格が設けられておらず、年齢、学歴、国籍に関係なく誰でも受験できます。
実際、合格者の過半数は40代以上といわれており、令和4年度の行政書士試験では、最年長の合格者が78歳、最年少の合格者が15歳という結果でした。
また法律系資格の中では比較的難易度が低く、取得しやすい資格なのもうれしいポイント。
例えば、司法試験のような難関資格を目指す場合、ロースクールに通う必要があり、非常に高い難易度が求められるため、ハードルが高いと言えるでしょう。
一方で、行政書士試験は科目数が少なく、難易度もそれほど高くないため、取り組みやすい国家試験です。
法律系資格に挑戦しようと考えている方にとっては、非常に良い選択肢となるでしょう。
独立・開業がしやすくなる
行政書士は士業の中で独立して開業しやすい資格とされており、資格腫臆するメリットとして挙げられます。
たとえば弁護士は司法試験を経て1年間の司法修習を受ける必要があり、司法書士は3つの新人研修を、税理士は2年以上の実務経験を積まなければ登録ができません。
しかし、行政書士は登録に際して研修や実務経験は求められません。
さらに、自宅を事務所として利用し、パソコンや電話があれば開業可能であり、初期投資が少なくて済むことも人気のひとつです。
自分のペースで働きたい方や独立を目指す方は、ぜひチャレンジしてみてください。
法律の知識が身に付く
行政書士資格を取得するために行政書士試験の勉強を行うことは、法律に関する知識を習得すできるメリットがあります。
法律の知識は行政書士としての職務を考えていない方にとっても役立つ知識であり、憲法、民法、行政法といった日常生活に関連する法律科目などにもつながります。
しかし、司法試験や司法書士試験と比較すると、その難易度はそれほど高くはありません。
とくに法学部で法律を学んでいる学生や法務部に所属する企業の社員にとって、法律の知識を深めるためにうってつけでしょう。
就職・転職に有利
行政書士資格を持っていれば、就職や転職の際に有利になるといったメリットがあります。
行政書士試験は比較的合格しやすい試験だといわれているものの、合格率が約10%と高い難易度を誇り、十分な学習がなければ合格は難しいです。
したがって行政書士資格を持つことは、優れた学習能力をアピールするのに有効なのです。
また行政書士になれば、くいっぱぐれる心配がなく長期にわたって働き続けられるのも魅力。
書類作成や許認可の申請代行、相談業務など、年齢や性別に関係なく活躍できます。
行政書士の収入には個人差がありますが、年収1000万円以上を得ている行政書士も多く、働き方次第で高収入を得られる可能性があるので取っておいて損はないでしょう。
他資格取得時にチャレンジしやすい
行政書士資格は先にも述べたように法律関連の資格の中で比較的取得しやすく、法律系資格の入門的な位置づけとされています。
なぜなら行政書士の資格を取得する過程で学ぶ内容は憲法、民法、行政法、商法など、司法試験でや他の法律系資格の試験範囲と重なる部分が多いからです。
実際、行政書士の資格は他の法律系資格との相性も良く、ダブルライセンスを取得することでキャリアの向上を図ることができます。
まずは行政書士試験に合格することを目指すことで、効率的に学習を進めることができ、自身の実力を示すひとつの基準にもなるでしょう。
行政書士から社労士を目指すメリットとは?試験内容や仕事内容の違い
行政書士試験の概要
| 受験資格 | なし |
| 試験時期 | 例年11月の第二日曜日 13:00~16:00 |
| 試験場所 | 全国 |
| 試験科目 | 全60問
法令等(択一式および記述式):憲法、行政法、民法、商法、基礎法学の中から46問出題 |
| 受験料 | 10,400円 |
行政書士試験は例年、試験日の約4ヵ月前に試験要項が発表され、行政書士試験の申し込みは7月下旬から8月下旬に行われます。
試験は各都道府県で実施され、受験者は現住所や住民票の住所に関係なく、任意の試験会場で受験することができます。
試験会場は毎年7月の第2週に行政書士試験研究センターのホームページにて公開されるためチェックしてみてください。
行政書士の受験資格には特に制限がなく、学歴、性別、国籍を問わず誰でも受験可能であり、17歳や18歳の合格者も少なくありません。
ただし、資格を取得しても、行政書士として登録できるのは20歳以上なので注意が必要です。
また行政書士試験の合格基準は、「行政書士の業務に関し必要な法令等科目」で122点以上(満点の50%以上)、「行政書士の業務に関し必要な基礎知識科目」で24点以上(満点の40%以上)、試験全体で180点以上(満点の60%以上)が必要です。
行政書士試験は絶対評価制であり、上記の条件を満たせば合格となります。
一部の国家試験では合格基準をクリアした上で成績上位に入る必要がありますが、行政書士試験は条件を満たせば合格が確定します。
行政書士資格の活かし方とは?就職先や会社員として働く場合のメリット
行政書士の就職事情
一般的に行政書士として資格取得後は「使用人行政書士」「開業行政書士」「兼業行政書士」の3つの進路に分かれます。
使用人行政書士とは、行政書士事務所雇われて就職する方法です。
とはいっても、「行政書士」という役職で求人を行っている法律関連事務所や企業は少ないのが現状であるため、使用人行政書士になる方はほんの一部に限られています。
「開業行政書士」とは、その名の通り独立して事務所を起ち上げ、行政書士として事務所の経営を行います。
「兼業行政書士」とは自ら事務所を起ち上げた後に行政書士としての仕事に加え、他の法律関連業務も行います。
また、中にはセカンドライセンスとして行政書士の資格取得を目指す方も決して珍しくはなく、不動産鑑定士や司法書士など関連職業の方がキャリアップやスキルアップのために行政書士の資格取得を目指します。
行政書士の資格取得者に有利な就職先
行政書士の資格取得後には「使用人行政書士」「開業行政書士」「兼業行政書士」の3つの進路がありますが、いずれを選択する際にも行政書士の国家資格を持っていることで就職は有利になります。
行政書士国家資格取得後の気にある就職事情ですが、資格取得者が必ずしも行政書士として就職するわけではありません。
そこで、具体的な就職先について一緒に見ていきましょう。
就職先1:法務事務所や弁護士事務所
行政書士資格保有者の主な就職先としてまず法務事務所や弁護士事務所が挙げられます。
先程も紹介した通り「行政書士」枠として求人を行っている事務所は少ないため、ほとんどの場合は将来開業する際に実務経験を積むために就職する方、もしくは弁護士事務所においてパラリーガルなど他の役職と兼業して働く方がほとんどです。
場合によっては各事務所の各事務業務や経理などを任されることもあるため、行政書士としてのスキルはもちろんのこと柔軟に対応する力も必要となります。
就職先2:一般企業の法務部
業種・業態問わずどんな企業にも「法務部」という部署が存在し、そこが行政書士資格取得者の一つの就職先になります。
しかし、一般企業においてインハウス、つまり行政書士として働くことは許されておらず、当然行政書士の専門業務を行うことは許されていません。
そのため、行政書士の資格はあくまでも採用面接の際のアピール材料の一つに過ぎません。
法務部では、一般企業が直面しやすい民法や商法にか関するトラブルが生じた際に問題解決のための助言や相談業務を行うことになります。
就職先3:事務所を独立して開業する
行政書士としてやっていく方のほとんどは遅かれ早かれ独立し事務所を起ち上げます。
しかし、資格取得後にいきなり独立することは難しいため、まずは各関連事務所において実務経験を積みながらクライアントを獲得していきます。
また、事務所を経営するためには行政書士としての専門スキルはもちろんのこと経営スキルも必要であるため、経営についてもしっかり学ぶ必要があるのです。
最初は比較的小規模な事務所や自宅の一室を利用し開業する方がほとんどでその場合には従業員の数も限られるため、事務作業や会計・経理、その他必要業務も事業主自らこなす必要があります。
行政書士とのダブルライセンスにおすすめの資格
行政書士は法律系の資格の中でもハードルが低く、メリットの多い資格です。
しかしダブルライセンスによって複数の資格があれば、さらに仕事の幅を広げることが出来ます。
ここでは、行政書士とのダブルライセンスにおすすめの資格についていくつかご紹介します。
社会保険労務士
社労士と行政書士はダブルライセンスを取得することで業務の幅を大きく広げることが可能です。
特に、行政書士に依頼が多い建設業界では労働安全に関する対策が求められ、労災申請の依頼も頻繁にあります。
たとえば建設労働者の雇用形態は常勤や日雇いなど多岐にわたるので、社労士の資格を持つことで労働契約や給与計算などの業務も行うことができます。
通常は社労士と行政書士の2名が必要な業務を1名で対応できるため、収入の向上が期待できます。
また、企業側も担当者を変更することなく依頼できるため、幅広い業務を任せることができるでしょう。
社労士試験には受験資格が設けられていますが、行政書士試験に合格している方は受験できます。
社労士を目指すが受験資格を満たしていない方は、まず行政書士試験に挑戦することを検討してみるのもひとつです。
行政書士から社労士を目指すメリットとは?試験内容や仕事内容の違い
宅地建物取引士
宅地建物取引士と行政書士の試験科目には民法が共通しているため、学習において非常に有利です。
行政書士試験では民法が重視されるものの、ほとんどの受験生が苦労する分野でもあります。
しかし宅建を学んだ方はその知識を活かせるので、学習がスムーズに進められます。
また、宅建業法や法令上の制限に関する法律は、行政書士の行政法において学ぶ判例の具体例として取り上げられます。
民法の知識があることで、他の科目に学習時間を充てることができ、効率的に学習を進めることが可能です。
ダブルライセンスを目指す方はぜひ宅地建物取引士を先に学んでおくといいでしょう。
行政書士資格は不動産業でも活かせる?兼業するならどの資格がいい?
司法書士
司法書士は主に登記業務を担当していますが、行政書士の資格を併せ持つことで、定款の作成から法務局への登記申請までを一貫して行うことが可能です。
また、司法書士としての学習経験を有する方にとっては学習面でもめりとがあります。
実際、司法書士試験で重要な憲法、民法、商法の三科目は、行政書士試験でも全体の約40%を占めています。
さらに、問題の多くは条文や判例に基づく基本的な内容であり、司法書士試験の学習を通じて得た知識が十分に活用できます。
ほかにも、行政書士試験特有の行政法や一般知識に関して重点的に学習を行うことで、行政書士試験の合格レベルに迅速に到達することができます。
行政書士・司法書士・社労士の違いとは?資格取得の難易度も比較
行政書士の資格は就職に有利
今回は行政書士の資格取得難易度や就職事情について詳しく紹介しました。
行政書士は未経験の方でも目指すことはできますが、高度な専門スキルを要する国家資格であることから非常に難易度の高い資格となっています。
また、資格取得後は各事務所に雇われる行政書士として就職する人は限られており、ほとんどの方は将来的に独立開業を目指します。
しかし、どんな形で就職するにしても行政書士としての資格を持っていることで有利になることは間違いありません。
行政書士の資格取得までの道のりは非常に険しいものですがそれだけ価値のある資格であるため、興味のある方はぜひチャレンジしてみてください。