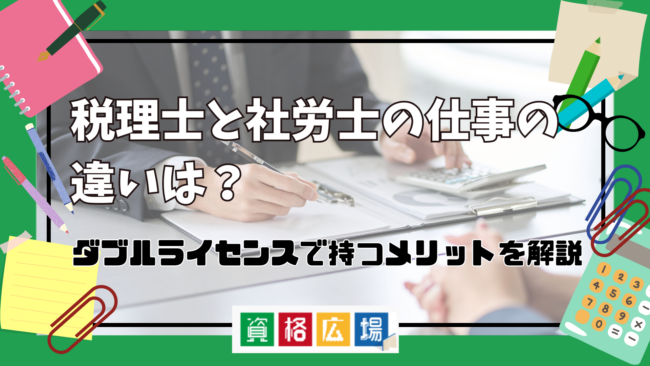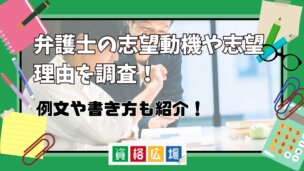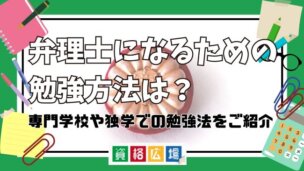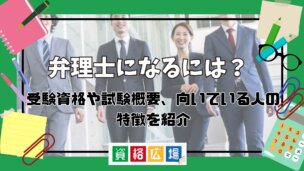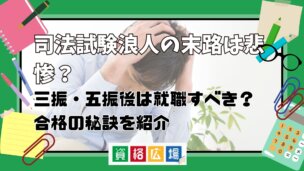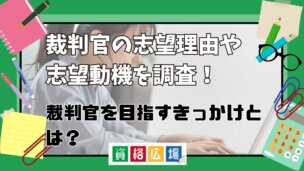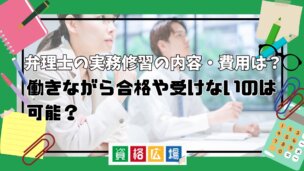税理士と社労士という資格について、取得を考えたことがある方は多いと思いますが、仕事内容や取得方法の違いについて、詳しく理解している方は少ないのではないでしょうか。
そこでこの記事では、まず、税理士と社労士の具体的な仕事内容による違いや、取得方法の違いについて説明します。
そしてダブルライセンスとして両方の資格を持つメリットについて、資格を持っている方と、仕事を依頼する方とに分けて解説していきます。
税理士と社労士という仕事に興味のある方、取得するかどうか迷っている方向けにまとめましたので、ぜひ最後までお読みください。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
社会保険労務士試験におすすめの通信講座
税理士と社労士それぞれの資格内容は?
税理士と社労士はどちらも国家資格です。
どちらも企業に対し有益になるためのコンサルティングを行ったり、サポートを行うのが主な資格・仕事内容になっています。
税理士はその名の通り、お金に関する専門家であり、社労士は人材に関する専門家です。
もう少し詳しく資格内容について見ていきます。
税理士とはどのような資格なのか
税理士とは、税理士法に基づく国家資格者です。
個人や法人あるいは個人事業主に対し、税務や会計に関する専門知識を用いて、税務に関する相談業務に応じるほか、税務書類の作成や、税務に付随する財務会計帳簿の作成などを代行します。
確定申告の時期が近づくと、多くの企業では、税理士と顧問契約を結び、法人税や消費税などの算出や、納税に向けた書類作成を依頼します。
そのほか、個人の確定申告を代行することもありますし、相続税や贈与税などの節税対策について相談されるなど、個人にとっても身近に相談できる専門家として知られています。
社労士とはどのような資格なのか
社労士とは、社会保険労務士法に基づいた国家資格者で、社会保険制度と労務法制の知識を活用し、企業等における給与・休暇などの労務制度及び関連規定の整備に向けたアドバイスを行います。
つまり社労士は、企業の成長に欠かせない「お金、モノ、人材」の経営資源のうち、人材に関する専門家なのです。
採用から退職までに関わる労働・社会保険に関する問題の解決や、企業年金制度の運用に関する相談に応じるなど、業務は多岐にわたります。
企業等の労務管理や保険加入手続きなどに関する各種規定は、労働組合や従業員代表との話し合いも経たうえで整備されますが、具体の条件整備や文言の整理は、専門知識を持つ社労士の力を借りて進められることが多いです。
税理士と社労士の仕事内容による違い
それぞれの大まかな内容が分かったところで、続いては主な仕事内容について簡単にまとめてみました。
ここまで来ると、税理士と社労士の資格や仕事内容の大きな違いが見えてくるのではないでしょうか?
税理士の主な仕事内容
税理士の主な仕事には、以下のようなものが挙げられます。
- 税務書類や会計帳簿の作成
- 税務代理
- 税務相談
- 中小企業の支援機関としての支援
税務書類や会計帳簿の作成
個人や企業に代わって、確定申告書、青色申告承認申請書のほか、相続税申告書など税務署に提出する税務書類を作成します。
また、会社法に定める中小企業の「会計参与」として、取締役と共同して、財務書類の作成や会計帳簿の記帳代行などを行います。
税務代理
個人や企業を代理して各種税務署類の作成及び申請を行うほか、税務署による税務調査の立会いや、確定申告の更正や追徴課税の決定への不服申し立てなどを行います。
税務相談
個人や企業経営者が税金のことで困ったときや分からないときに、税理士が相談に応じます。
中小企業の支援機関としての支援
中小企業等経営強化法において、中小企業に対し、専門性の高い経営改善に関する支援を行う「認定経営革新等支援機関」の一つに税理士が認定されています。
社労士の主な仕事内容
社労士の主な仕事には、以下のようなものが挙げられます。
- 労務に関する相談、指導
- 出産、死亡、労災、年金などの社会保険における相談、申請手続き
- 労務に関する各種助成金の申請手続き
- 就業規則・36協定の策定
労務に関する相談、指導
企業等における労使関係の維持や、良好な職場環境づくりに向け、全般的な相談や指導を行います。
出産、死亡、労災、年金等の社会保険における相談や申請手続
労働者の出産、ケガ・病気、死亡、労働災害などにおいて、社会保険制度に基づく申請手続きや保険料の算出や、関連する各種相談に対応します。
労務に関する各種助成金の申請手続き
働き方改革の推進や、社会環境の激変時における雇用の維持、55歳以上の高年齢者の雇用促進など、国の政策では、雇用の維持や労働者の能力開発を支援する各種の助成金が用意されています。
社労士は、中小企業の経営者がこれらの制度の活用を躊躇しないよう、各種相談や申請手続きを行い、企業の発展をサポートします。
就業規則・36協定の策定
労働関係の法改正に対応し、就業規則の策定・変更作業を行います。
また、時間外・休日労働や有給休暇の付与条件などを規定する労使協定(いわゆる36協定)の整備や見直しを支援します。
つまり簡単にまとめると、
・社労士は労働に関する各種相談、手続き、ルール作りの専門家
・税理士は、税務に関する各種相談、手続きの専門家
以上の点が、両者の違いです。
税理士と社労士の取得方法による違い
税理士と社労士の資格の取得方法、つまり受験資格には、次のような違いがあります。
税理士は下記の内いずれか1つの条件を満たす必要が有ります。
- 大学等で法律学や経済学を1科目以上履修した者
- 弁理士、行政書士、司法書士、不動産鑑定士等の業務または業務の補助に通算2年以上従事した者
- 日商簿記検定1級合格者
一方で、社労士は下記のいずれか1つの条件を満たすことが受験資格となります。
- 大学・短大・専門職大学・高専を卒業
- 行政機関で公務員として、あるいは社労士事務所などに3年以上の実務経験
- 行政書士の資格を取得している
税理士独自の免責制度
税理士特有の取得方法として、「税理士試験免除制度」があります。
これは具体的には、
・弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)
・公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)
については税理士試験を受験する必要がなく、必要な研修等を受ければ登録可能となる制度です。
さらに、大学院から修士又は博士の学位を授与された者は試験の一部が免除されるほか、
税務署に勤務した国税従事者については、
・10年又は15年以上税務署に勤務した国税従事者は、税法に属する科目が免除
・23年又は28年以上税務署に勤務し指定研修を修了した国税従事者は、会計学に属する科目が免除
という免除制度があります。
社労士についてはこのような免除制度がありません。この点が大きな違いです。
社労士試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!
社労士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。
合格者には受講費全額返金orお祝い金3万円の特典もあるのでモチベーションの維持も期待できます!
最短ルートで合格が目指せる!
アガルート公式HPはこちら
ダブルライセンス取得のメリット
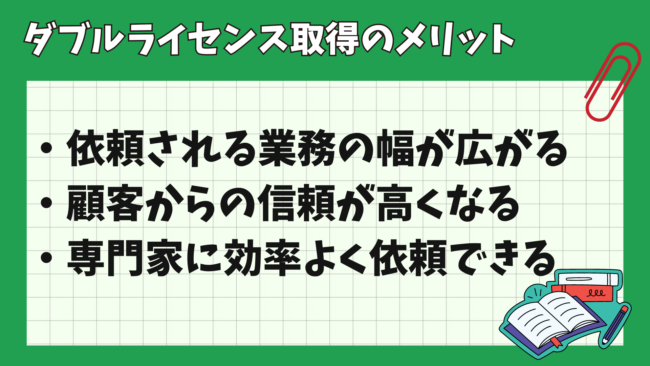
最後に、仕事内容の異なる税理士と社労士の両方を取得すると、どんなメリットがあるのかについて説明していきます。
将来的に独立したい。と考えている方や、企業内で高収入を得るために頑張りたいという方はダブルライセンスを取ることも視野に入れてみるのはいかがでしょうか?
依頼される業務の幅が広がる
ダブルライセンスを持つと、顧客の依頼に応えられる業務が増え、企業の顧問契約のオファーを受けることも増えていくでしょう。
顧客からの信頼が高くなる
税理士と社労士のダブルライセンスを持っていると、優秀な人材として認知されるようになります。
それだけでなく、同じ専門家に労務・税務に関する助言や手続きを依頼できるので、顧客からの信頼が高まります。
専門家に効率よく依頼できる
企業としては、労務・税務問題を一か所に依頼できると、人件費や業務委託費を縮減できるので効率性が高まります。
税理士と社労士の違いやダブルライセンスのメリットまとめ
以上、社労士と税理士の資格の違いと、ダブルライセンスを持つメリットについて説明しました。
企業や個人事業主の経営において頼りになる存在であり、取得しておけば専門性の高い業務を依頼され、無くてはならない存在になれます。
企業内で専門性を生かすことも可能ですし、ある程度経験を積めば、独立開業してしっかり稼ぐことも夢ではありません。
この記事が、税理士・社労士の資格取得に関心ある方の参考になれば幸いです。