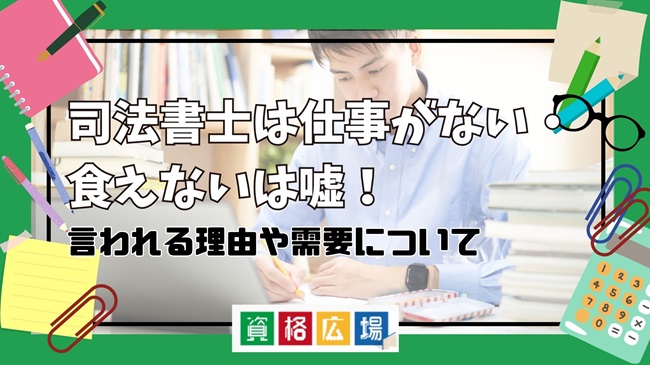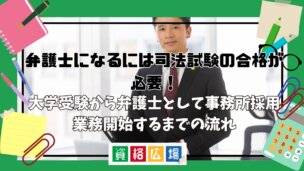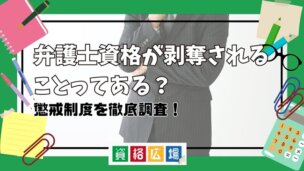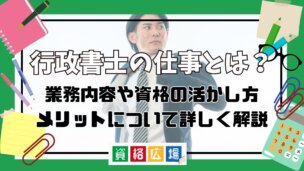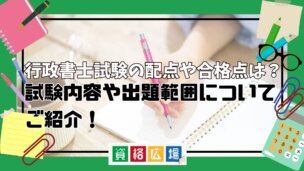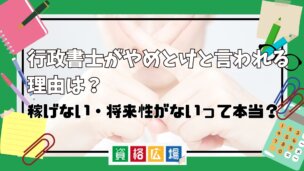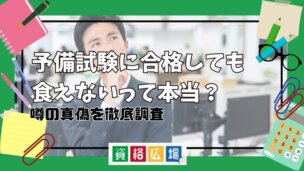司法書士は専門性の高い士業の1つであることから稼げる仕事というイメージをもたれていましたが、近年では「仕事がない」「食えない」といった意見が囁かれるようになっています。
その噂が本当かどうかを検証すべき、当記事では、
・『司法書士に仕事がない』と言われる理由
・司法書士の今後の需要
・稼げる司法書士になる方法
を中心に情報をまとめています。
「司法書士資格を取得するか迷っている人」「司法書士として活躍したい人」は参考にしてください!
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
「食えない」のに増え続ける司法書士数
司法書士連合会によると、現在、日本司法書士連合会に登録している司法書士の人数は22,907人です。(2023年4月1日時点)
| 年度 | 司法書士数 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 令和4年度 | 22,907人 | +189 |
| 令和3年度 | 22,718人 | -24 |
| 令和2年度 | 22,742人 | +110 |
| 平成31年度 | 22,632人 | +144 |
| 平成30年度 | 22,488人 | +205 |
| 平成29年度 | 22,283人 | +270 |
直近10年間(平成25年~令和4年まで)で比較すると司法書士数は1928名、平均すると1年で約190名増えています。
司法書士は難関資格なので、取得までに数年を要したり、参考書や予備校の受講料など、ある程度の学習コストもかかります。
自己投資の割にリターンが少ないのであれば司法書士を目指す人は年々減少していくはずですが、伸び率は緩やかであるものの実際は登録者数が毎年増えているのです。
『司法書士に仕事がない』と言われる理由
司法書士数は毎年増加している一方で、司法書士には「仕事がない」「食べていけない」と言われるのはなぜでしょうか。
考えられる理由をいくつか挙げてみました。
登記件数は10年連続で減少しているから
司法書士の主な仕事は不動産や法人などの登記ですが、両案件とも最近の10年間で30%前後減少しています。
司法書士業界全体の案件数から見れば、仕事が減ったという見方もできます。
司法書士制度は1872年(明治5年)から存在し、長きにわたり法律分野において専門性の高い職業であり続けていましたが、インターネットの発達などによる技術革新によって一般人との情報格差が縮まったことが理由の1つです。
司法書士がいなくても登記申請はできるから
そもそも司法書士の仕事の1つである登記の代理・申請は、司法書士の資格がない人でも行えます。
登記申請は必ずしも専門家に頼む必要はなく、少しでも費用を抑えるために自分で登記をするという選択も可能です。
以前は登記に必要な知識を得ることが大変でしたが、今はネットで調べれば簡単に申請に必要な書類や書き方が分かるようになったので、自分で書類を作成することもできるでしょう。
そのため「司法書士に頼らなければ」という認識が全体的に薄くなっているという傾向があり、司法書士の仕事がない状態になりやすいのです。
仕事がAIに代替されると考えられているから
司法書士のメイン業務となる法務局への登記書類の作成や申請代行などの事務作業は、将来発達したAIに代替されるのではと考えられています。
前述したようにインターネットが登場しただけでも司法書士に仕事は減ったのに、さらに高度な作業ができるAIが台頭すればより一層業務を奪われやすくなります。
司法書士には依頼者の相談に乗る・専門的な提案するといったコミュニケーションが必要になるので、完全に仕事がなくなることはないですが、一部の業務をAIが担うことは確かでしょう。
低収入の司法書士がいるから
司法書士をはじめとする国家資格を取得できれば、勝手にどんどん仕事が舞い込み、楽してたくさん稼げるようになるわけではありません。
効率の悪い業務の仕方をしていたり営業力がなかったりすれば、当然ながら仕事がないので低収入になります。
ちゃんと稼げる能力がある司法書士の年収は数千万円にも上るものの、稼げなければ年収200~300万円という人はザラにいます。
「司法書士に仕事がない」という噂は的外れで、正しくは「仕事がない司法書士がいる」ということを覚えておきましょう。
司法書士に依頼するメリットは今も昔も変わらない
登記の申請についてよく分からない素人がゼロから調べて申請するのは難しく、非常に時間がかかります。
そのため、費用よりもとにかくスピードを求める方にとって、司法書士に依頼することは大きなメリットです。
また、自分で調べて時間をかけて申請したにも関わらず、書類に不備があった場合は一発で登記が通らないことがあります。
確実に登記を申請したい、二度手間を無くしたい方にとっても司法書士へ依頼することはリスクヘッジになります。
このように、登記に必要な複数の書類の用意から申請までを責任を持って行ってくれる司法書士へのニーズは今も昔も変わらないので、今後も食えなくなることはないでしょう。
司法書士に求められる新たな需要
登記件数は減少しているものの、司法書士の業務内容は登記だけではありません。
平成14年に行われた司法書士法改正により、条件付きで司法書士でも訴訟業務が担当できるようになり、司法書士の活動フィールドは広がりを見せています。
①『司法書士法改正』によって司法書士の仕事が増える
2002年(平成14年)の司法書士法改正により、司法書士に対し「簡裁代理権」が付与されました。
この簡裁代理権の付与によって、司法書士は依頼者の代理人として簡易裁判所に出廷し弁論したり、和解に応じたりすることが可能になりました。
簡裁代理権とは
簡裁代理権とは、簡易裁判所で扱われる民事訴訟事務の権限のことを指します。
法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、請求額が140万円までの民事事件について、以下のことを行えます。
- 民事訴訟手続
- 即決和解手続
- 支払督促の手続
- 証拠保全の手続
- 民事保全の手続
- 民事調停の手続
平成14年改正以前は、弁護士法72条により、弁護士以外が訴訟代理人にとなり示談交渉をしたり、紛争に介入することは一切できませんでした。
しかし「簡裁訴訟代理等関係業務」が規定されたことで、140万円以下の訴訟であれば司法書士が代理人として介入でいるようになったため、「紛争解決に司法書士を利用する」という選択肢が増えました。
このように司法書士の業務は「登記」以外にも増えており、今後も活躍の場は広がりそうです。
②『相続登記義務化』によって、登記件数が増加する
ワイドショーでも取り上げられることが多い「所有者不明土地問題」は、皆さんも一度は耳にしたことはあると思います。
亡くなった親の土地を子どもが相続した際に、名義人を変更する手続きを「相続登記」といいますが、登記をする/しないは当事者の任意に任されています。
そのため、登記しないまま放置されている土地が全国的に増えてしまい、持ち主が分からなくなる事態が起きています。
このような問題を考慮し、2021年4月に「相続登記を義務化する」改正法案(民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案)が参議院本会議で可決され、2024年を目処に施行される見込みです。
相続登記義務化によって登記件数の増加が予想されており、総じて司法書士が相続登記を依頼される機会は増えていくだろうと言われています。
相続登記義務化とは
相続登記義務化とは、従来義務ではなかった相続登記を義務化することで、怠った場合は罰則(10万円以下の過料)が科されることになります。
国土交通省の「地籍調査における土地所有者等に関する調査」によると、2016年時点で所有者不明土地は全国に約410万haあり、このまま加速すると2040年までには約720万haになるとも言われています。
410万haは日本の面積の20%に匹敵する大きさで、九州の面積を上回る土地が放置されていることになります。
相続登記義務により、以下の期間内に登記をしなければいけません。
- 相続の開始を知り、かつ所有権を取得したと知った日から3年以内
- 遺産分割で所有権を取得した際は、分割の日から3年以内
そのため、登記件数は今後増えていくことが予想され、司法書士に「登記業務」を依頼する人も増えていくでしょう。
③少子高齢化が司法書士の需要を高める
少子高齢化の影響を受け案件数が増えている司法書士業務に、成年後見業務があります。
成年後見人は家族や親族がなることもできますが、弁護士・司法書士・社会福祉士といった専門家に依頼することもできます。
本人の財産が多額であったり、債権回収を行う必要があったりする場合には弁護士に依頼するケースが多いですが、相応な財産はあるけれど弁護士に依頼するほどではない場合や財産に不動産が多い場合などは司法書士が成年後見人に選任されます。
より詳しく成年後見人制度について見てみましょう。
成年後見人制度とは
成年後見人制度とは、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分なため、契約等の法律行為を行えない人に代わって後見人が契約を締結したり財産を管理したりできる制度のことです。
成年後見人制度が創設された当時(2000年)は、親族が後見人になる割合のほうが圧倒的に高く91%を占めていました。
しかし、身寄りのない高齢者の増加や親族による不正などといった理由から、第三者(特に専門職である弁護士・司法書士・社会福祉士)が成年後見人になるケースが増えてきました。
専門職の選任数は2000年では全体のわずか8%でしたが、2020年には69%にまで大きく増加しており、今後も成年後見人として司法書士の需要は高まっていくと予想されています。
④組織内司法書士の需要が高まっている
昨今ではコーポレートガバナンスへの注目度の高まりやコンプライアンスの重視が素因となり、官公庁や企業などの組織内で司法書士資格を持つ法務人材の需要が増えています。
圧倒的な売り手市場である有資格者ですが、司法書士の登録者は少ないため、官公庁や企業で働く司法書士は未だ増えていないのが現状です。
また、司法書士は他の士業と比較しても、登録者数が少ないことが見て取れます。
| 士業 | 会員数 |
|---|---|
| 司法書士 | 23,059人 |
| 弁護士 | 44,916人 |
| 社会保険労務士 | 44,870人 |
| 行政書士 | 48,768人 |
| 税理士 | 80,692人人 |
「組織内弁護士」や「組織内会計士」は知っているけど、「組織内司法書士」は聞いたことがないという方もいると思います。
そもそも組織内司法書士は、官公庁や企業などの組織に所属する司法書士を指す言葉です。
しかし、現行の制度においては司法書士登録をしたまま企業に属することは難しく、企業の法務部に所属するためには兼業する必要があります。
日本組織内司法書士協会では「組織内司法書士制度」の確立を目指しており、今後ますます司法書士の活動領域は広がっていくとされています。

司法書士の廃業率は高いのか
司法書士資格を取得し、十分に経験を積んだ人の中には独立を目指している方も多いでしょう。
司法書士の主な仕事である不動産の登記業務が減少している中、独立後に失敗してしまう廃業率は高いのでしょうか?
結論から言うと、さまざまな業種の個人事業主の中でも、廃業率は比較的に低いと言われています。
こちらでは司法書士が廃業になりにくい理由と廃業になってしまう原因について紹介していきます。
司法書士が廃業になりにくい理由
司法書士として独立開業する場合、開業資金や運用資金が他の士業系と比較すると安い傾向にあるため長く続けやすく、廃業になりにくいといわれています。
長く続けるほど顧客も徐々に増えて経営が安定していきますので、続けやすさというのは大切な要素です。
以下では司法書士が廃業になりにくい理由を3つに分けて紹介していきます。
開業資金があまりかからない
司法書士の開業費用は比較的安いといわれています。
司法書士として開業する場合、一般的な事務用品を揃えれば事業をスタートできます。
飲食店やクリニックのように専門機材や設備は特に必要ないので、他の業種と比べても司法書士の開業費用は安いです。
仕入れ費用がかからない
司法書士の仕事では、仕入れ業務を行うことがないので仕入れ費用が発生しません。
そのため仕入れサイクルが回らなくなったり、資金がショートするなどの心配がなかったりするので廃業するリスクは少ないです。
小売り業のように先に資金が出ていくモデルではないので、安定して収益を得ることができます。
固定費が安い
毎月かかる費用は光熱費や通信費くらいですので、固定費に関しても他の業種と比べるとかなり少ないです。
1番コストがかかるのは事務所の賃料ですが、自宅開業や共同事務所を選ぶなどして工夫すれば費用は安く抑えられます。
こうした毎月のランニングコストの低さも廃業率を抑えている要因の1つと考えられます。
司法書士が廃業になる原因
続けやすさがある司法書士ですが、それでも廃業となってしまうケースはあります。
経営が安定している事務所が多数ある中、廃業となってしまうのはどのような原因があるのでしょうか?
以下では、廃業となってしまう原因について解説していますので確認していきましょう。
資金不足によるもの
廃業になってしまう原因の1つとして資金不足が考えられます。
事務所の経営が軌道に乗るまでの運営資金や生活費を十分に用意していなければ、開業して間もなく廃業してしまうなんてこともありえます。
突然の出費にも対応できるように、十分な資金を用意してから事業をスタートさせるといいでしょう。
営業不足によるもの
開業したばかりの時期は、新規顧客を獲得し続けるために営業や人脈を築いていくことが必要です。
営業を続けなければお客さんは集まらずに仕事がない状態が続きやすくなるので、開業してすぐは積極的に営業を行う施策をしないと廃業してしまいます。
営業スキルを磨いたり、ホームページを作ったり、ダブルライセンスを取得して他の司法書士にはない強みを作ったりするなど、できる限り顧客を獲得できるように努めましょう。
営業や人脈を築いた成果は短期間では出しづらいですが、根気よく活動を続けていくことが大切です。
業務過多によるもの
独立開業の後、しばらくは1人で事務所を運営していくことになるでしょう。
司法書士の仕事以外にも営業、経理、雑務など全て1人でこなさなければなりません。
そうなると体力的にも負担が大きくなりますので、忙しすぎて体を壊して事業が続けられなくなってしまうケースもあります。
外注できる内容は他社に依頼するなどして、業務過多にならないように体調管理には気を付けましょう。
稼ぐ司法書士と稼げない司法書士の年収比較
一般的なサラリーマンの平均年収は約440万円ですが、司法書士の平均年収は約600万円と言われているため給与水準は高いと言えます。
司法書士が稼げないと言われる原因は、平均年収を押し上げているのは一部の稼げる司法書士であり、半数以上が一般サラリーマンと同等かそれ以下だからです。
司法書士として1,000万円以上の年収がある司法書士も存在する一方で、中には何年経っても年収200万円台から抜け出せないという方も存在します。
司法書士資格があるから〇〇万以上稼げるという目安が存在しないため、稼ぐ司法書士と稼げない司法書士が存在し、大概して司法書士は「食えない」と揶揄されることがあります。
ちなみに、司法書士の年収の中央値は400万~550万円と言われています。
稼いでる司法書士は『独立開業』か『組織内司法書士』
司法書士になって高収入を目指す場合は、独立開業する、或いは組織内司法書士になるといいでしょう。
独立・開業した司法書士の平均年収は500万円程度と言われており、1,000万円以上稼ぐ司法書士は登録者の上位15%前後と言われています。
独立すると自分で仕事を獲得しなければならないため、本人の営業力や人脈、力量で差が出てきます。
一方、日本組織内司法書士協会による年収に関するアンケートによると、組織内司法書士の平均年収は全体として高い水準であることが分かります。
| 順位 | 年収 | 全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 1位 | 「750万円~1000万円未満」 | 全体の32.8% |
| 2位 | 「500万円~750万円未満」 | 全体の27.6% |
| 3位 | 「1,000万円~1,250万未満」 | 全体の19% |
「仕事がない司法書士」にならない方法

せっかく資格を得たならば、仕事がない・食えない司法書士にはなりたくないですよね。
どうすれば稼げる司法書士になれるのか、具体的な方法の一例をご紹介します。
事務所に所属するよりも独立した方が最初は稼ぎづらいので、開業したばかりの司法書士を想定して解説します。
コミュニケーション能力を高める
食べていける司法書士になるためには、何よりもコミュニケーション能力を身につける必要があります。
自分は司法書士だからと天狗にならず、「何について知りたいのか」「どのように解決したいのか」など依頼者に真摯に向き合って悩みを引き出さないと、継続した顧客獲得は厳しくなるでしょう。
また与えられた仕事だけをこなせばいいという訳ではなく、「他にどんなことに悩んでいるのか」「違う解決方法もあるのではないか」と自ら提案もしていかないと稼げるようにはなれません。
依頼者の立場になって希望を最大限まで聞き出し、頼ってよかったと思ってもらえるように、コミュニケーション能力はしっかり磨いていきましょう。
できる限り宣伝する・人脈を広げる
いくらコミュニケーション能力に長けていても、司法書士である自分の存在を人に知ってもらわないと仕事の依頼は来ないでしょう。
ですから、できるだけ自分を宣伝して顔を売り、人脈を広げることにも専念してください。
SNSやブログなどネット媒体を使ってPRしたり、異業種交流会などイベントに参加して様々な人に自分のことを覚えてもらうようにしたりすると良いですね。
最初は依頼者が数名しか集まらなくても、だんだんと口コミが伝播して案件数が増えていくようになるかもしれません。
専門性を持って自分をブランディングする
司法書士は全国に万単位でいるので、依頼者にはたくさんの司法書士の中から自分を選んでもらわねばなりません。
特に専門知識を持っていない依頼者からすると、どのような司法書士を選べばいいか分からないので、何か指標となるものを掲げることをおすすめします。
「成年後見人制度に強い」「相続問題の解決実績が多い」など、ノウハウが豊富にある専門分野を明示して営業するとよいでしょう。
自分をしっかりブランディングできれば、依頼者が困った際に真っ先に相談してくれやすく、案件獲得につながりやすくなります。
ダブルライセンス所有者になる
司法書士の他にもう1つ別の資格を取得してダブルライセンス所有者になれば、希少価値が高まるので仕事がないという状況に陥りづらくなるでしょう。
司法書士と相性の良いおすすめの資格は「土地家屋調査士」と「行政書士」になります。
土地家屋調査士は不動産の登記を生業としており、行政書士は公的書類作成のスペシャリストですので、司法書士と分野が重なっているからです。
それぞれの試験内容も司法書士試験と近しくて勉強がしやすいため、気になる方は調べてみましょう。
司法書士は仕事がない・食えないって本当?まとめ

不動産や法人などの登記件数の減少により、司法書士は「仕事がない」と言われることがありますが、以下の理由から司法書士の将来性は十分にあると言えるでしょう。
- 『簡裁代理権』により、法廷という新たなフィールドが広がった
- 『相続登記義務化』によって、登記件数は増加が予想される
- 少子高齢化による成年後見の依頼も増加が予想される
- 『組織内司法書士』や法務人材の需要が年々高まっている
また「司法書士は稼げない」と言われるのは、収入格差が出やすい職種であるからと言えます。
司法書士は「取れば一生安泰な資格」ということはなく、取得後にどのように活用していくかが稼ぐ司法書士と稼げない司法書士になるかの分かれ目になります。
営業力を鍛えて顧客の満足度を高め、どんどん仕事が獲得できる司法書士になれば仕事がないということにはなりづらいため、ネットや周りの意見に振り回されないように気をつけましょう。