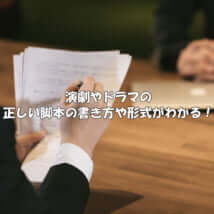こちらでは、高卒認定(大検)を受験される方に必要な情報を紹介しております。
高卒認定(大検)資格取得に関する難易度、試験科目や費用などの基本情報を掲載。
必要な勉強期間やオススメ参考書もまとめてみました。
高卒認定(大検)を受験される皆様を応援しています!
それでは見ていきましょう。
高卒認定(大検)とは?
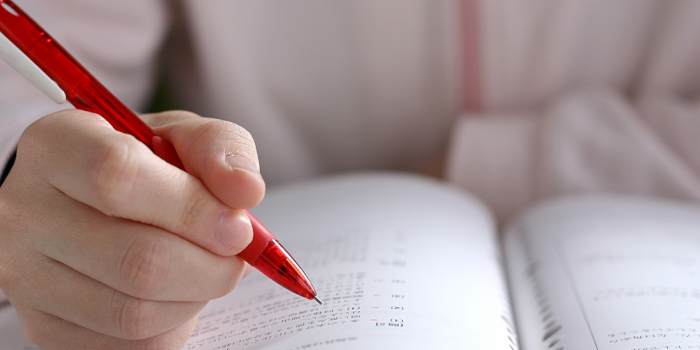
高卒認定(大検)とは、高校卒業程度の学力があるかを認定するための国の試験です。
高卒認定資格は、様々な理由により高校を卒業できなかった方の就職・資格試験時に活用することができます。
「高卒認定」と「大検」という呼び方がありますが、両者は同じものです。
2004年度までは大検という名称が使われていましたが、それ以降は試験範囲や受験条件を若干変更し、「高卒認定」に改めました。
「大検」という名称が長く使われていたため現在も知名度が高いですが、正式名称は「高卒認定」となります。
「高卒認定(大検)」と「高卒資格」
勘違いされやすいですが、「高卒認定(大検)」と「高卒資格」は別のものです。
「高卒認定(大検)」は、高校卒業程度の学力があるかを認定する試験であるのに対し、
「高卒資格」は、高校を卒業すれば誰でも手に入れることができます。
高卒認定(大検)の試験科目
高卒認定(大検)の試験科目は、以下の通りです。
| 教科 | 試験科目 | 科目数 | 要件 |
| 国語 | 国語 | 1 | 必修 |
| 地理歴史 | 世界史A,世界史B | 1 | 2科目のいずれか1科目必修 |
| 地理歴史 | 日本史A,日本史B,地理A,地理B | 1 | 4科目のうちいずれか1科目必修 |
| 公民 | 現代社会、倫理、政治・経済 | 1又は2 | 「現代社会」1科目 又は「倫理」及び「政治・経済」の2科目 |
| 数学 | 数学 | 1 | 必修 |
| 理科 | 科学と人間生活、物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎 | 2又は3 | 必修だが、条件あり |
| 外国語 | 英語 | 1 | 必修 |
引用元:文部科学省 公式サイト 平成30年度高等学校卒業程度認定試験 試験科目・合格要件・出題範囲
出題範囲はどれも、「現在の高校生が使用している教科書」となっています。
また、過去に一部科目合格している場合など、人によっては試験科目が一部免除になる場合があるので、受験者は確認してみましょう。
高卒認定(大検)の出題形式と合格基準
高卒認定(大検)は、4択マークシート形式です。
高卒認定(大検)の合格成績は、科目ごとにA,B,Cの3段階評価がつけられます。
A 100~80点、B 79~60点、C 59~最低点 という基準になります。
最低点については毎年変動がありますが、だいたい40~45点くらいが目安のようです。
また、高卒認定(大検)は、一度に8科目すべて合格する必要はありません。
合格した科目は次回試験以降免除になるため、何回か分割して受験し、高卒認定資格取得を目指すことも出来ます。
高卒認定(大検)取得のメリットは?
高卒認定(大検)に合格すると、国立・市立・私立の大学、短大、専門学校などの受験資格を得ることができます。
また、進学以外にも、国家試験の受験資格や採用試験に活用することもできます。
「高卒認定(大検)」とは、中卒、高校中退、不登校、定時制・通信制の高校の生徒など、あらゆる方々の将来を選択肢を広げるための1つの手段であると言えるでしょう。
高卒認定(大検)合格者の就職先
高卒認定(大検)資格を取得すれば、「応募資格 高卒以上」の求人に応募することができます。
現在では高卒認定(大検)の知名度が上がり、採用時に「高卒認定」と「高卒」に差をつける企業はほとんどありません。
しかし先述したように、「高卒資格」と「高卒認定」は全く別の物であるため、そこはしっかり押さえた上で採用面接に臨みましょう。
また、高卒認定(大検)資格を高卒と同等とみなしている採用試験、国家資格は数多くあります。
文部科学省の公式サイトに掲載されているので、ご確認下さい。
参照:高等学校卒業程度認定試験の合格を高等学校卒業と同等とみなしている採用試験、国家資格一覧
高卒認定(大検)の難易度や合格率は?
高卒認定の合格率は、40%前後となっています。
40%という数字を見ると難易度が高いように思われますが、これは試験科目と出題範囲が広いことが原因です。
例えば、高卒認定の合格率ではなく、1科目以上の合格率を見ると、毎年80%前後まで上がります。
したがって、勉強する時間が十分に取れない方は、
一度で8科目すべての合格を目指すのではなく、複数回に分けて集中して受験するのが得策です。
勉強期間や参考書など、勉強法をご紹介

高卒認定(大検)の勉強期間
高卒認定(大検)は、自分のペースに合わせて何度でも受験することができます。
また、中卒・高校中退など境遇も様々であるため、一概に勉強期間を定めることは難しいです。
ペースを作って効果的に勉強したい人は、通信高校が開講している「高卒認定資格コース」がオススメです。
以下に、高卒認定資格コースを開講している通信高校一覧のリンクを掲載しますので、ご確認下さい。
参照:通信制高校ナビ
高卒認定(大検)の勉強法やオススメ参考書
高卒認定(大検)の勉強をする際に真っ先に思いつくのは、書店に並ぶ高校生向けの参考書を使って勉強することだと思います。
芸能人やアスリートは家庭教師をつけて高卒認定(大検)の勉強をしていたり、金銭的に余裕があれば学校や通信講座を受講することもできたりしますが、
一番費用が抑えられる方法はやはり独学です。
しかしここで1つ気を付けたいのは、「高校生向け参考書の多くは、大学受験を見据えて作られている」ということです。
高卒認定取得後に大学受験を見据えている方は効果的かもしれませんが、高卒認定では市販の参考書レベルの問題はあまり出ません。
参考書を選ぶときは、比較的やさしいものを選ぶようにしましょう。
オススメの参考書は、「高校とってもやさしいシリーズ」(旺文社)です。
また、高卒認定(大検)用の参考書もあります。
有名なのは、「高卒認定ワークブック」(J-出版)です。
過去問から勉強する
高卒認定(大検)受検において、過去問研究は必須です。
なぜなら、高卒認定(大検)の出題内容や形式には、科目ごとにほぼ一定のパターンがあるからです。
過去問は最低でも3年間分以上は取り組んで、傾向を掴んでおきましょう。
文部科学省 公式サイトには、昨年度分の過去問題と解答が掲載されています。
参照:平成29年度第2回高等学校卒業程度認定試験問題
しかし、公式サイトに掲載されている過去問には解説はありません。
過去問をしっかり勉強するためには、過去問題集を活用しましょう。
おすすめの過去問題集は、「高卒認定過去問題集」(声の教育社)です。
こちらは、Amazon売れ筋ランキングでも上位にランクインしています。
高卒認定(大検)の費用や日程、試験会場
高卒認定(大検)の費用
高卒認定(大検)の受験料は、受験する科目数によって異なります。
7~9科目受験の場合 8,500円
4~6科目受験の場合 6,500円
1~3科目受験の場合 4,500円
高卒認定(大検)の金銭的支援
また、金銭的な理由で高卒認定(大検)の受験が難しい場合、理由によっては支援金を受け取れる場合があります。
厚生労働省が行っている「高等学校卒業程度認定試験合格支援事業」を確認してみて下さい。
高卒認定(大検)の日程
高卒認定(大検)は1年間に2回(合計4回)実施されます。
参考までに、2018年度の試験日程は、以下の通りです。
①2018年8月2日(木)、3日(金)
②2018年11月10日(土)、11日(日)
高卒認定(大検)の試験会場
高卒認定(大検)の試験会場は、各都道府県に1つずつ、計47箇所あります。
現住所や本籍地に関わらず、受験したい会場を選ぶことができます。
高卒認定(大検)の合格発表
高卒認定(大検)の合格発表は、試験日からおよそ1ヶ月後です。
大学出願や就職試験を控えている方は、スケジュールを確認して下さい。