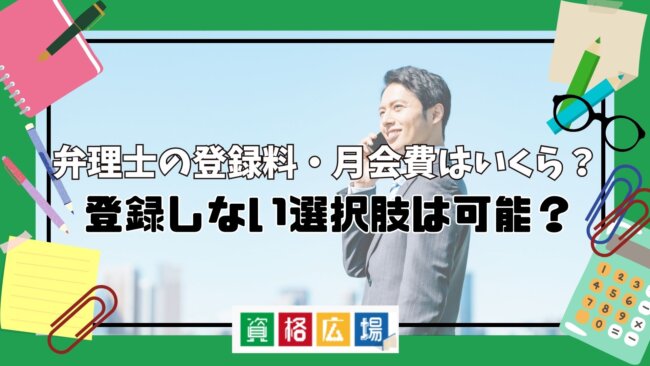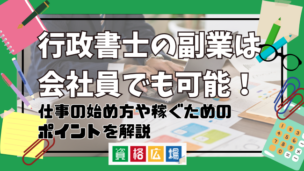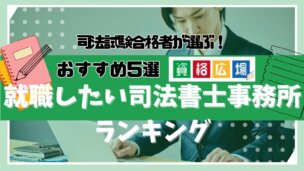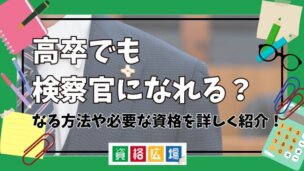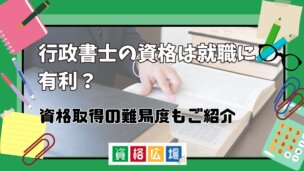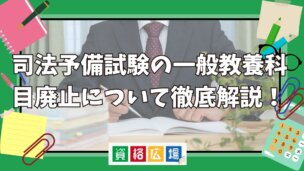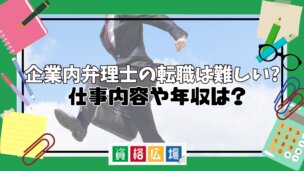弁護士や公認会計士といった士業には、それぞれ士業の業務を管理したり問題に対処したりする会合があります。
弁理士も例外ではなく「弁理士会」という会合が存在し、弁理士業務を行うにはこの弁理士会に登録をしなければなりません。
資格を取得したら弁理士協会に登録することが一般的ですが、登録しないという選択肢はあるのでしょうか?
また、弁理士の登録料や月の会費、弁理士の登録抹消や再登録に関しても併せて解説していきますので、興味のある方は是非最後までご覧ください。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
弁理士登録とは?登録しないこともできる?
弁理士の資格を取得した後、登録が必要であるという話を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、弁理士登録は必須事項になるのでしょうか?
また、登録せずに弁理士の仕事をすることはできるのでしょうか?
弁理士として正式に働くためには登録は必須
弁理士として働くためには、資格試験に合格した後、実務修習を終えて弁理士会に登録する必要があります。
登録をせずに弁理士業務を行ってしまうと、罰金などの他に弁理士資格をはく奪されることがあります。
特許申請などの独占業務を行う際には、必ず弁理士登録を済ませるようにしましょう。
弁理士登録をあえて行わないことがある?
弁理士登録を行わなければ弁理士として働くことはできませんが、例えば一般企業の知財部などに勤めている方の中には、あえて登録をしない方もいます。
知的財産に関わる知識を必要としているだけで、弁理士として働く権利は必要ないという場合は登録をせず、その知識を生かして活動していることがあります。
「せっかく資格を取得したのであれば、弁理士登録した方がメリットがあるのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、実は弁理士会への登録には多額の費用が必要であり、さらに実務修習で多くの時間を使います。
弁理士として働かない場合には大きな負担となるので、意図的に弁理士登録をしていないという方も多くいます。
弁理士登録の方法
弁理士登録の方法について解説していきます。
登録に必要な書類が非常に多く面倒に感じるかもしれませんが、弁理士として働く第一歩だと考えてしっかりチェックしながら用意しましょう。
弁理士登録に必要な書類
弁理士会に提出する書類は以下のようになります。
- 1.弁理士登録申請書・届出書
- 2.誓約書
- 3.勤務証明書
- 4.履歴書(顔写真も必要)
- 5.登録後の会費納付方法について
- 6.銀行振込等の写し貼付(振込の場合のみ)
- 7.登録免許税納付証明書
- 8.住民票
- 9.弁理士となる資格を証する書面
- 10.身分証明書(本籍地の市区町村で発行したもの)
すべての申請書類には同じ印鑑を使用しなければなりません。
認印(みとめいん・届出をしていない個人の判子)も使用できますが、シャチハタといったスタンプ式のものは不可です。
住民票や身分証明書などは、発効から3ヶ月以内の物を提出する必要があります。
提出書類の詳細は、日本弁理士会のホームページをご確認ください。
書類は弁理士会に持参、郵送、どちらでもOK
弁理士会へ提出する書類は、東京都千代田区にある弁理士会に持参しても良いですし、郵送することも許可されています。
それぞれの方法について、住所や注意点をまとめました。
持参の場合
持参の場合は、書類に使用したものと同じ印鑑を持って行ってください。
書類に不備があった場合、その場で訂正することができます。
持参する際の日本弁理士会の受付時間や場所は以下の通りです。
受付曜日:月曜日~金曜日
受付時間:午前9時~午後5時
受付場所:〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビル14階
日本弁理士会の事務所の受付で弁理士登録の申請をしに来た旨を伝えれば、会員課担当者が書類を点検し、問題なければ受理してくれます。
なお、申請書類の点検に15分~20分程度かかりますので、時間に余裕を持ったうえで向かってください。
郵送の場合
郵送の場合は封筒表書きに「弁理士登録申請書類」と朱書きをして、以下の住所に必ず書留で郵送してください。
〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-4-2
日本弁理士会 会員課
持参の場合と場所が異なるので、送り間違えないように気を付けてください。
また、費用の入金を確認するため、振込の日付・金額・振込人名が分かるもの(振込用紙のコピー等)または「銀行振込等の写し貼付」を申請書類に同封してください。
条件が少しややこしいので、もっと詳しく知りたい方は弁理士登録申請の手引きをご参照ください。
弁理士登録の登録料や月の会費はどのくらい?
弁理士登録に必要な登録料や、月ごとに支払う会費をご紹介していきます。
弁理士の資格を取得した後にも、弁理士として働くためには多額の費用が必要になります。
弁理士登録の際に必要な費用
弁理士登録を行う際に必要な費用は以下のようになります。
| 名目 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税 | 60,000円 |
| 登録料 | 35,800円 |
| 月会費 | 15,000円 |
登録免許税とは、登録免許税法に基づいて技能証明について課せられる国税で、弁理士の場合は60,000円です。
また、弁理士の登録料は35,800円で、月会費は15,000円です。
登録する際には初月の会費も同時に支払う必要があるため、合計で50,800円となります。
登録免許税も合算すると110,800円もの額がかかり、かなりの大金であることが分かります。
言うまでもないですが、月会費15,000円は毎月必要で、ランニングコストとなることに注意しましょう。
実務修習費用も合わせるとさらに高額になる
実務修習とは、弁理士に必要な知識を深めるべく、弁理士として働く前に受講必須となっている研修のことです。
映像講義のeラーニングと、実際に修習生が集まって座学で行われる集合研修があり、年末から翌年の年度始めまで半年近くにわたって開かれます。
実務修習を受けるには受講料118,000円が必要で、上記した登録料や会費を併せると20万円以上かかります。
所属している企業や弁理士事務所が費用を負担してくれる場合がありますが、どこにも属さないまま独立開業したいと考えている方の場合は自己負担になり、かなりの出費となるでしょう。
弁理士登録を行うメリットとは?
弁理士登録には書類の用意・提出といった手間がかかったり、多額の登録料が必要になったりすることが難点となりますが、それに見合うメリットはあるのでしょうか?
1番のメリットは弁理士業務が行えること
弁理士登録の1番のメリットは、やはり弁理士として業務を行うことを認められることでしょう。
弁理士の年収は一般サラリーマンと比較しても高い水準になっていますので、真面目に働けば登録料や会費を回収することは十分可能です。
また、弁理士会主催の弁理士同士の交流会や、ベテラン弁理士による勉強会などに参加できることもメリットです。
会合に参加すれば、人脈が広がったり、仕事をもらえるチャンスが巡ってきたりするので、特に独立して活動している人には大きな魅力となるでしょう。
弁理士の年収については、以下の記事をご覧ください。
弁理士に案件を紹介してくれることがある
弁理士登録をしておくことで、日本弁理士会から直接仕事を紹介してもらえる場合があります。
弁理士会に個人や企業から相談があった際に、適任となる弁理士を選んでマッチングしてくれるサービスがあるので、そこで選ばれれば仕事が斡旋されます。
相談費用や報酬は弁理士側が自由に決められ、売り上げアップに期待ができるため、登録しておいて損することはないでしょう。
ただし、紹介を受けた方も弁理士も契約の締結を義務づけられてはいないので、仕事を紹介されたからといって絶対に稼げるとは限らない点に留意してください。
弁理士登録が抹消されることはある?再登録の仕方は?
「弁理士会に一度登録ができれば一生安泰」という訳ではなく、登録後もいくつかのルールによって登録が抹消されることがあります。
ここでは、登録が抹消される条件や再登録の方法などを解説していきます。
登録が抹消されるのはどんな時?
日本弁理士会では、登録を抹消した弁理士の名前をホームページで公開しています。
あたり前ですが、特許申請書類を偽造したり、代理人手数料などを横領したり、特許庁に手数料を納付しなかったりと、弁理士法に背いてしまうと厳しい処分と共に登録が抹消されてしまいます。
しかし、ホームページで公開している全員が不祥事を起こして抹消されたというわけではありません。
家庭の事情や高齢になり引退して弁理士を辞めることになった場合や、弁理士として働くのではなく一般企業に転職した場合など、自ら依頼したことで登録抹消される「申請抹消」をして名前が載っていることもあります。
再登録することはできるの?
弁理士の登録を抹消した後に再び弁理士登録をする場合、特別なことは何もなく、もう一度書類を提出して登録料を払うことで再登録が完了します。
しかし、登録料の滞納や弁理士として悪行を働き、弁理士法で処罰を受け登録抹消された場合は、再登録が不可能になっていることがあります。
弁理士会への登録料・月会費まとめ
今回この記事では、弁理士の登録料や月の会費、登録しない選択肢について解説してきました。
登録料と初月の会費と合わせて50,800円、加えて登録免許税が60,000円必要になるため、弁理士登録するにはトータルで110,800円が初期費用としてかかります。
さらに、弁理士として活動するには実務修習を終えていなくてはならず、この実務修習にも別途118,000円が必要です。
また、弁理士にはならずに一般企業の知財部などで働く場合は、弁理士登録をしなくても問題ありません。
しかし弁理士登録をしていないにもかかわらず弁理士の業務を行うのは違法行為ですので、自分にとって登録は必須か、登録した方がメリットがあるのか、よく検討しましょう。