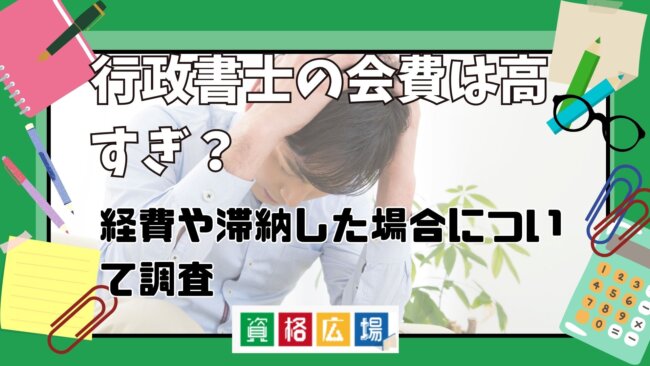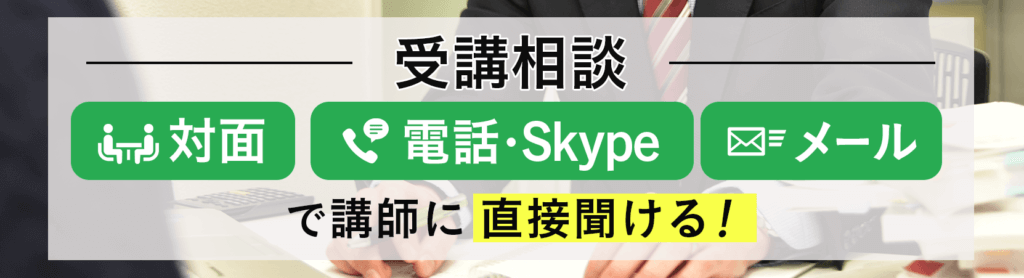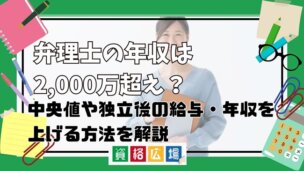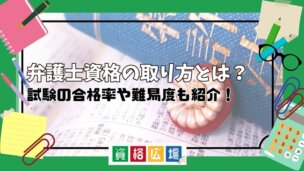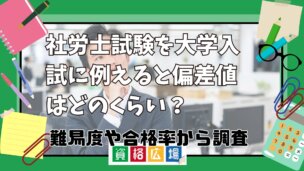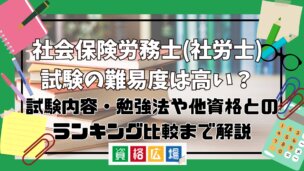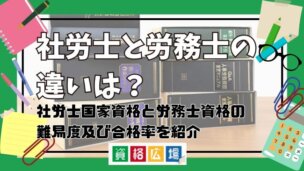行政書士へ登録する際には入会金を支払う必要があり、その後も会費を支払わなければなりません。
行政書士の会費は「高い」と言われることもあり、実際に行政書士としての開業を躊躇している人もいるでしょう。
こちらの記事では、行政書士の会費の仕組みや金額、滞納するとどうなるのか等を解説していきます。
行政書士試験に合格後、行政書士の登録を迷っている人にとって役立つ内容となっているので、ぜひ参考にしてください。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
行政書士試験におすすめの予備校・通信講座TOP3
行政書士の会費は高すぎる?
行政書士として開業する場合、開業する事務所を管轄する都道府県行政書士会に加入しなければなりません。
つまり、試験に合格するだけでは行政書士として開業することはできず、都道府県行政書士会への加入と、日本行政書士会連合会への登録が必要となります。
行政書士の会費はいくら?
東京都の行政書士会の会費は月6,000円となっており、年間で換算すると72,000円です。
会費は各都道府県で差がありますが、年換算すると60,000~80,000円程度となります。
会費は、事務所を運営し続ける限り払い続ける必要がある「ランニングコスト」です。
稼いでいるか、稼げていないかに関係なく支払う必要があるため、開業したばかりで稼ぎが少ない時期だと、負担に感じるでしょう。
ちなみに、行政書士になるためには、「行政書士会によって定められた登録手続きを行う」ことが法律で定められています。
そのため、単なる合格者で、登録を受けずに行政書士の仕事をすることは許されません。
行政書士会には「支部」もある
行政書士会には、都道府県単位よりも小さく、県内のエリアを単位とする「支部」が存在します。
行政書士に登録すると支部には強制加入となり、支部に対しても会費を支払う必要があります。
支部会費は支部ごとに異なりますが、年会費として5,000~10,000円が相場です。
このように、県の行政書士だけでなく、支部に対しても会費が発生する点は注意しましょう。
他の士業と比較すると?
行政書士に限らず、士業として開業する場合は、入会金や会費を支払う必要があります。
行政書士と他の士業の会費を比較すると、下記のようになります。
| 行政書士 | 7~8万円 |
|---|---|
| 弁護士 | 50~60万円 |
| 司法書士 | 20~30万円 |
| 税理士 | 10~15万円 |
| 社会保険労務士 | 42,000円(勤務型) 96,000円(開業型) |
行政書士の会費は、他の士業と比較すると「やや安め」と言えます。
とはいえ、年間7〜8万円を継続して支払うのは、決して軽くはない負担です。
詳しくは後述しますが、会費を滞納すると多くのペナルティを受けることになるため、気を付けましょう。
行政書士登録には登録料や年会費等出費が多い
行政書士の開業を進める際には、加入や登録に必要となる「一時的な出費」と、会費の「継続的な出費」が発生します。
行政書士登録にあたり、様々な出費が発生するため、登録前に「いくら必要になるのか」知っておくことが重要です。
行政書士登録で必要な初期費用
東京都行政書士会の例を紹介すると、登録の際に必要となる出費は下記の通りです。
| 入会金 | 200,000円 |
|---|---|
| 登録免許税 | 30,000円 |
| 登録手数料 | 25,000円 |
| 東京都行政書士会会費3ヶ月分 | 18,000円 |
| 東京行政書士政治連盟会費3ヶ月分(任意) | 3,000円 |
| バッジ(任意) | 3,000円 |
東京行政書士政治連盟会費とバッジ代を支払わない場合でも、開業の初期費用として273,000円が求められます。
なお、各都道府県行政書士会で入会金や会費は異なります。(ちなみに、大阪と神奈川の入会金は250,000円、最安は山形の100,000円)
他にも、もし事務所を賃貸する場合は敷金や礼金、さらに備品代などが発生するため、出費が嵩みます。
このように、個人差はあるものの、行政書士の開業にあたっては「50〜100万円程度」は用意する必要があると言えます。
行政書士登録で必要な書類
行政書士の登録にあたり、提出する書類も多くあります。
- 行政書士登録申請書
- 履歴書
- 誓約書
- 東京都行政書士会入会届
- 東京行政書士政治連盟加入届(任意)
- 事務所写真
- 行政書士となる資格を証する書面
- 本籍記載のある住民票
- 身分証明書
- 戸籍抄本
- 顔写真5枚(縦3cm x 横2.5cm)
- 事務所の使用権を証する書面
特に、戸籍抄本は入手できるまでに時間がかかるケースがあるため、早い段階で取り寄せることをおすすめします。
行政書士の会費を払わなければならない理由とは?
「高い会費を支払うのは嫌」と感じる人は多いですが、会費を支払わないと行政書士として仕事をすることができません。
また、支払っている会費は行政書士の運営に使われているため、決して無駄金ではありません。
実際に行政書士たちが支払う会費はどのように使われているのか、支払わなければならない理由についてまとめてみました。
会報誌送付やセミナー開催に使われる
行政書士会は、徴収した会費を使って行政書士会の運営を行っています。
会報誌の送付やセミナー開催など、行政書士事務所を運営する上で役立つものも多くあるため、有効活用すると良いでしょう。
特に、会報誌では法改正の内容や実務を想定したマニュアルなどを記載しているため、直接仕事に役立つ便利な資料です。
また、セミナーに参加すれば、実務のポイントなどを学べる上に、行政書士同士の交流を深められるメリットがあります。
他にも、様々な有益な情報を提供してくれるため、海保石を熟読し、セミナーに参加すればスキルアップに役立つでしょう。
交流会やイベントに使われる
行政書士会員向けの交流会やイベントなども、徴収した会費を使って開催されています。
このような交流会やイベントは、様々な業界の人と会える場で、人脈を広げられる貴重な機会です。
特に、独立開業している人にとって、人脈は大きな財産となるため、参加して損することはありません。
逆に、会報誌を読まず、セミナーや交流会にも参加しないと、会費を捨てているようなものです。
行政書士としてスキルアップし、仕事を受けるチャンスを広げるためにも、行政書士会からの情報はチェックすると良いでしょう。
行政書士の登録料や会費は経費で落ちる?
高額な行政書士登録費用や会費ですが、これらの出費は経費で落ちます。
国税庁のホームページによると、経費に該当するのは下記の通りです。
- 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用
- その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用
端的に言うと、「業務に関連する出費は経費にあたる」ことになるため、当然のことながら行政書士の登録料や会費は経費に該当します。
なお、やや話がそれますが、開業する際には開業届と共に「青色申告承認申請書」を提出して青白申告の適用を受けるのがおすすめです。
これにより、年間最大65万円を収入から控除できるため、経費と併せて税金負担を軽減する効果的な手段となるためです。
行政書士の会費を支払うタイミングは?滞納したらどうなる?
行政書士の会費を支払うタイミングや支払い方法は、各都道府県によって異なります。
また、高額な会費を支払い続けるのは抵抗がある、という人もいると思われますが、結論として会費を滞納するのはおすすめしません。
行政書士の会費を支払うタイミングや、滞納するとどうなるのか、詳しく見ていきましょう。
行政書士の会費を支払うタイミング
行政書士の会費を支払うタイミングや支払い方法も、都道府県ごとに違いがあります。
そのため、開業を予定している都道府県の行政書士会のホームページを見るか、問い合わせて確認すると良いでしょう。
例としていくつかの都道府県での会費の支払い方について下記にてまとめました。
| 北海道 | 6,000円/月を3ヶ月分まとめて支払う |
|---|---|
| 秋田県 | 会費4,650円/月を年1回か年2回かの支払い方法を選択 |
| 東京都 | 6,000円/月を3ヶ月分まとめて支払う |
| 兵庫県 | 会費6,000円/月を半年払い |
| 宮崎県 | 4,400円/月を3ヶ月分まとめて支払う |
基本的に、会費は口座から引き落とされるため、特段振込をする必要はありません。
しかし、都道府県によっては自ら納付する必要があるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
行政書士の会費を滞納するとどうなる?
行政書士の会費を滞納すると、行政書士会が提供するセミナーに参加できなくなる他、会報誌が送付されなくなる等の不利益を被ります。
会費を滞納すると、具体的には行政書士会から「会員資格の停止」が行われ、行政書士会の提供する研修会やセミナーに参加できなくなります。
会員資格の停止を受け、その後も滞納を続けると、行政書士会から「廃業の勧告」を受け、行政書士としての信用を失います。
行政書士資格を剥奪されるわけではありませんが、信用が失墜することから、廃業の勧告は「実質的に廃業と同じ」と捉えるべきです。
つまり、会費を滞納するとろくなことが無いため、しっかりと納めることが大切です。
また、支部会費を滞納した場合も、行政書士会と同様に研修会やセミナーに参加できなくなるなど、業務に大きな支障が出るペナルティを受けます。
行政書士の登録を迷っている方へ
行政書士試験には合格したものの、入会金や会費の支払いに対して抵抗を感じている方も多いでしょう。
実際、会費の負担は軽くないため、「行政書士合格者として、別の仕事に就いた方が良いかも」と感じてしまうのは仕方のないことです。
しかし、行政書士は副業規模でも開業できるため、登録するべきか迷っている方は登録してみることをおすすめします。
実際に「週末起業」という形で、本業の傍らで行政書士として開業している人もいます。
週末起業であれば、本業による収入を得つつ、行政書士としての実務を行いながら貴重な経験を積むことも可能です。
もちろん、週末起業であっても会報誌が送られ、セミナーや勉強会にも参加できるため、有益な情報を得ることができます。
入会金や会費の支払いは発生しますが、リスクを抑えて行政書士として開業できるため、週末起業も一つの方法として検討すると良いでしょう。
行政書士を目指すならアガルートで!

今回は行政書士試験に合格した後の登録についてご紹介しましたが、もしこれから試験に挑戦しようと考えている方へ向けておすすめの通信講座をご紹介します。
独学よりも効率的に学習を進めることによって短期間で結果を出すことが出来るため、ぜひ最後までご覧ください!
元大手予備校のカリスマ講師による講義
アガルートの行政書士試験講座で教鞭を執るのは、過去に大手予備校のLECで講座を担当していた豊村慶太講師です。
17年以上の指導の中で6,000人以上の受験生をサポートしており、本試験に合格するための最良の勉強法を熟知しています。
また講義で使用するフルカラーテキストは講師が自ら作成しており、重要箇所がすぐに分かる視認性の良さや条文等の紐づけによる効率性などメリットだらけです。
初学者の方でも安定して合格へ向かっていけるのがアガルートの特徴となっています!
多くの面で実績を残す
先述したような点から教材の質が非常に高いアガルートですが、令和4年度の行政書士試験では97.8%もの問題をカバーしていました。
アガルートのカリキュラムをしっかりと網羅できれば着実な実力が備わるということであり、他社の通信講座にはない大きな魅力です。
またアガルートは合格率でも大きな実績を残しており、2023年度の試験では56.11%という驚異の実績を残しています。
これは全国平均合格率の4.01倍もの結果であり、アガルートだからこそ実現できたとする方も多くいらっしゃいました。
まずは受講相談
無制限の質問対応や追加講義などが充実しており、他の通信講座と比較しても受講生サポートが非常に手厚くなっています。
合格特典による最大で全額返金も非常に特徴的で、タイミングによってはお得に講座を受講できる割引情報も公開されています。
少しでもアガルートの行政書士試験講座が気になった方は、ぜひこちらから公式サイトをご覧ください!
行政書士の会費はいくら?使用用途や滞納した場合まとめ
行政書士の会費は都道府県ごとに異なりますが、決して安くないため、負担に感じてしまうこともあるでしょう。
「会費を払いたくないから」といって滞納すると、会員資格の停止など不利益を被るため、滞納は避けるべきです。
また、会費の他にも開業にあたって様々な出費が発生するため、開業を検討している方は資金計画を入念に練ると良いでしょう。