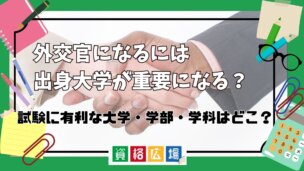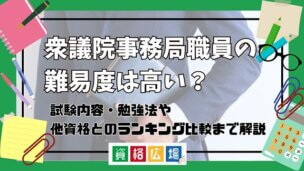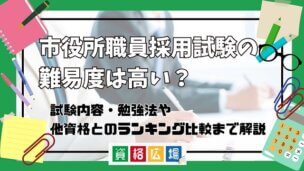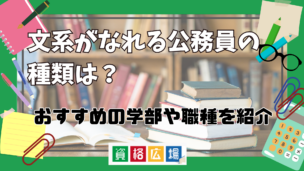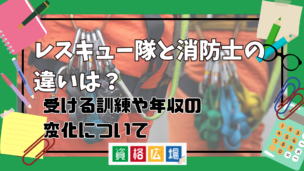社会的に問題になっている不景気や物価高騰などで不安な世の中で、倒産するリスクがなく将来的にも安定している公務員は人気の職業です。
その中でも、勤務時間が一定でワークライフバランスが整っている市役所職員になりたい、興味があるといった方は多いです。
しかし、市役所職員になるには、試験内容をしっかり理解し、入念に対策する必要があります。
本記事では、市役所職員を目指す方に向けて、市役所職員になるにはどうすればよいか、試験難易度だけでなく、市役所職員の仕事内容やメリットなど詳しく解説します。
市役所職員になるには何から対策すればよいか分からないと悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
この記事で分かること
- 市役所職員になるにはどうすればよいか
- 市役所職員の試験の難易度
- 市役所職員になるメリット
公務員試験の難易度は高い?他資格との難しさランキング比較や合格率・偏差値・勉強時間の目安を解説
公務員講座ならアガルート!

公務員試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
アガルートでは、「地方上級」「国会一般職」「専門職」「裁判官」など、さまざまな公務員試験に対応したカリキュラムが用意されています。
通勤や家事の合間など隙間時間も活用することができるので、効率的に学習を進めることができる講座です。
市役所の公務員試験の難易度
市役所職員の倍率は自治体によって異なりますが、どのくらいでしょうか。
採用試験で重視するポイントは自治体によって異なり、筆記試験の最低ラインをクリアすれば合格できる自治体もあれば、筆記試験倍率が高いが面接倍率はそれほど高くない自治体もあります。
市役所職員の倍率は5.2倍
総務省が発表する地方公務員における働き方改革に係る状況によると、令和4年度の地方公務員試験受験者数は438,651人でした。
合格者数は84,804人だったため、倍率は5.2倍です。
技術職の公務員採用は競争が激しい
一方で、技術職の公務員採用は競争が激しく、一部自治体は先行枠を設けて早期採用を行っている傾向にあるといわれています。
近年では技術職の応募者数が採用予定人数よりも少ない自治体も増えていますが、合格には公務員としての適性や面接での評価も考慮されるため、油断は禁物です。
予定数に満たなくても全員が合格するわけではなく、面接対策もかなり重要なポイントとなります。
教養科目と専門科目が課せられる場合が多く、しっかりとした筆記対策も必要となるでしょう。
市役所の公務員試験の倍率は高い?難易度・試験内容・試験日程も解説
公務員試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!
公務員試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。
合格者には受講費全額返金orお祝い金3万円の特典もあるのでモチベーションの維持も期待できます!
最短ルートで合格が目指せる!
アガルート公式HPはこちら
市役所の公務員試験の概要
市役所職員採用試験の概要は、自治体によって異なります。
希望する自治体の募集要項をチェックしましょう。
試験日に向けて、取りこぼしが無いように学習や準備を進めてください。
市役所の公務員試験の受験日程
市役所職員の試験日程は、自治体によって異なります。
令和5年度の東京都職員 1類A採用の受験日程は、以下の通りです。
| 受付期間 | 3月28日(火曜日)午前10時00分から4月4日(火曜日)午後3時00分まで(受信有効) |
|---|---|
| 受験票発行日 | 4月21日(金曜日) |
| 第1次試験日 | 5月14日 |
| 第1次試験合格発表日 | 6月15日 |
| 第2次試験日 | 7月4日(火曜日)もしくは7月5日(水曜日)のうち、指定された1日 |
| 最終合格発表日 | 7月27日(木曜日) |
日程が被らなければ、他の自治体との併願も可能です。
市役所の公務員試験の受験資格
市役所役員になるには、学歴などは関係ありませんが、多くの自治体で年齢制限が設けられています。
高卒程度の試験では21歳程度、大卒程度の試験では30歳程度までが受験できる年齢です。
また、経験者採用の場合は受験できる年齢も上がりますが、40歳程度と定めている自治体が多くあります。
地方上級公務員とは?仕事内容や職種・試験の難易度(倍率)について解説
市役所の公務員試験が難しいと言われる理由
市役所の職員採用試験が難しいと言われる理由をまとめました。
- 採用人数が決まっている
- 試験の範囲が広い
- 人物重視の面接もある
- 人気が高く競争が激しい
理由①採用人数が決まっている
公務員として働く市役所の職員は、採用人数が決まっています。
試験結果の上位順に採用されるため、一定以上のレベルが求められます。
応募者がどれだけ多くても、採用人数枠が増えることもありません。
合格基準点をクリアしたからといって、必ずしも採用されるわけではないのです。
理由②試験の範囲が広い
市役所職員に限らず公務員採用試験の出題範囲は広いです。
さらに、その行政ならではの問題や現状についても理解が必要でしょう。
基礎的な学問の知識だけでは、採用に結びつきません。
まんべんなく勉強をし、地域について理解することも重要です。
理由③人物重視の面接もある
市役所職員採用試験では、人物重視の面接も実施されます。
筆記試験が満点でも、人物試験で失敗すると採用されません。
面接はコミュニケーション能力や判断力、臨機応変な対応力が試される試験です。
「この人と働きたい」と思ってもらえるように、効率的な対策をしましょう。
理由④人気が高く競争が激しい
公務員試験の競争が激しいことは、職種ならではの特徴です。
市役所職員を希望する人も多くいるでしょう。
地域に貢献したい、安定した仕事をしたいなど、志望理由は様々です。
競争に勝ち抜けるように、採用試験の対策を練ってください。
市役所の公務員試験の難易度を他試験とランキングで比較
| 区分 | 採用倍率 |
|---|---|
| 市役所職員 | 5.2倍 |
| 一般行政事務 | 3.8倍 |
| 学校事務 | 5.8倍 |
| 警察事務 | 9.2倍 |
市役所職員採用試験の難易度は、他試験と比べても易しくありません。
採用倍率は5倍前後が目安です。
ただし、自治体によっては採用試験の難易度が下がる地域もあります。
市役所の公務員試験の科目
市役所職員になるためには、面接とは別に筆記試験を受験し、合格しなければなりません。
筆記試験では、主に教養試験・基礎能力試験・論作文試験が課されます。
事務系職員の試験内容と技術系職員の試験内容を解説していきます。
事務系職員の試験内容
| 時間 | 試験内容 | |
|---|---|---|
| 教養試験 | 2時間10分 | 一般教養についての五肢択一式(40題必須解答) |
| 専門試験 | 2時間30分 | 高度な専門知識についての記述式(5題中1題選択解答 |
| 論文 | 1時間30分 | 課題式(1題必須解答) |
東京都職員の事務系職員の試験でみてみると、第1次試験(教養試験・専門試験)と論文、第2次試験(口述試験)となっています。
第2次試験は口述試験となり、「職務に関連する専門知識及び人物についての個別面接」を行います。
技術系職員の試験内容
| 時間 | 試験内容 | |
|---|---|---|
| 教養試験 | 2時間30分 | 一般教養についての五肢択一式(知能分野)27題必須解答(知識分野)社会事情:3題必須解答その他:14題中10題選択解答 |
| 専門試験 | 2時間30分 | 高度な専門知識についての記述式(2題中1題選択解答) |
| 論文 | 1時間30分 | 課題式(1題必須解答) |
東京都職員の技術系職員の試験では、高校までに学んだ一般教養問題が出題され、専門試験は職種によって出題される問題が異なります。
第2次試験も口述試験となり、内容は事務系職員と同様に「職務に関連する専門知識及び人物についての個別面接」となっています。
地方公務員試験の難易度は高い?他資格とのランキング比較や合格率・偏差値・勉強時間の目安について解説
難易度の高い市役所の公務員試験に合格するポイント
市役所職員採用試験合格のためには、以下のポイントに気を付けましょう。
- 配点の多い科目の勉強を優先する
- 早めに勉強スケジュールを計画する
- 面接対策にも力を入れる
- 自治体の情報や現状を把握する
- アピールできる資格を取る
下記では、市役所の公務員試験に合格するための勉強のコツを紹介します。
働きながら公務員試験を受けるのは無理?辛い?受かるための勉強法・合格のポイントを解説
ポイント①配点の多い科目の勉強を優先する
公務員試験は配点の多い科目を優先的に勉強してください。
特に以下は力を入れたい科目です。
- 数的処理
- 文章理解
- 社会科学
- 憲法
- 民法
- 経済原論
筆記試験は6割以上の点数を取らなければ、合格は難しいです。
初学者は、数的処理の勉強から始めることがおすすめです。
ポイント②早めに勉強スケジュールを計画する
勉強のスケジュールを早めに立ててください。
試験日までの学習計画を立てることで、進捗管理がスムーズに行えます。
余裕を持って計画しておけば、勉強できなかった日もカバーしやすいです。
採用試験日に向けて準備するためにも、早めに勉強スケジュールを計画しましょう。
ポイント③面接対策にも力を入れる
市役所職員採用試験では個別面談が行われます。
事前に、志望動機と自己PRを記載した面接カードを提出します。
面接では、自分をうまくアピールできるように徹底的な自己分析が必要です。
話し方や態度についても、十分に注意してください。
服装や身だしなみに不安がある人は、第三者にチェックしてもらいましょう。
ポイント④自治体の情報や現状を把握する
市役所職員採用試験を受ける自治体の現状を把握しましょう。
統計やニュースから情報を集め、問題と改善点を探してください。
自分ならこの自治体でどう働くか、なるべく詳しく考えられるとベストです。
公務員試験は情報をどう集めるかが、合格の鍵となります。
ポイント⑤アピールできる資格を取る
事務系で最も必要とされるのはパソコンのスキルや簿記、TOEICの資格です。
市役所でもパソコンでの作業はとても多く、情報処理やエクセル等のパソコンスキルも必須となります。資格とまではいかずとも、使いこなせる程度にはなっておく必要があるでしょう。
税務や決算書類のある業務に就いた場合は日商簿記2級や全経簿記1級があれば、スムーズに業務をこなすことも出来、大変役立ちますし、取得推奨する自治体もあるので資格取得をおすすめします。
TOEIC、TOEFL、英検は英語を使う業務も多いので、市役所職員でなくても取得しておく方が有利でしょう。採用試験の際、資格加点になる自治体も多いです。
その他、民法・農地法等に強くなる「宅建」は意外と難易度が低く取得しやすいですし、保健、税金等の「ファイナンシャルプランナー」の資格も難易度が高くないので取得しておくと役立つでしょう。
市役所職員採用試験のそれぞれの対策方法
ここでは、市役所の公務員試験に合格するための以下のそれぞれの対策方法について紹介します。
- 教養試験
- 専門試験
- 論文試験
- 集団討論
- 面接試験
教養試験の対策
教養試験の試験範囲はかなり広く、知識に関する分野は高校時代の学習に類似しているため比較的学びやすいですが、知能に関する分野はやや難しいといわれています。
特に、判断推理、数的推理、資料解釈の三つの領域は、コツを掴まないと解答に時間を要することがあるでしょう。
独学で学ぶ場合、教養試験に関しては学習計画を立てられない人も多いので、通信講座や予備校などを利用するのが一般的です。
また高得点を狙うのではなく、60%以上の得点を目指して焦点を絞った学習を行うことで合格に近づけるといわれています。
専門試験の対策
専門試験では、大学卒業レベルの知識が求められます。
所属する学部や学科によって有利になる場合もありますが、初心者でも公務員になるための学習を行えば、採用試験に合格できるのであきらめる必要はありません。
もし専門試験の学習に割く時間が足りないのであれば、専門試験が実施されていない自治体を選ぶのもひとつです。
また、専門試験と教養試験の内容が重なる部分については、専門試験を先に学ぶことで教養試験でも活かせます。
論文試験の対策
論文試験は、「テーマに沿った内容であるか」「テーマに関する正確な知識を有しているか」「論理的な構成がなされているか」「誤字や待ち型表現がないか」といった基準に基づいて評価されます。
また、要点を明確かつ簡潔に表現するといった文章の可読性も評価の一部となっている傾向にあります。
自己評価は客観的に行うことが難しいですが、過去に出題されたテーマに基づいて論文を作成し、模範解答と照らし合わせることが基本的な学習方法です。
公務員試験に特化した教材を繰り返し解くことで傾向を掴んだり、添削指導を受けるのも有効です。
集団討論の対策
集団討論に備えるためにはよく取り上げられるテーマについての知識を深め、かつディスカッションの技術を習得することが重要です。
最近では人物評価が重視される傾向があり、筆記試験での成績が優れていてもコミュニケーション能力が不足しているために不合格となるケースが増えているので万全の準備が必要です。
過去に出たテーマなどを見て、可能な範囲でシミュレーションを行っておきましょう。
面接試験の対策
市役所の面接試験では一般的な質問をされる傾向にあり、よくある質問を集めた想定問答集を繰り返し練習することが大事です。
さらに本番ではより深い質問も出される可能性があるため、市役所に関する詳細な情報を公式ウェブサイトで調査しておくのも有効です。
面接では、単に人柄やコミュニケーション能力だけでなく、的確な回答を提供できるかどうかも評価されますが、何度も訓練をすることでも十分合格に近づけます。
まや面接前に面接カードを記入することが求められる場合もあるため、その書き方にも慣れておくようにしましょう。
地方公務員試験の難易度は高い?他資格とのランキング比較や合格率・偏差値・勉強時間の目安について解説
市役所の公務員試験のスケジュール
市役所の公務員試験は一般的に6月下旬から開始されるのが一般的で、試験年の前年の9月ごろから学習を進めるのがベターです。
9月~12月はまず広範囲の教養試験から始め、一般知能を中心に進めましょう。
なお専門試験がある場合は択一式の出題内容から取り組みます。
専門試験は教養試験と重複することも多いので、並行して進めると効率よく進められます。
また1~3月頃は専門科目や教養科目の一般知能の学習と並行して一般知識と論文試験をおこないます。
前年分も含め、早い時期から情報収集することで傾向もつかめるはずです。
4月~6月の試験開始までは筆記試験対策の総復習や問題演習などと合わせて、面接対策と集団討論対策をおこないます。
市役所の公務員試験専用の教材を使った対策や第三者に添削・模擬面接などをおこなってもらうのもいいでしょう。
市役所職員になる方法
市役所職員になるには、市役所の採用試験に合格しなければいけません。
市役所職員には大きく分けて事務系職員(一般行政職)と技術系職員(技術職)があり、かつ一次試験と二次試験に分かれることがほとんどです。
しかし試験の日程や試験内容については各都道府県や市役所によって異なるため、働きたい市の市役所HPをこまめにチェックするようにしましょう。
大卒が市役所職員になる方法
大卒の日々が市役所職員になるためには、大卒区分の公務員試験に合格しなければなりません。
大卒区分の人が受けられる職種は、多くあります。
自治体によって試験内容が異なるため、希望する自治体の過去問を利用するなどの対策が必要です。
高卒が市役所職員になる方法
高卒の人が市役所職員になるためには、大卒区分もしくは高卒区分の試験に合格する必要があります。
高卒区分の試験は、自治体によって採用していない場合もあるため、事前に確認しましょう。
中途採用から市役所職員になる方法
中途採用から市役所職員になるためには、経験者採用試験に合格する必要があります。
自治体によって年齢制限を設けている場合もあるため、受験可能な自治体を事前に調べておきましょう。
文系がなれる公務員にはどんな種類がある?おすすめの学部や職種を紹介
英語を使う公務員の職種はある?英語力を活かせる職種や必要な英語力のレベルを紹介
市役所職員の仕事内容
市役所職員としての仕事内容は多岐にわたりますが、大きく分けて以下の事務系職種と技術系職種に分けられます。
事務系職種
事務系職種は市民課やスポーツ振興課、まちづくり課など多様な部署で様々な業務を担当しています。
特に市民課では住民票や戸籍謄本の発行、出生届や婚姻届の受理、転入届や転出届の受理、住民基本台帳(マイナンバー)登録など、市民の生活に直結した業務を担当しています。
また市役所職員は市民の声にも対応し、公平性を保ちつつ市民に安心感や納得感を提供するため、広い視野と高いスキルが必要とされています。
技術系職種
技術系職種の市役所職員は、主に市道や公園の維持・管理に従事します。
例えば、陥没した道路に対する対応や建築物の耐震工事の設計、建築基準法の確認などが業務となります。
専門職も存在し、機械や電気、化学分野の知識を持つ職員もいます。
上記の職種は市民と直接関わりは少ないものの、市民の安心で便利な生活を維持する上で欠かせない存在であり、自らの専門知識を活かせる魅力があります。
市役所職員の給与・年収
総務省の調査によると、市役所職員(一般行政職)の平均給与月額は396,793円、平均年収は6316,842円となっています。
公務員の年収には、給与月額12か月分に加えて、民間企業のボーナスに相当する期末・勤勉手当が加算されるものとなっています。
なお、市役所職員といっても自治体や勤続年数によって給与が大きく異なるため注意が必要です。
参照:総務省
市役所職員に向いている人の特徴
ここでは、市役所職員に向いている人の特徴についてご紹介します。
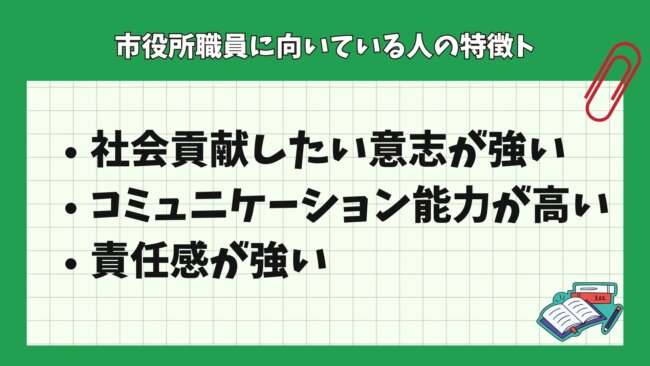
- 社会貢献したい意志が強い
- コミュニケーション能力が高い
- 責任感が強い
市役所職員は厳密にいうと営利性があまりない仕事でもあるので、サービス精神がある方や社会貢献したい意志が強い人向けだといえます。
「だれかのためになりたい」「数字よりも感謝されたい」といった気持ちを仕事で優先している人にはおすすめです。
またどの仕事でもそうですが、市役所職員はとくに様々な部署や仕事内容が多岐にわたるので、成長意欲のある方や学び続ける姿勢がある人であればやりがいを感じられるでしょう。
市役所の公務員試験対策におすすめの予備校・通信講座
市役所職員採用試験対策におすすめの予備校・通信講座を紹介します。
公務員試験に特化している講座であれば、より効率的に勉強ができますね。
同じスクールでも講座ごとに特徴があるのでチェックしましょう。
アガルートアカデミー
| 講座名 | 目指せる自治体例 |
|---|---|
| 教養+専門型ワイド対策カリキュラム | 地方上級、政令市、国家一般職、国家専門職 |
| 教養+専門型スタンダード対策カリキュラム | 地方上級、政令市、国家一般職 |
| 教養型対策カリキュラム | 市役所、国立大学法人、SPI試験 |
アガルートアカデミーは、地方公務員向けの対策講座も豊富です。
また近年の人物重視の傾向を受けて、二次試験、面接対策を手厚くサポートするようなカリキュラムへとリニューアルをおこないました。
独学では鬼門となる面接対策もカリキュラム内に含まれており、かつ回数無制限で講座を受けられるので、自分が納得できるまで対策したい人におすすめです。
令和5年度の公務員試験の内定者数は210名となっており、年々アガルート内の内定者数は増えつつあります。
アガルートの公務員試験講座の評判・口コミは?料金費用や合格率・講師やテキストの評価を解説
質問体制が整っているアガルートアカデミーは、これから公務員を目指す人にもぴったりです。
2025年合格目標カリキュラム アウトレットセール(20%OFF)

全ての方を対象に、2025年合格目標の対象講座の講座を20%OFFで販売しています。
さらに、対象者の方は最大20%OFFになる割引制度も併用してご利用できます。
| セール名 | 2025年合格目標アウトレットセール20%OFF |
|---|---|
| 割引額 | 20%OFF |
| 期間 | 2025年2月16日(日)まで |
| 対象講座 |
※定期カウンセリングはセール対象外です。 |
| キャンペーン詳細 | https://www.agaroot.jp/komuin/cp_sale/ |
LEC東京リーガルマインド

LEC東京リーガルマインドは、公務員試験の種類が豊富です。地方公務員を目指す人も勉強しやすい講座と言えます。
LEC公務員試験講座の評判・口コミは?料金費用や合格率・講師やテキストの評価を解説
市役所向けの公開模試も定期的に行っているため、有効活用したいですね。
LEC東京リーガルマインドの超短期カリキュラムは最短2ヶ月で市役所職員採用が目指せます。
市役所職員になるには予備校を利用するのもひとつ
市役所職員になるには、自身の学力に応じた難易度の採用試験を受け、地方公務員の資格を取得する必要がある事が分かりました。
採用試験には一次試験から、最大で三次試験まであり、教養試験、専門試験、適性試験の3種があります。
一次試験を突破すれば、後は面接と小論文で自己のアピールをしていくだけです。
市役所職員になるには、学力も大切ですが、あなた自身が親しみやすく、自己啓発力もあり、市民の為に力を注ぎたい等の自己アピールが大切。
第三者からのアドバイスや勉強のコツなどが知りたいといった方は予備校で対策するのもおすすめです。