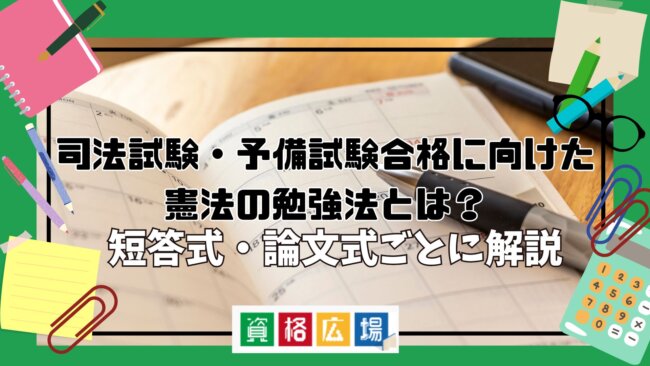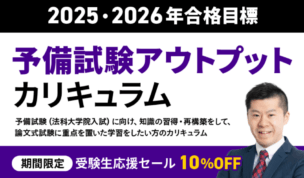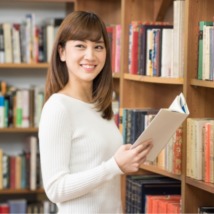憲法は短答式試験・論文式試験のどちらでも問われるもので、いずれにしても難易度が高いといわれています。
例えば短答式試験での憲法は通年平均点が他科目と比べても低い傾向にあり、論文式試験はそもそも論文の書き方が分からないといった方もすくなくありません。
そこで今回は、短答式試験・論文式試験ごとに憲法のおすすめの勉強法について解説します。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
司法試験・予備試験における憲法とは
司法試験および予備試験における憲法の学習では、総論、人権、統治の3カテゴリーの理解が必須です。
短答式では、全選択肢の正誤を判断する必要があり、消去法が使えないため、難易度が高いと言われています。
一方で論文式試験は、最近では「憲法適合性」を問う問題が中心で、法律が憲法に適合するか否かを論じる形式が一般的です。
判例や異なる見解を取り入れつつ、結論への論理的な展開が求められます。
憲法の習熟には深い理解と論理的思考が要求され、効果的な学習法を身につけることが成功の鍵となります。
【2024年最新】司法試験の内容とは?試験科目や出題形式・出題範囲を徹底解説
短答式試験合格のための憲法の勉強法
憲法の短答式試験では、総論・人権・統治分野にわたり、判例や学説の知識が問われることが多いです。
出題形式としては判例の知識確認問題、見解問題、学説・条文確認問題の3つで構成されています。
判例問題では判例の趣旨を詳細に理解すること、見解問題では異なる学説や判例の批判・根拠を把握すること、学説・条文問題では通説や具体的な憲法条文の知識が求められます。
そこでここでは、短答式試験合格のための憲法の勉強法についてご紹介します。
判例を意識する
憲法の問題では、判例の理解とその応用が重要です。
判例に基づいて合憲または違憲の結論を導く際、判例の結論と問題の事例がどのように異なるかを明確にする必要があります。
また、違憲審査基準を定立する際には、その判例がどのような考慮要素をもとにどのレベルの審査基準(厳格、中間、緩やか)を適用しているのかを把握し、問題に適切に適用することが求められます。
上記の学習により、理論と実践の間のギャップを埋めることができます。
過去問を繰り返し解く
司法試験の憲法において、人権分野は重要な出題エリアです。
特に、よく出題される人権とそうでない人権が存在するため、過去問演習を通じてこれらの傾向を把握し、今後の試験に備えることが重要です。
また、過去の出題趣旨や採点実感を分析することで、出題者が何を求めているのか理解することができ、効率的に点数を稼ぐ準備ができます。
特に、違憲審査基準の設定においては、規制の目的、権利の性質、制約の程度を考慮し、薬事法判決や小売市場許可制判決などの重要判例との対比を通じて論じることが求められます。
過去の試験問題を繰り返し解くことで、再度出題される可能性のある人権問題への対応力を高めることが推奨されます。
芦部憲法を読む
司法試験の憲法において、人権分野は重要な出題エリアです。
特に、よく出題される人権とそうでない人権が存在するため、過去問演習を通じてこれらの傾向を把握し、今後の試験に備えることが必要です。
また、過去の出題趣旨や採点実感を分析することで、出題者が何を求めているのか理解することができ、効率的に点数を稼ぐ準備ができます。
特に、違憲審査基準の設定においては、規制の目的、権利の性質、制約の程度を考慮し、薬事法判決や小売市場許可制判決などの重要判例との対比を通じて論じることが求められます。
過去の試験問題を繰り返し解くことで、再度出題される可能性のある人権問題への対応力を高めることが推奨されます。
論文式試験合格のための憲法の勉強方法
憲法の論文式試験の出題形式には、①主張反論型、②リーガルオピニオン型の2つがあります。
当事者としての立場で主張を論じつつ、他方当事者からの反論を想定しながら私見を述べる出題形式なので難易度が高いといわれています。
また出題形式は異なるものの、いずれの形式でも憲法では問題となる法令の合憲性を論じることや私見に対する反論を論じることが求められている傾向にあります。
答案の型を覚える
憲法の論文式試験での答案作成では、人権ごとの答案の型を意識することが重要です。
経済的自由を例に、以下のような答案の型の流れを覚えておくといいでしょう。
- 問題提起:本件法律が特定の権利を制約し、憲法に反する可能性があるかの確認。
- 人権保障の有無:対象となる権利が憲法により保障されているかの検討。
- 人権制約の有無:本件法律がどのようにしてその権利を制約しているかの分析。
- 違憲審査基準の定立:どの審査基準(厳格、中間、緩やか)を用いるかの選定。
- 個別具体的検討:目的の正当性、手段の適切性を検証。
- 結論:法律が合憲か違憲かの結論。
上記の答案の流れに従って書くことで論点漏れを防ぎ、採点者にも伝わりやすく、効果的な答案を作成できるでしょう。
また、勉強中には、これら答案の各部分にどの論点が関連しているかを意識することで、アウトプット時の知識の整理と応用がしやすくなります。
判例を意識する
憲法の答案作成では、第三者による添削を受けることで確実に実力が身に付きます。
とくに憲法では法令で侵害される権利と法令で守られる利益の対立関係を論じることが求められるため、単なる法令の要件当てはめではなく、法律論を展開しなければいけません。
自己の価値判断に偏らないよう、外部のフィードバックを通じて法律論としての適切な答案の書き方を学ぶようにしましょう。
司法権・予備試験対策用の通信講座やスクールでは添削をしてくれるところがほとんどなので、積極的に活用してみて下さい。
司法試験の配点と採点方法・採点基準は?合格点や足切り点など気になるポイントも併せて解説
司法試験・予備試験の憲法の勉強法は過去問演習が大事!
今回は、短答式試験・論文式試験ごとに憲法のおすすめの勉強法について解説してきました。
司法試験・予備試験の憲法の短答式では、全選択肢の正誤を判断する必要しなければならず、かつ消去法が使えません。
また論文式試験は、最近では「憲法適合性」を問う問題が中心となり、法律が憲法に適合するか否かを論じる形式になるので答案の型を身に付けたり第三者に添削を依頼するのも有効です。
いずれにしても、判例を意識することや過去問演習はっかあせないでしょう。
司法試験・予備試験の憲法の勉強法を今回の記事を参考にしてみてください。