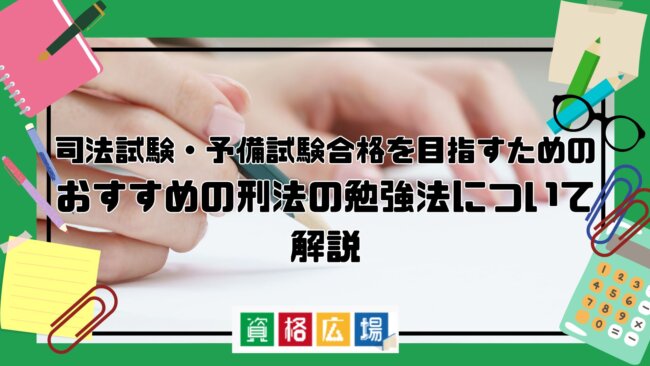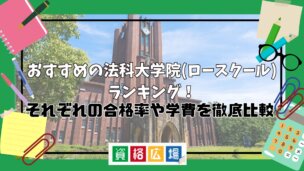司法試験・予備試験には刑法とよばれる分野があり、短答式・論文式のいずれにも含まれています。
しかしなかには、「刑法ってどんな風に勉強すればいいの?」と悩む方もいるでしょう。
そこで今回は、司法試験・予備試験合格を目指すためのおすすめの刑法の勉強法についてご紹介します。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
司法試験・予備試験における刑法とは
刑法は司法試験・予備試験の必須科目で、試験の合否に大きく影響します。
刑法の論文は構成要件該当性、違法性阻却事由、責任阻却事由の流れで書かれることが多く、比較的書きやすいとされています。
刑法は犯罪行為を法規範と照らし合わせて判断し、社会秩序と個人の自由の調和を図る法的思考力を養成するために設けられた要素です。
理論体系が独特であり、具体的な事例に法規範を適用する能力だけでなく、法規範の総合的な解釈と事実関係の的確な評価が求められます。
また、法文の適切な理解と適用、重要判例の精読と活用も必要ということより、刑法の学習で手を焼く受験生も少なくないといわれています。
しかし刑法を克服することで、法律家としての深い法的思考力が身につき、司法試験・予備試験合格に結び付くので避けられない分野と言えるでしょう。
刑法は論理的な要素が強いため、犯罪に関する内容が多く、初心者でも興味を持ちやすい科目です。
刑法の勉強時間の目安は約300時間とされており、一般的には問題集や過去問を利用した演習を重ねることで、出題傾向に慣れることができるといわれています。
【2024年最新】司法試験の内容とは?試験科目や出題形式・出題範囲を徹底解説
短答式試験合格に向けた刑法の勉強法
刑法の短答式試験では、判例知識や条文知識の他に論理問題・見解問題・穴埋め問題が一定数出題されます。
例えば、令和3年度の予備試験で刑法の13問中4問、司法試験では20問中7問が上記のタイプの問題でした。
上記の問題は単なる知識問題とは異なり、事実のあてはめ能力や事務処理能力を要求され、解答には比較的時間がかかる傾向にあるといわれています。
ただし、現行の試験では難易度がやや下がっており、基本知識をしっかり理解していれば対応可能な問題が多いとされています。
ここでは、短答式試験合格に向けた刑法の勉強法についてご紹介します。
過去問を繰り返し解く
短答式試験の刑法の合格を目指す際、過去問の周回勉強法が非常に有効です。
一周目は問題を解き、解答を確認し詳細な復習は避けてスピードを重視し、二周目では間違えた問題にマークをし、軽く解答を読むことを繰り返します。
さらに三周目では間違えた問題のみを取り上げ、解答を読んでもいまいち理解できないところがあればテキストに立ち返ってしっかり復習していきましょう。
正解した問題からは、記しを消すようにしておくとより効率的に学習を進められます。
四周目以降は間違えた問題を解き直し、記しを消すことを繰り返します。
上記のプロセスを通じて、記しをすべて消せた時点で、短答式試験に合格するレベルに達することができるでしょう。
条文に立ち返る癖をつけておく
司法試験の勉強において、条文に立ち返る習慣を身につけるようにしましょう。
条文は法律家間の共通言語として機能し、自分の主張を伝えたり相手の主張を分析する上で不可欠です。
もし問題を間違えた際は解説だけでなく、関連する条文も確認してください。
条文を基に知識や思考、論証を整理することで事実関係を正確に捉え、適切な回答を導出する力が養われます。
条文に立ち返る癖をつけておくことで短答式試験だけでなく論文式試験にも役立ち、問題解決能力や論理的思考力の向上につながります。
有名な判例をおさえておく
過去問を多く解くことで日本の司法試験合格レベルに達することはできますが、さらに精度を上げるためには有名な判例の学習が重要です。
特に、繰り返し出てくる重要判例、例えばクロロホルム事件や大阪南港事件などを押さえることで、論文試験対策にもつながります。
上記の判例は実際の試験で頻出するため、理解を深めておくことがおすすめです。
刑法の短答式試験では判例を理解し、その立場からの検討を求める問題が多く、学説の対立点についても把握しておく必要があります。
効果的な学習には、論文の過去問や短文事例問題集を使った演習がおすすめです。
論文式試験の学習を進める中で、短答式試験の知識も身につけることが重要で、特に刑法においてはこの相互作用が非常に重要となります。
短答プロパーの学習を行う
刑法の短答プロパーの学習を通じて、上位合格を目指しましょう。
短答プロパーとは、論文式試験ではあまり聞かれない、短答に固有に必要になる知識のことを指します。
特に短答試験固有の知識、如く罪刑法定主義や執行猶予などの分野は、論文試験ではあまり問われませんが、短答試験では毎年出題されるため抑えておくことをおすすめします。
上記のトピックに関する総論的な知識を基本書からしっかりと学習し、条文の素読も併せて行うことが効果的です。
条文の素読は、訴訟系科目を含め、全体的に法律の理解を深めるのに役立ちます。
さらに、他科目での失敗を刑法の点数でカバーできるよう、満点に近いスコアを目指すための対策が求められます。
司法試験の刑法の論文式試験では、特定の登場人物に対する犯罪成立の可能性を検討する問題が多く出題される傾向にあります。
たとえば、住居に侵入し金銭を奪う場合、住居侵入罪や強盗罪の成立が考察されるケースがあります。
採点実感によると、試験で重視されるのは刑法総論・各論に関する基本的な知識や問題点の理解、事実関係の正確な分析と法規範の適用能力、結論の妥当性と法的思考過程の論理性が挙げられます。
したがって刑法学習においては、これらの要素を意識し、事例に対して論理的で根拠のある法的判断が行えるよう訓練することが必要です。
上記のアプローチにより、司法試験での高い評価を目指すことができます。
ここでは、論文試験合格に向けた刑法の勉強法についてご紹介します。
答案の型を身につける
刑法の論文対策においては、答案の型を理解しマスターすることが重要です。
刑法の答案は「構成要件該当性→違法性→有責性」という順序で論じられるのが一般的で構成要件該当性は客観面と主観面に分けて考えます。
上記この型をしっかり把握することで何をどれだけ暗記するかが明確になり、学習効率が上がります。
また、答案構成で迷うことなく、試験時間を有効に活用することが出来るメリットもあります。
最低限の暗記をおこなう
刑法の論文対策では答案の型を理解し、型に基づいて必要な部分を暗記することが重要です。
例えば窃取や不法領得の意思など、現場で即座に思い出せない用語や概念は暗記が必要です。
刑法は論理的な科目であるため暗記が不要と思われがちですが、公式を覚えるように、基本的な知識は暗記する必要があります。
しかし型をしっかり把握していれば、必要な暗記量を減らすことができ、より効率的な学習が可能になります。
過去問に取り組む
過去問に取り組む際は、学んだ答案の型を崩さずに解くことが重要です。
過去問を解く段階になれば覚えた知識をどのように点数に結びつけるかを重視するようにします。
そのため、答案を解く際は、既に学んだ型や知識をしっかりと活用することが求められます。
試合で速い球が来た時にフォームを崩さずに対応するように、学んだ通りに過去問を解くことで、効果的に知識を試験に活かすことができるでしょう。
第三者からの添削を受ける
刑法の論文技術を向上させた後は、第三者に答案を見てもらいフィードバックを受けるといいでしょう。
なぜなら、自習だけでは答案の構成が崩れたり、内容があいまいになる可能性があるからです。
司法試験では、試験委員会を説得できる文章力が求められるため、特に重要です。
答案を司法試験合格者などの経験者に見てもらい、的確なアドバイスを受けることで、さらなるスキルアップが期待できます。
司法試験・予備試験合格の講座がある通信講座や予備校では、合格者や講師からの添削をおこなっているところもあるので積極的に活用してみてください。
司法試験の難易度は高い?他資格とのランキング比較や合格率・偏差値・勉強時間の目安について解説
司法試験・予備試験の刑法の勉強法でNGの勉強法
ここでは、司法試験・予備試験の刑法の勉強法でやってはいけない勉強法についてご紹介します。
暗記を怠る
司法試験の勉強で基本書を読むことは重要ですが、ただ読むだけでは不十分です。
基本書の内容を完全に理解し、実際の試験で答案として書き下ろせるレベルに達していなければ意味がありません。
基本書を読むことで勉強した気になることはよくありがちですが、実際には暗記と理解が必要なので怠らないようにしましょう。
読んだ内容をしっかり答案に反映させるためにも、暗記は効果的です。
型を決めないまま勉強を進めてしまう
刑法の勉強では、答案を書く際には型を確立することが大事です。
型を決めることで勉強の効率が上がり、試験での思考時間も短縮できます。
反対に行き当たりばったりで自分のやり方で答案を書く方法は刑法では効果が低く、たとえたまに良い評価を得られたとしても普遍性はありません。
特に刑法では現場思考問題が頻出するため、しっかりとした型があれば、知識だけでは対応できない問題に対しても最低限の答案を書くことができます。
したがって、答案作成は我流を避け、確固たる型に基づいて行うようにしましょう。
添削を受けずにアウトプットのみおこなう
先ほど述べたように刑法の勉強では、一人で学ぶと型が乱れたり知識が曖昧になったりすることがあるため、第三者に答案を見てもらって修正を加えるのが大事です。
上記の過程を省くと自分では型に沿っていると感じても、実際は我流で答案を書いている可能性があります。
したがって、アウトプットのみに偏らず、定期的に添削を受けて軌道修正を行い、効率的に合格を目指しましょう。
司法試験の六法全書の使い方は?六法の種類と選び方・注意点を解説
司法試験・予備試験の科目ごとの勉強順について
司法試験の勉強を始める際はまず民法・商法・民事訴訟法から学び始めるのが良いでしょう。
次に、刑法・刑事訴訟法を学び、刑法は比較的イメージしやすく、答案のパターン化が多いため、対策がしやすい科目です。
7月~9月にわたって憲法・三峰・刑法のインプット、9月~12月で短答式試験対策・論文式試験対策を行うのがベストでしょう。
刑事訴訟法は刑法の知識を前提にしているため、刑法をある程度理解した後に勉強を進めると効率的です。
さらに、憲法・行政法の勉強を始めると良いでしょう。
憲法は全ての法律の基本となる重要な法規範ですが、具体的なイメージが持ちにくいため、初学者には難しい部分もあります。
行政法も同様に、憲法の理解がある程度進んでから学ぶと理解しやすいです。
最終的には、選択科目の対策を行います。
基本科目の知識が身についているため、新たに学ぶ科目にも法的思考や基本的な法規範の知識が応用できます。
選択科目は基本科目との関連性が深いことも多く、相乗効果を得られる可能性があります。
上記の流れで勉強を進めることで、法的思考力や具体的な法規範の適用能力を段階的に高めていくことができ、最終的に司法試験における高いパフォーマンスを目指すことが可能です。
司法試験・予備試験の刑法は判例を抑えることが大事!
今回は、司法試験・予備試験合格を目指すためのおすすめの刑法の勉強法についてご紹介してきました。
刑法では論理的な要素が強いため、犯罪に関する内容が多く、初心者でも興味を持ちやすい科目とされていますが、クリアすることでより法律に関する理解が深まります。
刑法の勉強法では有名な判例をおさえておくことで、短答式だけではなく論文式試験対策にもつながります。
ほかにも過去問を繰り返し解いたり、第三者に添削してもらうのも効果的です。
今回の記事を参考に、司法試験・予備試験の刑法を突破してみて下さい。