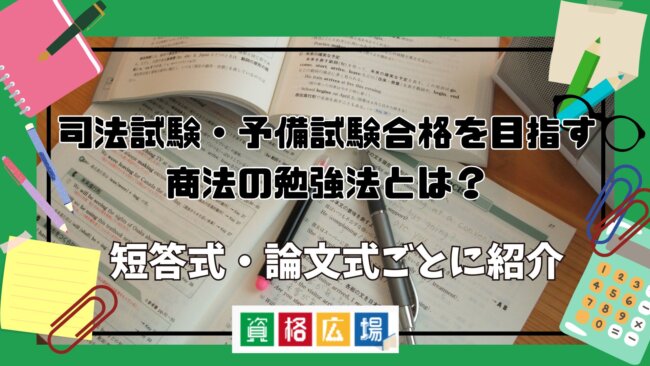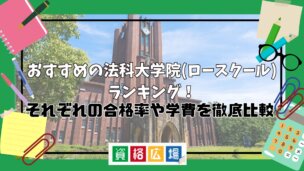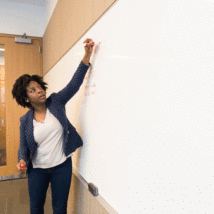司法試験・予備試験には商法といった科目があり、短答式・論文式の形式で出題されます。
商法とは簡単に言うと、商人や商行為に関する法であり、商法・会社法・手形小切手法・保険法・金融商品取引法の分野に分けられます。
そこで今回は、司法試験・予備試験合格を目指すための商法の勉強法についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみて下さい。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
司法試験・予備試験における商法とは
司法試験および予備試験における商法の攻略は、特に会社法の熟知が重要となります。
短答式試験では商法の問題の大部分が会社法から出題され、商法総則や商行為法、手形法などの分野からの出題は少ない傾向にあります。
実際、商法総則や手形法からの出題は予備試験でも限られており、司法試験ではこれらの範囲からの問題はほとんどありません。
以上により、会社法に特化した学習が効果的となります。
会社法を中心に条文の理解を深め、条文を基にした問題解決能力を鍛えることが商法試験における成功のカギです。
また論文式試験においても同様に会社法が中心的な役割を果たしており、他の商法分野への依存は低い傾向にあります。
したがって、受験生は会社法の深い知識と理解を構築し、過去問を解く際にもその知識を活用して実践的な学習を行うのが望ましいでしょう。
過去問を繰り返し解くことで司法試験および予備試験の商法科目での壁を乗り越えることができます。
【2024年最新】司法試験の内容とは?試験科目や出題形式・出題範囲を徹底解説
司法試験・予備試験短答式試験の商法の出題傾向
短答式試験の商法において会社法からの出題が最も多く、全15問中11問がこの分野からとなっています。
そのため、合格を目指すなら先ほども述べたように会社法の攻略が必要不可欠です。
ちなみに商法は商法総則・商行為法からは2問、手形・小切手法からも2問が出題される構成となっておりますが、会社法が出題の中心であることは変わりないでしょう。
また商法の試験においては条文の理解が中心となるため、条文をしっかり学習し、その理解を深めることも重要です。
過去問を解く際には、条文の意味を正確に捉え、具体的な事例への適用を行う能力を養う勉強法がおすすめ。
条文をもとにした詳細な理解を助けるために、各条文が何を規定しているのか、どのような問題に関連して出題されるのかを意識しながら学習を進めることで条文知識を効果的に試験で活用できるようになります。
司法試験・予備試験短答式試験の商法の勉強法
司法試験の短答式試験では憲法、民法、刑法の3科目のみが出題されるため、商法の短答は含まれません。
しかし、司法試験予備試験では、法律基本7科目が出題範囲に含まれ、これには商法も含まれます。
予備試験の商法短答では、会社法を中心に、商法総則や手形法・小切手法の知識も問われるため対策が必要です。
ここでは、司法試験・予備試験短答式試験の商法の勉強法についてご紹介します。
条文は趣旨にさかのぼって考える
商法の短答式試験対策として、特に会社法の条文知識が重要です。
会社法の条文は、取締役会や監査役などの機関設置義務に関するものが多く、覚えるのが難しいといわれています。
条文はただ暗記するのではなく、条文の趣旨や背景を理解することが記憶に定着させやすくするポイントです。
例えば、大会社に会計監査人の設置が義務付けられている条文は、大規模な取引と多くの利害関係人が存在するために強い監視が必要とされることが背景にあります。
条文の趣旨を理解することで、記憶が定着しやすくなり、試験での応用が効きやすくなります。
覚えにくい条文については、基本書を参照するなどして詳しい説明を読むのもひとつです。
組織再編の分野は図や表を使って理解を深める
商法の短答式試験対策において、会社法の複雑な条文を効果的に理解するためには、図や表を用いる方法がおすすめです。
特に、会社法の中でも組織再編の分野では、視覚的なツールを活用することでより分かりやすくなります。
例えば、会社分割を理解する際には、「新設分割」と「吸収分割」という二つの異なる概念を図で表すことで違いが明確に。
この方法により、条文の理解が深まるだけでなく、長期的な記憶の定着にも寄与します。
図や表は自分で描いてみることが重要で、抽象的な概念が具体的な形として頭に残りやすくなります。
参考書や基本書を活用しながら、自らがアクティブに情報を整理し視覚化することで商法の理解を深め、短答式試験の準備を整えるようにしましょう。
試験直前は短答プロパーメインで対策する
商法の短答式試験では、会社法以外にも商法総則や手形法、小切手法が出題されます。
上記の分野は論文式試験でほとんど問われず、一般的に短答プロパーとされていますが、毎年一定数の問題が出るため試験の直前には対策が必要となります。
手形法と小切手法に関しては2026年の廃止が予定されており、今後の出題範囲に変更がある可能性もあるため要注意。
試験範囲などは年度によっては異なるケースもあるため、毎年法務省のホームページなどで動向をチェックするようにしてください。
司法試験・予備試験論文式試験の商法の勉強法
商法・会社法は、主に商法総則・商行為、手形法、会社法の3つの分野から出題されますが、とくに会社法が中心です。
商法総則・商行為や手形法は予備試験でごく少数問われるのみで、司法試験では出題されていないため、これらの分野への過度な時間投資は避けるべきです。
司法試験の商法・会社法では、事実関係を分析し、会社法上の論点を抽出する能力、論理的思考力、基本的な理解力が求められます。
特に、法的手続の適正さや取締役の損害賠償責任など、具体的な法的手段の選択や要件充足性が問われることが多く、民法と同様の法理解が有効です。
会社法の習得には、これらの論点に焦点を当てた効率的な学習が推奨されます。
ここでは、司法試験・予備試験論文式試験の商法の勉強法についてご紹介します。
条文を参照しながら制度趣旨を理解する
商法・会社法の勉強では、条文の長さと引きの難しさに苦労する人がすくなくありません。
つまづく理由で考えられるのは、条文が複雑で様々な場面で準用されるため、いまいち意味が読み取りにくくなっているからです。
したがって商法の論文式試験の学習する際は制度の趣旨を理解しながら、辛抱強く条文を参照することが大事です。
また、法律学習全般に言えることですが、特に会社法では目次を積極的に活用すると良いでしょう。
目次を法律の収納ケースと考え、条文を引く際にどのセクションに属するかを常に確認することで、より条文検索能力が向上し効率的な学習ができるようにしなります。
条文を引くことを意識する
商法の論文式試験における会社法は条文操作が重要だとされています。
日常の勉強では、条文を引く練習に特に力を入れてみるといいでしょう。
たとえば、株式に関する条文が100条代に集中しているなど、条文の内容と位置の関連を理解しておくと、試験中に迅速に情報を探すことが出来るようになります。
また頻出の条文番号は暗記しておくことで、試験中の時間を節約することができます。
何度も条文を引いていると次第にスピードも上がってくるので、横着せずに日々の学習からたくさん引く習慣を身に付けてみてください。
頻出分野の書き方を身に付ける
商法の論文式試験における重要な論点には、取締役の責任や株主総会の取消事由といった分野が含まれます。
実際に過去の司法試験や予備試験で頻出しているため、対策しておく必要があるでしょう。
特に取締役の責任に関しては、株式会社に対する損害賠償責任(会社法423条)や第三者に対する損害賠償責任(会社法429条)の解答には一定の型があります。
取締役の責任や株主総会の取消事由について効率よく学ぶためには、事例問題集を活用し、繰り返し解くことがおすすめです。
問題集を使って具体的な処理手順を繰り返し練習することで、答案の型が自然に身につき、論文式試験でのパフォーマンス向上が期待できます。
初めは難しいかもしれませんが、解説や解答例を参考にしながら積極的に問題に取り組みましょう。
過去問を繰り返し解く
商法の論文式試験対策として、過去問演習のは外せないでしょう。
予備試験や司法試験では、過去に出題された似たタイプの問題が再出題されることが多く、過去問に取り組むことで直接的な試験対策になります。
特に、近年の試験では問題が長文化し、事実関係が詳細に記される傾向にあるため、これらの情報をどう答案に反映させるかが重要です。
合格者の再現答案を参考にすることで、実際に合格点を得るための答案作成技術をより効率的に学ぶことができます。
再現答案を通じて合格者がどのように事実を評価し、条文に当てはめていったかを分析し、その方法を自分のものとすることが論文試験での高得点へとつながります。
過去問を繰り返し解くことで論理的な思考力と条文操作能力の両方を鍛えるようにしましょう。
アウトプットは早めにしておく
商法・会社法の学習においては、基本書の読み通しによるインプットのみに頼ることが学習者にとっては非効率なことが多いです。
とくに商法や会社法では実務経験がなく具体的なイメージを持ちにくいため、インプットに時間を割くよりも問題演習を通じたアウトプットを早い段階で取り入れることが効果的です。
アウトプットを行うことで、どのような点が法的に問題になりうるのかを明確にし、条文と事実の関連を深く理解できルメリットがあります。
特に会社法では、事実から条文へと法的な分析を繰り返すパターンが一般的であり、普段から条文を中心に学習を進めることが重要です。
合うトップっとによる学習は条文知識の強化と共に理解の深化を促し、基本書の読み通しのみよりも学習効果を高めることができるためできるだけ早めに取り掛かるようにしましょう。
司法試験の勉強時間はどれくらい?社会人の1日のスケジュールや合格まで何年かかるか解説
司法試験・予備試験商法でやってはいけない勉強法
ここでは、司法試験・予備試験の商法でやってはいけない勉強法についてご紹介します。
周辺知識の確認をしない
商法短答式試験対策において過去問の演習は不可欠ですが、単に過去問を解くだけでは不十分です。
なぜなら近年の予備試験では、過去の問題の知識だけで対応できない新しい形式の問題が増えているからです。
そのため、過去問を解いた後はただ答えを確認するだけでなく、該当する条文を確認し関連する周辺知識も広げることが重要です。
周辺知識を広げる勉強法については、択一六法やその他の法律参考書が役立ちます。
上記の参考書は各分野の法律知識を表や図で整理していることが多く、効率的な学習に重宝するでしょう。
過去問を解くことで得た知識を、これらの資料を用いてさらに拡張し、深化させることが予備試験対策の成功への鍵となります。
条文の文言を意識しない論述をおこなう
商法の論文式試験では、条文操作が非常に重要です。
特に会社法のような分野では、問題設定に対してどの条文が適用されるかを明確にし、条文の具体的な文言に基づいて論点を展開することが求められます。
実際に法務省が公表する司法試験の採点実感によると、「会社法上の問題点について論じなさい」という設問に対し、単に問題を提起するだけでなく、具体的に会社法第854条第1項の文言をどのように解釈し、適用するかを詳細に論じる必要があることが指摘されています。
つまり詳細な条文の解釈が欠けている答案は評価が低くなりがちだということがわかります。
したがって、商法・会社法を学ぶ際には、日々の学習で条文の正確な文言を把握し、それに基づいて具体的な法的問題の分析を行う習慣を身につけるようにしましょう。
参考:法務省
復習を怠る
商法・会社法の勉強において、繰り返し出題される典型論点への対策は欠かせません。
典型の論点は一度理解し答案の書き方をマスターすれば、高得点を獲得しやすい分野となります。
最大限に活かすためには、一度解いた問題の復習を怠ってはなりません。
典型論点に対する知識や答案の質は周囲の受験生も向上させているため、答案の細部にまで注意を払うことで差をつけられます。
したがって、一度学んだからと安心せず、何度も復習し理解を深めて答案の完成度を高めるようにしましょう。
繰り返し復習することで知識の定着を図れば、実際の試験でも反映されるはずです。
司法試験・予備試験商法の勉強法では条文を抑えることが大事!
今回は、司法試験・予備試験合格を目指すための商法の勉強法についてご紹介してきました。
商法は商法総則・商行為法からは2問、手形・小切手法からも2問が出題される構成となっておりますが、会社法が出題の中心となる傾向にあります。
なかでも会社法の条文は、取締役会や監査役などの機関設置義務に関するものが多く、覚えるのが難しいといわれています。
会社法の条文を抑えるには趣旨や背景を理解するのがポイント。
反対に条文の文言を意識しない論述を行ったり、一度解いた問題の復習をおこたると結果に結びつきません。
司法試験・予備試験の勉強では予備校や通信講座などを利用すれば、添削なども受けられるのでぜひ活用してみてください。