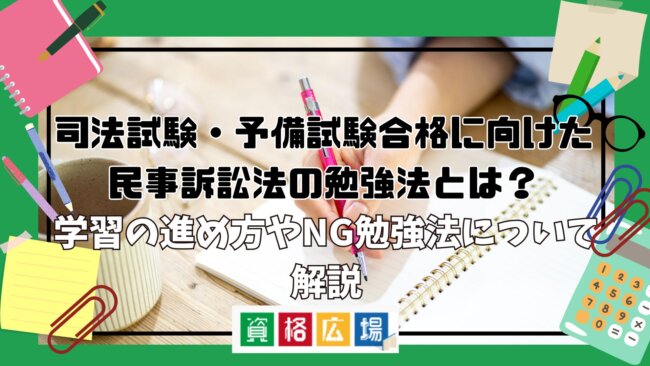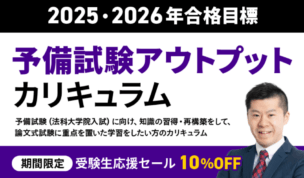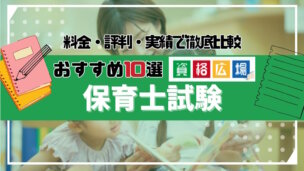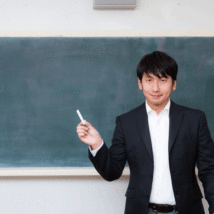司法試験・予備試験の民事訴訟法は、はじめて学習する人にとってかなりハードルが高い科目だとされています。
なぜなら、条文知識や判例知識を満遍なく問われるため、バランスが重要だからです。
そこで今回は、司法試験・予備試験合格に向けた民事訴訟法の勉強法について解説します。
司法試験・予備試験における民事訴訟法とは
民事訴訟法は司法試験・予備試験の中で特に難易度が高い科目とされ、条文知識と判例知識のバランスが求められます。
具体的な勉強法としては訴訟の各段階で必要な手続きを理解し、条文の知識を深めることが一般的です。
さらに、主要な判例については結論だけでなく、背後にある論理を理解することも求められます。
ちなみに短答式試験では手続きの流れや実体法との関連性を把握することが鍵となり、論文式試験では問題の指示に従うことが求められます。
論文式試験においても、問題の誘導に従うことが重要であり、正しい知識を持っていても指示に従わなければ正解にならないという特性を持っています。
【2024年最新】司法試験の内容とは?試験科目や出題形式・出題範囲を徹底解説
民事訴訟法の短答式試験合格におすすめの勉強法
民事訴訟法の短答式試験では、単なる条文知識だけでなく、具体的な訴訟手続きや管轄などに関する詳細な知識が問われるため特別な対策が必要です。
具体的には、主要な手続きの流れや訴えの提起から訴訟の終結までの各段階での重要ポイントを理解し定着させるために、問題集を使った繰り返しの演習やケーススタディを通じて実際の訴訟の状況を想定する勉強が効果的です。
また、過去問分析を行い、どのような問題がどの程度の頻度で出題されているかを把握し、重点的に学習する範囲を絞ることも重要です。
ここでは、民事訴訟法の短答式試験合格のためのおすすめの勉強法についてご紹介します。
過去問を繰り返し解く
予備試験の短答式試験対策として、過去問の繰り返し解析と学習が有効です。
なぜなら過去に出題された問題やそれに類似した問題が頻繁に出題されるため、過去問演習を通じて問題形式や出題傾向に慣れることができるからです。
解答時には、ただ正誤を判断するだけでなく、その選択肢が条文、判例、学説のどれに基づくものかを理解し、誤答の理由とその修正方法も考慮しながら解くようにしましょう。
また、新しい判例や理論にも対応できるよう、関連分野の重要判例や知識を判例集や基本書で補強することもおすすめです。
包括的なアプローチを取ることで、予備試験の短答式試験において高いパフォーマンスを発揮することができるようになります。
条文知識・判例知識を身に付ける
民事訴訟法の勉強では、条文知識を効果的に身につけるために訴訟の全体的な流れを常に意識するといいでしょう。
なぜなら、民事訴訟法の短答式は個々の手続きが訴訟のどの段階で必要とされるのかを把握しなければ、論点だけ覚えていても本番で通用しないからです。
また、制度や条文が設けられている理由についても理解を深めることが、記憶の定着と実際の試験への応用につながります。
特に、民事訴訟法は条文だけでなく、処分権主義や弁論主義といった基本的な概念や制度の趣旨を理解することが不可欠です。
概念や制度の趣旨への理解は論文式試験にも直結するため、短答式試験の準備が論文式試験の対策にも役立ちます。
判例に関しては重要判例を中心に結論だけでなく判例の背後にある論理もしっかり学ぶようにしましょう。
特に司法試験で頻出の百選掲載の判例は、その理由や論理の流れまで詳しく把握しておくことが重要です。
判例知識は短答式試験だけではなく、論文式試験での評価を左右する要素となり得るため、短答式試験の勉強が直接的に論文対策になるのです。
制限時間を意識して解く
民事訴訟法の短答試験においては、各問題を約2分程度で回答する必要があるとされています。
実際には民事訴訟法、民法、商法の3科目を合わせて1時間半で解かなければならないため、民訴に割り当てられる時間は30分以下を目標にしなければいけません。
したがって、効率的な時間管理が求められます。
そこで短答式試験試験の対策としては、日頃から時間を計って問題を解く訓練をするのがおすすめです。
具体的には、過去問を用いて年度別に問題を解き、30分以内に一年分を解き切るようにしてみてください。
普段の学習や過去問を解くにあたって試験時に時間の制約を意識することで、確実に問題を解くスキルが身につき、実際の試験でのパフォーマンス向上が期待できるでしょう。
司法試験の勉強時間はどれくらい?社会人の1日のスケジュールや合格まで何年かかるか解説
民事訴訟法の論文式試験合格におすすめの勉強法
民事訴訟法の論文式試験では、短答式試験で求められる浅く広い知識に対し、より狭く深い知識が求められるのが特徴です。
特に、弁論主義や処分権主義、既判力といった複雑な概念の理解が求められ、具体的な訴訟手続きよりも理論的な深掘りが必要です。
そのため、論文式では条文素読を越えた深い議論を展開できるような勉強が効果的となっています。
ここでは、民事訴訟法の論文式試験の勉強法についてご紹介します。
原理や原則について正確に把握しておく
民事訴訟法の勉強では条文の要件解釈を深く理解し、把握することが非常に大切です。
例えば、補助参加の利益に関する民訴法42条の「訴訟の結果」や「利害関係」などの理解が求められます。
また民事訴訟法は他の科目と比較して条文から離れた知識が問われることもありますが、法律学習の基本は条文から始まることを忘れてはいけません。
条文を基にした勉強を徹底することが、苦手意識を克服する第一歩になります。
さらに、民事訴訟法は手続法であるため、訴状の提出から始まり判決が確定するまでの一連の流れを意識しながら解くこともポイントです。
手続の各段階でどの原理や原則が問題になるかを把握し、実際の訴訟流れを想像しながら条文を学ぶように意識してみてください。
判例の具体的な事案を抑える
民事訴訟法における判例はかなり重要なポイントとなります。
なぜなら試験では直接的な判例の再現だけでなく、似たような事例を少し変えて出題されることが多く、判例の背後にある論理や法理を深く理解しておく必要があるからです。
判例学習では、以下の点を重視して学習を進めるといいでしょう。
- 判例の具体的な事案の詳細を把握する。
- その判例が取り上げられた問題の所在を明確にする。
- 学説の対立点を理解し、どのような議論がなされているかを捉える。
- 最終的に裁判所がどのような判断を下したかを理解する。
上記の方法により判例の事案を正確に理解し、類似の事案が試験で問われた際には、その事案との違いを踏まえて適切な論述ができるようになります。
また、判例の理解はただ事実を暗記するだけではなく、裁判所の判断理由や法的な考え方を深く把握することも必要です。
法的な考え方を理解することで、司法試験の論述で求められる判例を踏まえた論述を展開するための基盤が形成されます。
判例を通じて具体的な法的問題を解決する過程を理解することが、民事訴訟法を含む法律学習において不可欠です。
実際の訴訟シナリオでどのように法律を適用するかの能力が試されるため、事例を基にした判例の学習をおこなうようにしてください。
基本論点を徹底的に抑える
民事訴訟法の論文式試験では幅広い知識の網羅よりも、問われうる基本の論点をしっかりと押さえることが重要です。
民事訴訟法の知識については多くの受験生がある程度知っている内容であるため、反対に基本の論点に即した内容を書けないと大きく差をつけられるリスクがあります。
特に、民事訴訟法は、弁論主義などの条文から派生した論点が多いのが特徴で、事前に学習しておかないと答案でカバーすることが困難といわれています。
基本的な論点や要件解釈は問題文から関連する条文を連想し、適切な論点に落とし込む訓練をすることが効果的です。
学習の初期段階では条文を連想し基本論点にフォーカスして、しっかりと理解・暗記を重ねるように意識してみてください。
過去問を繰り返し解く
民事訴訟法の学習においては、過去問の繰り返し解くことが重要です。
なぜなら民事訴訟法は他の科目と比べて幅広い知識を問うわけではなく、どれだけ深く理解しているかが試されるため、思考力の鍛錬が必要不可欠だからです。
例えば、実際にも令和4年の司法試験では、「主観的追加的併合が認められないとする判例の射程を考慮した問題解決」は、単に判例を暗記しているだけでは解答できない深い理解が求められる問題が出題されました。
過去問を解く際には、ただ答えを見るだけでなく、問題が試している知識の深さや思考の複雑さを自問自答しながら進めることがポイント。
過去問を繰り返し解くことで論理的かつ深い理解が求められる民事訴訟法の試験に対応できるようになっていくでしょう。
司法試験・予備試験における民事訴訟法のNGの勉強法
ここでは、民事訴訟法の勉強法でやるべきではない勉強法についてご紹介します。
民事訴訟法の勉強法で迷っている方や、なかなか結果が出ないといった方はぜひ参考にしてみてくださいね。
丸暗記に頼る
まず民事訴訟法において、判例の結論だけを丸暗記する勉強方法は避けるべきです。
なぜなら、民事訴訟法の試験では与えられた規範の結論を単に知っているだけでは不十分であり、試験で問われるのは理由付けや論理的根拠だからです。
特に民事訴訟法では、判例の結論は基本的な知識として多くの受験生が把握しているため、ただそれを記述しても高評価は得られません。
試験で求められるのは判例がなぜその結論に至ったのか、しっかり論理を理解し説明できるかどうかです。
したがって判例を学ぶ際には単に結論を覚えるのではなく、背後にある法理や論点をしっかりと理解し、具体的な理由付けまで深く学習することが重要です。
民事訴訟法の試験で効果的に知識を展開し、高い評価を得られるでしょう。
条文から離れて学習を進める
民事訴訟法の勉強においては、条文から離れた論点や複雑な概念も興味深く学習してしまう人も少なくありません。
しかし、司法試験はあくまで実務家を目指す試験であるため、実務で最も重視されるのは条文の理解と運用能力です。
民事訴訟法においても条文を根底から理解し、実務での適用能力を試す問題が多く出される傾向にあります。
そのため、複雑な理論や判例の学習も重要ですが、まずは先立って条文の深い理解に努めるようにしましょう。
実際の司法試験や予備試験では、条文操作能力が直接的に問われることが多く、条文を理解する能力や適用能力が合否を左右することも少なくありません。
民事訴訟法の勉強では、まずは条文の確実な理解を最優先にし、その上で論点や判例を結びつけて学習を進めてみてください。
答案を一切書かない
民事訴訟法の勉強においては知識を覚えるだけではなく、自ら答案を書く練習を行うことが非常に重要です。
したがって逆に答案を一切書かない勉強法を進めていたり、単なる暗記問題や知識問題ばかりに重視している方は要注意。
特に、思考力を問うような問題が多い民事訴訟法では、実際に手を動かして答案を作成する過程が知識を自分のものにし、実際の試験で使いこなす能力を養う上で欠かせません。
また、自分だけでの復習に留まらず、第三者からの添削を受けることで客観的な評価や多角的な批判を得ることも得策です。
プロの予備校講師や通信講座などからの専門的な添削を受けることで、最新の試験傾向を踏まえた具体的なアドバイスを受けることができるでしょう。
「答案の書き方が分からない」「なかなか点数が伸びない」と悩んでいる方はぜひ積極的に活用してみて下さい。
総合的な勉強法を通じて、民事訴訟法の苦手意識を克服し、より高いレベルの理解と応用力を身につけることが望まれます。
司法試験予備試験の効果的な勉強法とは?最短スケジュールで合格するための方法を解説
司法試験・予備試験合格に向けた民事訴訟法の勉強法では条文や判例を整理して覚えることが大事!
今回は、司法試験・予備試験合格に向けた民事訴訟法の勉強法について解説してきました。
条文知識を効果的に身につけるためには、訴訟の全体的な流れを常に意識するような勉強法で進めていくことをおすすめします。
なぜなら、民事訴訟法の試験では与えられた規範の結論を単に知っているだけでは不十分であり、試験で問われるのは理由付けや論理的根拠だからです。
したがって、民事訴訟法の勉強法では暗記に頼るのではなく、判例や手続きの流れなど実務的な能力を身に付けるようにしましょう。
予備校や通信講座では、第三者からの有益なアドバイスや多角的な視点で批判してくれるので活用してみるのもひとつです。