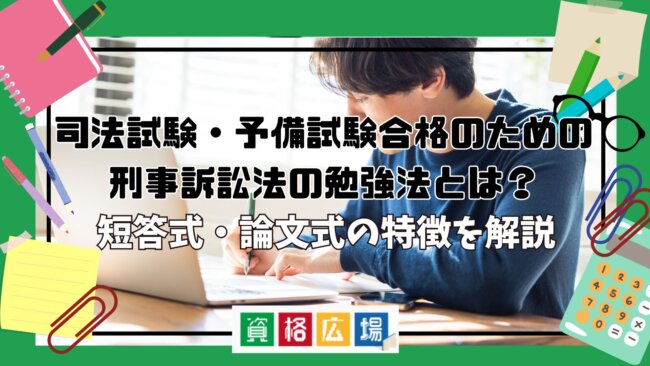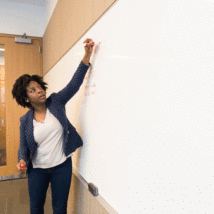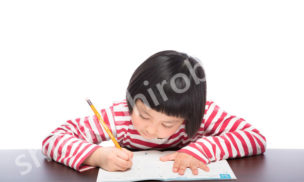刑事訴訟法は憲法・民法・刑法と比べると、つい勉強が後回しになってしまい、なかなか手が回らないという方も少なくありません。
刑事訴訟法は刑事事件につき公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障を全うしながら、事案の真相を明確にすることを目的としたものです。
後回しになりがちですが実は刑事訴訟法は、基礎をしっかりと抑えて正しい方法で勉強すれば、コスパ良く点数を伸ばせる科目でもあります。
そこで今回は、司法試験・予備試験合格に向けた刑事訴訟法の勉強法についてご紹介します。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
司法試験・予備試験における刑事訴訟法とは
刑事訴訟法は犯罪捜査や刑事裁判の手続きを規定する法律で、民事訴訟法とは異なります。
刑事訴訟法とは法律知識と事実の評価というスキルが求められ難しいと感じることもありますが、推理力や論理的思考力を活かせば高得点を目指せる科目でもあります。
特に、法律知識だけでなく常識論でアプローチ可能な部分が多いため、比較的少ない勉強時間で効率良く得点を伸ばせるといった特徴を持ちます。
刑事訴訟法を深く理解し適切な学習方法を選べば、司法試験・予備試験の成功に大きく貢献する科目です。
【2024年最新】司法試験の内容とは?試験科目や出題形式・出題範囲を徹底解説
刑事訴訟法の短答式試験の特徴
刑事訴訟法の短答式試験では、捜査、証拠、公判手続きに関連する問題が出題されます。
刑事訴訟法の試験では判例や条文に基づく問題に加え、実際の現場での思考を求める問題も頻繁に登場します。
出題形式は多様で、「正しいものの組み合わせを答えるもの」、「正しいものに1、誤っているものに2を選ぶもの」、「正しいものの個数を答えるもの」などがあり、問題文の正確な読解が特に重要とされています。
このため、細かく問いの意図を理解することが成功の鍵となります。
刑事訴訟法の短答式試験合格への勉強法
ここでは、刑事訴訟法の短答式試験の勉強法についてご紹介します。
判例・事例を通読する
刑事訴訟法の短答式試験では、判例に関する詳細かつ正確な知識が非常に重要です。
なぜなら刑事訴訟法は立法があまり進まず、判例が法の適用において中心的な役割を果たしてきたという背景があるからです。
試験形式は主に選択肢の正誤を問うもので理由付けを含めた深い理解が求められるため、結論だけでなく判例の背景や理由も把握することが求められます。
効果的な勉強方法としては、判例集を用いて具体的な事案と判旨を繰り返し読み、判例の射程や適用範囲について深く理解する方法がおすすめです。
判例や事例の射程を意識しながら読み進めるようにしてみてください。
逐一条文を確認する
刑事訴訟法の短答試験対策では、判例知識に加えて条文知識の習得も欠かせません。
具体的な勉強方法としては条文を逐一引いて確認し、理解を深めるやり方が推奨されます。
特に捜査の期間制限や公判前整理手続きのように手続きが複雑で条文が多い分野では、関連条文を素読することから始めると良いでしょう。
もし理解が難しい場合は、自分で図を描いたり、条文の流れを視覚化することも助けになります。
ほかにも、択一六法などの法律参考書を利用すると、複雑な手続きや条文が分かりやすく整理されているのでより効率的に学習を進められます。
また特定のまとまりごとに読んでみるのもひとつ。
例えば、逮捕に関する知識を学習する時には199条から217条をまとめて読めば、どのような順序で条文が規定されているかが大きな目線で見ることができますし、ストーリーとして条文を把握できるのでぜひ参考にしてみてください。
過去問を何度も解く
刑事訴訟法の短答対策において、過去問を繰り返し解くことは有効な勉強法と言えます。
過去問を解く際はただ正解するだけでなく、選択肢ごとに理由付けができるまで徹底的に解析するようにしてみてください。
また、各選択肢に対して自信の度合いを○(理由付けまで自信あり)、△(結論は理解しているが理由付けに自信なし)、×(結論と理由付けが不明)のように印をつけて解く方法もおすすめです。
印をつけてわかりやすくしておくことで学習の進行状況が視覚的に明確になり、どの問題を重点的に復習するかが容易になります。
解いた後には関連する条文や判例も確認し、内容の確実な理解と記憶の定着を図ることが大切です。
効率的かつ効果的な短答対策が可能となり、本番の試験でも落ち着いて解答できるでしょう。
予備試験合格者は司法試験合格率が高い!司法試験の難易度低下は本当?
刑事訴訟法の論文式試験の特徴
刑事訴訟法の論文式試験では、捜査手続と公判手続の二つの主要な段階に関する問題が出題されます。
捜査手続は被疑者が起訴される前の刑事手続で、逮捕や捜索差押などが含まれます。
公判手続は起訴後の手続で、例えば違法な捜査によって得られた証拠の法廷使用が問題になることがあります。
刑事訴訟法の論文式試験では問題の正確な把握、関連事実の分析と法解釈に基づく適切な法準則の適用、そして論理的な展開を求められる傾向にあります。
したがって、刑事手続上の問題点に対する法的解決を筋道立てて説得力のある形で論じる能力が試されます。
具体的な論文式試験対策としては上記の点に注意し、事例を通じて具体的な問題解決のプロセスを習得することが大切です。
刑事訴訟法の論文式試験合格への勉強法
ここでは、刑事訴訟法の論文式試験の勉強法についてご紹介します。
判例への理解を深める
刑事訴訟法の論文式試験における判例の役割は非常に重要であり、実際の司法試験や予備試験においても判例に基づいた問題が頻繁に出題されています。
したがって判例の詳細な学習とその適用範囲の理解は、試験での成功に不可欠な存在といえるでしょう。
刑事訴訟法の論文式試験では、判例の「射程」を正確に理解し、具体的な事案にどのように適用するかを見極める能力が求められます。
しばしば判例とは異なる微妙な事案が出題されるため、表面的な知識ではなく、その背後にある法理と事実の関係を深く把握することが求められます。
出題された事案が判例に類似している場合でも全く同じ法的結論を導くわけではないことが多いので、判例の適用時にはその差異を慎重に評価しすることが大事です。
具体的な試験対策としては、判例集を利用して具体的な判例を繰り返し学習し、それぞれの判例がどのような法的問題に対応しているかを理解することがポイントです。
また、過去問を解く際にはなぜその判例が適用されるのか、どのような理由でその判例が選ばれたのかを考えることが助けになります。
さらに、判例の射程を意識し、似たような事案に対して自らの言葉で論理的に論じる練習を行うことで、試験での論述力を高めることができます。
出題趣旨・採点実感を読み込む
司法試験および予備試験において、試験終了後に発表される出題趣旨や採点実感は試験委員会からの重要なフィードバックとなります。
特に刑事訴訟法において出題趣旨や採点実感は重要性が高く、試験対策でも避けては通れないでしょう。
例えば、強制捜査と任意捜査の区別は例年刑事訴訟法の論文式試験で頻繁に取り上げられるテーマであり、過去の出題趣旨や採点実感でも言及されています。
おすすめの勉強法としては、強制捜査の定義や任意捜査の判断枠組みなど、細かく説明された内容を理解し、暗記することで、試験で高得点を目指せます。
出題趣旨・採点実感は教科書のような役割を果たし、効率的かつ効果的な学習をサポートするため意識して日々の学習に役立ててみてください。
手続きの流れ・事実関係の時系列を意識する
刑事訴訟法の学習においては、以下の2つの時間軸を意識することが非常に重要です。
まず、手続の流れという意味での時間軸。
刑事訴訟法は刑法の手続を規定しており、捜査から始まり判決の言い渡しに至るまでの一連のプロセスを理解する必要があります。
各手続きがどの段階に位置するかを把握し、勉強する事項の位置付けを正確に認識しながら学習を進めてみてください。
また、事実関係の時系列という時間軸も大事です。
司法試験では捜査が進むにつれて明らかになる事実や証拠関係に基づき、被疑者への嫌疑が高まる様子を理解し対応する能力が求められます。
反対に事実関係の時系列を意識せずに答案を作成すると、実際の訴訟プロセスを反映していないと評価されることがあるので要注意。
刑事訴訟法を学ぶ際は手続きの段階を追う時間軸と事実が展開する時間軸の両方を意識し、それぞれの視点から事案を分析することが効果的な学習と試験対策につながります。
論文式試験対策では「あてはめ」は有効か?
刑事系科目、特に刑事訴訟法においては、「あてはめ勝負」という表現がよく用いられることがあります。
なぜなら、試験問題に記載された事実が多く、その事実を法律に適切にあてはめる能力が求められるためです。
ただし、あてはめ勝負が強調される一方で法律論を軽視して良いという意味ではないので要注意。
規範が正確に書けていても、それを適切に事実に適用できない場合、規範を本当に理解していないと見なされることがあります。
つまり、あてはめる過程は規範の理解を示す重要な手段となり、刑事訴訟法を学ぶ際には法律論と事実の適用、つまりバランスよく学習することが大事です。
各答案を見比べてポイントを掴む
なかなか論文式試験の点数アップに結び付かないといった方は、模範答案や合格ギリギリの答案、上位答案など、さまざまなレベルの答案を比較するといいでしょう。
さまざまなレベルの答案と自分の答案を見比べることで自分の答案がどの位置にあるのか、また合格に必要な答案がどのようなものかを把握できるメリットがあります。
特に、合格ギリギリの答案を見ることで、最低限書くべき内容とその基準が明確になります。
上記の方法により、「この問題でこの論点は落としてはいけない」という重要な論点が直感的に理解できるため、効率的な復習や試験対策につながります。
また第三者から添削を受けることも有効です。
予備校や通信講座では司法試験・予備試験合格者や担当講師による添削サービスをおこなっているため、客観的な視点や点数につながるアドバイスをもらえる可能性が高くなります。
制限時間を意識して解く
刑事訴訟法の勉強試験は120分という短い時間内に問題文を読み、答案を完成させなければいけません。
時間切れで答案が途中で終わってしまうことを避けるためには、過去問を繰り返し解いて問題文の読解速度と事案分析のスピードを上げる訓練が必要です。
また、時間の無駄を省くために事前に用意した論証パターンを活用し、答案作成プロセスを効率化することも重要です。
さらに、書きやすいボールペンを選ぶ、書くスピード自体を向上させる訓練もおすすめ。
上記の準備を事前にしっかりと行うことで、試験中に時間に追われる心配を軽減し、知識を最大限に発揮できるようになります。
司法試験の勉強時間はどれくらい?社会人の1日のスケジュールや合格まで何年かかるか解説
刑事訴訟法でやってはいけない勉強法
ここでは、刑事訴訟法の勉強法でやってはいけない勉強法についてご紹介します。
なかなか点数アップできないと悩む方はぜひ参考にしてみてください。
具体的事情を無視した論述をおこなう
刑事訴訟法の論文式試験においては、しばしば判例の事案が微妙に変更された問題が出題されるため、単に判例の規範や結論に安易に飛びつくのはおすすめではありません。
なぜなら刑事訴訟法の採点者は判例との差異を意識した論述を期待しており、設問の事案が判例と異なる部分については、違いを深く分析し、詳細に論じることが求められるからです。
実際にも近年の司法試験や予備試験では、設問の事例が非常に詳細に記載されており、具体的な事案に即した論述が重要視されています。
そのため、日常の勉強や答案練習では、問題文に記された具体的事実をできるだけ多く拾い上げ、事実に基づいた詳細な論述を行うことが推奨されます。
上記のアプローチにより、試験で求められる高度な法的分析と論述スキルを養うことができます。
論証パターンを暗記する
司法試験・予備試験の刑事訴訟法の勉強法として抽象的な論証パターンを単に暗記するだけでは、具体的な事案に対する適切な当てはめができなくなってしまいます。
刑事訴訟法の問題解決ではしばしば相反する二つの利益を比較衡量し、妥当な結論を導く必要があります。
たとえば、「人権保障と真実発見の調和」のような一般的な規範だけでは不十分で、事案の具体的な性質に応じた詳細な規範を導出することが重要です。
つまり判例から規範や考慮すべき要素を抽出し、具体的な事案に適用する能力が求められるということです。
なお、規範の暗記にあたってはただ覚えるだけでなく、規範がどのように具体的な事案に応じて活用されるかを理解し、実践的な知識として定着させることがカギとなります。
マイナーな論点にまで手を広げる
司法試験・予備試験の刑事訴訟法科目では、主要な典型論点に加え、時々マイナーな論点も出題されることがあります。
しかし、マイナーな論点に過度に学習リソースを割くことは有効ではありません。
なぜなら試験が相対評価であるため、マイナー論点において受験生間で大きな得点差がつくことは少なく、結果的に効率的な学習戦略とは言えないからです。
刑事訴訟法の勉強法で重要なのは、ほとんどの受験生が得点を取ることができる典型的な論点でミスを避け、しっかりと得点を確保することです。
典型論点を落とすと大きな得点差が生じ、試験全体の成績に大きく影響する可能性があるので注意しましょう。
マイナーな論点に手を広げるよりも頻出の重要論点を何度も復習し、重要論点を完璧に理解することに集中する方がより点数アップにつながります。
司法試験・予備試験の刑事訴訟法は時間軸を意識して勉強することが大事!
今回は、司法試験・予備試験合格に向けた刑事訴訟法の勉強法についてご紹介してきました。
刑事訴訟法は刑事事件の手続きを規定する法律で、捜査、公訴提起・公判手続、証拠、裁判の4つの主要な分野に分かれています。
令状主義や強制処分法定主義などの重要な原則が存在し、原則を理解するためには条文知識、制度の趣旨、判例などを正確に把握することが求められます。
また、刑事訴訟の各手続きには時間的制約が伴うことが多く、手続きの流れや時間軸を常に意識しながら学習を進めることが重要です。
刑事訴訟法を学ぶ際は、具体的な問題がどの手続きのどの段階に関連するのかを明確にすることで、より理解が深まり、答案作成時にも効果的な論述ができるようになります。
今回の記事をぜひ刑事訴訟法の勉強法の参考にしてみて下さいね。