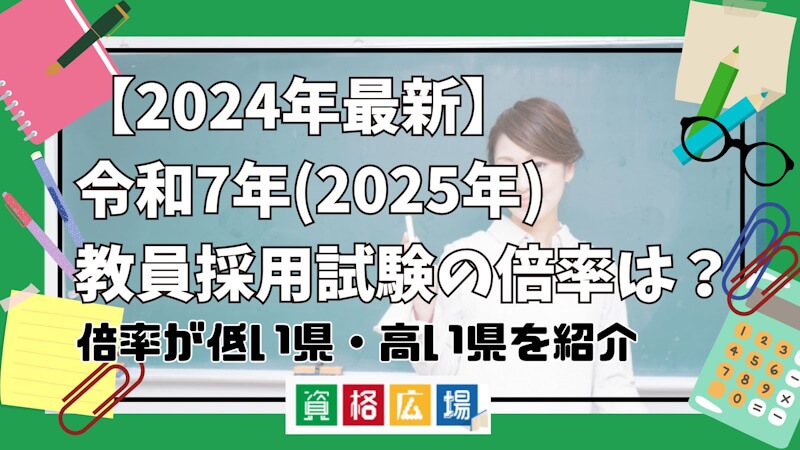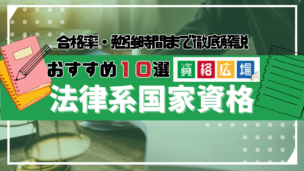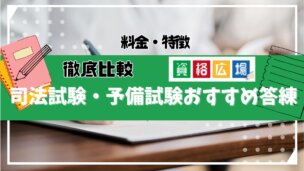教員採用試験は年に1度しかない重要な試験です。
試験合格を目指す方の中には、教員採用試験の倍率がどれくらいなのか気になる方も多いのではないでしょうか。
結論、団塊世代の定年退職などから、近年の教員採用試験の倍率は下降傾向にあります。
ただし、倍率が低いからといって試験の難易度も低いとは限りません。
また、各都道府県や自治体によっても、教員採用試験の倍率には差があります。
この記事では、近年の教員採用試験の倍率の推移や、倍率が低い都道府県・高い都道府県などを紹介します。
教員採用試験を受ける際の参考にしてください。
教員採用試験の難易度は高い?他資格とのランキング比較や合格率・偏差値・勉強時間の目安について解説
教員採用試験の倍率は下降傾向にある
文部科学省の最新の調査結果によると、令和5年(令和4年実施)の公立学校教員採用試験の全体の倍率は3.4%で、過去最低の倍率となりました。
過去10年の教員採用試験全体の倍率の推移は以下の通りです。
| 年度 | 受験者 | 採用者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 | 121,132名 | 35,981名 | 3.4倍 |
| 令和4年 | 126,390名 | 34,315名 | 3.7倍 |
| 令和3年 | 134,267名 | 35,067名 | 3.8倍 |
| 令和2年 | 138,042名 | 34,875名 | 4.0倍 |
| 令和元年 | 148,465名 | 34,952名 | 4.2倍 |
| 平成30年 | 160,667名 | 32,986名 | 4.9倍 |
| 平成29年 | 166,068名 | 31,957名 | 5.2倍 |
| 平成28年 | 170,455名 | 32,472名 | 5.2倍 |
| 平成27年 | 174,976名 | 32,247名 | 5.4倍 |
引用元:文部科学省『令和5年度(令和4年度実施)公立学校教員採用選考試験の実施状況のポイント』
上記の通り、教員採用試験の全体の倍率は、年々下降傾向にあります。
受験者数は年々下降傾向にありますが、一方で採用者数は上昇傾向にあるためです。
採用者数が増えている要因の一つは、団塊世代の定年退職により、教員の人材確保が必要になっているところにあります。
ただし一時的な要因ですので、倍率の下降傾向は数年程度で止まると考えて良いでしょう。
その後は、また倍率が上昇していく可能性がありますので、今のうちに教員採用試験を受けておきたいところです。
高等学校教諭資格取得の難易度は?試験情報・報酬相場を徹底分析
教員採用試験は倍率=難易度ではない
教員採用試験の倍率は、確かにその難易度をある程度反映しますが、倍率が高いからといって必ずしも難易度が高いわけではありません。
倍率とは応募者数と採用枠の割合を示すもので、一般的には倍率が高いほど競争が激しくなるため難易度が高いと考えられがちです。
しかし、実際の教員採用試験の難易度は、他の要因にも大きく影響されます。
例えばある地域では教員不足が深刻であり、比較的多くの採用枠が設けられているため倍率が低い場合でも、試験内容自体が非常に高度であることがあります。
逆に、人気の高い地域や学校では多くの人が応募するため倍率が高くなることがありますが、試験内容が比較的標準的であることも考えられます。
したがって、倍率の高さと難易度が比例しているとは一概には言えません。
教員採用試験は年に1度しかない試験です。
また、複数の自治体で試験を受けることが日程的に難しい場合もあります。
一発勝負なため、他の受験者のレベルは基本的に高いと考えると良いでしょう。
教員採用試験に合格するためには、入念な準備・試験対策をしてから臨んでください。
中学校教諭普通免許状資格取得の難易度は?試験情報・報酬相場を徹底分析
都道府県別|令和7年度(2025年)教員採用試験の倍率
令和6年度(2024年)に実施の、令和7年度(2025年)の教員採用試験の倍率をまとめました。
倍率は志願者数と採用予定者数をもとに算出しています。
また、各都道府県に加えて、一部指令都市の教員採用試験の倍率も算出してまとめています。
| 都道府県 (自治体) |
合計の 倍率 |
小学校の 倍率 |
中学校の 倍率 |
高校の 倍率 |
特別支援の 倍率 |
養護の 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | 2.9 | 0.9 | 4.6 |
| 札幌市 | 3.8 | 2.8 | 5.7 | 5.7 | 2.0 | 7.8 |
| 青森県 | 3.3 | 1.4 | 3.5 | 8.1 | 2.9 | 9.8 |
| 岩手県 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 4.6 |
| 宮城県 | 3.5 | 1.6 | 4.9 | 4.9 | 15.6 | – |
| 仙台市 | 4.2 | 2.7 | 5.1 | 5.1 | – | – |
| 秋田県 | 2.6 | 1.0 | 3.0 | 7.5 | 1.7 | 5.0 |
| 山形県 | 2.4 | 1.5 | 2.9 | 4.7 | 1.1 | 8.0 |
| 福島県 | 2.7 | 1.2 | 2.8 | 8.4 | 3.3 | 10.4 |
| 茨城県 | 3.0 | 1.9 | 3.3 | 4.7 | 1.8 | 10.8 |
| 栃木県 | 4.1 | – | – | – | – | – |
| 群馬県 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 4.8 | 2.9 | 6.1 |
| 埼玉県 | 3.0 | 2.0 | 3.7 | 4.2 | 1.5 | 9.3 |
| さいたま市 | 4.9 | 3.8 | 7.7 | 7.7 | 1.5 | 11.6 |
| 千葉県 | 2.4 | 1.6 | 2.8 | – | 2.7 | 6.5 |
| 千葉市 | 2.4 | 1.6 | 2.8 | – | 2.7 | 6.5 |
| 東京都 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 1.1 | 12.9 |
| 神奈川県 | 3.5 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 2.1 | 10.5 |
| 横浜市 | 3.1 | 1.9 | 5.2 | – | 3.4 | 11.5 |
| 川崎市 | 2.3 | 1.7 | 2.8 | 1.6 | 2.7 | 7.0 |
| 相模原市 | 3.6 | 2.7 | 4.2 | – | – | 17.0 |
| 新潟県 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 3.5 |
| 新潟市 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 7.4 |
| 富山県 | 2.0 | – | – | – | – | – |
| 石川県 | 3.0 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 17.8 |
| 福井県 | 3.1 | 2.3 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 7.9 |
| 山梨県 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 8.2 | 1.8 | 7.0 |
| 長野県 | 3.7 | 2.6 | 4.1 | 5.4 | 2.2 | 11.3 |
| 岐阜県 | 3.2 | 2.1 | 3.0 | 5.4 | 2.4 | 12.5 |
| 静岡県 | 4.3 | 3.0 | 6.2 | 5.5 | 1.8 | 21.7 |
| 浜松市 | 4.3 | 2.9 | 5.9 | – | 2.1 | – |
| 愛知県 | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 3.9 | 2.3 | 5.8 |
| 名古屋市 | 3.7 | 2.6 | 5.7 | 5.7 | 1.3 | 13.8 |
| 三重県 | 3.5 | 2.4 | 3.7 | 5.6 | 3.4 | 11.2 |
| 滋賀県 | 3.4 | 2.5 | 3.9 | 3.8 | 2.5 | 9.7 |
| 京都府 | 4.1 | 3.0 | 5.2 | 4.6 | 2.3 | 10.2 |
| 京都市 | 4.5 | 3.2 | 6.8 | 9.7 | 2.8 | 9.3 |
| 大阪府 | 4.6 | 3.4 | 5.1 | 6.7 | 2.7 | 12.1 |
| 大阪市 | 3.3 | 2.4 | 3.8 | – | – | 11.6 |
| 堺市 | 4.3 | 3.1 | 6.0 | – | – | 12.4 |
| 豊能地区 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | – | – | – |
| 兵庫県 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 5.0 | 3.2 | 9.3 |
| 神戸市 | 4.6 | 3.7 | 5.7 | 5.7 | 3.2 | 9.9 |
| 奈良県 | 5.0 | 4.0 | 5.4 | 5.6 | 3.4 | 12.1 |
| 和歌山県 | 3.8 | 3.0 | 5.4 | 3.4 | 2.6 | 6.4 |
| 鳥取県 | 5.2 | 3.4 | 5.8 | 8.5 | 6.9 | 24.6 |
| 島根県 | 3.3 | 2.1 | 2.7 | 7.3 | 2.4 | 11.0 |
| 岡山県 | 4.0 | 2.5 | 4.4 | 6.6 | 2.6 | 17.5 |
| 広島県 | 2.9 | 1.8 | 3.8 | 3.8 | 1.6 | 7.8 |
| 広島市 | 2.9 | 1.8 | 3.8 | 3.8 | 1.6 | 7.8 |
| 山口県 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | 3.9 | 2.2 | 21.0 |
| 徳島県 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 5.3 | 27.3 |
| 香川県 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 5.3 | 5.3 | 25.7 |
| 愛媛県 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 11.9 |
| 高知県 | 5.8 | 4.4 | 7.8 | 6.8 | 2.5 | 12.7 |
| 福岡県 | 2.5 | 1.2 | 2.1 | 5.7 | 1.6 | 20.8 |
| 北九州市 | 3.1 | 2.6 | 3.9 | – | 2.1 | 16.0 |
| 福岡市 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 8.0 | 1.7 | 16.1 |
| 佐賀県 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 5.8 | 1.5 | 11.2 |
| 長崎県 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 5.0 |
| 熊本県 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | – | 4.6 |
| 大分県 | 2.3 | 1.4 | 2.8 | 5.3 | 1.2 | 10.9 |
| 宮崎県 | 2.7 | 1.4 | 3.0 | 5.0 | 2.4 | 6.6 |
| 鹿児島県 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 6.8 | 1.5 | 3.8 |
| 沖縄県 | 5.5 | 2.8 | 5.3 | 14.9 | 10.9 | 35.0 |
特別支援学校教諭資格取得の難易度は?試験情報・報酬相場を徹底分析
令和7年度(2025年)教員採用試験の倍率が低い都道府県
令和6年度(2024年)に実施、令和7年度(2025年)の採用予定の教員採用試験の倍率の中から、倍率が低い都道府県や都市10選を、ランキング形式で以下にまとめました。
| 倍率が低い順 | 都道府県/都市 | 倍率 |
|---|---|---|
| 1位 | 新潟県 | 1.5 |
| 2位 | 長崎県 | 1.7 |
| 3位 | 富山県 | 2 |
| 4位 | 北海道 | 2.1 |
| 4位 | 佐賀県 | 2.1 |
| 4位 | 鹿児島県 | 2.1 |
| 5位 | 川崎市 | 2.3 |
| 5位 | 新潟市 | 2.3 |
| 5位 | 愛媛県 | 2.3 |
| 5位 | 大分県 | 2.3 |
倍率が最も低いのは新潟県で1.5倍でした。
また新潟市も倍率2.3で、8位にランクインしています。
その他、長崎県、富山県、北海道、佐賀県など、北海道・北陸や九州でのランクインが多い印象です。
最も倍率が高かったのは高知県の5.8倍で、新潟県とは約4倍もの差がありました。
なお、同じ都道府県でも自治体によって倍率は異なりますので、教員採用試験を受けたい自治体の倍率を事前に確認しておきましょう。
養護教諭(保健室の先生)の資格取得の難易度・仕事内容など紹介
令和7年度(2025年)教員採用試験の倍率が高い都道府県
次に、令和7年度(2025年)教員採用試験(令和6年実施)で、倍率が高い都道府県を見てみましょう。
| 倍率が低い順 | 都道府県/都市 | 倍率 |
|---|---|---|
| 1位 | 高知県 | 5.8 |
| 2位 | 沖縄県 | 5.5 |
| 3位 | 鳥取県 | 5.2 |
| 4位 | 奈良県 | 5 |
| 5位 | さいたま市 | 4.9 |
| 6位 | 豊能地区 | 4.7 |
| 7位 | 大阪府 | 4.6 |
| 7位 | 神戸市 | 4.6 |
| 7位 | 京都市 | 4.6 |
| 8位 | 徳島県 | 4.5 |
倍率が最も高いのは、高知県で5.8です。
次いで沖縄県が5.5、鳥取県が5.2という結果でした。
地方でも教員採用試験の倍率が高いところは多いようです。
また、奈良県・大阪府・神戸市・京都市など、関西圏の自治体からのランクインが多めになっています。
あくまでも目安の倍率ですが、教員採用試験を受験する際の参考にしてください。
教員採用試験の採用者の出身学歴
| 区分 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 計(※) |
|---|---|---|---|---|
| 国立教員養成大学・学部 | 4,857(4,801)人 | 2,349(2,148)人 | 691(693)人 | 8,815(8,578)人 |
| 一般大学・学部 | 11,042(10,145)人 | 6,268(6,059)人 | 3,084(2,989)人 | 23,756(22,252)人 |
| 短期大学等 | 444(469)人 | 124(125)人 | 39(34)人 | 825(861)人 |
| 大学院 | 691(752)人 | 848(820)人 | 785(778)人 | 2,585(2,624)人 |
| 計 | 17,034(16,167)人 | 9,589(9,152)人 | 4,599(4,494)人 | 35,981(34,315)人 |
参照:文部科学省『令和5年度(令和4年度実施)公立学校教員採用選考試験の実施状況のポイント』
令和5年度の教員採用試験の採用者のうち、おおよそ60%以上が一般大学・学部卒出身者であることがわかりました。
一般大学・学部卒の次に採用者の割合が高かった国立教員養成大学・学部卒の割合は全体の20%程度で、大学院卒の割合は7.2%・短期大学等の割合は2.3%であり、いずれも10%未満となっています。
教員採用試験の倍率は年々低下している
教員採用試験の倍率は、年々減少傾向にあります。
教員採用試験の全国平均倍率から見ても過去の平成12年度の平均倍率は13.3倍と最も高く、令和5年度の平均倍率は3.4倍と最も低い結果となっています。
一方、平成14年度以降の平均倍率はほぼ一貫して低下しており、平成24年度以降は6倍を下回っています。
倍率が低下している主な要因としては採用者数の増加と受験者数の減少にだと考えられます。
最近では、過去に大量に採用された教員が定年を迎える時期に差し掛かっており、多くの自治体が採用者数を増やしてるといった状況となっています。
また、教員を目指す新卒者の数も減少傾向にあり、受験者数も減少しています。
採用倍率は受験者数を採用者数で割ることで算出されるため、同じ受験者数に対して採用者数が増加すれば、採用倍率は低下します。
逆に、同じ採用者数に対して受験者数が減少した場合も、採用倍率は低くなります。
しかし採用倍率が低くても教員採用試験に合格するにはスキルや知識が必要不可欠となっているので、倍率に関わらず万全の対策が必要です。
教員採用試験の試験内容
教員採用試験は一般的に筆記試験・論文試験・面接試験・実技試験から構成冴えるのが一般的です。
しかし詳しい試験内容は自治体によって異なるので、ホームページでチェックしておくことが大事です。
筆記試験
教員採用試験の筆記試験は教職教養・一般教養・専門教養の3つに分かれており、試験内容は以下の通りとなります。
- 教職教養…教育原理、教育法規、教育心理、教育史、教育時事
- 一般教養…教科問題(国語、算数、英語、理科、社会)時事問題、一般常識
- 専門教養…志望教科に関する専門知識、指導要領、指導方法など
教職教養試験では教員としてはたらくために必要な教養が問われます。
試験内容としては学習指導要領についての理解を深めることに加え、文部科学省からの指示や人権教育の基本理念についても学ぶことが重要です。
一般教養試験の教科問題では、高校レベルの5教科に関する知識について聞かれる以外、時事問題や一般常識に関しては、過去3年間の主要なニュースや出来事に関連する問題が出題されることもあります。
また専門教養試験では、志望する教科に特化した専門的な内容が出題されます。
出題内容は志望する区分によって異なり、中学や高校の各科目を志望する場合には大学レベルの知識が必要となるといわれています。
論文試験
教員採用試験の論文試験では、決められたテーマについて制限時間内に指定の文字数で論文を作成するものとなっています。
過去のテーマだと「児童・生徒一人ひとりの長所や可能性を引き出し、伸ばすための教育」に対する自分の考えなどについてきかれるものがありました。
過去問などを繰り返し解くことで、問題の傾向や回答のポイントを掴むようにするといいでしょう。
面接試験
面接試験は、教員としての適性や情熱を評価するための試験です。
近年では各自治体において人物重視の傾向が強まっているため、面接試験はかなり重要な試験となっているので対策が必要です。
面接の形式は自治体ごとに異なりますが、多くの自治体では複数回の面接が実施されることがほとんど。
例えば、愛知県では、2回の口述試験を通じて愛知が求める教師像に合致しているかどうかで採用が決まります。
志望する自治体の試験内容をしっかりと把握し、十分な準備を行うことが重要です。
第三者に面接してもらうなど、客観的な意見をもらうことで本番でも自信をもって臨めるでしょう。
実技試験
実技試験は、受験者が希望する学校種や教科に応じた実技を評価するための試験です。
試験は全ての受験者に実施されるわけではなく、おもに小学校の教員や中学校・高校の音楽、美術、家庭科、英語、保健体育などの教員を目指す方々が対象となります。
また実技試験の具体的な内容は教科によって異なりますが、音楽では歌唱やピアノ演奏、家庭科では被服製作や調理、美術ではデッサンなどが行われるといわれています。
実技試験を受ける際は事前に志望する自治体の試験内容を確認し、練習を重ねることが大事です。
教員採用試験のスケジュール
教員採用試験の一般的なスケジュールは以下の通りとなります。
| 出願時期 | 3月下旬〜4月 |
| 一次試験 | 6〜7月 |
| 二次試験 | 8〜9月 |
| 合格発表 | 9月下旬〜10月 |
教員採用試験の出願期間は3月下旬から4月にかけておこなわれ、一次試験は6月から7月に行われます。
さらに、二次試験は8月から9月に実施され、合格発表は9月下旬から10月にかけて行われます。
一部の自治体では一次試験や二次試験が複数回行われたり、三次試験が実施されることもあるので注意が必要です。
ただし、教員採用試験の日程は各自治体によって異なるため、 詳細な日程については、各自治体の公式ウェブサイトをかくにんするようにしましょう。
また教員採用試験の勉強は試験1年前の5月~7月ごろから始めるのがベストであり、計画的に進めることが大事です。
倍率が高くても教員採用試験に合格するならアガルートを受講しよう
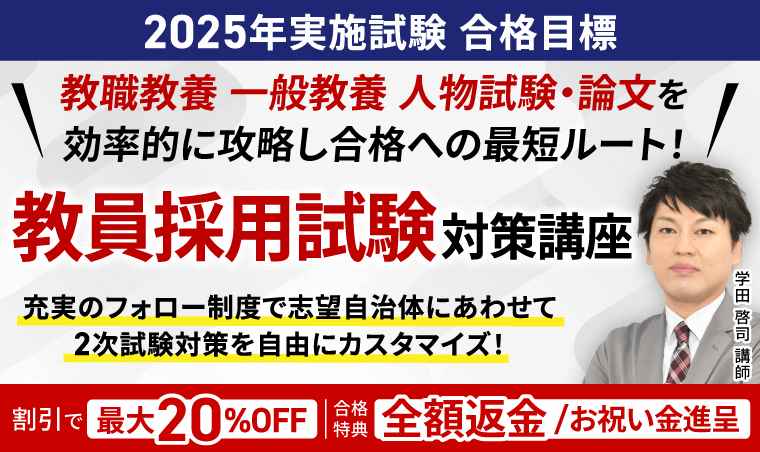
アガルートの教員採用試験対策講座は、志望する自治体に合わせてカリキュラムをカスタマイズできます。
合格カリキュラムは以下の通りです。
- 2025/教員採用試験/合格カリキュラム・・・107,800円(税込)
- 【オプション】オフィスアワー追加申込み(1回分)・・・16,500円(税込)
- 【オプション】追加添削(1回分)・・・1,650円(税込)
また、以下の単科講座のみの受講も可能です。
- 2025/教員採用試験/合格総合講義/教職教養・・・43,780円(税込)
- 2025/教員採用試験/合格総合講義/人物試験・論文・・・43,780円(税込)
- 2025/教員採用試験/合格総合講義/一般教養・・・43,780円(税込)
フォロー制度が手厚く、自分に最適なカリキュラムを見つけられます。
最大20%OFFになる割引制度もあるので、ぜひ活用してください。
合格すれば全額返金か、祝い金をもらえる点もアガルートならではの特徴です。
倍率が高い自治体でも最短ルートで合格したい方は、アガルートの教員採用試験対策講座の受講をぜひ検討してみてください。
教師になるには資格が必須!教師になるための進路・大学・勉強とは?
教員採用試験の倍率を事前に確認しておこう!
教員採用試験の倍率は、団塊世代の定年退職の影響で近年は下降気味です。
令和7年度(2025年)の教員採用試験試験(令和6年実施)では、倍率が最も低いのは新潟県で1.5倍でした。
倍率が最も高いのは高知県で5.8倍です。
ただし、団塊世代の定年退職の影響は徐々に薄まり、再び倍率は上昇していくと考えられます。
なお、倍率が高い=難易度が高いというわけではありません。
倍率の高さに関わらず、教員採用試験合格に向けて万全を期しましょう。
志望自治体に最適なカリキュラムで学習を進めたい方は、アガルートの教員採用試験対策講座の受講をおすすめします。
最大20%OFFでリーズナブルに受講できます。