造園施工管理技士検定の受験資格は、1級・2級ともに令和6年以降変更となります。
この記事では、1級2級の造園施工管理技術検定の新受験資格について、実務経験なしでも良いのか、学歴は必要なのかなどをそれぞれ徹底解説します。
また、令和6年後も令和5年度までの旧受験資格で受験できる例も紹介します。
造園施工管理技士検定の受験を検討している方は必見です。
マイナーだけど一生食べていけるすごい資格19本!受験資格や受験料・合格率について紹介【最新】
令和6年以降|1級造園施工管理技術検定の新受験資格
1級造園施工管理技術検定の受験資格は、令和6年(2024年)以降新しく変わりました。
第1次検定と第2次検定それぞれで、1級造園施工管理技術検定の新受験資格を詳しく紹介します。
- 1級造園施工管理技術検定|第1次検定の受験資格
- 1級造園施工管理技術検定|第2次検定の受験資格
造園施工管理技士資格取得の難易度は?試験情報・報酬相場を徹底分析
1級造園施工管理技術検定|第1次検定の新受験資格
| 1級造園施工管理技術検定 | 19歳以上(受検年度末時点での年齢) |
|---|
引用元:一般財団法人 全国建設研修センター『令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります【新受検資格】 』
令和6年(2024年)以降、1級造園施工管理技術検定の第1次検定は、受験年度末時点での年齢が19歳以上の方は誰でも受験できます。
平成18年4月1日に生まれた方も含むれませす。
第1次検定では、学歴や実務経験などは問われません。
従前は一定の学歴や実務経験を満たす必要がありましたが、令和6年以降は一定年齢以上の方は受験できる門戸の広い国家資格になっています。
1級造園施工管理技術検定|第2次検定の新受験資格
| 受験資格要件 | 第2次検定の受験に必要な実務経験年数 |
|---|---|
| 令和3年度以降の 1級 第1次検定合格者 |
合格後 5年以上の実務経験年数 |
| 合格後 特定実務経験(※1)1年以上を含む 3年以上の実務経験年数 |
|
| 合格後 監理技術者補佐(※2)としての 1年以上の実務経験年数 |
|
| 2級第2次検定(旧実地試験含む)に合格した後、 1級 第1次検定に合格した者 (1級 第1次検定受検予定者を含む) |
2級合格後 5年以上の実務経験年数 |
| 2級合格後 特定実務経験(※1)1年以上を含む 3年以上の実務経験年数 |
|
| 技術士第2次試験合格者 (土木施工管理技術検定のみ) |
合格後 5年以上の実務経験年数 |
| 合格後 特定実務経験(※1)1年以上を含む 3年以上の実務経験年数 |
(※1)特定実務経験とは、通常の実務経験の要件に加えて,建設業法の適用を受ける請負金額 4,500 万円(建築一式工事は 7,000 万円)以上の
建設工事において、監理技術者または主任技術者(当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下又は自ら監理技術者
若しくは主任技術者として施工管理を行った経験をいいます。
(※2)監理技術者補佐としての実務経験は、対象となる業種の主任技術者資格を有する者が、1 級第1次検定に合格後、特例監理技術者(2つの現場を
兼務している監理技術者)のもとで1つの現場に専任配置された工事に関するものに限ります。単なる監理技術者の補助等は認められません。
引用元:一般財団法人 全国建設研修センター『令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります【新受検資格】 』
1級造園施工管理技術検定の第2次検定では、第1次検定とは異なり実務経験が問われます。
受験資格要件と実務経験を確認して、自分が受験資格を満たしているか確認してください。
なお、令和10年度(2028年)までは、新受験資格または旧受験資格のどちらかで受験できます。
旧受験資格の詳細は後述でチェックしましょう。
令和6年以降|2級造園施工管理技術検定の新受験資格
2級造園施工管理技術検定の受験資格は、第1次検定は従前通り、第2次検定は令和6年(2024年)以降から変更されています。
1級2級それぞれで、受験資格を詳しく紹介するので参考にしてください。
- 2級造園施工管理技術検定|第1次検定の受験資格
- 2級造園施工管理技術検定|第2次検定の新受験資格
造園技能士資格取得の難易度は?試験情報・年収・給料・報酬相場を分析
2級造園施工管理技術検定|第1次検定の受験資格
| 2級造園施工管理技術検定 | 17歳以上(受検年度末時点での年齢) |
|---|
引用元:一般財団法人 全国建設研修センター『令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります【新受検資格】 』
2級造園施工管理技術検定の第1次検定の受験資格は、従前から変更はありません。
受験年度末時点の年齢が、17歳以上であれば誰でも受験可能です。
平成20年4月1日に生まれた方も含まれます。
また、従前通り学歴や実務経験に制限はありません。
2級造園施工管理技術検定|第2次検定の新受験資格
| 受験資格要件 | 第2次検定の受験に必要な実務経験年数 |
|---|---|
| 令和3年度以降の 1級 第1次検定合格者 |
合格後 1年以上の実務経験年数 |
| 令和3年度以降の 2 級 第1次検定合格者 |
合格後 3年以上の実務経験年数 |
| 技術士第2次試験合格者 (土木施工管理技術検定のみ) |
合格後 1年以上の実務経験年数 |
| 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者、 又は電気通信主任技術者試験合格者であって 1級又は2級 第1次検定合格者 (電気通信工事施工管理技術検定のみ) |
電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた後、 又は電気通信主任技術者試験合格後 1年以上の実務経験年数 |
引用元:一般財団法人 全国建設研修センター『令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります【新受検資格】 』
2級造園施工管理技術検定の第2次検定では、上記いずれかの受験資格要件と実務経験を満たす必要があります。
実務経験は最低でも1年以上必要になりますので、第1次検定に合格してすぐに第2検定を受験できるとは限らない点に注意してください。
なお、2級造園施工管理技術検定の第2次検定は、1級造園施工管理技術検定と同様に、令和10年度(2028年)までは新受験資格または旧受験資格のいずれかを受験可能です。
詳細は以下で解説します。
施工管理技術検定を旧受験資格で受験できるケース
令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります。
第2次検定は、新受検資格に変わりますが、令和6年度から令和10年度までの5年間は制度改正に伴う経過措置として、【令和6年度からの新受検資格】と【令和5年度までの旧受検資格】のどちらの受検資格でも受検が可能です。 一般財団法人 全国建設研修センター『1級造園施工管理技術検定』
上述の通り、施工管理技術検定は令和6年(2024年)~令和10年(2028年)まで、新受験資格または旧受験資格のどちらかでの験できると公式サイトに記載されています。
ここでは、施工管理技術検定の第2検定の旧受験資格をそれぞれ紹介します。
新受験資格と比較して、最適な方を選びましょう。
なお、申込締切後は、受験資格の新旧の変更はできません。
- 1級造園施工管理技術検定|第2次検定の旧受験資格
- 2級造園施工管理技術検定|第2次検定の旧受験資格
造園施工管理技術検定の旧受験資格を詳しく見てみましょう。
1級造園施工管理技術検定|第2次検定の旧受験資格
令和3年度(2021年)以降の1級第1次検定に合格し、以下(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)のいずれかで実務経験がある方は、令和5年までの旧受験資格で1級造園施工管理技術検定の第2次検定を受験できます。
(イ)
| 区分 | 学歴と資格 | 必要な実務経験年数 | |
|---|---|---|---|
| 指定学科 | 指定学科以外 | ||
| (イ) | 学校教育法による ・大学 ・専門学校の「高度専門士」 |
卒業後3年以上 の実務経験年数 |
卒業後4年6ヵ月以上 の実務経験年数 |
| (1年以上の指導監督的実務経験年数が 含まれていること) |
|||
| 学校教育法による ・短期大学 ・高等専門学校(5年制) ・専門学校の「専門士」 |
卒業後5年以上 の実務経験年数 |
卒業後7年6ヵ月以上 の実務経験年数 |
|
| (1年以上の指導監督的実務経験年数が 含まれていること) |
|||
| 学校教育法による ・高等学校 ・中等教育学校(中高一貫6年) ・専修学校の専門課程 |
卒業後10年以上 の実務経験年数 |
卒業後11年6ヵ月以上 の実務経験年数 |
|
| (1年以上の指導監督的実務経験年数が 含まれていること) |
|||
| その他(学歴を問わず) | 15年以上の実務経験年数 (1年以上の指導監督的実務経験年数が 含まれていること) |
||
引用元:一般財団法人 全国建設研修センター『1級造園施工管理技術検定』
(ロ)
| 区分 | 学歴と資格 | 造園施工管理に関する 必要な実務経験年数 |
||
|---|---|---|---|---|
| 指定学科 | 指定学科以外 | |||
| (ロ) | 2級造園施工管理技術検定第2次検定に合格した者 (令和2年度までは実地試験) |
合格後5年以上の実務経験年数 (本年度該当者は平成30年度までの 合格者) (1年以上の指導監督的実務経験年数が 含まれていること) |
||
| 2級造園施工管理技術検定第2次検定合格後、実務経験が5年未満の者 (令和2年度までは 実地試験) |
学校教育法による ・高等学校 ・中等教育学校 (中高一貫6年) ・専修学校の専門課程 |
卒業後9年以上 の実務経験年数 |
卒業後 10年6ヵ月以上 の実務経験年数 |
|
| (1年以上の指導監督的実務経験年数が 含まれていること) |
||||
| その他(学歴を問わず) | 14年以上の実務経験年数 (1年以上の指導監督的実務経験年数が 含まれていること) |
|||
引用元:一般財団法人 全国建設研修センター『1級造園施工管理技術検定』
(ハ)
| 区分 | 学歴と資格 | 造園施工管理に関する 必要な実務経験年数 |
|
|---|---|---|---|
| 指定学科 | 指定学科以外 | ||
| (ハ) | 技能検定合格者
職業能力開発促進法による1級「造園」技能検定合格者 |
10年以上の実務経験年数
1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること。 |
|
引用元:一般財団法人 全国建設研修センター『1級造園施工管理技術検定』
(ニ)
| 区分 | 学歴と資格 ※専任の主任技術者の実務経験が1年(365日)以上ある者 |
造園施工管理に関する 必要な実務経験年数 |
||
|---|---|---|---|---|
| 指定学科 | 指定学科以外 | |||
| (ニ) | 2級造園施工管理技術検定第2次検定に合格した者 (令和2年度までは実地試験) |
合格後3年以上の実務経験年数 (本年度該当者は令和2年度までの 合格者) |
||
| 2級造園施工管理技術検定第2次検定合格後、実務経験が3年未満の者 (令和2年度までは実地試験) |
学校教育法による ・短期大学 ・高等専門学校(5年制) ・専門学校の「専門士」 |
- | 卒業後7年以上 の実務経験年数 |
|
| 学校教育法による ・高等学校 ・中等教育学校 (中高一貫6年) ・専修学校の専門課程 |
卒業後7年以上 の実務経験年数 |
卒業後8年6ヵ月以上 の実務経験年数 |
||
| その他(学歴を問わず) | 12年以上の実務経験年数 | |||
| その他 | 学校教育法による ・高等学校 ・中等教育学校 (中高一貫6年) ・専修学校の専門課程 |
卒業後8年以上 の実務経験年数 |
卒業後9年6ヵ月以上 の実務経験年数職業能力開発促進法による2級「造園」技能検定合格者に限ります。(合格証書の写しが必要です。)この資格を取得していない場合11年以上の実務経験年数が必要です。 |
|
| その他(学歴を問わず) | 13年以上の実務経験年数 | |||
引用元:一般財団法人 全国建設研修センター『1級造園施工管理技術検定』
(ホ)
| 区分 | 学歴と資格 | 造園施工管理に関する 必要な実務経験年数 |
||
|---|---|---|---|---|
| 指定学科 | 指定学科以外 | |||
| 指導監督的実務経験年数が1年以上、主任技術者の資格要件成立後、専任の監理技術者の指導のもとにおける実務経験が2年以上ある者 | 2級造園施工管理技術検定第2次検定に合格した者(令和2年度までは実地試験) | 合格後3年以上の実務経験年数 (本年度該当者は令和2年度までの 合格者)※2級合格後、以下の両方を含む3年以上の実務経験年数を有している者 ・指導監督的実務経験年数を1年以上 ・専任の監理技術者の配置が必要な工事において、監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験年数 |
||
| 学校教育法による ・高等学校 ・中等教育学校 (中高一貫6年) ・専修学校の専門課程 |
指定学科を卒業後8年以上の実務経験年数
※左記学校の指定学科を卒業後、以下の両方を含む8年以上の実務経験年数を有している者 |
|||
引用元:一般財団法人 全国建設研修センター『1級造園施工管理技術検定』
2級造園施工管理技術検定|第2次検定の旧受験資格
2級造園施工管理技術検定の第2次検定の旧受験資格を満たすには、以下イ、ロのいずれかに該当する必要があります。
- イ|2級造園施工管理技術検定・第1次検定の合格者で、一定の要件を満たす方
- ロ|第1次検定免除者
イ|2級造園施工管理技術検定・第1次検定の合格者で、一定の要件を満たす方
2級造園施工管理技術検定・第1次検定の合格者で、次のいずれかに該当する場合、2級造園施工管理技術検定の第2次検定を受験できます。
| 学歴又は資格 | 造園施工に関する実務経験年数 | |
|---|---|---|
| 指定学科の卒業者 | 指定学科以外の卒業者 | |
| 大学卒業者 専門学校卒業者(「高度専門士」に限る) |
卒業後1年以上 | 卒業後1年6月以上 |
| 短期大学卒業者 高等専門学校卒業者 専門学校卒業者(「専門士」に限る) |
卒業後2年以上 | 卒業後3年以上 |
| 高等学校卒業者 中等教育学校卒業者 専修学校の専門課程卒業者 |
卒業後3年以上 | 卒業後4年6月以上 |
| その他の者 | 8年以上 | |
| 技能検定合格者 | 4年以上 | |
※1指定学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、園芸学、林学、都市工学、交通工学又は建築学に関する学科をいいます。
※2技能検定合格者とは、平成16年度以後の職業能力開発促進法による2級造園技能検定合格者 で、4年以上の実務経験年数がある者のことです。(1級造園技能検定合格者および平成15 年度までの2級造園技能検定合格者は実務経験年数は不要。)
※3実務経験年数は、2級第2次検定の前日(令和6年11月16日(土))までで計算してください。
※4高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、旧大学入学試験検定規則(昭和26年文部省令第13号)による検定、旧専門学校入学者検定規則(大正13年文部省令第22号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規定(大正8年文部省令第9号)による試験に合格した者を含みます。
引用元:一般財団法人 全国建設研修センター『2級造園施工管理技術検定』
ロ|第1次検定免除者
- 平成28年度以降の学科試験のみを受検し合格した者で、(2)イのうち第1次検定の合格を除く2級造園施工管理技術検定・第2次検定の受検資格を有する者(当該合格年度の初日から起算して12年以内に連続2回の第2次検定を受検可能)
- 技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち、技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「林業・林産」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係わるもの、「農業農村工学」、「林業・林産」又は「森林土木」とするものに限る。)に合格した者で、第1次検定の合格を除く2級造園施工管理技術検定・第2次検定の受検資格を有する者(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の第2次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)、林業部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「林業」又は「森林土木」とするものに限る)とするものに合格した者を含む。また、技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第45号)による改正前の第2次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「林業」又は「森林土木」とするものに限る)とするものに合格した者を含む。)
- 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、平成27年度までの2級の技術検定の学科試験に合格した後、学校教育法による大学を卒業(高等学校又は中等教育学校在学中及び大学在学中に規則第2条に定める学科を修めたものに限る。)し、高等学校又は中等教育学校を卒業した後8年以内に行われる連続する2回の実地試験(第2次検定)を受検しようとする者で、造園施工管理に関し1年以上の実務経験を有する者
※ 実務経験年数は、2級第1次(後期)・第2次検定の前日(令和6年11月16日(土))までで計算してください。
※ 「実務経験」とは、造園工事の施工に直接的に関わる技術上のすべての職務経験をいい、具体的には下記に関するものをいいます。
・受注者(請負人)として施工を指揮・監督した経験(施工図の作成や、補助者としての経験も含む)
・発注者側における現場監督技術者等(補助者も含む)としての経験
・設計者等による工事監理の経験(補助者としての経験も含む)
なお、施工に直接的に関わらない以下の経験は含まれません。
・設計のみの経験
・造園工事の単なる雑務や単純な労務作業、事務系の仕事に関する経験
引用元:一般財団法人 全国建設研修センター『2級造園施工管理技術検定』
1級2級造園施工管理技術検定の基本情報
1級・2級造園施工管理技術検定の最新の基本情報を以下にまとめました。
受験資格を満たしているか確認したら、令和6年度(2024年)の最新スケジュールや必要情報をチェックして、試験本番に備えましょう。
| 令和6年度(2024年) | 1級造園施工管理技術検定 | 2級造園施工管理技術検定 |
|---|---|---|
| 申込期間 | インターネット:5月7日(火)~5月21日(火)23:59 書面:5月7日(火)~5月21日(火) |
【第1次検定(前期)】 インターネット:3月6日(水)~3月21日(木)23:59 【第1次検定・第2次検定、第1次検定(後期)、第2次検定】 インターネット:7月9日(火)~7月23日(火)23:59 書面:7月9日(火)~7月23日(火) |
| 申込用紙の販売 | 郵送:4月9日(火)~5月13日(月) 窓口売:4月9日(火)~5月21日(火) |
郵送:6月24日(月)~7月15日(月) 窓口:6月24日(月)~7月23日(火) |
| 試験日 | 第1次検定:9月1日(日) 第2次検定試験日:12月1日(日) |
第1次検定(前期): 6月2日(日) 第1次検定(後期)、第2次検定: 11月17日(日) |
| 合格発表 | 第1次検定:10月3日(木) 第2次検定:令和7年3月5日(水) |
第1次検定(前期):7月2日(火) 第1次検定(後期)、第2次検定、第1次検定(後期): 令和7年1月6日(月) 第2次検定: 令和7年3月5日(水) |
| 受検手数料 | 第1次検定:14,400円(非課税) 第2次検定:14,400円(非課税) |
第1次検定・第2次検定: 14,400円(非課税) 第1次検定: 7,200円(非課税) 第2次検定:7,200円(非課税) |
造園施工管理技術検定に合格するならアガルートを受講しよう
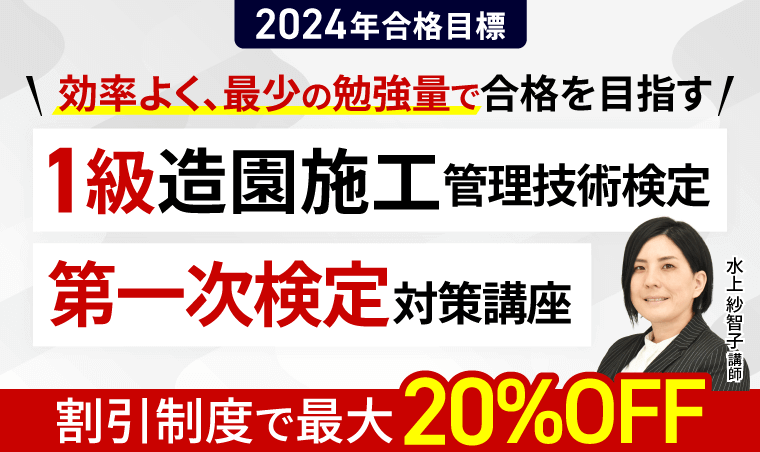
アガルートでは、最短ルートで造園施工管理技術検定の合格を目指せます。
オンライン講座なので、自分のペースで学習を進めることができ、忙しい社会人にもピッタリ!
効率的かつ体系的なカリキュラムが特徴です。
初学者も学習経験者も、必要最小限の勉強量・時間で合格を狙えます。
対応講座は以下の通りです。
- 2024年合格目標 1級第1次検定対策講座・・・162,800円(税込)
最大20%OFFになる割引制度も実施しているのでお得です。
1級2級造園施工管理技術検定の受験資格を理解しておこう
令和6年(2024年)以降の造園施工管理技術検定試験の新受験資格を、以下にまとめました。
【造園施工管理技術検定|第1次検定の新受験資格】
| 1級 | 19歳以上(受検年度末時点での年齢) |
|---|---|
| 2級 | 17歳以上(受検年度末時点での年齢)従前から変更なし |
引用元:一般財団法人 全国建設研修センター『令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります【新受検資格】 』
造園施工管理技術検定の第1次検定では、1級2級のいずれも一定の年齢要件を満たしていればOKです。
学歴や実務経験を問われません。
【造園施工管理技術検定|第2次検定の新受験資格】
| 区分 | 受験資格要件 | 第2次検定の受験に必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
| 1級 | 令和3年度以降の 1級 第1次検定合格者 |
合格後 5年以上の実務経験年数 |
| 合格後 特定実務経験(※1)1年以上を含む 3年以上の実務経験年数 |
||
| 合格後 監理技術者補佐(※2)としての 1年以上の実務経験年数 |
||
| 2級第2次検定(旧実地試験含む)に合格した後、 1級 第1次検定に合格した者 (1級 第1次検定受検予定者を含む) |
2級合格後 5年以上の実務経験年数 | |
| 2級合格後 特定実務経験(※1)1年以上を含む 3年以上の実務経験年数 |
||
| 技術士第2次試験合格者 (土木施工管理技術検定のみ) |
合格後 5年以上の実務経験年数 | |
| 合格後 特定実務経験(※1)1年以上を含む 3年以上の実務経験年数 |
||
| 2級 | 令和3年度以降の 1級 第1次検定合格者 |
合格後 1年以上の実務経験年数 |
| 令和3年度以降の 2 級 第1次検定合格者 |
合格後 3年以上の実務経験年数 | |
| 技術士第2次試験合格者 (土木施工管理技術検定のみ) |
合格後 1年以上の実務経験年数 | |
| 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者、 又は電気通信主任技術者試験合格者であって 1級又は2級 第1次検定合格者 (電気通信工事施工管理技術検定のみ) |
電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた後、 又は電気通信主任技術者試験合格後 1年以上の実務経験年数 |
引用元:一般財団法人 全国建設研修センター『令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります【新受検資格】 』
造園施工管理技術検定の第2次検定では、受験資格要件に応じて必要な実務経験年数が異なる点に注意してください。
なお、制度改正に伴う経過措置として、第2次検定では令和10年(2028年)までは新受験資格と旧受験資格のどちらでも受験可能です。
自分にとって最適な方の受験資格を選んで、造園施工管理技術検定に臨みましょう。










