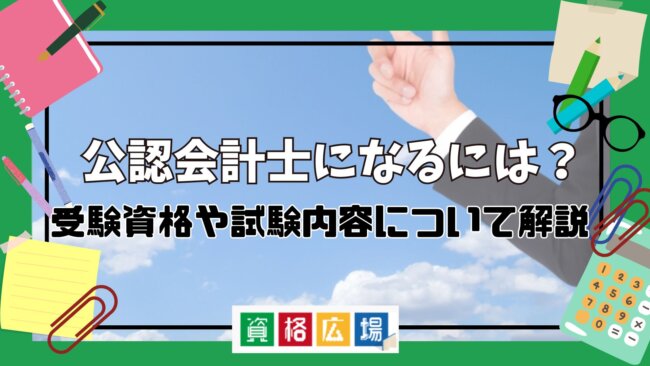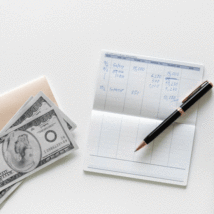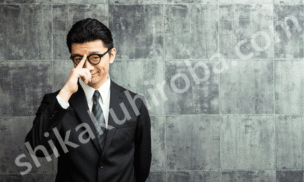公認会計士は幅広い年齢層の男女が目指せる、会計と監査の専門家仕事です。
専門性の高い資格であることから就職や転職、キャリアアップにも役立ちます。
そこで今回は公認会計士の難易度や年収相場などについて紹介します。
CPA会計学院で公認会計士を目指す
公認会計士ってどんな仕事?

公認会計士は、企業の監査業務・会計業務・コンサイルティング業務・税務業務を主に行います。
特に最初に述べた「監査業務」は、会社が作成した損益計算書や貸借対照表等の財務諸表について、会社とは独立した第三者である公認会計士が適正であるかを述べる必要がある為、公認会計士にしかできない仕事とも言えます。
企業の経営や会計に関して専門知識を生かしてアドバイスやさまざまな提案(合併や経営戦略について)をすることで企業の経営サポートをするのも公認会計士のお仕事です。
公認会計士になるには
公認会計士になるには公認会計士試験に合格する必要があり、試験には短答式・論文式試験に突破しなければいけません。
ここでは、公認会計士になるためのステップについて紹介します。
受験資格
公認会計士になるには公認会計士試験に合格する必要があり、受験資格はありません。
2005年以前の旧試験制度では、大学卒業や旧1次試験の合格が受験資格として求められていました。
しかし、2006年度以降の新試験制度では、受験資格に関する制限が撤廃され、年齢、性別、学歴、国籍に関係なく、誰でも公認会計士試験を受けることができるようになりました。
実際、高校卒業者や大学在学中に合格する人が増え、さまざまな年代の合格者が誕生しています。
公認会計士試験は誰でもいつでもチャレンジできるといえます。
短答式試験
短答式試験は年に2回の受験チャンスがあり、第I回は12月の初めに、第II回は翌年の5月の終わりに、いずれも日曜日に実施されます。
試験科目は合計4科目で構成されており、企業法(60分/100点)、管理会計論(60分/100点)、監査論(60分/100点)、財務会計論(120分/200点)が含まれており、特に財務会計論の配点が高いことが特徴です。
短答式試験に合格すると、その年、翌年、さらには翌々年の3年間にわたり論文式試験を受験することができるようになります。
短期合格を目指すためには、まず短答式試験に合格することが重要です。
論文式試験
短答式試験に合格しあら論文式試験の受験資格を得られ、論文式試験は年1回、8月下旬の3日間(金土日)に例年おこなわれています。
- 1日目…監査論(120分/100点)・ 租税法(120分/100点)
- 2日目…会計学午前(120分/100点)・ 会計学午後(180分/200点)
- 3日目…企業法(120分/100点)・ 選択科目(120分/100点)
論文式試験は相対評価に基づく試験であり、短答式試験に合格した受験者が対象となります。
受験生は、経営学、経済学、民法、統計学の中から1科目を選択することができますが、ボリュームが少ない経営学を選ぶのが一般的です。
また、会計学の午前の部は管理会計論、午後の部は財務会計論に相当し、短答式試験と同様に財務会計論(いわゆる簿記)の配点が高く設定されています。
論文式試験の合格基準は、受験科目の総合成績において得点比率52となっており、もし1科目でも得点比率が40%に達しない場合、合格できない可能性があります。
したがって、苦手分野を作らず、均等に知識を習得することが論文式試験を突破するための重要なポイントとなります。
公認会計士として登録するまでのステップ
公認会計士試験の論文式試験をクリアしても、実際に公認会計士に慣れるわけではありません。
実務要件・所定の単位取得が終わると終了黄砂の受験資格が与えられ、合格すれば公認会計士に慣れます。
ここでは、試験に合格してから公認会計士として登録するまでのステップについて紹介します。
3年間の就労経験
公認会計士になるには以下の条件で3年間積む必要があります。
- 監査法人での監査経験
- 国・地方自治体での監査経験
- 金融機関での資金運用(ファイナンス)の経験
- 資本金5億円以上の事業会社での原価計算・財務分析の経験
上記の中で最も多いのは監査法人での監査経験です。
監査法人での実務経験は最終的に受験する修了考査の勉強にもつながります。
実務補修所での計270単位の取得
実務補習所とは公認会計士論文式試験に合格した者(正確には、公認会計士協会の準会員)が公認会計士として登録するために必要な単位を取得するための研修機関及びその制度のことです。
公認会計士協会の準会員となると、1年目から3年目までの間に合計270単位を取得することが求められます。(1単位は約1時間の講義に相当します)
授業形式には、対面でのライブ講義とe-learning形式の講義があり、必修科目以外は自由に選択することができます。
さらに、補習所での学習成果を確認するために、定期的に考査と称される小テストが行われます。
考査は全10回実施され、所定の得点を上回ることが必須条件となっているため、合格しなかった場合は再受験が必要です。
270単位以上を取得し、かつ10回の考査に合格することで、修了考査を受験する資格が与えられます。
修了考査
| 修了考査 | 概要 |
|---|---|
| 実施時期 | 年1回(12月または1月) |
| 回答形式 | 記述式 |
| 科目 | 会計に関する理論及び実務/300点 監査に関する理論及び実務/300点 税に関する理論及び実務/300点 経営に関する理論及び実務/200点 公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理/100点 |
| 合格点 | 総点数の60%を基準として、修了考査運営委員会が相当と認めた得点比率 |
| 足切り | 1科目でも40点に満たない科目がある場合、不合格になる可能性がある |
| 合格率 | 50~70% |
| 科目合格 | なし |
修了考査の例年の合格率は50%から70%の範囲で変動しますが、短答式試験や論文式試験と比較すると、合格の難易度は低いと考えられます。
修了考査は通常、12月または1月に行われ、監査法人では試験休暇として約2週間の特別休暇が取れます。
したがって監査法人の職員は、この特別休暇に有給休暇を1週間から2週間追加することで、約1ヶ月の試験勉強期間を確保することが一般的です。
さらに、8月の夏休み中に少し勉強を行うことで、合格基準に達することが可能です。
もし不合格となった場合は、再度1年後に受験しなければならないため、十分な対策が求められます。
論文式試験に合格し、実務要件を満たし、補習所で必要な単位を取得した後に修了考査に合格することで、初めて公認会計士として登録されることができます。
また公認会計士として登録するためには、登録費用として入会金4万円、施設負担金5万円、登録免許税6万円の合計15万円を支払う必要があります。
さらに、公認会計士になると年会費として12万円が必要です。登録審査には1~2ヶ月を要するため、多くの人が7月から8月頃に公認会計士として登録を行います。
公認会計士試験合格には5,000時間~7,000時間かかる
公認会計士試験(短答式および論文式)に合格するためには、5,000時間から7,000時間の学習が必要とされています。
大手予備校のウェブサイトやパンフレットでは、3,000時間から4,000時間で合格可能との宣伝が見受けられますが、学習の進め方に迷っている場合は時間がかかると思っておいた方が良いでしょう。
例えば、6,000時間を3年で割ると、1日あたり約5時間半の学習時間となりますが、短答式試験の半年前からは、毎日10時間の学習を続ける必要があるでしょう。
公認会計士の専門学校(養成所)や通信講座について
公認会計士の勉強には、専門学校や通信講座の利用も有効です。ご自身にあった受講プランを立ててみてはいかがでしょうか?
公認会計士の年収相場

公認会計士は、会計のプロフェッショナルとしてコンサルティングや公認会計士しかできない監査業務を行うため一般企業に勤めている人よりは年収は高いといえます。
平均で約800万円ほどで安定した生活が送れると言えるでしょう。
また、パートやアルバイトでの時給も1000円~2500円と高く、女性の育児による離職後でも有利に就職できるでしょう。
公認会計士の将来性
会計基準のグローバル化が進み、今までは様々な会計基準が使用されていたのを一つに統一しようという動きが出ています。
会計基準が変われば会社の管理体制や処理の仕方も変える必要があり会計士の経験や知識が求められます。
また、海外に進出する企業に対して現地の決算数値を見ながらの意見など、会計士にしかできないプロフェッショナルな提案が求められます。
公認会計士の独立について
公認会計士の多くは独立して自分の事務所を立ち上げることが多いです。
公認会計士の増加により、顧客の獲得が難しいとされていますが経営がうまくいけば大幅な年収アップは期待できます。
また、公認会計士の資格取得者は同時に税理士の資格も取得したことになります。
公認会計士の仕事だけでなく、税理士などの仕事も請け負うことで仕事の幅が広がり、より多くの顧客が確保されます。
公認会計士のキャリア
他にも、公認会計士は企業の経営管理部長やCFOのキャリアもあります。
特に、ベンチャー企業のCFO、経営管理部長として上場に携わることができれば、非常に貴重な経験ができることでしょう。
上場する際に株式やストックオプションを保有していれば、キャピタルゲインを得ることもできます。
実際に、公認会計士や税理士として監査法人に勤めた後、上場に貢献した人も多くいます。
詳しくは下記参考サイトの記事をご覧ください。
公認会計士試験に合格したいなら予備校を利用するのがおすすめ
今回は公認会計士になる方法について紹介してきました。
公認会計士になるには公認会計士試験に合格する必要があります。
公認会計士試験は短答式試験・論文式試験にパスしなければならず、合格しても実務経験や修了試験を突破しなければ公認会計士としては活躍できません。
学生のころから公認会計士を目指すのであれば、経営や簿記の知識があれば有利になるでしょう。
社会人から公認会計士になるには専門学校や予備校に通うのもひとつです。
専門学校や予備校なら学習のスケジュールが定められており、合格に必要なカリキュラムやノウハウが揃っているのでおすすめです。
公認会計士試験に合格するには5,000時間から7,000時間の学習が必要とされており、1日5~6時間の学習を1年半~2年程度続けるイメージとなています。
今回の記事を参考にしてみてください。