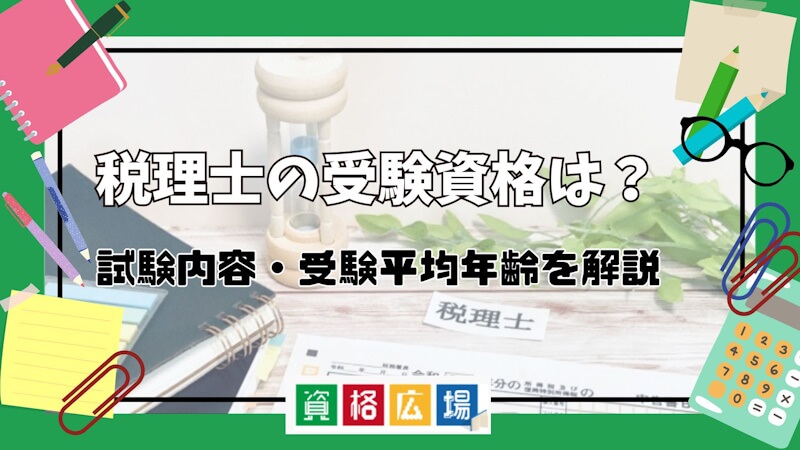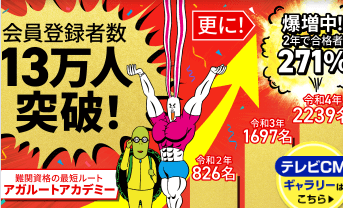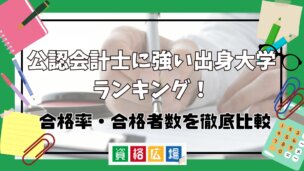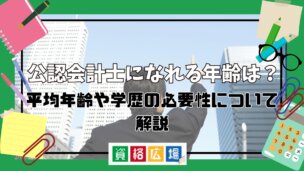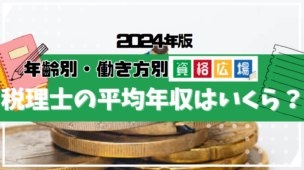税理士は、企業や個人の税務をサポートする重要な専門職です。
これから税理士を目指そうとしている方や、既に学習を始めている方で、受験資格など具体的な情報を知りたいと思う方は多いのではないでしょうか。
結論、税理士は学歴・資格・職歴・認定による受験資格で、いずれかを満たす必要があります。
また、令和5年から税理士の受験資格は緩和されている点も特徴です。
この記事では、税理士試験に必要な受験資格の詳細や、緩和後の要件を詳しく解説します。
また、受験資格がない方や、高卒の方が受験資格を最短ルートで得る方法も解説しているので、ぜひ最後まで読んでください。
税理士に受験資格はある?
税理士になるためには、いくつかの受験資格を満たす必要があります。
以下では、学歴、資格、職歴、認定の4つの受験資格について詳しく説明します。
- 税理士の受験資格①学歴
- 税理士の受験資格②資格
- 税理士の受験資格③職歴
- 税理士の受験資格④認定
税理士の受験資格①学歴
税理士試験の受験資格には学歴要件があります。
学歴による受験資格と、証明書類を以下にまとめました。
| 学歴による受験資格 | 証明書類 |
|---|---|
| 大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者 | 成績証明書 (卒業年月の記載がないものは卒業証明書も必要) |
| 大学3年次以上の学生で社会科学に属する科目を含め62単位以上を取得した者 | 成績証明書 (大学3年次以上であることが確認できるもの) 年次の記載がないものは大学3年次以上であることが確認できる書類(年次の記載がある在籍証明書等)も必要 ※ 大学3年次以上であることが確認できない成績証明書が多いので注意してください。) |
| 専修学校の専門課程(1修業年限が2年以上かつ2課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上に限る。)を修了した者等で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者 | 成績証明書 (卒業年月の記載がないものは卒業証明書も必要) 及び 課程証明書 (当該専門課程が左欄の1及び2の要件を満たす課程であることについて都道府県知事等が発行した証明書を専修学校が原本証明したもの) |
| 司法試験に合格した者 | 所管官庁の合格証明書 |
| 旧司法試験法の規定による司法試験の第二次試験又は旧司法試験の第二次試験に合格した者 | 所管官庁の合格証明書 |
| 公認会計士試験短答式試験合格者 | 公認会計士・監査審査会会長発行の「公認会計士試験短答式試験合格通知書」又は「短答式試験合格証明書」 |
| 公認会計士試験短答式試験全科目免除者 | 公認会計士・監査審査会会長発行の「公認会計士試験免除通知書」又は「免除証明書」 |
引用元:国税庁『受験資格について』
なお、社会科学に属する科目は、以下3つの科目に属するものになります。
- 法律学に関する科目
- 経済学に関する科目
- その他の科目
社会科学に属する科目①法律学に関する科目
- 法学
- 法律概論
- 日本国憲法
- 民法
- 刑法
- 商法
- 行政法
- 労働法
- 国際法等
社会科学に属する科目②経済学に関する科目
- (マクロ又はミクロ)経済学
- 経営学
- 経済原論
- 経済政策
- 経済学史
- 財政学
- 国際経済論
- 金融論
- 貿易論
- 会計学
- 簿記学
- 商品学
- 農業経済
- 工業経済等
社会科学に属する科目③その他の科目
- 社会学
- 政治学
- 行政学
- 政策学
- ビジネス学
- コミュニケーション学
- 教育学
- 福祉学
- 心理学
- 統計学等
税理士の受験資格②資格
特定の資格を保有している場合も受験資格があります。
以下の資格と証明書類を確認してください。
| 資格による受験資格 | 証明書類 |
|---|---|
| 日本商工会議所主催簿記検定試験1級合格者 | 日本商工会議所発行の合格証明書 (合格証書は不可) |
| 公益社団法人全国経理教育協会主催簿記能力検定試験上級合格者(昭和58年度以降の合格者に限る。) | 公益社団法人全国経理教育協会発行の合格証明書 (合格証書は不可) |
| 会計士補 | 日本公認会計士協会発行の登録証明書 |
| 会計士補となる資格を有する者 | 公認会計士・監査審査会発行の旧公認会計士試験第二次試験合格証明書又は同試験の免除科目が全科目に及ぶことを証する書面 |
引用元:国税庁『受験資格について』
税理士の受験資格③職歴
職歴も受験資格の一つです。
税理士試験の場合、以下の事務又は業務に通算2年以上従事した方は受験資格を得られます。
| 職歴による受験資格 | 証明書類 |
|---|---|
| 弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士の業務 | 登録証明書及び当該業務に2年以上従事したことを証する書面(同業者2人以上の証明) |
| 法人又は事業を営む個人の会計に関する事務 | 職歴証明書 |
| 税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務 | 職歴証明書 |
| 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務 | 職歴証明書 |
| 行政機関における会計検査等に関する事務 | 職歴証明書 |
| 銀行等における貸付け等に関する事務 | 職歴証明書 |
引用元:国税庁『受験資格について』
職歴証明書の様式のひな形は以下になります。
職歴証明書の様式のひな形
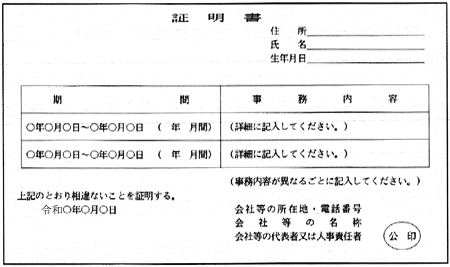
引用元:国税庁『受験資格について』
税理士の受験資格④認定
税理士は、国税審議会より受験資格に関して個別認定を受けた方も受験資格を有します。
国税審議会より受験資格に関して個別認定を受けた方とは、以下の方が例に挙げられます。
1 問11の「学識」に掲げる者と同等以上の学識を有すると認められる方(例えば、外国の大学を卒業した方で、社会科学に属する科目を1科目以上履修している方(問23参照))。
2 問11の「職歴」に掲げる事務又は業務に類すると認められる事務又は業務(例えば、商工会や青色申告会における複式簿記による記帳(経理)及び決算指導の事務や信用金庫(組合)や協同組合における貸付審査事務)に、通算して2年以上従事した方(問24、25参照)。引用元:国税庁『受験資格について』
また、証明書類は以下があります。
(個別認定申請に必要な書類)
- 1. 税理士試験受験資格認定申請書(様式は、問26参照)
- 2. 学識、職歴、事務又は業務の内容を証明する書面
- 3. 郵便番号、住所及び氏名を明記し、所要額の切手(特定記録であれば280円、簡易書留であれば470円、書留であれば600円の切手)を貼ったA4判大の返信用封筒
引用元:国税庁『受験資格について』
税理士試験の受験資格は令和5年から緩和されている
令和5年から税理士試験の受験資格が緩和されています。
受験資格が緩和される理由の一つとして、多様なバックグラウンドを持つ人々に受験機会を提供し、税理士業界の人材確保を図ることが背景にあります。
これにより、様々な分野から優秀な人材が税理士を目指しやすくなります。
具体的な要件は以下の通りです。
- 会計学に属する科目の受験資格の撤廃
- 税法に属する科目の受験資格の緩和
税理士試験は科目合格制で、一度合格すれば生涯有効です。
緩和された条件をしっかり確認して、税理士試験の合格を目指しましょう。
会計学に属する科目の受験資格の撤廃
以下、会計学に属する科目の受験資格の制限がなくなりました。
- 簿記論
- 財務諸表論
以前は大学の3年次以降に受験するか、高校生・大学1、2年生は日商簿記1級を取得してから受験することが必要でした。
しかし現在は会計学に属する科目のみ受験申込みが、誰でもできるようになっています。
税法に属する科目の受験資格の緩和
また、以下の税法に属する科目の受験資格が緩和された点も大きな変更点の一つです。
- 所得税法
- 法人税法
- 相続税法
- 消費税法又は酒税法
- 国税徴収法
- 住民税又は事業税
- 固定資産税
以前は、法律学または経済学に属する科目を1科目以上履修することが必須でしたが、現在は科目要件がより広範囲な「社会科学」に変更となりました。
そのため、文系学部・理系学部を問わず、多くの方が税理士試験を受験できるようになっています。
税理士試験の受験資格がない場合の対処法
上述の受験資格要件を満たしていない方でも、ポイントを押さえることで、最短ルートで受験資格を満たせます。
- 学歴を補う
- 資格の取得
- 実務経験を積む
自分にとって最適なルートで、受験資格を満たせるように動きましょう。
学歴を補う
大学等に再入学し、必要な単位を取得することを検討します。
特に社会科学に属する科目を履修することで、学歴要件を満たすことができます。
例えば、通信制の放送大学は1科目からでも履修可能です。
資格の取得
日商簿記検定1級を取得することで、税理士試験の受験資格を得るのも一般的な方法です。
以下の方は、日商簿記検定1級の取得を検討しましょう。
- 高卒
- 大学1、2年生
ただし日商簿記検定1級は難易度が高い資格なので、通信講座を利用するなどして、しっかり勉強する必要があります。
実務経験を積む
高卒や大学1、2年生の方や、学歴・資格要件を満たすのが難しい場合、実務経験を積んで、職歴による受験資格を満たす方法もあります。
以下のような事務又は業務で、通算2年以上従事すれば受験資格を得られます。
- 法人又は事業行う個人の会計に関する事務
- 銀行、信託会社、保険会社等において、資金の貸付け・運用に関する事務
- 税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助事務
なお、通算2年以上の職歴が必要であって、同じ職場で勤務を続ける必要はありません。
高卒で税理士の受験資格を満たす方法
高卒であっても、税理士の受験資格を満たす方法はあります。
おすすめは以下のいずれかです。
- 日商簿記検定1級を取得する
- 会計事務所や税理士事務所で通算2年以上勤務する
まず、日商簿記検定1級を取得することで、税理士試験の受験資格を得ることができます。
ただし、難易度が高い資格ですので、しっかりした学習計画が必要です。
また、会計事務所や税理士事務所などで、通算2年以上勤務する方法もあります。
働きながら税理士に関する知識を深められるので、実践的な知識やスキルも身に付くでしょう。
高卒の方でも、一定の要件を満たせば税理士試験の受験資格を得られるので、合格に向けて挑戦しましょう。
税理士試験合格後に税理士になる方法
税理士試験に合格したからといって、すぐに税理士として活躍できるわけではありません。
税理士になる方法を以下で解説します。
- 税理士試験合格後に実務経験を2年以上積む
- 税理士試験を受けなくても税理士になる方法がある
税理士試験合格後に実務経験を2年以上積む
税理士試験に合格した後、正式に税理士として登録するためには、2年以上の実務経験が必要です。
この実務経験は、税理士事務所や会計事務所での税務や会計に関連する業務を通じて得られます。
実務経験を積んだ後、税理士会に登録し、国税庁に正式な登録申請を行うことで、税理士としての活動を開始できます。
税理士試験を受けなくても税理士になる方法がある
税理士になるには、税理士試験で会計2科目+税法3科目の計5科目に合格したうえで、2年以上の実務経験を積む必要があります。
しかし、税理士試験を受けなくても税理士になる方法があります。
具体的には以下の通りです。
- 弁護士または公認会計士の資格を保有する
- 税務署で23年以上勤務し、かつ指定の研修を修了する
公認会計士試験に合格して登録を受けた者や、弁護士資格を有する者は、税理士試験を受けずに税理士登録を行うことができます。
これらの資格を持つことで、税理士試験の一部または全てが免除されるため、別のルートから税理士になることが可能です。
また、税務署で23年以上勤務している、かつ指定の研修を修了している方も、税理士試験を受けずに税理士登録できます。
例えば、税務署を退職した方はセカンドキャリアとして、税理士として働く方が多いです。
税理士とのダブルライセンスにおすすめの資格
税理士資格を持っていると、他の資格と組み合わせることでさらにキャリアの幅を広げることができます。
特に中小企業診断士や社会保険労務士、行政書士といった資格は、税理士との相性が良く、ダブルライセンスとしておすすめです。
これらの資格を取得することで、顧客に対する総合的なサービス提供が可能となり、業務の幅が広がります。
以下に、税理士とのダブルライセンスにおすすめの資格を詳しく紹介します。
- 中小企業診断士
- 社会保険労務士
- 行政書士
中小企業診断士
中小企業診断士は、中小企業の経営に関する診断・助言を行う専門家です。
税理士としての知識に加え、中小企業診断士の資格を持つことで、企業の財務状況や経営戦略について総合的なアドバイスができるようになります。
以下の表に、中小企業診断士の主要業務と税理士業務との関連性を示します。
| 主要業務 | 関連性 |
|---|---|
| 経営診断 | 財務分析と関連 |
| 経営助言 | 税務戦略と関連 |
| 資金調達支援 | 財務計画と関連 |
中小企業診断士の資格を取得することで、クライアントの経営課題に対して、より広範な視点から解決策を提案することが可能となり、信頼性が高まるでしょう。
また、税理士として顧客サービスをより充実させることができます。
企業の経営改善や成長支援に対するアプローチを強化することで、クライアントに対する付加価値を高めることも可能です。
社会保険労務士
社会保険労務士は、労働社会保険法令に基づく手続きや、労務管理に関するコンサルティングを行う専門家です。
税理士としての知識に加え、社会保険労務士の資格を持つことで、労務管理や社会保険手続きについても対応できるようになります。
以下の表に、社会保険労務士の主要業務と税理士業務との関連性を示します。
| 主要業務 | 関連性 |
|---|---|
| 社会保険手続き | 給与計算と関連 |
| 労務管理 | 企業経理と関連 |
| 労働法務相談 | 法務対応と関連 |
社会保険労務士の資格を取得することで、人事労務の分野でもクライアントをサポートできるため、総合的なコンサルティングサービスの提供が可能です。
また、税理士としてのサービス範囲を拡大し、クライアントにより幅広いサポートを提供できるでしょう。
特に中小企業において、税務と労務の両面から支援することで、企業経営の安定化に寄与できます。
行政書士
行政書士は、行政手続きに関する書類の作成や、許認可申請の代行を行う専門家です。
税理士としての知識に加え、行政書士の資格を持つことで、企業の設立手続きや各種許認可の申請業務にも対応できるようになります。
以下の表に、行政書士の主要業務と税理士業務との関連性を示します。
| 主要業務 | 関連性 |
|---|---|
| 許認可申請 | 企業設立と関連 |
| 契約書作成 | 法務対応と関連 |
| 遺言書作成 | 相続税対応と関連 |
行政書士の資格を取得することで、企業法務や相続手続きなどの分野でもクライアントをサポートできるため、総合的なサービスの提供が可能となります。
また、税理士としての業務範囲を広げ、クライアントに対するトータルサポートを実現できるでしょう。
さらに、企業の成長支援や個人の相続手続きにおいて、税務と法務の両面からアプローチすることで、より信頼性の高いサービスを提供することができます。
税理士試験の合格を目指すならアガルートを受講しよう
税理士試験の合格を目指すなら、アガルートの受講がおすすめです。
アガルートは質の高い講師陣と充実したカリキュラムで知られており、試験対策に必要な知識を効果的に学ぶことができます。
初学者・学習経験者それぞれに向けたコースがあるので、自分のペースで学習を進められるのも大きなメリットです。
オンライン講座形式で提供されるため、いつでもどこでも受講できます。
さらに、模擬試験や個別指導、個別カウンセリングも充実しており、合格に向けたサポートが充実しています。
アガルートで効率的に学習し、税理士試験の合格を目指しましょう。
税理士の受験資格を満たしているか確認しよう
税理士試験に合格するためには、学歴・資格・職歴・認定のいずれかの受験資格を満たしている必要があります。
ただし、受験資格を満たししていれば大学在学中の方、高卒の方、社会人の方も幅広く受験可能です。
指定科目の修了や実務経験は、税理士として必要な専門知識とスキルを身につけるために重要です。
自分がこれらの受験資格を満たしているかを確認し、税理士試験への準備を進めましょう。
税理士試験は難易度が高い試験ですので、独学では不安な方は、アガルートの受講を検討しましょう。