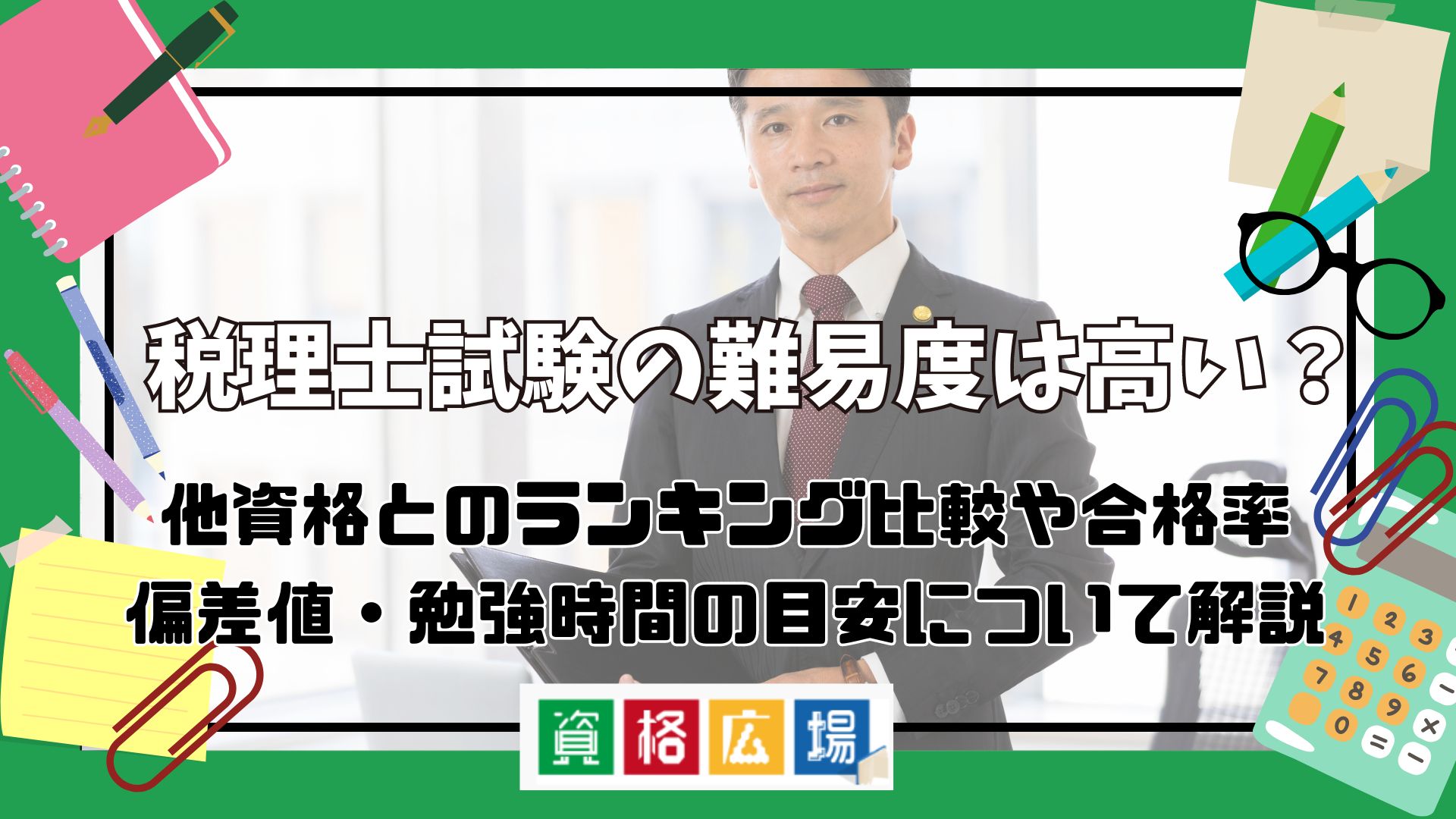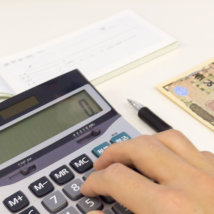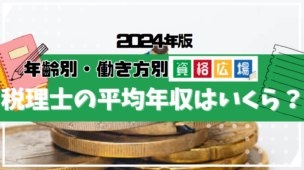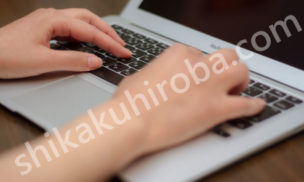税理士とは、主に個人や企業の「税金」関係のサポートを行うのが仕事です。
そんな税のプロフェッショナルである税理士になるには、まず税理士試験に合格するところから始まり、2年以上の実務経験を積む必要があります。
この記事では、税理士になる方法から税理士試験を受験するにあたっての受験資格、難易度や合格率についてまでを詳しく紹介していきます。
税理士資格取得の難易度は高い?受検資格や合格率・必要な勉強時間を徹底解説
税理士試験の難易度
税理士になるには多くの難関を乗り越えねばいけない、と言われていますが、第一の難関である税理士試験の難易度や合格率は一体どのくらいなのでしょうか?
税理士試験に関する情報とともに、試験の難易度や合格率を紹介していきます。
税理士の平均年収はいくらくらい?年齢別・働き方別の給与を紹介
税理士試験の合格率は10~20%
数多く存在する資格の中でも、税理士試験は難易度が高いと言われています。
各科目により差は生じますが、試験の合格率は例年10~20%と推移しています。税理士資格は国家資格であるため難易度はやはり高いといえますね。
また、学歴による合格率ですが、現役大学生は20%以上を超えるといわれていますが、それ以外の学歴には大きな差はないといわれています。
年齢別でいうと、25歳以上の合格率が高く、年齢が上がるほど合格率が下がっていく傾向にあるようです。
税理士試験は、全11科目のうちの会計科目2科目と税法科目3科目の5科目に合格する必要があり、各科目の合格基準は60点以上と難易度が高くなっています。
さらに5科目同時に全て合格することは不可能と言われているほど難易度が高く、1年に1、2科目ずつ受験するのが一般的です。
税理士試験に合格するまでの期間は平均4~6年
税理士試験に合格するまでにかかる期間は、人によって異なりますが平均4~6年、7~10年近くかかる方もいます。
税理士試験は1年に1回しか受けることができず、さらに5科目以上合格しなければいけないことから難易度の高い試験だといわれているのですね。
5科目を1度に合格する必要はないので複数年にわたって合格科目を取得していく受験方法が一般的とされています。
さらに税理士試験に合格後も2年以上の実務経験が必要となりますので、税理士になるには長い道のりを歩む必要がありそうです。
税理士試験の内容
税理士試験の内容は以下の通りです。
| 受験科目 | 全11科目 |
|---|---|
| 試験時間 | 各科目120分 |
| 出題形式 | 記述方式 |
| 合格基準 | 各科目とも満点の60% |
合格点は満点の60%と決められていますが、各科目の配点は公表されていません。
税理士試験は科目合格制度があるため、数年かけて合格を目指すことが一般的です。
受験申込科は以下の通りです。
| 受験申込科目数 | 受験手数料 |
|---|---|
| 1科目受験 | 4,000円 |
| 2科目受験 | 5,500円 |
| 3科目受験 | 7,000円 |
| 4科目受験 | 8,500円 |
| 5科目受験 | 10,000円 |
2024年(令和6年度)の試験日程
令和6年度税理士試験の日程及び試験科目をまとめました。
| 月日 | 時間 | 科目 |
|---|---|---|
| 8月6日(火) | 9時から11時 | 簿記論 |
| 12時30分から14時30分 | 財務諸表論 | |
| 15時30分から17時30分 | 消費税法または酒税法 | |
| 8月7日(水) | 9時から11時 | 法人税法 |
| 12時から14時 | 相続税法 | |
| 15時から17時 | 所得税法 | |
| 8月8日(木) | 9時から11時 | 国税徴収法 |
| 12時から14時 | 固定資産税 | |
| 15時から17時 | 住民税又は事業税 |
引用:国税庁公式サイト
税理士試験の難易度が高いと言われる理由
税理士試験の難易度が高い理由には以下の4つがあります。
- 試験科目が多い・範囲が広い
- 税法の改正への理解が必須
- 教材を探すのが難しい
- 資格を取得するまでに年数が必要
法律が新しく変わることで、勉強の内容も更新しなければなりません。
自分にあった教材を探すことに苦労する受験生もいるようです。
稼げる・儲かる資格おすすめランキングTOP10!取得難易度や収入アップ・副業でも活用できる資格を徹底比較
理由①試験科目が多い・範囲が広い
試験科目が多い・範囲が広いことも、税理士試験の難易度が高いことに関係しているでしょう。
税理士試験の科目は必須科目と選択科目に分かれています。
【会計学に属する必須科目】
- 簿記論
- 財務諸表論
【税法に属する選択科目】
選択科目は以下の中から3科目を選択します。
しかし、法人税法、所得税法のどちらかは選択必須なので注意しましょう。
- 所得税法
- 法人税法
- 相続税法
- 消費税法又は酒税法
- 国税徴収法
- 住民税又は事業税
- 固定資産税
税理士試験は科目ごとに独立している試験です。
全ての科目で合格点を上回らなくてはなりません。
理由②税法の改正への理解が必須
税理士試験の難易度の高さは、税法の改正も関わってきます。
改正を理解し、常に新しい情報を勉強するのが難しいと感じる受験生も多いようです。
法律は常に変化し続け、試験では税制に準拠した最新の答えが求められます。
税法の改正は、現役の税理士でも理解するまでに時間がかかる場合もあるでしょう。
受験生となると、基礎的な内容から理解しなくてはならないため、さらに難しくなる傾向です。
理由③教材を探すのが難しい
税理士試験対策の教材は、入手が難しいことに注意しましょう。
官公庁から発行されている税理士試験対策の教材はありません。
税法の解説や説明などは、教える側もより深い理解が必要です。
加えて、試験の内容や方法について毎年変更されることも税理士試験の特徴でしょう。
試験勉強に関する、最新情報が網羅されている教材を探す難易度も高いと言えます。
行政書士と税理士の仕事内容の違いは?ダブルライセンスのメリットも紹介!
理由④資格を取得するまでに年数が必要
税理士試験は全ての科目に合格するまで、年数がかかります。
複数の科目全てに合格するためには、数年単位の勉強と対策が必要と考えましょう。
平均的に合格までに数年間かかることも、税理士試験の難易度が高くなる原因です。
ただし科目合格制度があるため、一度も試験で全ての科目に合格する必要はありません。
税理士試験の難易度を他試験と比較
税理士と公認会計士試験、司法書士試験、司法試験、医師の合格率をまとめました。
令和5年度のデータは以下の通りです。
| 試験 | 合格率 |
|---|---|
| 税理士 | 10~20% |
| 公認会計士 | 7.60% |
| 司法書士試験 | 約5.2% |
| 司法試験 | 45.34% |
| 医師 | 91.70% |
難関資格と比較すると、税理士試験は中間レベルのものと考えられるでしょう。
ただし、各業種の合格までの道のりは税理士とは異なります。
学歴や業務にかかわる職歴が求められる資格ばかりです。
一概に合格率だけでは、各資格の難易度は測れません。
【最新】人気資格おすすめランキング15選!通信講座で取得できる便利な資格を徹底比較
税理士の試験科目
税理士試験の科目は以下の2種類に分かれています。
- 会計学に属する必須科目
- 税法に属する選択科目
選択科目の中でも必ず受けなければならない試験もあるので注意してください。
税理士試験は科目合格制で、受験者は一度に5科目を受験する必要はありません。
1科目ずつ受験してもよいことは税理士試験のメリットです。
令和5年度から試験内容が少し変わりましたが、難易度自体は大幅に低くなったわけではありません。
国家資格の難易度ランキング一覧!独学でとれる資格や合格率・勉強時間まで解説
会計学に属する必須科目
税理士試験の必須科目は会計学に属する2種類です。
- 簿記論
- 財務諸表論
以上の科目は必ず受けなければいけません。
合格基準点は各科目とも満点の60パ-セントです。
試験は国税庁の国税審議会によるものです。
税法に属する選択科目
税法に属する選択科目は以下の通りです。
以下の科目から3項目を受験しましょう。
ただし、所得税法又は法人税法のいずれか1科目を必ず選択しなければなりません。
- 所得税法
- 法人税法
- 相続税法
- 消費税法又は酒税法
- 国税徴収法
- 住民税又は事業税
- 固定資産税
合格基準点はどの科目も満点の60パ-セントです。
範囲が広く深い知識が必要になるので、1年で合格するとなると相当な努力が求められます。
難易度の高い税理士試験の勉強法
税理士試験は難易度が高いため、合格のためには勉強法にもこだわりましょう。
自分なりに効率の良い方法を探すことも重要です。
最新の効率を理解し、取りこぼしのないように知識を深めてください。
時間配分を計算して勉強することも、合格への第一歩です。
独立や起業におすすめの資格ランキング!起業への近道になる資格は?
ポイント①過去問で傾向をチェックする
過去問を勉強すれば税理士試験の出題傾向が読み取れます。
傾向をチェックして、どのような試験内容になるのか考えましょう。
効率的に点数を取るためにも、過去問を解くことが重要です。
これまでどのような問題が出題されたか、出題傾向を確認してください。
ポイント②時間配分や解答順を考える
試験の時間配分や解答順も、高得点を狙う鍵です。
実際の試験時間と同じ計算で、過去問を解いてみましょう。
先にといた方がいい問題や、時間がかかる問題がわかりやすくなります。
どのような配分なら、より高得点を狙えるのか時間を計って練習することが重要です。
ポイント③難問・奇問を見分ける
税理士試験の対策では、難問や奇問を見分ける訓練をしましょう。
過去問を解くことで出題傾向が掴めます。
珍しい問題や難問が苦手な人は、解答に時間がかかってしまいます。
優先すべき問題を判断するためにも、 難問・奇問を見分けることが重要です。
ポイント④法改正に合わせて勉強する
法改正に合わせて最新の勉強をしましょう。
税法は早いスパンで改正が行われています。
古い法律の情報では、税理士試験に合格することができません。
常に新しい情報を覚えられるように、法改正があったらチェックしてください。
過去の問題は、税理士試験が実施された年の法律に基づいているので注意しましょう。
ポイント⑤簿記論から勉強する
簿記論を勉強すれば会計や税法の基本が身につきます。
他の科目とも親和性が高く、内容が頭に入ってきやすいでしょう。
加えて、簿記論は受験資格がありません。
これから税理士試験の受験を考える人の勉強にも簿記論がおすすめです。
税理士試験は独学で合格できる?
税理士試験は独学でも合格できるのでしょうか。
予備校や通信講座では、税理士向けの勉強ができます。
しかし完全独学となると、合格までに年数がかかることもあるようです。
スタディングの税理士講座の評判は?口コミからわかる特徴や料金まとめ
独学合格が難しい理由①モチベーションの維持が難しい
税理士の勉強を独学で行う場合、モチベーションの維持が難しいことに注意しましょう。
試験合格までには数年単位の挑戦と予想できます。
成立試験に3年以内で合格できる受験生は、少ないと考えてください。
試験対策中もモチベーションの維持や、勉強への根気強さが求められるでしょう。
独学合格が難しい理由②独学向けの学習教材が少ない
税理士試験独学向けの市販テキストは、種類が豊富とは言えません。
簿記論や財務諸表評論の教材は販売されているものが多いです。
その一方で、ほかの科目は探すのに苦労するでしょう。
税法にかかわる科目は、独学では学びづらいことに気をつけてください。
独学合格が難しい理由③疑問点を解消しづらい
税理士試験の対策で疑問点が出た場合、独学では解除しづらいです。
独学となると、勉強に関わる相談ができる相手がいません。
一人で学習を進めなくてはいけないので、行き詰まる人もいます。
税理士は、回答を暗記すれば合格できる試験ではありません。
問題の意図や内容を理解するためには、独学にこだわることは危険です。
試験対策やモチベーション維持が不安な人には、予備校・通信講座の利用をおすすめします。
税理士試験対策におすすめの予備校・通信講座
税理士対策におすすめの予備校や通信講座は、資料の一括請求が便利です。
少しでも興味がある人は、無料の資料請求をしてみましょう。
給付金対象の予備校・通信講座もあるので、おすすめです。
税理士は高収入が期待できて、独立後は年収1000万円以上も夢ではありません。
資格を取るためには努力が必須ですが、ハイリターンが見込めます。
キャリアに迷っている人は、積極的にチェックしてください。
有名税理士講座から探す

ユーキャン、TAC、資格の大原、LEC、ヒューマンアカデミーなどの有名通信講座の資料を一括請求可能!
有名かつ実績の高い通信講座の情報を一括で無料資料請求できるから、最適な通信講座が見つかります。
入力項目は氏名・年齢・資料送付先住所などの基本事項のみで1分もかからない簡単入力のみ!しつこい勧誘やメールはもちろん一切なし。気軽に資料請求だけでも、ぜひ!
税理士とは
税理士は税の専門家として、幅広い業務に携わる仕事です。
税の知識が身についている税理士は、人から頼られる場面も多いでしょう。
仕事では公正な立場で活動しなくてはなりません。
社労士と税理士の違いとは?難易度・年収の違いやダブルライセンス取得のメリットまで解説
税理士の仕事内容
税理士の仕事で多いものには以下があります。
| 税務書類の作成 | 確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書、 その他税務署などに提出する書類を作成 |
|---|---|
| 税務代理 | 確定申告・青色申告の承認申請 税務調査の立会い 税務署の決定に不服がある場合の申立てなど |
| 税務相談 | 税金のことに関する質問対応 |
税理士の平均年収
厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、税理士の平均年収は約746万円です。
ただしこの統計は、公民会計士の年収も含めた計算になります。
また年間賞与や特別給与額を合わせたものなので注意してください。
働き方や勤務する企業、仕事をしている地域などによって、年収は左右されます。
税理士試験以外で資格を取得する方法
税理士になるには、税理士試験で資格を取得する以外にも方法があるのをご存知ですか?
もし現在、税理士を目指している方は是非参考にしてみて下さいね。
将来有望な国家資格・民間資格18選!これからの時代に役立つ需要のある・将来性の高い資格を厳選
税理士になるには弁護士か公認会計士の資格を取る
税理士になるには「弁護士」または「公認会計士」の資格を持っていれば税理士試験を受験する必要がなく、税に関する職に就くことが可能です。
弁護士や公認会計士になるには必要である「司法試験」や「認会計士試験」が、法律・会計処理に携わる知識も問われているため、税理士としての仕事をすることも認められています。
税理士になるには税務署で23年以上勤務
税理士になるには、税務署で勤続23年以上の実務経験があれば、税理士試験を受験することなく税理士資格を取得することが可能です。
税務署での勤続年数が長いことで、税務に関しての実務や知識を十分に習得していると見なされます。さらに独立し開業することも可能。
税理士試験の受験資格
一般的に税理士になるには税理士試験を受けることから始まりますが、その試験を受けるためには必要な受験資格があります。
必ずこの受験資格の条件を満たしていないと試験を受けることができませんので、事前にしっかり確認していきましょう。
税理士試験に必要な学歴による受験資格
税理士試験を受験するために必要な学歴による受験資格は以下を参考にしてみてください。
1.大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で、法律学又は経済学を1科目以上履修した者
2.大学3年次以上で、法律学又は経済学を1科目以上含む62単位以上を取得した者
3.一定の専修学校の専門課程を修了した者で、法律学又は経済学を1科目以上履修した者
4.司法試験合格者
5.公認会計士試験の短答式試験に合格した者
国税庁
また、学歴による受験資格では「成績証明書」や「卒業証明書」、「課程証明書」「他試験の合格証明書」などの書面の提出が求められます。
税理士試験に必要な資格による受験資格
税理士試験を受験するために必要な資格による受験資格は以下が挙げられます。
1.日商簿記検定1級合格者
2.全経簿記検定上級合格者
国税庁
資格による受験資格で提出が必要になる書面は「日本商工会議所発行の合格証明書」や「公益社団法人全国経理教育協会発行の合格証明書 」など。この場合、合格証書では受理されませんので注意が必要です。
税理士試験に必要な職歴による受験資格
税理士試験を受験するために必要な職歴による受験資格も紹介していきます。
1.法人又は事業行う個人の会計に関する事務に2年以上従事した者
2.銀行、信託会社、保険会社等において、資金の貸付け・運用に関する事務に2年以上従事した者
3.税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助事務に2年以上従事した者
国税庁
職歴による受験資格では、主に「職歴証明書」の提出が必要になってきます。
税理士試験の受験資格がない場合
何らかの理由で受験資格を満たすことができない方は「日商簿記1級」を取得するか「大学の科目履修制度」を利用して経済学や簿記論になどの1科目を履修・単位を取得し、受験資格を取得する方法が推奨できます。
ですので、大卒ではない方や理系大卒の方が税理士を目指せないわけではありませんよ。
税理士試験は難易度が高いので予備校で学ぼう
税理士試験は難易度が高いことに注意しましょう。
国家資格に強い予備校や講座などで学ぶことをおすすめします。
独学の場合は、合格までに年数がかかることを覚悟してください。
税に関わる専門家として活躍するためには、効率のいい勉強が必須です。