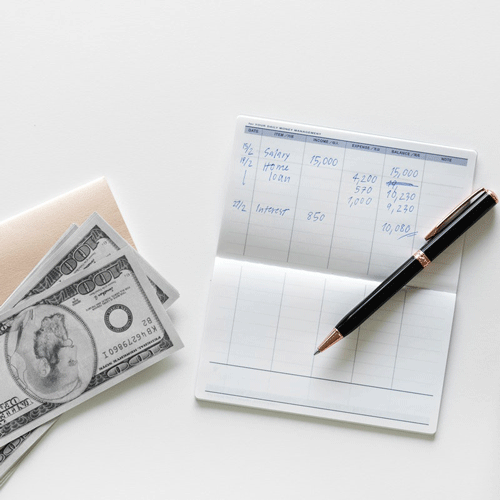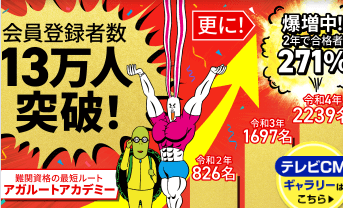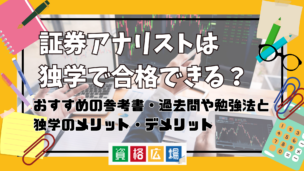一言に金融業関連の資格には実に様々な種類がありますが、その代表的な職業として投資診断士とFP(ファイナンシャルプランナー)が挙げられます。
双方とも投資や資産運用に携わる業務を行なう際に必要となる資格ですが、それぞれ取得の目的が異なります。
また、投資診断士とFP資格にはどのような違いがあるのでしょうか?
そこで、今回は投資診断士とファイナンシャルプランナーの違いや、実務に強いのはどちらなのかということも含め徹底比較してみます。
投資診断士とは?

投資と一口に言ってもたくさんの種類があり、不動産投資や株式投資、FXといった従来の方法からビットコインをはじめとする仮装通貨など最近注目を集めている方法まで実に様々です。
いずれにせよ、老後の不安解消や資産構築のために投資を行う人がいますが、素人にとって正しい知識、正しい方法で投資を行うのは非常に難しいと言われています。
投資診断士とは、投資に関する正しい知識、正しい方法を投資希望者に教え失敗のリスクを減らすためのサポートするのにふさわしい人を認定するための資格です。
投資診断士の資格取得方法
投資診断士の資格を取得するにあたって、特に年齢や学歴による制限は無いため誰でも目指すことができます。
投資診断士の資格を取得するためには、申込み後に届くテキストと動画教材を使って課題をまずクリアする必要があります。
テキストと動画教材では、試験を主催する投資診断協会の基本理念や投資に関する知識、投資商品など投資に必要な全般的な知識について学びます。
この自宅学習が修了後、各試験会場で投資診断士の資格試験に合格することによって資格を取得することができます。
試験では自宅学習で学んだ内容に関して問われ、試験は全60問の選択式で行われます。
FP(ファイナンシャルプランナー)とは?
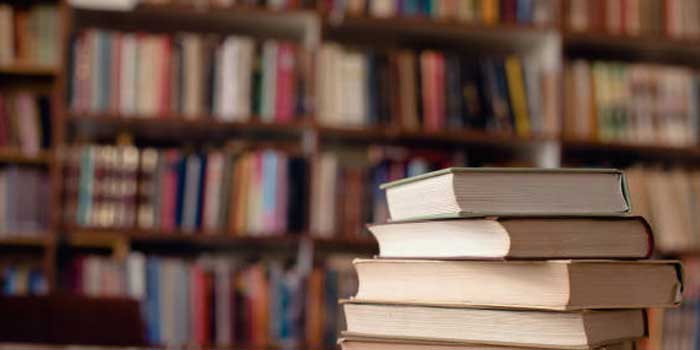
FP(ファイナンシャルプランナー)とは、個人のクライアントに対して資産運用や資金計画、資設計などお金を守るための全般的な提案を行う職業となります。
FPは主に生命保険や遺産相続、住宅ローンや教育費などライフイベントに沿った資産設計、年金や保険、不動産や税金などのアドバイスを専門家としての立場から行います。
FPの資格取得方法
FPの関連資格には、国家資格である3〜1級FP技能士資格と民間資格のAFP、CFPの3種類があります。
3級FP技能試験を例に上げると、試験は学科試験と実技試験の2分野に分かれています。
学科試験では、「ライフプランニングと資金計画」「リスク管理」「金融資産運用」「タックスプランニング」「不動産」「相続・事業承継」の全6科目から出題され、マルバツ式と三肢択一式になっています。
一方実技試験では、「個人資産相談業務」「保険顧客資産相談業務」「資産設計提案業務」から1つ選択して答える方式になっています。
投資診断士とFP(ファイナンシャルプランナー)の取るメリットは?
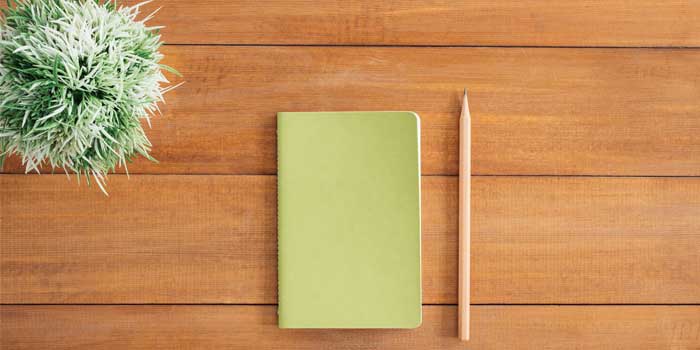
次に投資診断士とFP(ファイナンシャルプランナー)の取得するメリットについて紹介していきます。
各資格において、どのようなメリットがあるのでしょうか?
投資診断士を取得するメリット
最初に投資診断士を取得するメリットについて見ていきます。
投資に関する幅広い知識が身に着く
投資診断士を取得するメリットは投資に関する幅広い知識が身に着くことにあります。
投資診断士は投資に関する知識を多角的視点から、広範囲で網羅していく資格となっています。
そのため、投資全体に関する知識が詳しくなることがメリットです。
名刺に投資診断士を記載できる
投資診断士を取得することで、名刺に投資診断士の資格名を記載できることがメリットになります。
名刺に投資診断士の資格名があることで、相手側からの見え方が変わり、アピール材料となります。
投資診断士の資格を取得して、正式なロゴを記載させることで対外的にアピールできるようになります。
FPを取得するメリット
次にFPを取得するメリットについて紹介していきます。
FPを取得するメリットはどのようになっているのでしょうか?
就職や転職で役立つ
FPを取得するメリットは就職や転職に役立つことにあります。
特に金融や保険業界ではFP資格を保持していると、評価の対象になることが多くなっています。
また、資格を持っていない人と比べて、より顧客に対して専門的で正確なアドバイスを行えるようになります。
金融や保険業界への就職を考えている方は特に、FP資格の取得をおすすめします。
独立・開業を目指せる
FPを取得することで独立・開業を目指すことができます。
独立事務所では金融機関と連携して代理販売業務や、人生設計のアドバイスを顧客に行っていきます。
どの業界でも独立は軌道に乗せるまでが困難ですが、FP業務は比較的ローリスクで始められるメリットもあります。
投資診断士とFP(ファイナンシャルプランナー)の違いは?
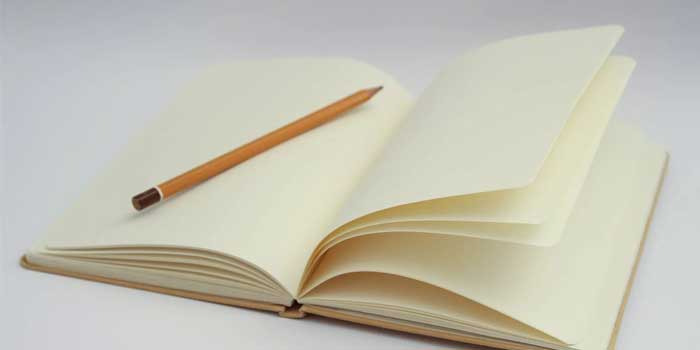
次に投資診断士とFPの違いについて紹介していきます。
投資診断士とFPにはどのような違いがあるのでしょうか?
民間資格と国家資格かの違い
投資診断士とFP(ファイナンシャルプランナー)の違いとして上げられるのは、民間資格か国家資格の違いがあります。
投資診断士は一般社団法人投資診断協会が認定している資格となっており、民間資格となっています。
それに対して、FP(ファイナンシャルプランナー)は、国家資格となっており、開催している団体が異なってきます。
民間資格と国家資格の違いは、法律に基づいて国が定める機関に提供されているかいないかの違いとなっています。
「投資」か「お金」の専門の違い
「投資」か「お金」の専門の違いあります。
投資診断士は名前の通り、投資に関する専門的な知識を付けていく資格内容となっています。
FP(ファイナンシャルプランナー)は、「お金」の専門として、将来の資産設計や資産計画のアドバイスなどを行っていきます。
一見似ているようですが、「投資」か「お金」かの専門が違いとなっています。
投資診断士とFPの試験範囲の違いは?
似ていると言われる投資診断士とFPですが、試験範囲ではどのような違いがあるのでしょうか?
以下が投資診断士とFPの試験範囲の違いとなっています。
| 試験範囲 | 試験内容 |
|---|---|
| 投資診断士 | ・投資診断協会の基本理念 ・投資に関する基礎知識 ・株式投資 ・不動産投資 ・生命保険 |
| FP | ・ライフプランニングと資金計画 ・リスク管理 ・金融資産運用 ・タックスプランニング ・不動産 |
情事の表を見て分かるように、投資診断士とFPでは試験範囲は大きく違ってきます。
金融のプロ、投資診断士とFP、実務に強いのはどっち?双方を徹底比較

投資診断士、FPの資格は金融業界のプロとして働く上でどちらも欠かせない資格となります。
しかし実際に実務をしていく上で有利になる資格はどちらなのでしょうか。
それぞれの役割や業務に注目しながら比較・違いについてみていきます。
「投資」の実務に関しては圧倒的に「投資診断士」が有利!
金融業界にも様々な業種、仕事がありますが、「投資」や「資産運用」という実務に関しては「投資診断士」の資格の方が就職やその後の待遇において圧倒的に有利となります。
決してFPの関連資格が役に立たないということではありませんが、投資診断士の資格は、証券や不動産投資など投資のスペシャリスト、エキスパートとしてそれぞれの分野において卓越した知識とスキルを持つものを認定するための資格です。
そのような「金融リテラシー」は金融業において実務をこなしていく上で必要不可欠なモノとなります。
そのため、投資診断士の資格を持っていることで金融リテラシーの証明にもなることからあらゆる場面において有利になるのです。
FP関連資格も金融業で働く上でぜひ持っておきたい資格
投資に関連する実務においては投資診断士の資格が圧倒的に有利ですが、金融業には投資以外にも資産設計や資産運用、税金に関するアドバイスなど重要な業務がたくさんあります。
ファイナンシャルプランナーとして働く際には必ずしも関連資格の取得は義務付けられていませんが、クライアントの「人生のパートナー」としての責務を果たすためには信用性が不可欠な要素となります。
そのため、金融業に限らず、個人のお金に関わることで働くことを検討されている方は、先程挙げたFP関連の資格はぜひ取得しておきましょう。
FP関連の資格は持っているだけで活躍できる場所が広がり、保険会社や金融機関はもちろんのこと、銀行や法律関連事務所、不動産会社など非常にたくさんの就職先があります。
自分がついたい職業を資格の兼ね合いを比較して挑戦する資格を選択するようにしましょう。
資格取得の難易度の比較
投資診断士、FP関連資格の取得を目指す際に気になるのが資格取得の難易度ですよね。
しかし、投資診断士の試験難易度は非公開になっているため、どれくらいの難易度や合格率なのか判断することはできません。
とはいっても、資格を取得するにはテキストを使った自宅学習と金融リテラシーに関する幅広い知識が問われるため、容易に合格できる試験では無いということが伺えます。
一方FP技能試験の場合、例年の合格率は3級で60〜80%、2級で30〜40%、1級で10%前後という数値が出ています。
そのため、投資診断士、FP関連資格どちらの資格を取るべきか判断する際には合格率ではなく、就職先の実務内容を考慮、比較して判断しましょう。
資格の方取得しやすさの比較
投資診断士とFPではどちらの資格の方が資格の取得がしやすいのか比較していきます。
資格の取得しやすさは、FP(ファイナンシャルプランナー)の方が取りやすくなっています。
FPは級ごとに難易度が分かれており、自分のレベルに合った難易度や必要な級で選択することができます。
また、3~2級は合格率が比較的低くなっているのもFPの方が取得しやすい要因となっています。
初心者の方は最初にFP資格に挑戦してみることをおすすめします。
FPを取得するならアガルート

これまで投資診断士とFPの違いについて比較してきました。
難易度の比較的優しいFP資格ですが、目指す際に独学での学習が不安な方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方はアガルート通信講座を利用してみてはいかがでしょうか?
- 業界でもトップクラスの合格率
- 各種割引が充実している
- 合格特典で受講料全額返金
アガルート通信講座は難関国家資格専門に扱う通信講座で、上記のような特徴を持っています。
充実したカリキュラムが比較的安価な値段で受けられることも大きな特徴の1つとなっています。
圧倒的合格率
アガルートの最大の特徴はやはり合格率となっています。
FP資格では2024年度の試験において2級の合格率が91.67%%と驚異的な合格実績を誇っています。
受講したほとんどの生徒が合格しており、アガルートの信頼度の高さが分かりますね。
投資診断士とFPについて徹底比較まとめ
今回は投資診断士、FP関連資格の試験概要や実務における優位性について比較や違いを紹介しました。
投資診断士は「投資」という専門業務を行なう金融企業に就職する際にぜひ取得しておくべき資格となり、一方FP関連資格は、投資を始め、資産設計や資産運用、住宅ローンや税金対策と言った金融業に限らず個人のお金に関わる実務を行なう際に必要な資格です。
どちらがより優れていてどちらが劣っているというわけではなく、実務の内容によってそれぞれの資格が必要となります。
アガルート通信講座はFPにおいて高い合格実績と合理的なカリキュラムが特徴なので、通信講座を検討している方はアガルート通信講座を利用してみてはいかがでしょうか?
金融業へ就職を考えている方は特に以上で紹介した内容をぜひ参考にしてください。
監修者情報
新倉 健太郎
株式会社ミエルモ CFO

大手不動産会社からベンチャー不動産会社で役員を経験し独立。事業譲渡後、現在は火災保険申請サポートサービスのミエルモを2019年に立ち上げ、現在では年間15,000件以上の依頼を受け業界最大手まで規模を拡大中。
所有資格等
簿記1級・FP・宅地建物取引士・自然災害調査士
公式サイト:https://mielmo.co.jp/