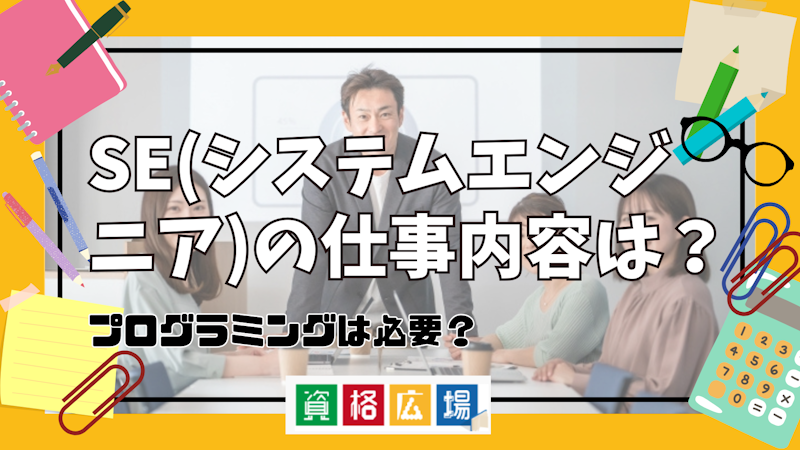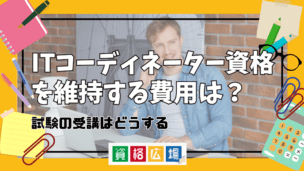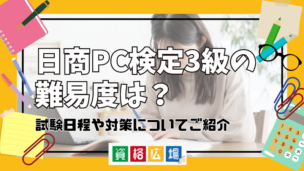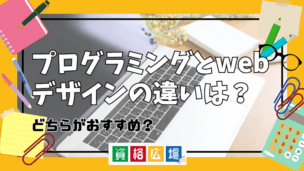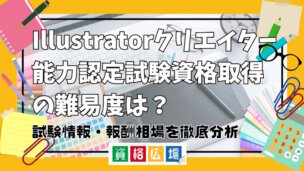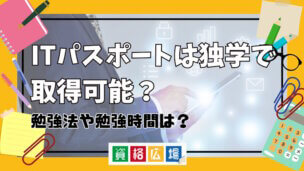ITエンジニアの一つであるSE(システムエンジニア)ですが、名前を聞いただけでは仕事内容が想像しにくいかもしれません。
また、SEは同じIT系の職種であるプログラマと混同されがちな職種でもあります。
そこで今回は、SEの仕事内容とはいったいどのようなものなのか、また、プログラマとの違いなどを詳しく解説していきます。
稼げる・儲かる資格おすすめランキングTOP12!取得難易度や収入アップ・副業でも活用できる資格を徹底比較【2024年最新】
SE(システムエンジニア)とは?

SE(システムエンジニア)は、主に「上流工程」と呼ばれるシステムの大まかな設計やプロジェクトの進捗具合の管理をするのが仕事です。
つまり、顧客と直接話し合い、顧客の要望をどのようなシステムで実現するのかを考えるのが主な仕事だと言えるでしょう。
また、システムが完成した後も運用や保守といった作業をするのもSEの役割です。
プロジェクト全体を最初から最後まで支える、システム開発にはなくてはならない存在だと言えるでしょう。
SE(システムエンジニア)の仕事内容は?
SEの仕事内容は大きく分けると要件定義、基本設計、詳細設計、テスト、運用・保守と分けることができます。
各段階でどのような仕事が行われているのか、詳しくご紹介していきます。
要件定義
要件定義では、顧客との話し合いをしながらどのようなシステムを作るのか、方針を定めることが目的となります。
特に、何が必要な機能で何が不必要な機能なのかを明確にして、顧客が求めている物を具体的に定義するのが要件定義での仕事です。
システム開発にも当然守らなければならない納期や費用が決まっているため、そうした条件を加味しつつなるべく顧客の要望に答えるようにしていかなければなりません。
また、顧客との間で認識にズレが無いよう、顧客の要望を正確に聞き出せるコミュニケーション能力も必要になってきます。
基本設計・詳細設計
次に、基本設計の段階でシステム全体の構成について決めていきます。
要件定義でわかった顧客の要望に基づいて、必要な機能や画面の構成、データの扱い方など全体的な設計をしていきます。
詳細設計では、基本設計で決めた機能や構成をどのように実装していくのか、実際のプログラミングに近い形で考えます。
要件定義ではそこまでITに関する知識が必要ありませんでしたが、基本設計、詳細設計となるにつれて段々とITに関する知識が必要になってくるのが特徴です。
テスト
設計段階が終わると実際にそれを開発することになりますが、開発はプログラマの役割でSEの仕事ではありません。
SEが再び必要になるのは開発が終わった後の、「テスト」の段階になります。
テストでは、その名の通り要件通りにプログラムが動くかどうかや、変な挙動をせず安全に動くかどうかをテストすることになります。
あらゆる条件下で正常に動くようにテストパターンを考えてバグを見つけなければならないため、テストをしっかり行えたかどうかでシステムの質が決まると言っても過言ではないでしょう。
全部いっぺんにテストするのは効率が悪いため、一般的には出来上がった小さなプログラムごとにテストをし、全部のプログラムが揃い次第「結合テスト」と呼ばれる全体のテストを行います。
保守・運用
テストでしっかりと動くことが確認できたらシステムの完成となりますが、これでSEの仕事が終わりになるわけではありません。
システムがきちんと動き続けられるよう「運用」や「保守」を行うのもSEの仕事のうちの一つです。
どれだけ設計やテストをしっかり行なっても発見できないバグや想定していなかったトラブルというものは起こります。
そうしたトラブルに迅速に対応し、システムが安定して使い続けられるように管理していくのがSEの最後の業務というわけです。
プログラマーとの違いは?
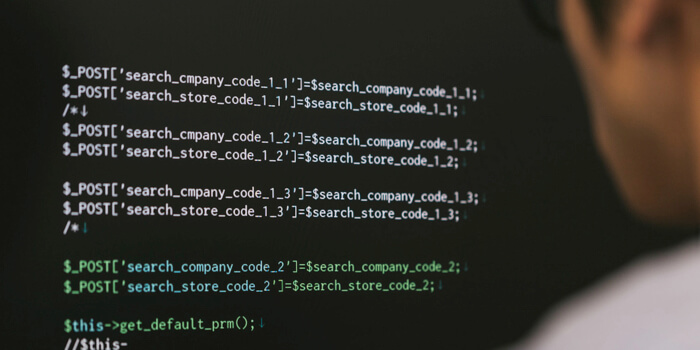
SEの業務内容を見てきた皆様はもうお分かりかと思いますが、SE(システムエンジニア)はシステムの設計を行うのが主な仕事なのに対し、プログラマーは実際にプログラミングを行うのが仕事です。
同じプロジェクトに関わるIT系の職種という意味では似ているかもしれませんが、その業務は全くと言っていいほど違います。
特に、プログラマーはプログラミングを中心としたITスキルが必須なのに対し、SEはそうした知識が無くても、理系・文系問わずなることができます。
また、ご紹介したようにSEには直接顧客と対話して必要な情報を聞き出すコミュニケーション能力や、納期や費用に合わせて全体の見通しを立てる管理能力が大切になってきます。
このように、求められるスキル自体もかなり差があります。
ただし、小規模なシステムの開発や少人数のチームなどではSEとプログラマを兼ねているという人も珍しくありません。
SEにプログラミングのスキルは必要?
SEは必ずしもプログラミングのスキルが必要というわけではありません。
各会社の分担の仕方にもよりますが、実際にプログラミングを行うわけではないためプログラミングのスキルを持っていないSEの方もたくさんいます。
しかし、設計の段階ではプログラミングをすることを意識した構成が大切になってきます。プログラミングのことを全くわかっていないのに詳細設計を行なってしまうと、プログラマの方が困ることになってしまいます。
そのため、もしSEを目指す場合には、必要最低限のプログラミングの知識を身につけておくことをおすすめします。プログラミングができるだけで業務の幅も格段に広くなるため、特にこれからSEを目指そうと考えている方はプログラミングの練習もしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
SE(システムエンジニア)とは、上流工程と呼ばれるシステム全体の設計を行う人のことを言います。
顧客の要望を聞きどのようにシステムを作っていくかを考えるのが主な仕事であるため、理系・文系問わず目指しやすいのがSEの特徴です。
しかし、全くプログラミングのスキルがいらないかと言えばそうではありません。プログラミングのスキルが業務で役立つ場合はたくさんあり、SEとプログラマを兼ねているという人もたくさんいます。
プログラミングは理系・文系問わず必須スキルになりつつあるため、SEになりたい方はぜひSEとプログラミングの勉強を並行して行なってみてはいかがでしょうか・<。