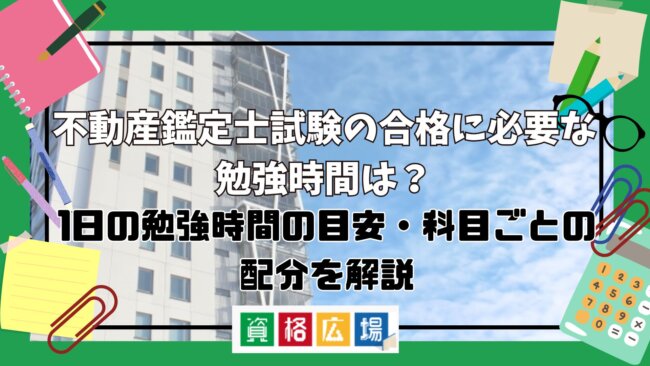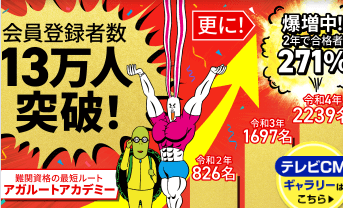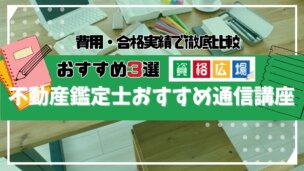不動産鑑定士試験は、不動産の評価に関する専門的な知識と技能を問う資格試験です。
不動産業界でのキャリアアップを目指す方や、独立を考えている方にとって非常に重要なものです。
これから不動産鑑定士を目指して勉強を始めようとしている方や、既に働きながら勉強している方も多いことでしょう。
しかし、どのくらいの勉強時間が必要なのか、どのように勉強時間を確保すれば良いのか、また効率的に勉強を進める方法について悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産鑑定士試験に合格するために必要な勉強時間の目安や、勉強時間の作り方、働きながら合格を目指すための方法、そして勉強を効率よく進めるためのポイントについて徹底的に解説していきます。
不動産鑑定士試験合格に必要な勉強時間は2,000〜4,000時間
不動産鑑定士試験に合格するためには、2,000〜4,000時間ほどの勉強時間が必要です。
この試験は非常に難易度が高く、幅広い知識を要求されるため、計画的な勉強が求められます。
しっかり勉強時間を確保し、効率的に勉強を進めることが合格への鍵です。
以下に、初学者と学習経験者、それぞれで必要な勉強時間を解説します。
- 初学者の場合
- 学習経験者の場合
初学者の場合
不動産鑑定士試験の初学者は、不動産や法律に関する基礎知識から学び始める必要があります。
このため、2,000〜4,000時間の学習時間が必要とされます。
例えば、1日3時間の勉強を続けた場合、約2〜4年の期間を見込むことができます。
以下の表に、1日あたりの学習時間に応じて、2,000時間から4,000時間の学習時間を達成するのに必要な期間をまとめました。
| 1日あたりの学習時間 | 2,000時間 | 2,500時間 | 3,000時間 | 3,500時間 | 4,000時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2時間 | 2年9カ月 | 3年5カ月 | 4年1カ月 | 4年9カ月 | 5年5カ月 |
| 3時間 | 1年10カ月 | 2年3カ月 | 2年9カ月 | 3年2カ月 | 3年7カ月 |
| 4時間 | 1年4カ月 | 1年8カ月 | 2年0カ月 | 2年4カ月 | 2年9カ月 |
| 5時間 | 1年1カ月 | 1年4カ月 | 1年7カ月 | 1年11カ月 | 2年2カ月 |
| 6時間 | 0年11カ月 | 1年1カ月 | 1年4カ月 | 1年7カ月 | 1年10カ月 |
| 7時間 | 0年9カ月 | 0年11カ月 | 1年2カ月 | 1年4カ月 | 1年6カ月 |
| 8時間 | 0年8カ月 | 0年10カ月 | 1年0カ月 | 1年2カ月 | 1年4カ月 |
初学者が不動産鑑定士試験の合格を目指すなら、まとまった勉強時間を確保して毎日学習することをおすすめします。
上記を参考に、自分の生活スタイルに合わせた学習計画を立ててください。
まとまった勉強時間を平日に確保することが難しい方は、平日の勉強時間は短くして、週末にまとまった勉強時間を取るよう調整すると良いでしょう。
学習経験者の場合
すでに不動産や法律に関する基本的な知識を持っている学習経験者の場合、必要な勉強時間は初学者に比べて短くなることが多いです。
一般的には2,000〜3,000時間の学習時間が目安となります。
過去問を解きながら、自分の弱点を洗い出し、その部分を重点的に学習しましょう。
また、宅建試験を勉強したことがある方も、少ない勉強時間で効率良く不動産鑑定士試験の合格を目指せます。
民法など宅建試験で学習した内容は、不動産鑑定士試験でも出題されることがあるからです。
宅建試験は不動産鑑定士と相性が良く、ダブルライセンスとしても高い人気を誇ります。
論文試験対策など、最新の傾向を押さえて効率よく学習を進めたい方は、通信講座の利用を検討しましょう。
不動産鑑定士試験の合格率
不動産鑑定士試験の合格率は、短答式試験が約33〜36%、論文式試験が約14〜17%、最終的な合格率は5〜6%程度といわれています。
難易度は行政書士や公認会計士といった高難易度の試験と比較すると合格率が低く、社労士や司法書士と同等のレベルに位置付けられます。
また不動産鑑定士試験にはそれぞれ合格基準が設けられており、短答式試験で約70%、論文式試験で約60%の得点が求められます。
各科目ごとに最低得点が設定されているため、全ての科目で一定以上の得点を取得する必要があります。
したがって合計点が合格基準に達していても、特定の科目で極端に低い得点を取った場合には合格できない可能性があるため、注意が必要です。
また、免除科目がある場合には、免除科目以外の科目の合計得点を基に、偏差値などを用いて総合点が算出されます。
以上のことから、不動産鑑定士試験の合格率は低く、難易度が非常に高いことが明らかです。
不動産鑑定士試験合格に時間がかかる理由
不動産鑑定士の試験合格を目指すなら、2,000〜4,000時間ほどの長期にわたる勉強が必要です。
なぜそれほどの勉強時間が必要なのか、主な理由を解説します。
- 不動産鑑定士は試験範囲が広いから
- 深い専門知識が問われるから
- 試験が2段階式になっているから
なお、一定の条件を満たしている方は一部科目が免除されて、勉強時間を短縮できる場合があります。
詳しくは後述をチェックしてください。
不動産鑑定士は試験範囲が広いから
不動産鑑定士試験は、非常に広範囲にわたる知識を問われます。
試験範囲は、不動産鑑定理論、経済学、財務会計、法規、建築関連知識など、多岐にわたります。
これらの知識は、単なる暗記ではなく、実務に即した応用力が求められるため、理解を深める必要があるわけです。
そのため、試験対策としては、すべての科目を網羅し、バランスよく学習を進めることが重要です。
この広範な範囲をカバーするためには、多くの勉強時間が必要となります。
深い専門知識が問われるから
不動産鑑定士は、不動産の価値を正確に評価するための高度な専門知識が求められます。
具体的には、土地や建物の市場価値、収益性、法的制約など、多様な要素を総合的に判断する能力が必要です。
試験では、このような深い専門知識を持っているかどうかが厳しく問われます。
また、理論だけでなく、実務に即した問題も出題されるため、実際のケーススタディを通じて知識を応用する力を養うことが不可欠です。
これらの高度な専門知識を習得するためには、十分な勉強時間を確保することが必要です。
試験が2段階式になっているから
不動産鑑定士試験は、短答式試験と論文式試験の2段階に分かれています。
まず、短答式試験では、基礎的な知識を幅広く問われ、これに合格しなければ次の論文式試験に進むことができません。
論文式試験では、より深い理解と応用力が試され、実際の鑑定業務に即した問題が出題されます。
なお、短答式試験に合格すると、合格した年を含めて3年間は論文式試験を受験できる仕組みです。
例えば、2024年に短答式試験に合格し、同年に論文式試験が不合格だったとしても、2025年と2026年は短答式試験を受験することなく、再度論文式試験に挑戦できます。
ただし、3年目である2026年の論文式試験で不合格の場合、不動産鑑定士に合格するには、2027年は再び短答式試験に合格する必要があります。
2段階式の試験で最大3年の猶予があるため、勉強に専念できない社会人受験生は特に、2年ほどの学習計画を立てている方が多いです。
不動産鑑定士試験の科目免除制度
不動産鑑定士試験には、一部の資格保有者や一定の条件を満たす受験者に対して、試験科目の一部が免除される科目免除制度があります。
この制度を活用することで、試験の負担を軽減し、効率的に合格を目指すことができます。
科目免除制度が適用される条件と、免除科目は以下の通りです。
| 科目免除制度 | 免除科目 |
|---|---|
| 司法試験または 旧司法試験第二次試験の合格者 |
民法 |
| 公認会計士または 旧公認会計士試験第二次試験の合格者 |
会計学及び合格した試験において受験した科目 (民法または経済学) |
| 大学等※において通算して3年以上法律学に属する科目の教授又は准教授(助教授)の職にあった者 法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 |
民法 |
| 大学等※において通算して3年以上経済学に属する科目の教授又は准教授(助教授)の職にあった者 経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 |
経済学 |
| 大学等※において通算して3年以上商学に属する科目の教授又は准教授(助教授)の職にあった者 商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 |
会計学 |
| 高等試験本試験に合格した者 | 合格した試験において受験した科目 |
※学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学(予科を含む。)、旧高等学校令による高等学校高等科又は旧専門学校令による専門学校
免除科目が複数該当する場合も、すべての免除を申請可能です。
詳細は国土交通省の公式サイトで確認しましょう。
科目免除制度を活用すれば、不動産鑑定士試験の勉強時間を大幅に短縮できます。
不動産鑑定士試験の各科目ごとの勉強時間配分
2段階式の不動産鑑定士試験を合格するためには、それぞれの試験の勉強時間を計画的に配分することが大切です。
各試験ごとの効果的な勉強時間配分について説明します。
- 短答式試験の勉強時間
- 論文式試験の勉強時間
短答式試験の勉強時間
短答式試験の勉強時間の目安は、700~1,000時間です。
短答式試験は、主に基礎的な知識を広範囲に問う形式です。
勉強配分の例は以下の通りです。
| 科目 | 700時間の場合 | 1,000時間の場合 |
|---|---|---|
| 鑑定理論(50%) | 350時間 | 500時間 |
| 行政法規 (50%) | 350時間 | 500時間 |
短答式試験では、試験科目の鑑定理論と行政法規を、バランスよく時間配分して勉強すると良いでしょう。
論文式試験の勉強時間
論文式試験の勉強時間は、1,500~3,000時間ほど必要です。
より高度な知識と実務に基づく応用力が試されます。
まずは短答式試験に合格した後に、論文式試験の勉強時間を適切に配分するのがおすすめです。
| 科目 | 1,500時間の場合 | 3,000時間の場合 |
|---|---|---|
| 鑑定理論 (50%) | 750時間 | 1,500時間 |
| 経済学・経済事情 (20%) | 300時間 | 600時間 |
| 不動産に関する法律 (20%) | 300時間 | 600時間 |
| 会計学 (10%) | 150時間 | 300時間 |
論文式試験では、特に鑑定評価理論に勉強時間を取ることをおすすめします。
なお、上記の勉強時間の配分はあくまで目安なので、自分の得意分野・弱点や学習習熟度にあわせて、配分を調整してください。
不動産鑑定士試験の1日あたりの勉強時間
以下の表に、1日あたりの勉強時間に応じて、必要な学習期間の目安をまとめました。
| 1日当たりの勉強時間 | 必要な学習期間 |
|---|---|
| 8時間 | 1年ほど |
| 平日4時間 休日8時間 |
2年ほど |
| 平日2時間 休日5時間 |
3年ほど |
1日にまとまった時間を取って受験に専念できる学生や主婦の方は、例えば1日8時間の勉強時間であれば、1年ほどの学習スケジュールで受験可能です。
社会人の場合、平日4時間・休日8時間で2年ほど、平日2時間・休日5時間で3年ほどの学習期間が日宇町になります。
自分の生活スタイルに合わせた学習計画で、無理なく不動産鑑定士試験の合格を目指しましょう。
不動産鑑定士試験の勉強時間の作り方
不動産鑑定士試験の勉強時間を確保するためには、日常生活の中で工夫が必要です。
仕事やプライベートで忙しい中でも、勉強時間を作り出す方法について解説します。
- 勉強時間を確実に確保する
- 勉強時間を管理する
- 優先順位をつける
- 生活リズムを見直す
特に、平日は勉強時間が取れないという社会人の方などは必見です。
勉強時間を確実に確保する
忙しい日常の中で勉強時間を確保するためには、早朝や夜間の時間を有効活用することが大切です。
また、通勤時間や休憩時間も積極的に勉強に充てることで、効率よく勉強時間を作り出すことができます。
週末や休日も有効に活用し、まとまった勉強時間を確保することも重要です。
例えば、週末に5時間ずつ勉強することで、1週間で10時間の勉強時間を確保できます。
勉強時間を管理する
毎日のスケジュールを立て、勉強時間を確保することが成功の鍵となります。
勉強時間を管理するためには、タイムマネジメントが非常に重要です。
具体的には、週ごとの目標を設定し、それを達成するために日々の計画を練ることが推奨されます。
- 週ごとに目標を設定する
- 毎日の勉強時間を記録する
- 定期的に進捗を確認し、計画を修正する
- 効率的に勉強するために、集中力が高まる時間帯を見つける
- 休憩を適切に取り入れて、無理なく続ける
以下に、効果的な勉強時間の管理方法の一例を紹介します。
勉強時間を記録し、定期的に見直すことで、より効率的な勉強が可能になります。
自分に合った方法を見つけ、計画的に勉強を進めましょう。
優先順位をつける
日常生活の中で優先順位をつけて、重要度の高いタスクから取り組むことが大切です。
例えば、仕事や家事などの優先順位を見直し、無駄な時間を削減することで勉強時間を捻出することができます。
また、勉強に集中するために、スマートフォンの使用時間を制限するなどの工夫も効果的です。
具体的には、毎日のスケジュールを見直し、優先順位をつけて効率的に時間を使うことが求められます。
しっかりとした優先順位をつけることで、無理なく勉強時間を確保し、効率的に学習を進めることができます。
生活リズムを見直す
勉強時間を確保するためには、生活リズムを見直すことも重要です。
規則正しい生活を送ることで、体調を整え、効率的に勉強を進めることができます。
例えば、毎日決まった時間に起きる、バランスの取れた食事を摂る、適度な運動をするなどの習慣を身につけることが推奨されます。
また、睡眠時間をしっかり確保することで、集中力を高めることができます。
生活リズムを整えることで、勉強の質を向上させ、効率的に学習を進めることが可能になります。
不動産鑑定士試験の勉強を効率よく進める方法
不動産鑑定士試験に合格するためには、効率的な勉強法を実践することが重要です。
ここでは、以下のポイントについて解説します。
- 効率的な学習プランを立てる
- 重要ポイントを絞って勉強する
- 少ない時間でも毎日継続する
- 鑑定理論から勉強する
- 通信講座で勉強する
効率的な学習プランを立てる
効率的な学習プランを立てるためには、まず自分の強みと弱みを把握することが重要です。
どの科目にどれだけの時間を割くべきかを明確にし、バランス良く勉強を進める計画を立てましょう。
例えば、苦手な科目には多めの時間を割り振り、得意な科目は復習に重点を置くなど、効率的なプランを作成します。
以下の表に、科目ごとの勉強時間配分の一例を示します。
| 科目 | 必要勉強時間 |
|---|---|
| 民法 | 300時間 |
| 経済学 | 300時間 |
| 会計学 | 400時間 |
| 不動産評価理論 | 500時間 |
| 法規 | 200時間 |
重要ポイントを絞って勉強する
勉強時間を無駄にしないためには、重要なポイントに絞った学習が必要です。
以下のリストを参考にして、無駄な勉強を排除しましょう。
- 頻出テーマに注力する
- 過去問を徹底的に分析し、出題傾向を把握する
- 自分に合った参考書や問題集を選ぶ
無駄を省いた効率的な学習を実践することで、短期間での合格を目指すことができます。
少ない時間でも毎日継続する
毎日少しずつでも勉強を継続することが重要です。
忙しい日常の中でも、隙間時間を有効活用する方法を考えましょう。
| 時間帯 | 勉強内容 |
|---|---|
| 朝の通勤時間 | テキストの読み込みや音声教材の視聴 |
| 昼休み | 過去問の確認や重要ポイントの復習 |
| 夜のリラックスタイム | 日中に学んだ内容の整理と記憶の定着 |
毎日の小さな積み重ねが、大きな成果を生むことを忘れないようにしましょう。
鑑定理論から勉強する
不動産鑑定士試験の中でも、鑑定理論は非常に重要な科目です。
最初に鑑定理論を徹底的に学ぶことで、他の科目の理解も深まります。
- 基本的な概念と理論をしっかりと理解する
- 具体的な事例を通して実践的な知識を身につける
- 過去問を繰り返し解くことで、出題傾向を把握する
- 模擬試験で実力を確認し、弱点を補強する
鑑定理論の理解が深まれば、他の科目の学習もスムーズに進めることができます。
通信講座で勉強する
通信講座を利用することで、効率的に学習を進めることができます。
以下に、通信講座の主なメリットをまとめました。
- 自分のペースで学習できる
- プロの講師からの指導を受けられる
- 最新の教材や情報を入手できる
- 質問サポートなどのサービスが充実している
通信講座を上手に活用することで、忙しい社会人でも効率的に学習を進めることが可能です。
不動産鑑定士とは
不動産鑑定士は国家資格を有する専門家であり、主に土地を中心とした不動産の価値を評価する役割を担っています。
不動産の環境や多様な条件を考慮し、価格の算定や適切な利用方法についての判断を行います。
土地を効果的に活用するためには、正確な価値評価と適正な利用に関する判断が不可欠であり、不動産の価値は地域や物件の状態、さらには関連する権利関係などによっても影響を受けます。
同じ不動産であっても、時代や社会情勢の変化により需要が変動し、価値が異なることも多く、専門的な知識と豊富な経験が求められます。
不動産鑑定士の主な業務は不動産鑑定評価であり、これは彼らの独占的な業務です。
ほかにも不動産の状態や環境、社会情勢などのさまざまな要素を考慮しながら、経済的価値を算定します。
自治体による地価公示や相続税標準地の評価、裁判における評価などが不動産鑑定評価の具体例です。
さらに、不動産関連のコンサルティングも不動産鑑定士の仕事のひとつであり、豊富な知識と経験を活かし、不動産の有効活用や開発計画に関する適切なアドバイスを提供します。
不動産鑑定士の試験について
不動産鑑定士試験の学習が計画的に進める必要があります。
ここでは、例年の不動産鑑定士試験の概要について紹介します。
- 願書受付…2月上旬~3月上旬
- 短答式試験…5月下旬(合格発表6月下旬)
- 論文式試験…8月上旬※3日間(合格発表10月下旬)
試験日程や開催地などは年度にとって異なるため、詳しい情報は国土交通省のホームページで確認するようにしましょう。
不動産鑑定士の平均年収
厚生労働省の統計によると、不動産鑑定士の平均年収は約754万円であり、これは給与所得者全体の平均年収である443万円と比べてもかなり高い水準であるといえます。
不動産鑑定士は安定した高収入を得られるといえるでしょう。
また、不動産鑑定士の年収は経験年数によって年収には顕著な差が生じます。
初年度の年収は600万円から800万円程度ですが、5年目には800万円から1,100万円、10年目には900万円から1,300万円に達する傾向があります。
さらに、独立した鑑定士の場合、収入は個々の営業能力や顧客との関係に、年間で数千万円の売上を上げる鑑定士も少なくありません。
しかし、独立不動産鑑定士として安定的に高収入を得るためには、相応の努力と営業力が求められるでしょう
不動産鑑定士試験の勉強時間を最短ルートにするならアガルートがおすすめ
不動産鑑定士試験の合格を目指すなら、アガルートの不動産鑑定士講座を受講しましょう。
アガルートの不動産鑑定士試験講座は、最新の試験傾向を反映したテキストと論証集を提供し、合格への最短ルートを実現します。
経験豊富な講師陣がわかりやすい講義を行い、個別サポートも充実しています。
さらに、分割手数料無料の教育クレジットローンや最大20%の割引制度、合格特典など、お得な情報も満載です。
忙しい社会人でも効率的に学習できるように設計されているので、合格に向けて効率良く学習できます。
詳細はアガルートの公式サイトを以下からご覧ください。
不動産鑑定士の合格のために勉強時間をしっかり確保しよう
不動産鑑定士試験に合格するために勉強時間の目安は2,000〜4,000時間ですが、人によって必要な勉強時間は異なります。
しかし重要なのは、計画的に勉強時間を確保することです。
まず、毎日のスケジュールを見直し、仕事や生活の中で無理なく勉強時間を作り出しましょう。
効率的な学習プランを立て、各科目ごとにバランス良く勉強時間を配分することが成功の鍵です。
また、アガルートで経験豊富な講師の講座を受講することも検討しましょう。
オンライン講座なので、いつでもどこでも、スキマ時間も活用しながら学習を進められます。