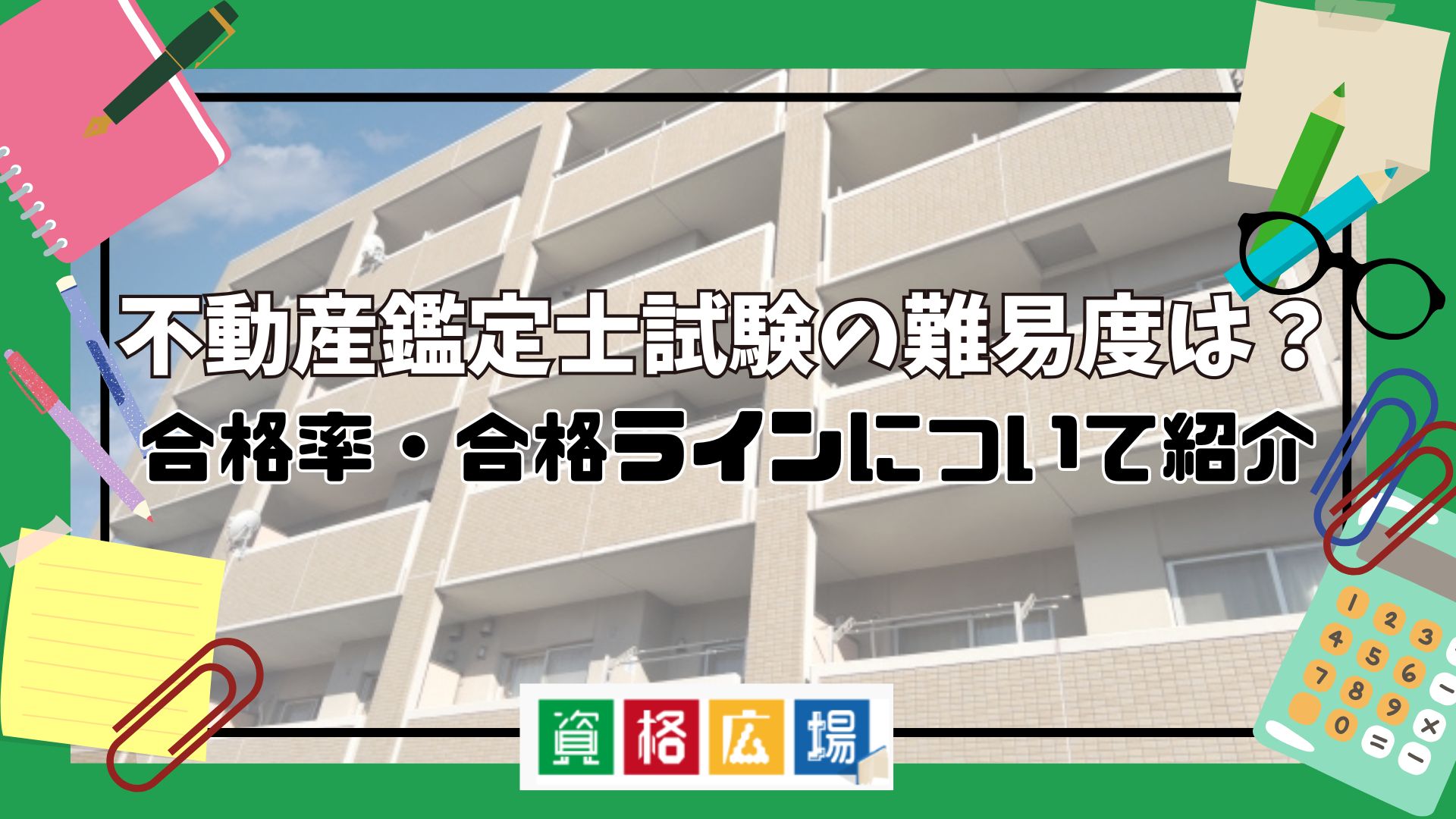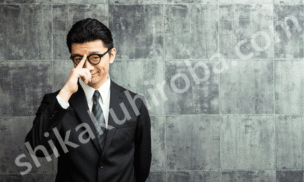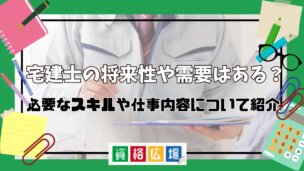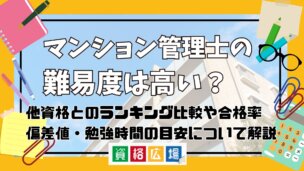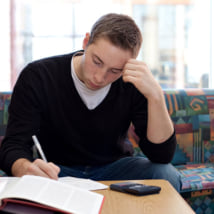2020年の東京オリンピック開催に伴い、江東区を始めとする近隣の地域の地価や不動産物件価格の高騰が話題になっていますが、それらの価値というものは実際にどのように決められているのでしょうか?
これからの時代知っておきたい不動産鑑定士に関して、主な仕事内容や国家試験の難易度、また気になる年収や将来性について調査しました。
■Amazon券3,500円分プレゼント特典
| 特典内容 | 対象講座のお申込みで、Amazon券3,500円分をプレゼント |
|---|---|
| 対象者 | こちらから対象講座に申し込んだ方 |
| 対象講座 |
|
| 期間 | 4月1日~4月30日まで |
| 問い合わせ先 | [email protected] ※株式会社アガルートではお問い合わせの受付を行っておりません。ご不明点やご質問は上記メールアドレス宛にご連絡下さい。 |
>> 資格広場限定キャンペーンの特典リンクはこちら
【キャンペーン提供方法について】
- Amazonギフト券の送付には最大で2ヵ月ほどかかる場合がございますので、予めご了承ください。
- 友人紹介制度を利用した場合は、Amazonギフトカード付与の対象外となります。
- 本キャンペーンは、東晶貿易株式会社及びパートナー会社協力の元、提供するキャンペーンです。
- プライバシーポリシー等に関する詳細はこちらからご確認ください。
資格取得を目指すなら今がチャンス!今すぐ講座をチェックして、特典をゲットしよう!
不動産鑑定士の最終合格率は約4~5%
不動産鑑定士試験の合格率は通年、短答式試験が約33〜36%・論文式試験が約14〜17%、最終合格率が5~6%程といわれています。
合格率や勉強時間で比較すると、司法書士試験と同じくらいの難易度であると言えます。
短答式試験の合格率は約33%~36%
不動産鑑定士試験の短答式試験の合格率は以下の通りとなります。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 | 1,675 | 606 | 36.2% |
| 令和5年 | 1,647 | 553 | 33.6% |
| 令和4年 | 1,726 | 626 | 36.3% |
| 令和3年 | 1,709 | 621 | 36.3% |
| 令和2年 | 1,415 | 468 | 33.1% |
| 令和元年 | 1,767 | 573 | 32.4% |
参照:国土交通省
論文式試験の合格率は約14%~17%
不動産鑑定士試験の論文式試験の合格率は以下の通りとなります。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 | 847 | 147 | 17.4% |
| 令和5年 | 885 | 146 | 16.5% |
| 令和4年 | 871 | 143 | 16.4% |
| 令和3年 | 809 | 135 | 16.7% |
| 令和2年 | 764 | 135 | 17.7% |
| 令和元年 | 810 | 121 | 14.9% |
参照:国土交通省
不動産鑑定士試験の合格ライン
不動産鑑定士試験の合格ラインは例年、短答式試験で約7割、論文式試験で薬6割程度とされています。
ただし不動産鑑定士試験は科目ごとに最低特典が設けられているので、全ての科目を満遍なく取らなければいけません。
短答式試験の合格ライン
不動産鑑定士試験の短答式試験の合格ラインは以下の通りとなります。
| 年度 | 満点 | 合格ライン |
|---|---|---|
| 令和6年 | 200点 | 140点(70%) |
| 令和5年 | 200点 | 132.5点(66.25%) |
| 令和4年 | 200点 | 150点(75%) |
| 令和3年 | 200点 | 140点(70%) |
| 令和2年 | 200点 | 133点(66.5%) |
| 令和元年 | 200点 | 140点(70%) |
参照:国土交通省
論文式試験の合格ライン
不動産鑑定士試験の論文式試験の合格ラインは以下の通りとなります。
| 年度 | 満点 | 合格ライン |
|---|---|---|
| 令和6年 | 600点 | 400点(67%) |
| 令和5年 | 600点 | 369点(61%) |
| 令和4年 | 600点 | 380点(63%) |
| 令和3年 | 600点 | 380点(63%) |
| 令和2年 | 600点 | 380点(63%) |
| 令和元年 | 600点 | 353点(59%) |
参照:国土交通省
不動産鑑定士の概要や難易度
不動産鑑定士の主な業務内容や社会での役割について理解していただけたでしょうか?
それでは、実際に不動産鑑定士を目指している方のために、資格取得までの道のりや試験概要、また難易度についても他の国家資格の難易度と比べながら紹介します。
是非参考にして下さい。
試験概要
まず不動産鑑定士国家試験の受験資格ですが、以前までは大卒以上という条件がありましたが2018年10月現在では条件は撤廃されています。
そのため学歴、年齢問わず誰でも受験することができます。
試験概要ですが、試験は大きく2分野に分かれております。
1つ目は不動産に関する基礎的な知識や行政法規や鑑定評価の理論など幅広い内容に関して問われる短答式試験、そして短答式試験に合格した者だけが受験できる民法や経済学、その他不動産に関連する法律など、学術的な知識が問われる論述式試験があります。
この2つの試験に合格してもまだ不動産鑑定士の資格を得ることはできません。
合格後約1年〜2年の間、実務修習にて不動産鑑定士に必要とされる実践的な技能や知識を習得します。
実務修習のカリキュラムの修了後にある修了考査にて合格点を獲得すれば、国土交通省の名の元に晴れて資格取得となります。
このように資格試験だけでなく実務修習もあるため不動産鑑定士の資格取得までの道のりは非常に長いものとなっております。
国家試験の中でも非常にハイレベルな難易度
不動産鑑定士国家試験の気になる難易度ですが、ズバリ、非常にハイレベルな難易度の国家資格に分類されます。
比較材料として、同分野の他の国家資格の難易度をいくつか挙げてみます。
まず、宅地建物取引士資格の合格の難易度は16〜17%(参照:Foresight)、管理業務主任者が22.5%(参照:資格の取り方)と言われています。
一方、不動産鑑定士の短答式試験の難易度は例年25%前後と比較的高くはないですが、論述式試験に関しては例年10%前後となっており、非常にハイレベルな試験となっています(参照:キャリアガーデン)。
試験までの対策、試験合格後の実務修習の負担を考えれば、不動産鑑定士の資格は容易には取得できない資格といっても過言ではないでしょう。
不動産鑑定士試験合格に必要な学習時間は2,000時間以上
不動産鑑定士試験に合格するためには、最低でも2,000時間の学習が必要とされています。
しかし上記の勉強時間はあくまで目安であり、学習を始める際の知識レベルや実務経験の有無によっても変わってきます。
例えば、不動産鑑定士試験には科目免除制度が存在し、公認会計士試験や司法試験に合格した方は一部の科目が免除されることがあります。
また、特定の科目を教授している方や博士号を取得した方も、免除の対象となります。
免除制度を利用することで、学習時間を短縮することが可能です。
一方で、免除を受けられない初学者は、3,000時間以上の勉強が必要になり、 仮に2,000時間の学習で合格できるとした場合、1年で合格するためには、週に約42時間の学習が必要です。
週に約42時間となると毎日約6時間の勉強を確保しなければならず、学生でも会社員でも両立が難しいといえるでしょう。
不動産鑑定士の難易度が高いと言われる理由
不動産鑑定士の難易度が高いと言われる理由には以下のものが挙げられます。
各科目に足切り点がある
不動産鑑定士試験が難易度が高いとされる理由の一つは、各科目に足切り点が設定されていることです。
不動産鑑定士試験は短答式試験が2科目、論文式試験が6科目の合計8科目から成り立っていますが、各科目には必ず足切り点が設けられています。
したがって、各科目で求められる最低得点があり、その基準を1点でも下回ると不合格となります。
また、各科目の足切り点については具体的な数値が公表されていないため、受験者は注意が必要です。
短答式試験では約70%、論文式試験では約60%の得点が合格の目安とされていますが、科目ごとの必要得点が明確でないため、苦手科目を持つことができない点も難しさの一因といえるでしょう。
出題範囲が広い
不動産鑑定士の試験が難易度が高いとされる理由の一つは、出題範囲の広さも関係しています。
例えば、短答式試験では、行政法規と鑑定理論の2つの科目が出題されます。
行政法規では、都市計画法や建築基準法を含む37の法令が出題範囲に含まれており、不動産関連の法令について幅広く学ぶ必要があります。
さらに、鑑定理論では不動産鑑定評価基準やその運用に関する留意事項が出題され、非常に専門的な内容を学習しなければなりません。
また論文式試験においては、合計6科目が出題され、 不動産鑑定士試験の主要科目である鑑定理論に加え、民法、経済学、会計学も出題範囲に含まれています。
法律学、経済学、会計学はそれぞれ独立した学問であるにもかかわらず、全てを広範囲にわたって深く学ぶことが求められます。
出題範囲が広いことは、学習に多くの時間を要し、妥協する人も少なくありません。
実務修習を修了しなければいけない
不動産鑑定士の試験が難しい理由のひとつには実務修習を修了する必要がある点もあります。
先にも述べたように、不動産鑑定士試験に合格しただけでは不動産鑑定士として認められず、実務修習を修了しなければいけませんn。
実務に即した研修を受け、研修の最終段階で行われる修了考査に合格することで、初めて不動産鑑定士としての登録が可能となります。
不動産鑑定士を目指す際に鑑定業者に転職する場合、仕事がそのまま実務修習となります。
しかし現在の職業を続けながら実務修習を受ける場合には、試験勉強と同様に仕事以外の時間を利用して講義を受講したり、不動産鑑定評価書を作成したりしながら修了考査の合格を目指す必要があります。
このように、不動産鑑定士試験の後に実務修習があることも、不動産鑑定士になるための高いハードルの一因となっています。
不動産鑑定士とは

不動産鑑定士とは、マンションや一般家屋、また土地などの不動産に対して評価を行い、経済的な価値を与える非常に高度なスキルを要する不動産の専門家です。
私たちが普段スーパーで購入する食べ物や飲食店で食べる料理など、あらゆるものに値段が付けられているように、不動産にも価値が必要となります。
しかし、一般家屋や土地などといった不動産は非常に漠然としたものであることから、野菜や果物のように値段をつけることは素人に取っては非常に困難なことです。その際に社会情勢や経済情勢を考慮し、不動産の鑑定、そして価値を与えるのが不動産鑑定士の重要な仕事です。
また、銀行などの金融機関から融資を受けるための担保物件の査定や、国有地・私有地を売買、処分する際の金額の決定など、私的な業務から公的な業務まで幅広い分野で不動産鑑定士は必要とされます。
不動産鑑定士は鑑定士系唯一の国家資格!
実は数ある国家試験の中で、不動産鑑定士は〇〇鑑定士と付く唯一の国家資格となります。
以上で不動産鑑定士の仕事について紹介したように、不動産鑑定士は民間業務から時には訴訟問題、時には国政にも携わる場合があるため、社会において非常に重要な役割を担っております。
そのため、宝石鑑定士などの数多くの鑑定士系の民間資格がある中、不動産鑑定士は日本の法律に基づいた重要な業務を行うことから、唯一国家資格に定められているのです。
不動産鑑定士の年収や将来性

不動産鑑定士の気になる年収ですが、資格取得までにかなりの努力を要することから、それ相応の収入を見込めることができます。
2015年厚生労働省の調査では、平均給与が約46万円とされているので、単純計算で522万円と普通のサラリーマンの年収に比べて大きく上回っております。
あくまでも平均額なため、不動産鑑定士として独立されている方は年収1,000万円〜稼いでいる方も実際にいるので、非常に高収入が見込める業種と言っても良いでしょう。
常に需要があり将来性のある職業!
社会に不動産がある限り、不動産鑑定士の仕事は決してなくなりません。
そのため、非常にハイレベルではありますが一度資格を取得してしまえば一生食っていけるといっても過言ではありません。
また、宅建士やマンション管理士など、住宅・不動産関連の国家資格と併用して取得することで様々なメリットがあります。
例えば、関連企業における業務の幅の拡大やスキルアップやキャリアアップ、また転職する際の十分なアピール材料にもなります。
過去にあったバブル期や高度経済成長期、また2020年の東京オリンピックなど、時代の節目や社会情勢・経済情勢が大きく変化する時、またマンションや土地の売買が行われるときなど、不動産鑑定士の専門スキルは必要不可欠なものです。
不動産鑑定士は常に需要があり、これからの時代も大変将来性のある職業です。
不動産鑑定士の難易度は?まとめ
不動産鑑定士の資格を得るためには、難易度の高い試験に合格するための知識量やスキルはもちろんのこと、資格取得までの長い道のりを制覇するための根気も必要となります。
しかし、不動産鑑定士の需要は社会から決してなくならず、これからの時代も将来性のある職業であることから努力するだけの価値はあります。
不動産鑑定士として、関連企業においてキャリアを積めば独立して高収入の年収を得ることも夢ではありません。本気で不動産鑑定士を目指す方は、最後まで諦めずに頑張って下さい!