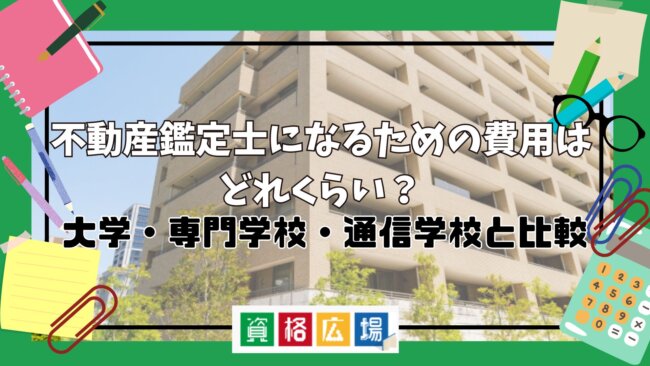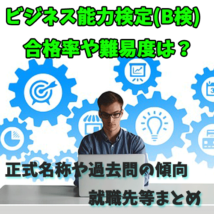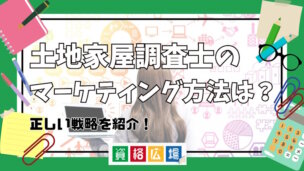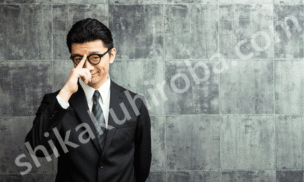不動産鑑定士は、不動産系の資格のなかでも最高峰の国家資格です。
近年、合格率は安定していますが、資格取得の難易度はもちろんのこと仕事に必要な知識も他の資格より格段と難しいと言われています。
今回は、不動産鑑定士になるための費用と通信学校で資格取得が可能なのか解説していきます。
■Amazon券3,500円分プレゼント特典
| 特典内容 | 対象講座のお申込みで、Amazon券3,500円分をプレゼント |
|---|---|
| 対象者 | こちらから対象講座に申し込んだ方 |
| 対象講座 |
|
| 期間 | 4月1日~4月30日まで |
| 問い合わせ先 | [email protected] ※株式会社アガルートではお問い合わせの受付を行っておりません。ご不明点やご質問は上記メールアドレス宛にご連絡下さい。 |
>> 資格広場限定キャンペーンの特典リンクはこちら
【キャンペーン提供方法について】
- Amazonギフト券の送付には最大で2ヵ月ほどかかる場合がございますので、予めご了承ください。
- 友人紹介制度を利用した場合は、Amazonギフトカード付与の対象外となります。
- 本キャンペーンは、東晶貿易株式会社及びパートナー会社協力の元、提供するキャンペーンです。
- プライバシーポリシー等に関する詳細はこちらからご確認ください。
資格取得を目指すなら今がチャンス!今すぐ講座をチェックして、特典をゲットしよう!
不動産鑑定士になるまでのステップとそれぞれにかかる費用
不動産鑑定士になるには以下のステップが必要です。
- 短答式試験(5月)
- 論文式試験(8月)
- 実務修習(12月~、1~2年間)
- 不動産鑑定士登録
試験日や試験実施値については毎年更新されるので国土交通省のホームページでチェックするようにしましょう。
仮に試験勉強を1年間続けた場合、学習開始から不動産鑑定士として活躍するまでに2年半~3年半程度かかる見込みとなります。
不動産鑑定士になるまでにかかる費用としては約40万~113万円程度かかるといわれています。
ここでは、それぞれにかかる費用の内訳について紹介します。
受験手数料
不動産鑑定士試験を受ける際には、12,800円(書面申請の場合は13,000円)の受験料が必要となります。
試験の種類に関わらず一律で設定されているため、短答式試験と論文式試験の両方を受験する場合でも、どちらか一方のみを受験する場合でも、受験料は同額であることに注意が必要です。
実務修習の費用
不動産鑑定士の実務修習を受講するためには、約31万円~106万円の費用が必要です。
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会が策定した令和6年度の実務修習計画によれば、実務修習の基本料金は310,100円で、講義、基本演習、修了考査にかかる費用が含まれています。
さらに、実務修習の料金に加えて、1回の演習ごとに2,500円または6,900円の審査料が必要となります。
審査料は演習の回数や内容によって異なるため、個々の状況により異なります。
なお、物件調査実地演習および一般実地演習の受講料は原則として無料ですが、実地演習を実施する機関で受講する場合は、別途料金が発生します。
各料金の上限は、物件調査実地演習が22,000円、一般実地演習が1回あたり56,000円となり、上限額の実地演習を受けた場合、最高で1,060,100円となります。
ただし、実地演習の料金は実施機関によって異なるため、一概に金額を示すことはできません。
費用について不安がある方は、自身が実地演習を行う機関に確認しておくといいでしょう。
登録手数料
不動産鑑定士としての登録を行う際には、手数料として60,000円が必要です。
また、上記の金額には試験勉強に関連する費用は含まれておらず、 総合的なコストを把握したい場合は試験勉強に必要な教材や問題集の費用も考慮する必要があります。
不動産鑑定士の資格勉強にかかる費用
不動産鑑定士になるために、指定された学校や学科に通う必要はなく、学歴問わず試験を受けることができます。
独学でも合格可能ですが、試験難易度の高さから大学・専門学校・通信学校に通い、集中的に勉強する人が多いようです。
不動産鑑定士の資格勉強にかかる費用をそれぞれ解説します。
大学・短大の場合
不動産鑑定士を目指せる大学・短大の費用は、1年間でおおよそ120万~170万が相場になります。
不動産鑑定士試験は、民法、経済学、会計学などが出題されるため、法学系や経済学部系に入学するといいでしょう。
ただし、学校で教わるレベルと不動産鑑定士試験で求められるレベルには差があるので、講義以外での勉強は必須です。
専門学校の場合
専門学校・予備校の費用は、1年間でおおよそ30~50万円が相場になります。
大学は4年間で学んでいきますが、専門学校になると1~3年と短期集中で授業を行っていきます。
資格取得に関するサポートは万全なので、お金を少し多く払ってでもすぐに合格したいといった人に合っていると言えます。
通信学校の場合
初心者向けのコースや学習者向けなど受講コースによって差がありますが、1年間でおおよそ30~100万が相場になります。
また、参考書なども別途取り揃える必要がありますが、専門書籍1冊あたり3000円以上します。
不動産鑑定士試験に向けて最後の追い込みで通う大学生や、働きながら資格勉強したい社会人など環境に合わせて学べる点があります。
不動産鑑定士の通信学校での資格取得

不動産鑑定士の通信学校での資格取得ですが、結論から言うと可能です。
学生で受験に専念できる人や忙しい社会人の人などさまざまな環境に合わせて利用できるのが最大のメリットです。
通信学校の学習方法は、ライブ講義・ビデオ学習・通信教育の3つあり、それぞれ自身の環境に合わせて学習形式を選択することができます。
ライブ講義
ライブ学習は、講師の講義をライブで受講して、答練・模試など決まった時間に受けるものです。
ライブで講義を行うため、時間の融通が利かないですが、臨場感があり学習効果が高いのが特徴です。
ビデオ学習
ビデオ学習は、通信学校の専門ブースに入ってビデオを見ながら学習することです。
通学時間が取られますが、時間の融通が利き、静かな環境で集中して学習できることが特徴です。
通信教育
通信教育は、自分の好きな場所で好きな時に学習することができます。
DVDを持ち歩かなくても、スマホやタブレットでいつでもどこでも学習できることが特徴です。
不動産鑑定士の通信学校の比較
不動産鑑定士を資格取得するための通信学校は「LEC」と「TAC」があります。
通信講座を大きく分けると「初心者向け」と「学習向け」があり、金額やサポート内容が変わってきます。
「LEC」と「TAC」の通信学校の中でもコースが分かれているのでそれぞれ違いを比較していきます。
| – | EC(東京リーガルマインド) | 資格の学校TAC |
|---|---|---|
| 学習スタイル | 通信講座 | 通信講座 |
| 初心者向けコース | 【短答特化型】 (費用:114,000円) まずは短答の合格を目指す方向け 【短答+論文フルコース】 (費用:383,000円) 学生・受験に専念できる方向け 【短答+論文基礎コース】 (費用:305,000円) 社会人で時間調整が利く方向 |
【1.5年L本科生】 (費用:455,000円) 忙しい社会人の方向け 【1年本科生】 (費用:455,000円) 社会人で時間調整が利く方向け 【10ヵ月本科生】 (費用:455,000円) 短期集中して専念できる方向け |
| 学習者向けコース | 【論文本科生】 (費用:419,000円) 【論文本科生B】 (費用:377,000円) 論文試験を初めて受ける方向け |
【論文合格コース】 (費用:312,000円) 論文試験を初めて受ける方向け |
| 分割支払い | 可能 | 可能(月々5,000円以上36回まで) |
| 受講料割引 | あり(早期割引) | あり (宅建受験経験者割引) |
| サポートの特徴 | ・WEBフォローとDVDフォローがある ・質問は無限にできる ・親切丁寧な添削 ・成績がWEBで確認できる ・受講料の割引幅が大きい ・資格合格後にお祝い金有り |
・通信でも教室講座が受講可能 ・いつでも始められる ・板書の講義録がもらえる ・WEB動画、音声がある ・高速再生機能付き ・自習室が使える |
「TAC」と「LEC」はどちらも初心者向けと学習向けの通信講座があります。
教材については、どちらも合格実績のある通信学校なので大きな違いはありません。
ただ大きく違うのは、サポート内容と金額です。
不動産鑑定士の通信学校を選ぶ基準ですが、サポート重視なら「TAC」で、金額重視なら「LEC」になります。
不動産鑑定士とは

不動産鑑定士とは、公認会計士試験と並んで3大国家試験の1つです。
不動産鑑定士は、地域の経済・交通の環境面や土地や建物に関する法律面を考慮して「不動産の有効利用」を判定し、「適正地価」を判断します。
つまり、不動産の価値だけでなく不動産の適正な利用についての専門家でもあります。
不動産鑑定士の仕事
不動産鑑定士は、不動産のエキスパートとしてさまざまな分野で活躍しています。
不動産鑑定士の仕事は、国や都道府県が土地の適正な価値を一般に公表するための、地価公示や地価調査の制度をはじめとした不動産鑑定業務があります。
また、個人や法人に対して不動産の有効活用、開発計画の策定をはじめとした不動産に関するアドバイスを行うコンサルティング業務があります。
不動産鑑定士が活躍する分野は広く、金融機関や保険会社、商社、鉄道会社などビジネスフィールドは、無限大に広げることが可能です。
不動産鑑定士になるには
不動産鑑定士になるには、国家試験(不動産鑑定士試)に合格しなければいけません。
短答式試験は、合格率は例年25%前後で、論文式試験の合格率は、例年10%前後で推移しています。
不動産検定試験は、民法や経済、会計知識が必要になり、試験後合格後には、実務研修を受講することが義務付けられています。
「講義」「基本演習」「実地演習」の3単元を取得後に受けられる修了考査に合格してはじめて、不動産鑑定士となります。
実務修習の修了考査は、実務修習をきちんとこなしていれば難しくありません。
実務修習の修了考査の例年の合格率は90%程度になるので、よほどのことがない限り合格できるでしょう。
不動産鑑定士のキャリアパス
不動産鑑定士のキャリアパスには以下のものが挙げられます。
独立開業
不動産鑑定士の中には、独立して開業するケースが多いといわれています。
独立することで、自身のペースで業務を進めることが可能となります。
在宅勤務も選択でき、自由度が高く、スケジュールの管理も自分自身で行えるため、ライフスタイルに応じた働き方が実現できます。
平均年収は400万円から数千万円以上に達することもあるといわれています。
ただし独立不動産鑑定士は成功すれば高い収入を得ることができますが、クライアントを獲得するためには営業活動やマーケティングが不可欠です。
また、独立開業にはリスクが伴うため、十分な計画と実務経験、スキルが求められます。
企業内鑑定士
不動産鑑定士として企業に就職することにより、安定した収入と充実した福利厚生を享受することができるメリットがあります。
企業内の不動産鑑定士は、不動産鑑定会社の社員や投資会社の不動産投資部門で業務を行うほか、金融機関や信託銀行において取引先からの依頼に基づく不動産鑑定評価や金融業務全般に関わる仕事もあり多岐にわたります。
年収はおおよそ600万円から1,000万円とされており、コンサルティング業界では700万円から1,500万円、金融業界では600万円から1,300万円程度が一般的な水準とされています。
企業での経験は、チームワークやプロジェクト管理のスキルを向上させるための貴重な機会となります。
キャリアの初期段階で豊富な実務経験を積むことができ、将来的なキャリアの向上にも寄与します。
公的機関への就職
不動産鑑定士は地方自治体や国土交通省などにおいて、不動産関連の公共事業や都市計画に携わる業務を行うこともあります。
公的機関での就職は、安定した職場環境と社会への貢献を実感できるキャリアの選択肢といえます。
公的機関の魅力は、定時勤務や充実した福利厚生にあり、長期的なキャリアの構築が可能となります。
公共の利益を考慮した評価や提言を行うため、高い倫理観が求められます。
不動産鑑定士になるための費用と通信学校での資格取得|まとめ
いかがでしたでしょうか。
不動産鑑定士になるための費用と通信学校での資格取得について解説させていただきました。
学生で受験に専念したい人や忙しい社会人の人でも、年間30万以上の費用で通信学校で資格取得は可能です。
不動産鑑定士の資格取得を目指して、資格学校を活用してみてはいかがでしょうか。