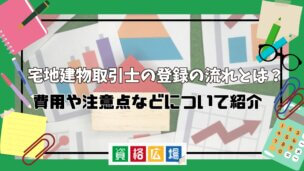宅建士は不動産業界の専門知識を持ち独占業務ができる人として、国家資格の中でも人気の資格として挙げられます。
しかしなかには、「宅建士はやめとけ」といった声も見受けられます。
宅建士の資格は取得まで時間がかかるものの、努力次第では十分合格できる資格です。
そこで今回は宅建士の取得をやめとけといわれる理由や取得するメリットについて紹介します。
宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。
宅建の取得はやめとけと言われる理由

ここでは、宅建の取得はやめとけと言われる理由について紹介します。
難易度が高く、取得まで時間がかかる
宅地建物取引士試験は、例年の合格率が15%~17%と国家資格の中では比較的易しいものの、合格するためには300〜400時間程度(犯として小戸)の学習が必要だとされています。
独学でも合格する人はいるものの、通信講座やスクールに通うなど金銭的にも時間的にもかかります。
また不動産業界で働く際にすべての業務に宅建資格が必須とされるわけではないため、わざわざ宅建の資格を目指す人は少ないと考える人も中にはいます。
不動産業界以外でアピールできないイメージがある
宅建士は不動産取引に特化した専門家であることから不動産業界以外ではあまり役立たないと見なされることが多いです。
したがって、よほど不動産業界で働きたいと考えている方以外だとわざわざ取得する必要がないと捉えるのです。
しかし実際には、宅建士の知識は金融、建設、保険、士業、公務員などさまざまな業界で活かせます。
たとえば、金融業界においては不動産担保ローンの審査や管理、不動産投資に関する業務があり、保険業界では不動産関連の保険商品の販売が例として挙げられます。
さらに、行政書士や司法書士として働く方の中には、不動産登記や相続、許認可手続きに必要な専門的な知識を得るために宅建士の資格をダブルライセンスとして取得するケースもあります。
以上のことから宅建の資格はイメージとは異なり、現実ではあらゆる可能性を秘めた資格だといえます。
資格を持っているより実力重視だから
不動産業界では資格の有無よりも営業成績が重視される傾向があることから、宅建を持っていても意味がないのではと考える人も多くいます。
しかし、多くの企業では資格手当が支給されており、宅建士の資格を持っていることで持っていない人よりもアドバンテージを得られるメリットがあります。
また専門家としての地位を確立することで、顧客からの信頼を得られる点も魅力です。
宅建士の資格を取得することは、実力向上のための重要なステップとなります。
資格取得と実力向上の両方を目指すことで、不動産業界での活躍が一層高まるでしょう。
本当にやめたほうがいい?宅建を取得するメリット

宅建は辞めとけと言われる理由について紹介してきましたが、本当に取得しないほうが良いのでしょうか?
そこでここでは、宅建を取得するメリットについて紹介します。
努力次第では十分取得できる資格
宅建の資格は学歴などの受験資格は特に定められていないため、充分な学習時間を確保すれば努力次第で十分取得できる資格です。
宅建試験に合格するためには一般的に約300〜400時間の学習が必要とされています。
同じ国家資格である司法試験に合格するためには3,000〜8,000時間、司法書士資格を取得するには3,000時間の学習が求められます。
上記の時間と比較すると、宅建資格はの学習時間で取得できるといえるでしょう。
しかし、宅建は決してだれでも簡単に取得できる資格ではなく、十分な準備と計画が不可欠です。
独学でも取得できる人もいますが、確実に合格したい方やスケジュールを立てるのが苦手な方は通信講座やスクールに通うのがおすすめです。
宅建士ならではの独占業務がある
不動産業界には有資格者のみが行うことができる以下の独占業務を担当できるメリットがあります。
- 重要事項の説明
- 重要事項説明書(35条書面)への記名押印
- 契約書(37条書面)への記名押印
上記の業務は宅建士にのみ許可されており、社会保険労務士や弁護士などの他の専門資格を持つ人には対応できないことから宅建士の需要は高いと言えます。
また不動産業界では賃貸や売買に関わらず、必ず1名以上の宅建士が企業に在籍することが求められています。
資格を持っていれば性別に関係なく、ライフスタイルに変化がある女性でも復職しやすいメリットがあります。
独占業務以外にも営業や商談、物件紹介など多岐にわたる業務を行いますが、重要な独占業務を任されることは大きなやりがいにつながるでしょう。
不動産業界の離職率は実は高くない
先にも述べたように不動産業界に対しては営業職を中心に「ノルマが厳しそう」といった印象を持つ方も少なくありません。
しかし、実際のデータを見てみると実はそこまで離職率が高くないといったデータがあります。
厚生労働省が発表したデータによれば、産業別の離職率は全体で15.4%です。
一方不動産業・物品賃貸業の離職率は16.3%で、全体の数値をわずかに上回っていますが平均的だといえます。
また宅地建物取引士の資格は不動産取引を行う際に金融業界でも重宝される資格です。
金融業・保険業の離職率は10.5%と非常に低い数値を示しており、宅建資格が有効とされる不動産業界や金融業界は必ずしも離職率が高いわけではなく、イメージほど厳しい業界ではないと考えられます。
年収アップにつながる
宅建士の資格を取得することで資格手当を通じて収入アップにつながるメリットがあります。
資格手当とは企業が基本給とは別に支給する特別な手当の一種であり、特定の資格をもつ場合や特定の資格試験に合格した際に支給されます。
資格手当の有無やその金額は企業によって異なるものの、宅建士の資格を持つことで一般的に1万〜3万円程度の手当が支給されることが多いです。
特に不動産業界では不動産取引を行う企業において宅建士の需要が高く、より高額な宅建手当が設定される傾向があります。
さらに、不動産業界では歩合制を採用している企業が多く、成果に応じて給与が決まる実力主義のため学歴や年齢に関係なく高収入を目指すことができるでしょう。
就職・転職で役立つ
宅建士の資格を取得することは就職や転職で役立つといったメリットがあります。
不動産業界では宅建業法により、従業員の5人に1人以上が専任の宅建士でなければならないと定められています。
もし宅建士が退職するなどして必要な人数を下回った場合、2週間以内に新たな宅建士を補充しなければいけません。
また実際には学歴よりも宅建士資格を重視する企業も多くあります。
宅建士の資格は不動産業界に限らず、金融業界や建設業界、保険業界などでも活用することができます。
宅建士の資格は定期的な更新や登録が必要ですが、一度取得すれば永続的に利用できる国家資格です。
専門的なスキルを身につけたい方や他の応募者と差別化を図りたい方は、ぜひ挑戦してみることをおすすめします。
顧客からの信頼獲得につながる
宅建士の資格を取得することで顧客からの信頼を獲得しやすいメリットがあります。
なぜなら宅建は世間的な認知度が高く、不動産取引における専門家として確かな知識があることをアピールができるからです。
宅建士試験は毎年約20万人が受験する試験であり、その受験者数の多さはこの資格の認知度の高さを示しています。
就職のしやすさや資格手当、顧客獲得にもつながるので不動産業界で働きたい方はぜひ取得しておくことをおすすめします。
副業の幅が広がる
宅建士の資格を取得することで副業の幅が広がるメリットもあります。
具体的には、週末に宅建士としての業務を代行したり、宅建士試験の講師を務めたりすることが考えられます。
ほかにも不動産関連のメディアでライターとして記事を執筆したり、YouTubeを利用して副業を始める方も実際にいます。
副業での活動は在宅で行えることが多く、自分のライフスタイルに合わせて働くことができるのも魅力です。
副業から得た収入は旅行や趣味に使ったり、将来のために貯蓄したりと、自由に活用することができます。
宅建士の知識を活かした副業を行うことで収入アップだけではなく、スキルアップにもつながります。
独立・開業にも挑戦できる
宅建士の資格を取得し、必要なスキルや経験を積むことで、独立して事業を展開することができるようになります。
独立開業には人脈の形成、事業計画の策定、資金調達、事務所の確保などが求められますが、リターンも大きく年収1000万円以上を目指すこともできます。
また、独立開業はワークライフバランスを重視し、自分のペースで働くことができるため、会社の方針に縛られることなく、自らの裁量で業務を進めることができる点も魅力です。
サラリーマンとして安定した職を選ぶか、独立開業によって自由を手に入れるかは人それぞれですが選択肢が増えるのはメリットだと言えるでしょう。
宅建を取得するメリットはある?デメリットや活かせる業界について紹介
宅建の資格取得時の注意点
ここでは、宅建の資格取得時に注意しておくべきポイントについて紹介します。
試験合格だけだと宅建士になれない
宅建士として実際に業務をおこなうには宅建の試験に合格するだけでは不十分であり、以下のいずれかの条件を満たし宅建士証を交付してもらう必要があります。
- 2年以上の実務経験
- 登録実務講習の受講
実務経験はお客様への説明業務や物件の調査など、具体的な宅建士の業務内容でなければならず、不動産屋の事務所で3年間働いていたとしても事務や経理のみのお仕事だった場合は認められないので注意が必要です。
登録実務講習は各地の資格スクール等で開催されているもので、講習を実施している場所によって費用に若干の変動はありますが、おおよそ12,000~20,000円程度かかるといわれています。
宅建の試験は独学だと難しい
宅建士試験は通年20万院程度が受験する人気の試験ですが、法律系資格としての出題範囲は非常に広く決して易しいものではありません。
宅建士の試験の合格率は例年15%~18%で推移しており、約6人に一人の難関資格であることがわかります。
また上記の割合はあくまで受験指導校を利用している受験者も含めた全体の合格率であるため、独学者に限るとその割合はさらに低下することが予想されます。
独学で合格を目指すならもともと法律の知識がある方や最新の情報を収集する力、よほど自身のモチベーションを維持できる人でないと難しいでしょう。
経済的な負担はかかるものの、一般的には独学だと難しいので通信講座もしくはスクールに通うことをおすすめします。
宅建士は高卒でもなれる?取得するメリットや勉強方法について紹介
宅建の試験について

ここでは、宅建の試験について基本的な概要についてご紹介します。
| 受験資格 | なし |
|---|---|
| 試験日 | 例年10月の第3日曜日 ※2025年は10月19日予定 |
| 受験料 | 8,200円 |
| 試験形式 | 4肢択一のマークシート形式、全50問、相対評価試験 |
| 試験時間 | 2時間 |
| 試験科目 | 「民法等」「宅建業法」「法令上の制限」「その他関連知識」の4科目 |
宅建士の例年の合格率は15〜17%程度であり、国家資格の中では易しいものであるものの相当な学習が必要です。
合格率の低さの理由として、宅建士試験が相対評価方式で実施されていることや明確な合格基準が設けられていないことが挙げられます。
ちなみに、過去5年の宅建の合格率をまとめると以下の通りとなります。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 241,436 | 44,992 | 18.6% |
| 令和5年度 | 233,276 | 40,025 | 17.2% |
| 令和4年度 | 226,048 | 38,525 | 17.0% |
| 令和3年度 | 234,714 | 41,471 | 17.7% |
| 令和2年度 | 204,250 | 34,338 | 16.8% |
宅建試験に合格するために必要な学習時間の目安は通常200時間~300時間程度とされています。
一般的な学習期間は約半年であり、実際仕事をしながら資格取得を目指す方もたくさんいます。
宅建士の資格は需要が高い
宅建士は資格取得の難易度が高い、不動産業界は競争が激しく就職後も労働条件も厳しいイメージがあるなどの理由で辞めた方が良いといった声が多いことがわかりました。
しかし実際はイメージよりも離職率は低かったり、資格手当が付くなどもメリットも多くあります。
宅建士は取得すれば専門知識が身につくだけなく独占業務を任せてもらえたり、独立に役立つので不動産業界や金融などで働きたい方にはおすすめです。
また宅建士試験は、正しい勉強方法で計画的に進めていくことができれば十分合格できる試験です。
今回の記事を参考に宅建士資格にチャレンジしてみてください。
宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。