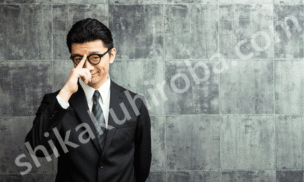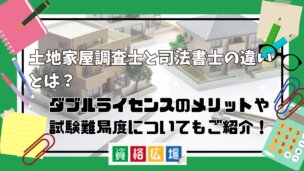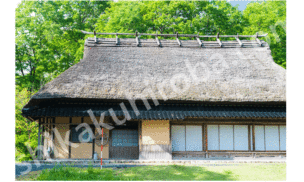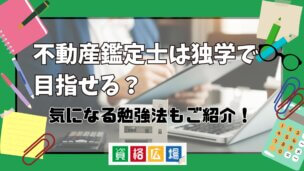不動産取引の専門家である宅建士。
宅建士になるには宅建の試験を受けて通り、資格登録をしなければ業務ができません。
宅建は学歴や実務経験、年齢による受験資格の制限がなく誰でも受験ができます。
しかし、資格登録を行う際はいくつかの条件を満たさなければ宅建士として働けないので注意が必要です。
そこで今回は宅建の試験や宅建士に慣れないケースについて紹介します。
宅建士おすすめ通信講座・予備校10選!予備校の特徴と費用紹介
宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。
宅建試験の受験資格に制限はない

先にも述べたように、宅建は学歴や実務経験、年齢による受験資格がなく誰でも受験できる試験です。
ここでは、それぞれの受験資格について詳しく見ていきます。
年齢
宅地建物取引士の試験には年齢制限がなく、子どもから高齢者まで幅広い年齢層の方が受験することができます。
実際令和5年度(2023年度)の試験では、10歳の男の子が合格し、最年少合格者として記録されたこともあります。
また、高齢者の例としては79歳で宅建を取得し、80歳で独立開業して成功を収めた女性がメディアに取り上げられたこともありました。
ちなみに令和6年度(2024年度)の宅建試験における合格者の平均年齢は35.9歳であり、性別ごとの平均年齢は男性が36.2歳、女性が35.4歳となっています。
参考:不動産適性取引推進機構「宅地建物取引士資格試験の結果 について」
学歴
宅建には学歴による受験制限はありません。
かつて宅建試験は昭和40年から平成7年までは「高等学校卒業以上」という学歴に基づく受験資格の制限がありましたが、平成8年以降はその制限が撤廃されたことで中卒でも受験できるようになりました。
先にも述べたように、実際令和5年度(2023年度)の試験では、10歳の男の子が合格し、最年少合格者として記録されたこともあります。
実務経験
国家資格の中には受験資格として実務経験を必要とするものもありますが、宅建の受験資格については実務経験の有無は問われません。
平成7年までは宅建も「2年以上の実務経験」が受験資格として求められていましたが、この要件は撤廃され、現在では実務経験は必要なくなりました。
不動産業界での経験がない方でも受験ができるので、合格すれば資格を取得することができます。
ちなみに実務経験が関係するのは、試験に合格した後の資格登録の段階となるので実際に宅建士として働く方は注意が必要です。
国籍
宅地建物取引士(宅建)は日本における国家資格であり、国籍に関する制限はありません。
したがって、日本国籍を有しない外国人も受験することができ、合格すれば宅建士として登録し、実際に業務を行うことができます。
ただし受験申し込み時に氏名を記入する際は注意が必要です。
住民票に記載されている氏名と異なる場合、合格後の資格登録に支障が出るおそれがあります。
申し込みの際には、住民票に記載された氏名(ローマ字、漢字、通称名のいずれか)を使うのが無難でしょう。
宅建試験を受験できないケースはある?
先にも述べたように、宅建試験には特定の受験資格は設けられていません。
ただし、過去にカンニングなどの不正行為を行った受験者は、最長で3年間受験を禁止されるため注意が必要です。
不正行為を行った者は受験の公正性を損なうため、受験機会を失うのはやむを得ません。
また、試験に遅刻した場合も原則として受験は認められません。
宅建試験は例年13時から15時までの120分間おこなわれますが、13時30分を過ぎると入室ができず、受験そのものができなくなってしまいます。
受験当日の際は時間に十分注意を払い、時間に余裕をもって行動することをおすすめします。
宅建士の難易度や合格率は高い?合格に向けたおすすめの勉強法も徹底解説
宅建に受験資格はないが資格登録には制限がある
宅建の試験自体には受験資格がありませんが、資格登録には制限があるため注意が必要です。
宅建士の資格登録には以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 宅建士資格試験に合格している
- 実務経験2年以上
- 登録の欠落事由に該当しない
実務経験が2年以上必要とされる面と見ると、「実務経験がないのに受験できるのに、資格登録はできないのか?」と驚かれる方もいるでしょう。
しかし、実務経験がない方でも「登録実務講習」を受講し、修了することで同等の要件を満たすことができます。
登録実務講習とはまず通信講座を受講し、その後1〜2日間のスクーリングを通じて不動産業の実務を学ぶものとなっています。
スクーリングの最終段階で行われる修了試験に合格すると、登録実務講習の修了証が授与されます。
さらに、宅建業者で2年以上勤務していて、業務が事務や受付など実際の取引に関連しない場合は、宅建の実務経験としては認められないので注意が必要です。
欠格事由となる例
資格登録する上では実務経験だけではなく、以下の登録の欠落事由に該当する人は登録ができません。
欠格事由とは宅地建物取引業法第5条において規定されている「宅建業の免許を取得できない理由」のことを指します。
不動産取引は高額な資産を扱うため、過去に不正行為や重大な犯罪歴を有する者が営業を行うことは消費者の保護や公正な市場の形成に悪影響を及ぼす可能性があるとされ制定されています。
- 成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者
- 免許を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者
- 免許取消処分前に廃業し、廃業届から5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などに
- より刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などに
- より刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 免許申請前5年以内に、宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした者
- 宅建業に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
- 事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人の申請により登録の消除がなされ、まだ禁止期間が満了していない者
- 宅建業の営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
参考:建設産業・不動産業:宅地建物取引の免許について – 国土交通省
財産に関する問題がある場合、宅地建物取引士の資格を取得することはできません。
裁判所から破産手続開始の決定を受けた人を対象としており、「復権」を得ていない人は宅建の資格登録が認められません。
復権とは、破産手続開始決定によって失われた法的資格を回復することを指します。
しかし、破産者であっても試験を受けることはでき、試験に合格した場合は資格の有効期限がありません。
したがって、自己破産後に試験に合格し、復権後に資格登録を行うことができます。
また精神的な機能に障害があり、判断能力に問題がある場合も、宅建士になることはできません。
具体的には、成年被後見人や被保佐人があてはまりますが、一律に欠落事由になるわけではなく個別に審査されることになります。
さらに宅建の資格登録における成年者は、2022年4月1日に20歳から18歳に引き下げられました。現在は18歳になれば資格登録ができます。
一見さまざまな条件があると見えがちですが、主に未成年、免許取り消し処分になった人、不正や犯罪を犯して5年を経過していない人などが当てはまると覚えておくといいでしょう。
宅建試験について

宅建の試験に関するスケジュールをまとめると以下の通りとなり、計画的な学習が求められます。
- 6月:官報公告
- 7月:試験案内の配布・申し込み受付開始
- 8月:試験日の通知
- 9月:受験票発送
- 10月:宅建試験日
- 11月:合格発表
宅建の試験は年に1回、例年10月の第3日曜日に全国で開催されています。
| 受験料 | 8,200円 |
|---|---|
| 試験形式 | 4肢択一のマークシート形式、全50問、相対評価試験 |
| 試験時間 | 2時間 |
| 試験科目 | 「民法等」「宅建業法」「法令上の制限」「その他関連知識」の4科目 |
申し込みの方法にはインターネット申し込みと郵送申し込みの2種類があります。
インターネット申し込みは、7月の上旬から中旬にかけての期間に行うことができ、原則として24時間いつでも提出できるのが特徴です。
一方、郵送申し込みは、7月の上旬から下旬までが受付期間となるので余裕をもって応募することが大事です。
宅建に独学で合格は可能?きつい?ゼロからできる効率の良い勉強法を紹介
宅建の合格率・難易度
宅建の合格率は例年15%~17%程度となっています。
司法試験などほかの国家資格に比べると難易度は低いですが、充分な対策が必要です。
過去10年分の合格率をまとめると以下の通りとなります。
| 年 | 申込者数 | 受験者数 | 受験率 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年 | 258,511人 | 209,354人 | 80.98% | 32,644人 | 15.59% | 35点 |
| 平成30年 | 265,444人 | 213,993人 | 80.62% | 33,360人 | 15.59% | 37点 |
| 令和01年 | 276,019人 | 220,797人 | 79.99% | 37,481人 | 16.98% | 35点 |
| 令和02年10月 | 204,163人 | 168,989人 | 82.77% | 29,728人 | 17.59% | 38点 |
| 令和02年12月 | 055,121人 | 035,258人 | 63.96% | 04,609人 | 13.07% | 36点 |
| 令和03年10月 | 256,704人 | 209,749人 | 81.71% | 37,579人 | 17.92% | 34点 |
| 令和03年12月 | 039,814人 | 024,965人 | 62.70% | 03,892人 | 15.59% | 34点 |
| 令和04年 | 283,856人 | 226,048人 | 79.63% | 38,525人 | 17.04% | 36点 |
| 令和05年 | 289,096人 | 233,276人 | 80.69% | 40,025人 | 17.16% | 36点 |
| 令和06年 | 301,336人 | 241,436人 | 80.12% | 44,992人 | 18.64% | 37点 |
宅建試験に合格するために必要な学習時間の目安は通常200時間から300時間程度とされています。
一般的な学習期間は約半年であり、仕事をしながら資格取得を目指す方もたくさんいます。
半年で合格を目指す場合、1週間で12時間程度の学習時間があれば到達できるでしょう。
宅建は独学でも合格するひとはいますが、ひとりでの学習に自信がない方やより効率的に学習を進めたい方であれば通信講座の利用がおすすめです。
宅建士とは

宅建士とは「宅地建物取引士」の略称であり、宅地建物取引業法に基づいて業務を行う不動産取引の専門家のことです。
国家資格であり、毎年約20万人が受験する人気のある資格のひとつとして挙げられます。
先にも述べたように宅建の試験に特別な受験資格はなく、日本国内に居住する方であれば、年齢や学歴に関係なく誰でも受験できます。
宅建士は主に宅地建物取引業者(不動産会社)において、土地や建物の売買や賃貸物件の仲介業務に従事します。
不動産の売買や賃貸は高額な取引であるため、知識が不足した状態で契約を結ぶと予期しないトラブルが発生することも少なくありません。
宅建士はトラブルを未然に防ぐだけでなく、顧客が事前に理解しておくべき重要事項を説明することが宅建士の重要な役割となっています。
また、宅建業者は従業員5名につき1名以上の宅建士を配置する義務があるため、宅建士は需要の高い職業であると言えます。
宅建士の年収はいくら?給料の相場や年収アップのポイントを解説
宅建士対策するならアガルートがおすすめ

受験資格が定められていないからこそ、実際に不動産業で働いたことのある予備知識がある人も、そうでない人も受験しに来ますし、試験勉強の環境が整った人も居れば独学な人も居ます。
宅建士を名乗れるようになるための第一歩が宅建試験合格となりますが、宅建試験合格者はさらに先の道のりを超えないと宅建業務に携わることはできません。
試験に関してはサックリと合格したい所なので、通信講座のアガルートアカデミーを利用しましょう!
アガルート通信講座は宅建士試験を初めとした難関国家資格を専門に扱う通信講座となっています。
アガルート通信講座は高い合格実績や豊富なカリキュラムが存在し、効率的に宅建士試験の対策を行うことができます。
宅建士試験の受験資格は不要
今回は宅建の試験や宅建士に慣れないケースについて紹介してきました。
宅建は年齢や学歴、実務経験、国籍といった受験資格に制限がありません。
しかし実際に宅建士を名乗れるようになるまでには、2年間実務経験や宅建登録実務講習を受ける必要があります。
宅建は、法律系・不動産系国家資格の中では難易度がそれほど高くない資格で、働きながら、半年ほどの勉強期間で合格を目指せます。
宅建は取得すれば不動産取引のプロとしてキャリアアップを狙えるでしょう。
今回の記事を参考に宅建士試験にチャレンジしてみてください。