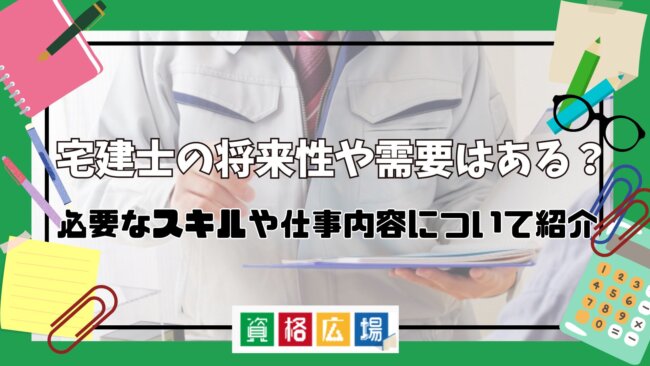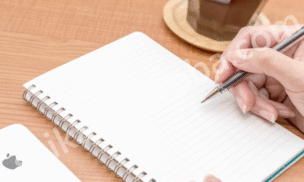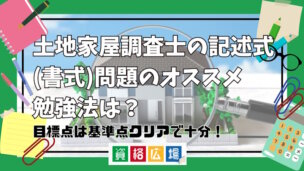不動産の紹介や内覧、契約書の作成などを行う宅建士の仕事。
一部では、宅建士の仕事はAIの発展や人口減少により宅建士の需要が減っているのではないかといった声も上がっています。
しかし宅建士の仕事に将来性はあります。
今回は宅建士の将来性や需要がある理由や長く活躍するために必要なスキルについて紹介します。
宅建士の仕事に将来性がある理由

ここでは、宅建士の仕事に将来性がある理由についていくつかご紹介します。
宅建士にしかできない独占業務がある
宅建士の仕事に将来性がある理由のひとつとして、宅建士にしかできない独占業務があることが挙げられます。
独占業務とは資格を持っている人しかできない業務のことであり、具体的には「重要事項説明」「重要事項説明書面への記名・押印」「契約書への記名・押印」が含まれます。
不動産取引においては、売買や賃貸に関わらず「契約」が行われます。物件の所在地や面積、支払い条件やキャンセルに関する取り決めなど、さまざまな情報が文書に記載されます。
不動産契約には難解な法律用語が多く含まれるため、書面を交付することで後日不明点が生じた際に再確認できるだけでなく、説明を行った証拠にもなります。
これらの仕事は国家資格である宅建士の資格を持っている人でないとできません。
また、宅建士には不動産業者における設置義務があります。
設置義務は不動産を扱う宅建業者に課せられた責任であり、宅地建物取引業者は従業員の5人に1人以上の宅建士を配置しなければならないという規定(宅地建物取引業法)のことです。
規模が大きい職場であれば一定数の宅建士を雇用する必要があり、不動産業がなくならない限り、宅建士の職務は消失しないと考えられます。
実際大手不動産会社の中には、全ての営業職に宅建士資格の取得を求めるところもあるといわれています。
AIに代替されにくい仕事である
宅建士の仕事には不動産取引における重要事項の説明や契約書への署名などが挙げられます。
上記の仕事は不動産の賃貸や売買に関わらず必須であり、先にも述べたように宅建業法に基づき宅建士のみが行うことができる独占的な業務です。
AIは書類作成などの不動産業務に関しては支援できるものの、重要事項の説明など宅建士の専門的な業務を代行することはできません。
宅建士の職務にはAIが担えない部分が多く、今後も宅建士の需要が高まると思われます。
また不動産営業では顧客との対話を通じて細やかなニーズを把握し、信頼関係を築くことが重要です。
たとえAIで具体的で客観的な購入希望条件があったとしても、顧客の感情やこだわり、さらにはその時の気分によって、希望する物件が変わることも少なくありません。
やはり直接的な会話を通じてしか得られない情報や提案もあるため、宅建士の仕事はこれからもAIには奪われにくいと考えられます。
現状、AIが代替可能な領域は発展したとしてもデータ分析や書類作成、誤りのチェックなどの事務的な作業に集中しているといわれています。
不動産業界そのものの需要が下がりづらい
不動産の需要がそもそも低下しにくい業界であるという点もまた、宅建士の将来性がある理由として挙げられます。
生活を営む上で「家」は不可欠なものです。
今後よほどの大規模な人口減少がない限り、不動産の需要は減少しにくいと考えられます。
日本はすでに人口減少の時代に突入しているといわれていますが、不動産取引は依然として活発に行われています。
とくに都心回帰の傾向が続く一方で、リモートワークの普及に伴い地方回帰の動きも見られています。
不動産取引は本質的に高額であり、時代の変化に伴いニーズなどが変化する業界でもあります。
以上のことから安、不動産の専門家である宅建士は安全な取引をするために今後も重要な役割を果たし続けるといえるでしょう。
宅建士の知識を活かせる新しい分野が生まれている
近年、リバースモーゲージという金融商品が注目を集めており、今後その取り扱い件数が増加することが見込まれています。
リバースモーゲージとは高齢者が所有する住宅や土地などの不動産を担保として銀行から融資を受け、居住者が亡くなった際にその不動産を売却することで返済を行う仕組みのことを指します。
リバースモーゲージはおもに銀行などによって提供される商品ですが、不動産に対する担保設定や売買が関与するため不動産に関する知識が求められます。
不動産取引の専門家である宅建士の資格を持つことで、こうした金融商品についてより詳細に説明することができ、宅建士は不動産業界だけでなく、金融や保険業界からも高い需要があるとされています。
宅建士の知識を必要とする新たな金融商品が登場しており、今後も宅建士の需要は持続的に高まると考えられます。
宅建士の有効求人倍率は約3倍
厚生労働省の住宅・不動産営業の最新のデータによれば、全国の有効求人倍率は3.08倍となっています。
有効求人倍率とは求職者一人あたりの求人件数を示す指標であり、「就職のしやすさ」を測るための重要な数値のことです。
例えば、求職者が100人いる場合に求人が200件存在するならば、有効求人倍率は2倍となります。
約3倍ということは、1人当たり3件は求人がいつかるということですね、
一般的に人手不足の状況下で多くの企業が求人を積極的に行っている場合、有効求人倍率は1を超え、数値が高いほど就職しやすいことを示します。
反対に企業が求人をあまり出さない場合、有効求人倍率は1を下回り、数値が低いほど就職しにくい傾向が見られます。
特に不動産会社だと宅建士の資格を持っている人が欲しいと思っており、入社後に資格支援をおこなうところもあります。
宅建士として長く活躍するために必要なスキル・能力

宅建士の仕事には将来性はありますが、長く活躍するためにはスキルアップや努力は必要です。
そこでここでは、宅建士として長く活躍するために必要なスキルや能力についていくつかご紹介します。
営業スキルを身に付ける
宅建士として長く活躍するために必要なスキルの中で、最も重要視されるのは高い営業力です。
どの業界においても営業力は重要ですが、特に不動産業界においてはかなり求められるスキルだといえるでしょう。
ほとんどの不動産会社では売上に基づくインセンティブ制度が整備されており、販売実績が収入に直結する傾向にあります。
つまり優れた営業力を持つことで未経験者でも経験者に対抗でき、学歴がない人でも高学歴の人に勝つことができるということですね。
営業力を向上させるために知識を増やすことも大事ですが、コミュニケーション能力を向上させるための実践的な訓練を日々の業務から積むのもひとつです。
ダブルライセンスを取得する
不動産業界で競争を勝ち抜くためには、営業力に加えてダブルライセンスを取得するのもひとつです。
不動産に関連する資格は宅建士だけではなく、以下のよう資格の取得がおすすめです。
- 賃貸不動産経営管理士
- 管理業務主任者
- マンション管理士
- ファイナンシャルプランナー
- 住宅ローンアドバイザー
- 行政書士
- 不動産鑑定士
- 土地家屋調査士
上記の資格を取得することで、他の宅建士との差別化を図ることが出来るメリットがあります。
国土交通省が示す令和5年度のデータによれば、宅建士の登録者数は約118万人に達しています。
もし宅建の資格のみを持っている場合、あなたはその中の118万人の一人に過ぎません。
しかし、複数の資格を取得することでほかの宅建士との細別化が図れます。
宅建士としてのキャリアを持続させるために積極的にダブルライセンスの取得を目指してみてください。
土地家屋調査士の難易度は高い?他資格とのランキング比較や合格率・偏差値・勉強時間の目安について解説
宅建士の仕事内容とは

宅建士とは「宅地建物取引士」のを略したものであり、宅地建物取引業法に基づく業務を遂行する不動産取引の専門家を指します。
この資格は国家資格であり、毎年約20万人が受験する人気のある資格です。
特別な受験資格は設けられておらず、日本国内に居住する方であれば、年齢や学歴に関係なく誰でも受験できます。
宅建士は主に宅地建物取引業者(不動産会社)において、土地や建物の売買や賃貸物件の仲介業務に従事します。
不動産の売買や賃貸は高額な取引であるため、知識が不足した状態で契約を結ぶと、予期しないトラブルが発生することも少なくありません。
宅建士はトラブルを未然に防ぐだけではなく、顧客が事前に理解しておくべき重要事項を説明することが宅建士の重要な役割となっています。
また宅建業者は従業員5名につき1名以上の宅建士を配置する義務があるため、宅建士は需要の高い職業であると言えます。
宅建士の試験について
宅建士になるには宅建士の資格を取得する必要があります。
宅建士の試験についてまとめると以下の通りとなります。
| 試験日 | 10月の第3日曜日 |
| 受験料 | 8,200円 |
| 試験形式 |
|
| 試験科目 | 「民法等」「宅建業法」「法令上の制限」「その他関連知識」の4科目 |
宅建士の合格率は令和6年度の時点で18.6%となっています。
過去10年間にわたり15%~17%の範囲となっており、一般的に難易度の高い資格とされています。
合格基準は試験ごとに異なりますが、50点満点中31点から38点の範囲です。おおよそ75%の正答率があれば合格が期待できるでしょう。
また試験に合格した後に実際に宅建士として業務を行うには、受験した試験地の都道府県に登録する必要があります。
登録申請時に実務経験がない場合は、実務講習の受講が求められます。
宅建の資格取得までの道のりや流れとは?高卒でも宅建士になれる?
宅建士の平均年収
厚生労働省のデータによると、宅建士を含む住宅・不動産営業の平均年収は579.5万円となっています。
例えば、大企業に勤務する宅建士の年収は約600万円程度、中小企業では500万円前後が一般的とされています。
事務作業のみの場合、年収は約300万円から始まり、不動産全般の業務を行う場合は500万円程度まで上がることもあります。
また、宅建士の年収は地域によっても差が見られる傾向にあります。
宅建士の平均年収が最も高いのは東京都で約700万円となっており、地方では低くなる傾向があります。
宅建士として独立した場合、ホームページ制作や事務所の賃料など、初期の必要経費が発生しますが、実力のある人であれば年収が1,000万円を超えることもできます。
宅建士に将来性はある!宅建士の資格取得にチャレンジしよう
今回は宅建士の将来性や需要がある理由や長く活躍するために必要なスキルについて紹介してきました。
宅建士の仕事は専門性の高い国家資格であることや、宅建士にしかできない独占業務があることから今後も将来性があるといえます。
またAIにはできない仕事や苦手とする仕事ができる点、宅建士の知識が求められる新しい金融などの分野が生まれたことにより不動産業界以外での需要も高まっています。
しかし宅建士の資格をとったからといって油断してはいけません。
長く活躍するためには営業力やダブルライセンスの取得など、研鑽する姿勢が大事です。
今回の記事を参考に宅建士の資格取得にチャレンジしてみて下さい。