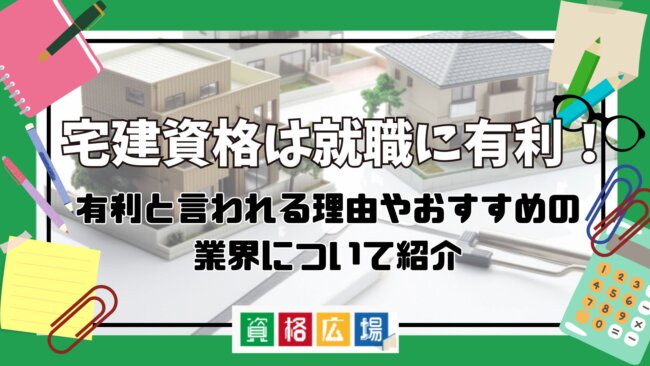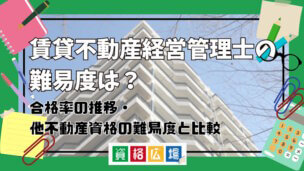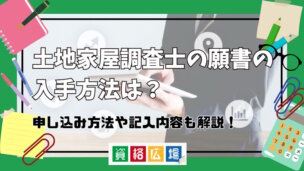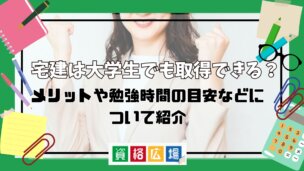難易度の高い資格のひとつとして、宅建が挙げられます。
実際、不動産業界などを目指す方は宅建の取得を目指す人も多くいます。
しかし実際、宅建の資格は就職や転職でどれくらい有利になるのでしょうか?
そこで今回は宅建資格を取得するメリットやおすすめの業界などについて紹介します。
宅建士おすすめ通信講座・予備校10選!予備校の特徴と費用紹介
宅建士の仕事とは

宅建士(宅地建物取引士)は不動産の紹介、内覧、契約書の作成および調印、重要事項の説明など、不動産取引に関連する幅広い業務を担当する専門職です。
土地や建物といった不動産は、取引金額が非常に大きく、また複数の法律が関与するため、一般の方が各物件の価値や条件を正確に理解することはできません。
したがって不動産の専門家である宅建士が、売主や買主に対して内容を明確に説明し、当事者間の契約を円滑に進めることで、不動産取引を全面的に支援します。
さらに宅建士は不動産取引をスムーズに行うだけでなく、取引に関する誤解やトラブルを未然に防ぐことによって私たちの重要な資産である不動産を守る役割を果たしています。
宅建士の独占業務
不動産取引において売買や賃貸を仲介する際には、売主と買主、または貸主と借主の双方に対して、契約書と重要事項説明書を交付することが法律で義務付けられています。
説明書には、対象となる不動産に関する法律や条件が記載されており、 契約書および重要事項説明書への署名・押印、並びに取引者への重要事項の説明は、宅地建物取引士しか対応できない独占業務にあたります。
したがって、宅建士がいなければ、不動産取引の根幹を成す契約業務を進めることは不可能です。
また宅建士は重要事項の説明は複雑な法律や権利関係が絡む不動産について内容を一般の人々が理解できるように、明確に説明する必要があります。
以上のような背景から、宅建士には不動産や法律に関する専門的な知識に加え、複雑な情報を正確に伝えるための高いプレゼンテーション能力が求められると言えるでしょう。
宅建士の資格が就職に有利と言われる理由
宅建士の資格は主に不動産業界や建設業界、金融業界などで有利になりやすいと言われています。
ここでは、宅建士の資格が有利と言われる理由について具体的に紹介します。
金融業界では宅建士の資格を持っている人が少ない
銀行や証券、リース企業において不動産関連の資格を有する人は非常に少なく、宅建士の資格保有者が重宝されやすい傾向にあります。
理由としては金融業界で働く人々が金融関連の資格取得に多くの時間を費やしているためです。
したがって宅建士の資格を取得することで、不動産取引に必要なリースやローンの業務に関与することができるなどほかの志望者と差別化ができるといえます。
また、金融業界の多くの人々は不動産に関する専門知識を持たず、不動産の価値の変動や将来的な見通しについてのみ理解しています。
宅建士の資格を持つことで、各種の建物や賃貸契約を迅速に理解し、金融商品の需要を的確に把握することができるメリットがあります。
不動産業界では設置が必須だから
各不動産業者は従業員5人に対して1人以上の宅建士を雇用する義務があることから、宅建士の資格は必須と言っても過言ではありません。
法令を遵守しない場合、各事業所は不動産取引を行うことができなくなります。
このため、宅建士の資格はすべての不動産事業所において必要とされており、設置義務と独占業務があるので今後も需要がなくなることはないでしょう。
特に新卒者にとっては、宅建士の資格を持っていることが就職活動において有利に働きます。
大手不動産企業への就職時に資格を取得しているとアピールポイントになります。
宅建士にしかできない独占業務がある
先にも述べたように宅建士には宅建士にしかできない独占業務があります。具体的には、重要事項の説明、重要事項説明書への記名、37条書面(契約書)への記名が挙げられます。
上記の3点は宅建士しかできない独占業務となっており、不動産業者は宅建士がいてはじめて不動産の購入や販売などの取引ができます。
そのため、宅建士は不動産業界にとって特に重要な地位を占めており、不動産業者は多くの宅建士を欲しています。不動産業界への就職を検討している方は、学生の時間のあるうちに取得しておくことでよりスムーズに業務に慣れることができるでしょう。
資格取得により努力できる人物だとアピールできる
宅地建物取引士の資格を取得することで、履歴書にその資格を記載することが可能です。
これは単に「宅建の資格を有している」というだけでなく、「資格取得に向けて努力を重ねることができる人物である」という点もアピールすることができます。
宅建士試験の合格率は毎年15%から17%程度と難易度が高めなので、取得した理由やエピソードなどにつなげやすいでしょう。
仕事においても自己研鑽や探求を続ける姿勢を示すことができ、採用担当者から高い評価を得ることが期待できるでしょう。
宅建士の資格を活かせるおすすめの業界

ここでは、宅建士の資格が活かせるおすすめの業界についていくつか紹介します。
金融業界
宅建士の資格を活かせる業界のひとつとして金融業界が挙げられます。
金融業界においては具体的に不動産担保ローンの審査や管理、不動産投資関連の業務において宅地建物取引士の知識が非常に役立ちます。
また宅地建物取引士は不動産の評価や法的制約に関する専門的な知識をもえいることから、顧客に対して適切なアドバイスができます。
人事評価において有利に働く可能性も高く、他の人よりも早く昇給や昇進する可能性も大いにあるでしょう。
銀行、信用金庫、証券会社など、さまざまな金融機関では宅地建物取引士の資格を持つ人材が求められています。
建設業界
建設業界においては不動産開発や建築プロジェクトに関連する業務において、宅建士の専門知識が重要な役割を果たします。
自社で不動産の売買を行っていない場合でも、営業活動などのビジネスシーンにおいて、法令や各種規制に関する知識が求められることは少なくありません。
宅建士の資格を持っていれば、顧客との交渉や契約の締結の場で信頼を得やすくなるというメリットがあります。
とくに最近では、建設会社が自ら不動産売買の部門を設立するケースが増えてきており、事業の拡大を目指す建設会社が宅建士を求める傾向も見られます。
保険業界
保険業界において火災保険や地震保険などの不動産関連商品を取り扱う際には、宅建士の専門知識が非常に役立ちます。
不動産の特性や価値、リスクを理解するためには、宅建士の知識が不可欠です。
そこで宅建士の資格取得で得た知識を活用することで、顧客に対して最適な保険商品を提案することが出来るようになります。
さらに、生命保険の営業においても、顧客のライフプラン作成を支援する際にも宅建士の知識は重宝します。
たとえばマイホームの購入や不動産投資に関する相談を受ける場合、宅建士の資格が顧客からの信頼アップにつながる可能性が高いです。
実際に損害保険会社や生命保険会社など、さまざまな保険会社で宅建士が活躍しています。
士業
司法書士や行政書士といった士業でも宅地建物取引士の知識は非常に有用です。
なぜなら、上記の職業では不動産登記、相続、各種許認可手続きなど、多岐にわたる業務において不動産に関する専門的な知識が求められるためです。
実際に、現場で活動している司法書士や行政書士が、業務上の必要から宅建士試験を受験することは少なくありません。
ダブルライセンスを取得することで複数の法律資格を持つことになり、扱える業務の幅が広がり年収アップや独立の選択肢にもつながります。
宅建士資格は副業としても活かせる
宅建士の資格は、主な職業だけでなく、副業にも活用することができます。
最近では、副業を許可する企業が増加しており、副業として宅建士の業務を行う人々も増えています。
例えば、週末にのみ活動する週末宅建士として、宅建士の独占業務を担当し、土日だけ働く方もいます。
週末には多くの不動産会社で宅建士が不足しているため需要もあります。
さらに、副業ライターとして不動産関連の記事を執筆したり、YouTubeを通じて情報を発信したりする方もいます。
宅建士の資格を持つことでより信頼性の高い情報を提供できるためアクセス数増加にもつながるでしょう。
以上のように宅建士の資格を取得することで、副業の選択肢が広がることでしょう。
宅建士の平均年収は350万~550万円程度
宅建士の年収は一般的に350万円~550万円程度とされています。
令和5年の賃金構造基本統計調査によれば、不動産業全体の平均年収は約536万円であり、宅建士の年収は業界全体と大きな差はないと考えられます。
なお年齢別に見ると40代から50代が最も高い年収を得ており、600万円以上の収入が見込まれています。
宅建士の資格は実力主義よりも年功序列が重視されるため、長期間勤務し役職に就くことで年収が増加する傾向があることがわかります。
また、企業に就職する場合、会社の規模や地域によって年収は大きく異なりますが、一般的には450万円から600万円程度であり、大手企業では1,000万円を超えることもあるようです。
さらに、宅建士として独立開業する場合、年収1,000万円を超える可能性もありますが、士業資格の独立開業と比較すると平均年収はそれほど高くなく平均的には400万円前後とされています。
開業直後は200万円以下になることも考えられるため宅建士としての独立はリスクが高く、ダブルライセンスの一環として取得するのが良いでしょう。
宅建士の年収はいくら?給料の相場や年収アップのポイントを解説
宅建士の試験について

宅建士試験は例年20万人程度が受験するといわれており、これは国内最大級の国家資格だといわれています。
ここでは、宅建士試験の概要について紹介してきます。
試験日
宅建試験の正式な日程は毎年6月の第1金曜日に発表されます。
発表は宅建業法に基づく実施公告が官報に掲載されるほか、一般財団法人不動産適正取引推進機構のウェブサイトに記載されるので時期が近付けばチェックしておくようにしましょう。
また、例年、全国で宅建試験は10月の第3日曜日に実施されており、2025年の場合は10月19日に行われる見込みです。
さらに、合格発表は同年の11月下旬に予定されています。
受験資格
宅建士試験には受験資格が設けられていません。
年齢、性別、学歴、職歴に加え、国籍についても制限がないため、誰でも受験することができます。
宅建士試験は誰にでも挑戦できるものでありながら、宅建士の資格には重要事項説明を行うなどの独占的な業務があるため他資格よりもハードルは低いといえるでしょう。
ちなみに受験手数料は8,200円となっていあす。
試験内容
宅建士試験は、選択肢から正解を選ぶマークシート形式で実施されまるのが特徴です。
試験問題は以下の科目で全50問で、登録講習を修了した受験者の場合は45問となります。
登録講習修了者とは登録講習機関での講習を受け、修了試験に合格した者を指します。
また登録講習を修了してから3年以内に受験する場合、一部の問題が免除される特典があります。
- 宅建業法:20問20点
- 権利関係:14問14点
- 法令上の制限:8問8点
- 税・その他:8問8点
合格率
宅建試験の合格基準や合格率は試験内容によって変動するため、その時々で異なりますが、合格基準は約7割、合格率は15%前後が目安です。
宅建資格合格には一般的には200~300時間、300~400時間程度の学習時間が必要だとされています。
宅建士試験に受験資格は無し!実務経験も無しですぐ宅建士を名乗れる?
宅建士は就職に有利!学習するなら通信講座がおすすめ
今回は宅建資格を取得するメリットやおすすめの業界などについて紹介してきました。
宅地建物取引士の資格は独占業務を行うことができるため、不動産業界に限らず、金融など多様な業界でも役立ちます。
特に、就職活動を控えている大学生にとっては、在学中にこの資格を取得することで、自己PRの材料となるでしょう。
銀行業務においても不動産に関する知識が求められることがあるため、社会人になってから取得を目指すのもひとつです。
最近では資格手当を支給する企業も存在するため、年収の向上や転職活動においても有利に働く可能性が高いです。
宅建士の試験は毎年10月に実施されるため、就職活動のスケジュールを考慮しながら、計画的に進めていきましょう。
なお、宅建士の合格率は約15%とされており資格の中でも難易度が高いため、通信講座などを活用することでより効率的に学ぶことができます。