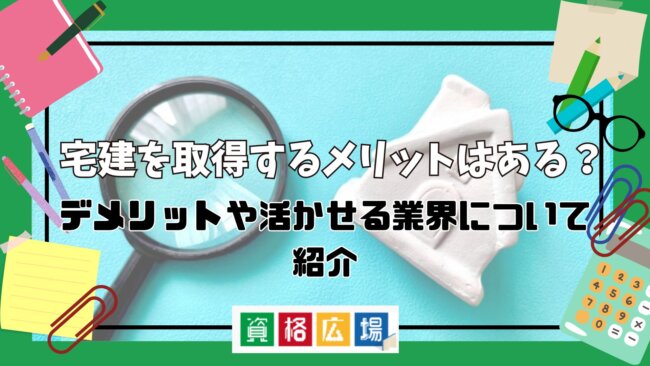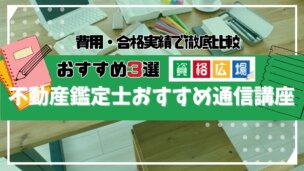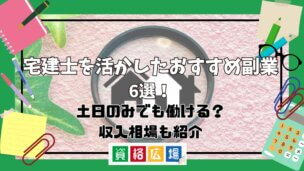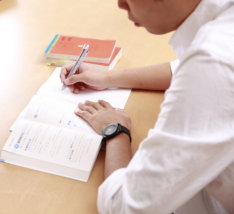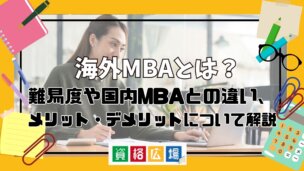宅建士になるには宅建の資格を取得するのが必要ですが、宅建は不動産業界だけではなくさまざまな業界やキャリアアップにつながるなどメリットがたくさんあります。
そこで今回は、宅建の資格を取得するメリットや反対にデメリットになることはあるかなどを紹介します。
宅建に合格するための目安勉強時間は?社会人が独学で合格する方法
宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。
宅建の資格を取得するメリット7つ

宅建は不動産に関わる資格であり、宅地・建物の売買や、賃貸を仲介する業務(宅地建物取引業)を行う際に必要となる専門知識を持った士業の一つです。
例年20万人前後が受験する国家資格で、国内最大規模といわれています。
宅地建物取引業を行う企業では従業員5人のうち宅建士を事務所に必ず1人配置しなければいけません。
宅建の資格を取得するメリットは宅建士に慣れるだけではなく、他にもさまざまなメリットがあります。
ここでは、宅建の資格を取得するメリットについてご紹介します。
宅建士にしかできない独占業務を担える
不動産売買や仲介の世界では、宅建士資格にしかできない下記のような独占業務が存在します。
- 重要事項の説明
- 重要事項説明書への記名・押印
- 契約書への記名・押印
上記3つの仕事は独占業務であるため、宅建士資格を保有している者しか行うことができません。
なお上記の独占業務は「宅建士である私が、責任をもって説明し、お客さんの理解を得られました」ということを意味する重要な仕事となっています。
一般的に、多くの人は不動産に関する専門知識は有しておらずまた不動産取引の経験はありません。
健全に不動産取引を行う、つまり不当な契約で一般消費者が不利益を被らないようにするためにも宅建士は社会的に重要な役割を果たしています。
収入アップにつながる
宅建士の年収は一般的な会社員よりも高いと考えられ、厚生労働省のデータによると宅建士を含む住宅・不動産営業の平均年収は579.5万円といわれています。
国税庁が示す一般的な会社員の平均年収は約460万円となっているので高い水準といえるでしょう。
またほとんどの不動産関連企業では基本給に加えて宅建士に対する資格手当を支給しており、資格手当は通常2万から4万円程度となっています。
つまり宅建士の資格を持っていれば、年収が24万から48万円ほど高くなる見込みがあるということですね。
さらに、宅建士は先にも述べたように特定の業務を独占的に行うことができ、不動産取引において必要不可欠な資格です。
企業にとって重要な存在であるため、昇進の機会が多く、資格手当に加えて役職手当も受けやすいという特徴があります。
以上のことから宅建士としての年収は高くなりやすく、キャリアの向上を目指す方にとって非常に有益な資格と言えるでしょう。
就職・転職に有利になりやすい
宅建士の資格を持つことは就職や転職において有利に働くといっためりとがあります。
とくに不動産業界では経験年数が同じであっても、宅建士の資格の持っているかどうかで業務の範囲には明確な違いが見られます。
やはり企業側としては資格を持つ人材を優先的に採用したいと考えるものです。
また、宅建士の資格を取得することで不動産業界以外の金融業界や建設業界でも活躍するチャンスが広がるメリットもあります。
例えば、銀行が提供する住宅ローンの貸し出しにおいては、対象となる不動産の価値が重要な要素となります。
他の応募者と差別化を図りたい方や就職・転職で活かしたいといった方は、なるべく早く宅建の資格を取得することをおすすめします。
生涯有効な資格である
宅建士の資格は一度取得すれば生涯にわたって有効です。
宅建士の試験合格後は登録実務講習を修了するか、2年以上の実務経験を積むことで宅建士として登録ができ、「宅地建物取引士証」を申請し受け取ることで晴れて宅建士としての業務を行うことができます。
特に女性は、結婚や出産などのライフイベントにより生活環境が変わりやすい特徴があります。
宅建士の資格は先にも述べたように不動産業界以外でも利用できるため、業種に関係なく将来的に再就職の際にも大いに役立うつでしょう。
宅建士の資格を取得することは手に職をつけることを意味するため、予期しない事態に備えたい方や自信を持って再就職を目指したい方にはおすすめの資格です。
ただし、宅地建物取引士証には5年間の有効期限があるため注意が必要です。
宅建士としての業務を継続する場合は、各都道府県の宅建協会などで更新手続きを行う必要があり、運転免許と同様に法定講習の受講が義務付けられています。
独立・起業に役立つ
宅建士の資格を取得することで、将来宅地建物取引業で独立や起業でも役立ちます。
独立して成功すれば会社員としての勤務よりも年収が上がったり、より自由な働き方が実現できるというメリットがあります。
また、宅建士としての知識は開業時の事務所選定にも大いに役立ちます。
不動産の価値を正しく判断できるためどの場所にオフィスを構えるのが有望かや賃料が適正かどうかを見極めることができ、独立時に不利な状況に陥るリスクを減らせます。
宅建士は独占業務ができる面もあるので、将来の選択肢を増やしたい方は持っておくべき資格といえます。
プライベートの不動産売買・貸借でも活かせる
なかにはプライベートでマイホームを建設または購入する機会を持つことでしょう。
しかし、不動産は非常に高額な投資であるため、失敗すると取り返しのつかない結果を招くリスクも少なくありません。
宅地建物取引士の知識を持つことで不動産の価値に基づいて価格が妥当かどうかや住宅ローンの返済計画に無理がないか、建設会社に問題がないかを自分自身で判断できるようになります。
また、賃貸物件においても知識を活用することで優良な物件を紹介してもらったり、退去時のトラブルを回避したりすることができます。
以上のことから宅建士は仕事だけではなくプライベートのさまざまな場面で役立つ資格であるといえます。
ダブルライセンスを目指せる
宅建士には、他の資格と重複する科目があるため、ダブルライセンスの取得を目指している方におすすめです。
例えば、マンション管理士だと区分所有法の部分やファイナンシャルプランナー(FP)だと不動産に関する部分が挙げられます。
上記のような資格取得を目指している場合、学習した内容を他方で再度学ぶ必要がなくなり、学習量や学習時間を削減できるというメリットがあります。
ダブルライセンスを取得することは専門性や職域を広げることにもつながります。
ダブルライセンスを持つことで他者や企業から高い専門性を持つ人材として評価され、さらなるキャリアアップ・収入アップを実現できるでしょう。
行政書士と宅建士のダブルライセンスのメリットは?仕事の違いや難易度について
宅建を取得するデメリットはある?
結論から述べると、宅建士資格を取得することによるデメリットは特にありません。
強いて言うならば、宅建士として登録するタイミングと5年に1度の更新のタイミングで手数料が発生することが挙げられます。
なお新規で宅建士登録をする際には下記の費用が発生します。
- 資格登録手数料:37,000円
- 実務経験が2年未満である場合の宅建士登録実務講習費用:約20,000円
- 取引士証交付申請手数料:4,500円
つまり実務経験が無い宅建士合格者が新規登録する際には約60,000円の出費が発生するため、この点は留意しておきましょう。
ただ職場によっては一連の手数料を会社が負担してくれることもあるため、事前に確認しておくことをお勧めします。
さらに5年に1度の資格更新時には16,500円の手数料が発生します。
また宅建試験に合格するためには約300時間の勉強が必要とされています。
すでに不動産業界で働いている方や転職を希望する方や自社で資格手当が支給されるケースを除けば、働きながらや育児・通学をしながらの学習が必要となるのでデメリットといえるでしょう。
以上のことから宅建の取得には金銭的・時間的リスクが伴うため、どのように資格を活かしたいのかなどを慎重に見極めることが大事です。
宅建の資格を活かせる業界
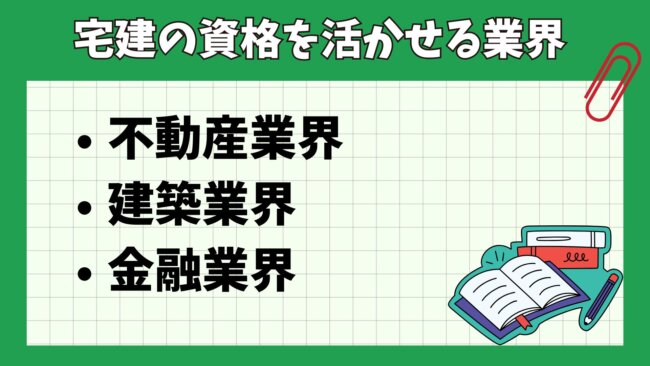
ここでは、宅建の資格を活かせる業界について紹介します。
不動産業界
宅建士資格を最も活かせる業界はやはり不動産業界になります。
不動産取引では重要事項の説明や契約書への記名押印のプロセスを踏みますが、これは宅建士資格を持っている者しか行うことができません。
また不動産業者の各事務所には5人に1人以上の宅建士を置く必要があるため、不動産業界において宅建士を持っている人材は貴重な存在なのです。
具体的には下記のような企業において宅建士資格保持者が活躍できます。
- 住宅を建てるハウスメーカー
- 物件を売買・賃借する不動産仲介業者
- 物件を管理する不動産管理会社
建築業界
土地や建物を仕入れるゼネコンやデベロッパーなど建築業界でも宅建資格は活かすことが可能です。
大手の建築会社では自社で建築を行った後に販売まで行うケースがあるため、宅建士資格保持者は重宝されます。
建築した不動産を販売・賃貸するためには宅地建物取引業の免許を得た上で宅建士を設置する必要があります。
そのため建築業界でも宅建士資格保有者は優遇される傾向にあり、建築業界で勤務している方・建築業界への転職を考えている方にとっても取得するメリットは大きいでしょう。
金融業界
銀行や信用金庫などの金融業界でも宅建士資格は活かすことが可能です。
例えば近年は高齢化の進展に伴って「リバースモーゲージ」という自宅を担保として資金を借りられる融資のサービスがあります。
このように不動産を担保とする融資業務においては、不動産に関する専門的な知識を有する宅建士資格保持者が活躍します。
他にも金融機関の窓口において金融商品の提案を行うこともありますが、「J-REIT」など不動産を活用した投資商品の説明をする際にも宅建士資格が活かせるでしょう。
また金融業界は不動産業界と深い繋がりを持っていることが多く、ローン審査や不動産を活用した資産活用などの場面においても宅建士資格は役立ちます。
宅建の試験について

宅建の試験は年に1度、例年10月の第3日曜日に全国で開催されています。
| 試験形式 | 四肢択一式によるマークシート |
|---|---|
| 試験料 | 8,200円 |
| 問題数 | 50問 |
| 試験時間 | 2時間 |
| 合格率 | 約15~17% |
| 合格ライン | 約7割 |
宅建試験の内容は、各問題に対して4つの選択肢から適切なものを選ぶ四肢択一式となっています。
出題数は50問で民法・宅建業法・法令上の制限・その他の4つの分野で構成されています。
合格点は明確に設定されておらず、受験者数や合格率に応じて変動する相対評価試験です。
一般的には約70%以上の正答、つまり50点中35点前後の得点があれば合格の可能性が高いとされています。
民法は50問中14問を占めており、日常生活に密接に関連する分野ですが、学習量が多いことから時間をかける必要があります。
出題範囲には、土地や建物の権利・不動産の所有権・抵当権・売買・賃貸借に関する契約が含まれます。
宅建業法は50問中20問を占めており、学習時間はそれほどかからないものの、正確な解答を導き出すための精度向上が必要です。
出題範囲は宅地建物取引業法や関連法令に関する内容で、土地や建物の公正な取引促進・宅建業に関する事項・宅建士の就業に関する法規が挙げられます。
法令上の制限に関しては50問中8問とそれほど多くはありませんが、専門用語やルールが多いため理解するまでに時間がかかるといわれています。
出題範囲には都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法などが含まれます。
その他の科目としても50問中8問が出題されており、固定資産税や登録免許税など、宅地および建物の税に関わる法令などから出題されます。
ほかにも税以外では、土地・建物、鑑定評価基準などから出題されます。
宅建合格後は登録手続きが必要
宅建の試験は合格したからといってすぐに宅建士としての業務を開始できるわけではありません。
資格取得時に実務経験が2年以上ある場合は、そのまま資格登録手続きに進むことができますが、実務経験が2年未満場合は実務講習の受講が必要となります。
さらに、試験合格後1年以内に資格登録を完了させることで宅地建物取引士証の交付申請が行えます。
申請が承認されれば宅地建物取引士証が交付され、晴れて宅建の独占業務に従事することができるようになります。
なお、合格日から1年を超えて資格登録を行う場合は、法定講習の受講が必要となるため注意が必要です。
宅建士の難易度や合格率は高い?合格に向けたおすすめの勉強法も徹底解説
宅建士とは
宅建士は「公正な不動産取引を行うため、宅地建物取引業法により定められた」国家資格です。
そのため宅建を持っていると、一般的に「不動産取引の専門家」と評価されます。
宅建士には不動産の売買や賃貸契約を締結する際には宅建資格を持っていなければできない業務(独占業務)が存在します。
不動産取引は一般的に高額になりますが、売る側も買う側も安心して取引ができるようにするために宅建士は重要な役割を果たしています。
不動産業界で働く会社員にとって宅建士資格は必須です。
実際宅建士資格を保有していなくても営業はできますが、「資格を持っている営業マン」と「資格を持っていない営業マン」では信頼度が大きく違います。
また、宅建資格がないと契約締結の際の「重要事項説明」ができないため、顧客を最後までサポートすることができません。
つまり、不動産業界への転職を目指している場合宅建資格はぜひとも保有しておきたい資格と言えます。
宅建は役に立たないって本当?宅建が生かせる業界や取得メリットを解説
宅建士を目指すならアガルート!

取得のメリットも多く活躍できる業界も多い宅建士資格ですが、効率よく合格を目指すのであれば通信講座を活用するのがおすすめです。
今回は満足度の高い講座として知られるアガルートの『宅建士講座』をご紹介します!
短期間で成長が可能なカリキュラム
アガルートの宅建士講座は効率性を重視しており、法律のプロである講師が自ら作成したテキストを使って学習します。
合格するためのエッセンスだけを詰め込み体系的に整理された知識をインプットできるため、最短ルートで合格を目指すことが出来るのは大きな魅力です。
また1回の講座は10分前後にまとめられており、移動時間や就寝前と言ったスキマ時間を活用して効率的に学習が進められます。
気軽に学習できモチベーションも保ちやすく一定のペースで学習できるため、着実な成長が期待できるのがアガルートの通信講座です。
→アガルートの宅建試験講座の評判は?口コミや費用などもご紹介!
全国平均を大きく上回る合格率
効率性を重視したアガルートの通信講座ですが、その効果は実績となって表れています。
初学者向けのカリキュラムである入門総合カリキュラムでは、全国平均の3.27倍である55.6%の方が合格を掴み取っているのです。
しっかりとした実績を打ち出しているアガルートの通信講座は32.780円(税込)から受講できるため、コストパフォーマンスも優れているのも嬉しい点となっています。
着実な成長が期待できるのはもちろんお財布にも優しいアガルートの受講をぜひご検討ください!
手厚い受講生サポートで安心
安価な通信講座では手薄になってしまうことも多い受講生サポートですが、アガルートでは盤石な支援を受けることが出来ます。
専用のFacebookグループを通じて何回でも質問することができ、月1回のホームルーム配信を通じて法改正などの情報を学ぶことが可能です。
情報面で他の受験生と違いをつけられるのはもちろん、学習する上でのモチベーションも高められるのは魅力的です。
優れた点の多いアガルートの宅建士講座が気になった方は、ぜひこちらから公式ページをご覧ください!
宅建の資格は仕事でもプライベートでも活かせる
今回は宅建士資格を取得するメリットやデメリット、資格を活かせる業界などについてまとめました。
学生でも会社員でも宅建士資格を取得することで就職や転職の幅が広がり、また資格手当などによる収入アップという経済的メリットも期待できます。
また不動産業界だけでなく建築業界や金融業界でも宅建士資格は活かせるため、当該業界に興味がある方は積極的に資格取得を目指すと良いでしょう。
宅建士試験はそこまで難易度が高くなくきちんと勉強すれば誰でも合格を目指せるレベルなので、職業人生を豊かにするためにも取得を検討してみてください。