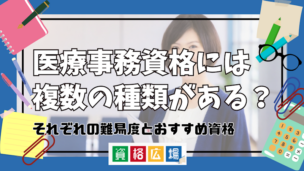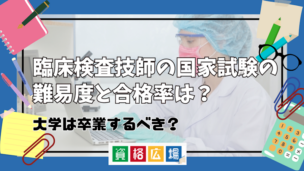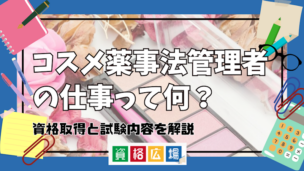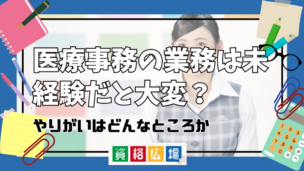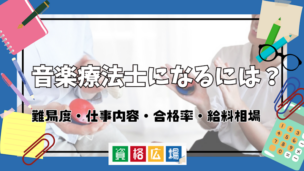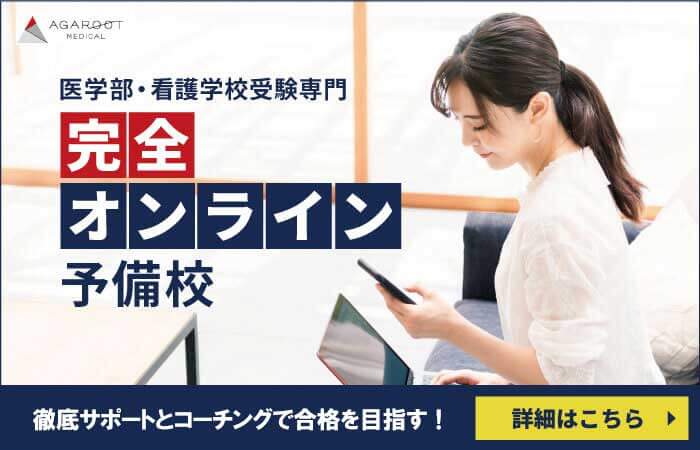医大生って数が少ないし、実際どんな大学生活をを送っているかあまりイメージできないですよね。やっぱりほかの学部の大学生とは学校生活も違うんでしょうか。そこで今回は、そんな医大生の学校での生活について、勉強以外のサークルの活動とかもしているのか、やはり医学をはじめとした勉強は忙しいのか、はたまた卒業してからも実習が多いのかについて説明していきます!
稼げる・儲かる資格おすすめランキングTOP12!取得難易度や収入アップ・副業でも活用できる資格を徹底比較【2024年最新】
医大生の生活①サークルなどの日常生活

医学生も普通の大学生と同じようにサークルに入って大学生活を過ごすことが多いです。
しかしながら、他の大学生以上に勉強が必要なため、そのサークル生活はやや特殊なようです。
医学部だけのサークルがあることも
医大生はほかの大学生以上に実習などの勉強の負担が大きいため、他の大学生のように頻繁にサークル活動を行うことができません。
そのため、医学生だけのサークルがある大学も少なくありません。
たとえば、東京大学には医学部生(とその卵である理三生)をメインとした鉄門サークルが存在します。
東大医学部の同窓会が鉄門倶楽部ですので、こう呼ばれますが、鉄門サークルの例として、鉄門サッカー部とか鉄門バドミントン部なんかがあります。
これらのサークルで、プレイヤーとして部員になれるのは基本的に理三生、医学部生のみで、かなり他の学部から独立したサークルであることが多いようです。(マネージャーは他大から迎えることが多いようですが。)
医大生だけの大会?
医大生がサークルとして他の学部から隔離的であるのは、単に忙しさだけが問題ではありません。
東日本では東医体、西日本では西医体という体育会系サークル・部活の大会の参加条件が医大生に限られているからです。
現実的な問題として、インターハイに出場した大学生選手と医学生選手が戦っても、試合は基本的にかみ合いません。どうしても練習量が十分に割けないからです。
そこで、このような医大生だけの大会があることで、医学生同士のつながりを深めるという目的はもちろんのこと、サークル活動として、現実的な試合環境が整えられているのです。
交流は医大生同士が多い?
体育会系の医大生の場合はどうしても閉鎖的空間にいざるを得ません。そのため、特に単科医大生の場合、学校外の知り合いといえば、中高の知り合い以外だとサークル・部活交流のある医大生に偏ってくるようです。
ただ、文科系サークルだったり、全学部サークルだとその限りではありませんし、交流関係は人によって大きく異なってくるのではないでしょうか。
医大生だけのサークルと聞くと、閉鎖的と思う人も少なくないかもしれませんが、将来同じ業界で働く人たちの集まりである医学部においては、学部ごとに区切られた空間は、卒業生を含めた縦横の人脈を広げる良い機会といえるでしょう。
医大生の生活②学校での勉強
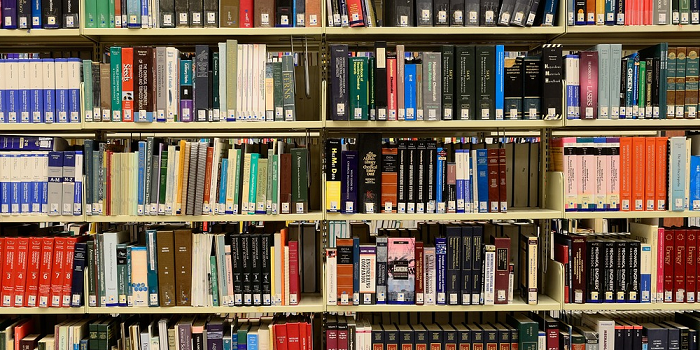
未知に包まれている医大生の学校生活ですが、今度は授業や勉強のほうにフォーカスを当ててみましょう。やはり実習も忙しいのでしょうか
医大生は解剖が忙しい?
この記事でもあるように、医師には総合的知識が必要です。そして、医大生が勉強しなければいけない内容に、解剖学があります。
解剖学では、人間の骨・筋肉・神経などの名称と位置を覚えていかなければならないで、かなりの暗記量になるようです。
さらに、解剖実習が始まり、医大生の実習生活が始まっていきます。
もちろん、暗記のための単語帳のようなものも存在しますが、受験時代に覚えていた英単語と違って、内容はとても専門的なうえ、実習で実際に活用しないといけないので、かなり苦労するようです。
解剖学をはじめとして、生理学・生化学などは基礎医学と呼ばれますが、医学について学び始める最初の期間であるということも相まって、基礎医学を学ぶ2,3年生はかなり忙しい学校生活を過ごしているようです。
さらに5,6年生では病院実習という大学を離れ病院で行う実習があり、より実践的な実習が始まっていきます。
空きコマはほとんどない
「大学生は人生の夏休み」だなんていわれたりしますが、そんな甘い言葉を医学生にけても、一笑に付されて終わりでしょう。
多くの学校の場合、全部の時間割が埋まるということはまずありません。
しかし、医学部の場合、この記事で述べたように6年間と勉強期間が長いとはいえ、教養科目にはじまり、基礎医学、臨床医学、社会医学と勉強することは山積みです。
ですから、教養科目と細胞生物学という高校生物の延長を勉強することがメインの1年生ですら、ほとんど空きコマは存在しません。
また、実習やグループワークのある授業も多いため、出席に関しても厳しく、医大生は必然と忙しい学校生活を過ごしているようです。
医大生の生活③卒業後の主な進路
医大生は実習が多く、大変な学校生活を送ることもしばしばですが、卒業すると実習などの勉強から解放されるのでしょうか。
卒業すれば実習から解放される
実習生活で忙しかった医学生生活からも、卒業と国試合格で解放されます。
したがって、学校を卒業してしまえば、もう実習をする必要はないんです。
ただし、これは言葉の綾のようなもので、実習生活からは確かに解放されますが、今度は研修生として忙しい毎日を過ごさなければなりません。
つまり医師になると実習がないのは、教師を目指す人が教員資格をとってから教育実習をしないのと一緒で、そもそも実習とは、まだ免許を持っていない人が、資格習得のために実地で勉強することだからです。
研修生はまだまだ見習い
医師は、国試合格後の二年間、初期研修を行わなければなりません。
この間は、まだ特別に診察科を決めておらず、様々な科を順番にローテーションして、横断的に勉強していく期間です。
したがって、資格的には医師だけれども、専門医や上級医からすれば、まだまだ医師見習いなわけです。
つまり、卒業してからは、実習はないけれど、実地で研修という形でたくさんの勉強をしていかなければならないのです。
医大生の生活まとめ
医学生の忙しさが、この記事をとおして何となくわかっていただけたでしょうか。一学生は、教養科目から、基礎医学・臨床医学・社会医学など専門科目まで、6年間を通して学び通さなければなりません。
そして、その勉強で忙しい日々は卒業してからも、研修生として続いていきます。研修生として医師の世界に踏み入ったとき重要なのが、医師同士のつながりです。
このようなつながりは、大学のサークル時代がからすでに形成され始めていることもわかりました。(さらに高校によっては医学部同窓会などもあり、実は中学受験から人脈が形成されていたりします。)
これだけ忙しい医学生生活を送るためには最低限の要領の良さが大切です。
医学部受験はいたずらに難しくて、賢い人がこぞって医学部に行くのは社会の損失だという嘆きを聞きますが、その難しい受験で、要領の良さを確認しているとわかっていただけたら、皆さんも医学部受験についても理解が深まるのではないでしょうか。