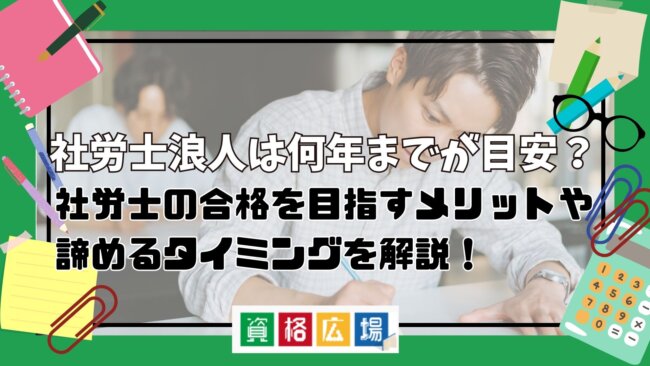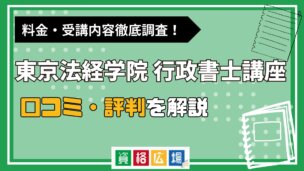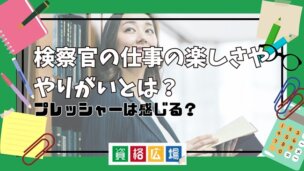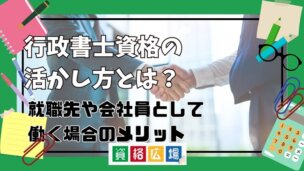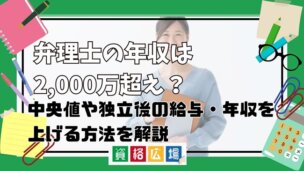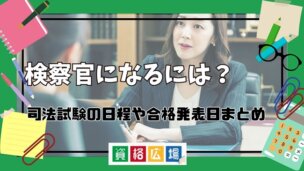社労士試験は非常に難易度が高いため、合格できず浪人してしまうのは良くあることです。
実際社労士の平均受験回数は「4~5回程度」と言われているため、もし浪人してしまっても気にする必要はありません。
こちらの記事では、社労士試験で浪人してしまった際に合格を諦めるタイミング、また浪人する苦労を乗り越えてまで社労士資格を取得するメリットなどを解説していきます。
社労士試験で浪人しており受験を継続するか悩んでいる方にとって役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
社会保険労務士試験におすすめの通信講座
社労士の浪人は何年くらいが普通?
冒頭で述べたように社労士試験は難関試験で、一発合格できる方が珍しいレベルです。
つまり、社労士を目指す際に浪人してしまうのは至って普通のことであり特段気にすることではありません。
まずは、社労士試験の平均受験回数や合格率などのデータを見ていきましょう。
社労士試験の平均受験回数について
社労士の平均受験回数に関する公式なデータはありませんが「4~5回」が平均受験回数とされています。
社労士試験は「1回~3回の受験で合格できる人」「5回以上受験して合格する人」の2つのグループに大別され、全ての人を平均すると「4~5回に落ち着く」ということです。
また社労士試験の合格率は5~8%程度となっているため、単純計算で「100人受験しても合格できるのは10人未満」ということになります。
そして社労士試験に合格するためには「1,000~1,200時間程度の勉強が必要」と言われているため、在職中の方が合格できるレベルの学力を習得するまでには相応の期間がかかってしまうでしょう。
当然試験問題は毎年変わるため、複数回受験しているにも関わらず不合格になってしまうといったケースは多々あります。
社労士試験の合格率について
続いて、ここ10年の社労士試験の合格率について見ていきます。
| 年度 | 合格率 |
|---|---|
| R5年度 | 6.4% |
| R4年度 | 5.3% |
| R3年度 | 7.9% |
| R2年度 | 6.4% |
| R1年度 | 6.6% |
| H30年度 | 6.3% |
| H29年度 | 6.8% |
| H28年度 | 4.4% |
| H27年度 | 2.6% |
| H26年度 | 9.3% |
上記のように合格率6%台の年度が多く、平均すると合格率5~8%の試験と言えます。
また社労士試験は学歴や実務経験など受験するための条件が設けられているため、「誰でも受験できるわけではない」点も特徴です。
つまり社労士試験は受験資格をクリアした人が受験した上で「合格率5~8%程度」という数字になっているため、かなり難易度が高く浪人するのは当たり前の試験と言って良いでしょう。
社労士は浪人してまで取得する価値があるの?
多くの人が浪人する社労士試験ですが、浪人してまで取得する価値はあるのでしょうか?
ここでは、社労士資格を取得するメリットをご紹介します。
難関資格の取得は人材価値の向上に繋がる
社労士は難関資格として知られているため、そんな難関資格を保有していることは自身の人材価値を向上させることに繋がります。
一般的に人材価値の向上に伴って就職先の選択肢が増えたり収入が増えたりするため、職業人生が豊かになるメリットが期待できます。
また社労士は専門性が高く仕事でもプライベートでも頼られる場面は多くあるため、自身の存在価値や自己肯定感を高められる点も大きなメリットと言えるでしょう。
就職や転職の際に有利になる
就職や転職をする際に資格を持っていると断然有利になります。
特に社労士のような専門性の高い資格を保持しているということは、下記のような知識・スキルの証明になります。
- 社会保険や年金、労務に関する知識を持っている
- 難関資格を取得できるだけの計画性を持っている
- 最終的に結果を出せる
- 勉強家で真面目
- 努力が苦にならず仕事能力が高い
- 入社後の教育が楽で教育コストがかからない
一般企業はもちろん、社労士法人や社労士事務所で就職・転職する際に社労士資格は強力な武器になります。
たとえ実務経験が無くても仕事を教える上で基礎部分となる知識は既に習得できていることから、非常に魅力的な人材として評価してもらえるでしょう。
勤務先によっては資格手当の対象となる
勤務先の規則によりますが、社労士資格を保有していると資格手当が支給されることがあります。
例えば「社労士資格保有者に月2万円の資格手当を支給」という企業があったとしましょう。
この場合社労士資格を「持っているだけ」で年間24万円、10年間で240万円の収入アップとなります。
予備校や通信講座に通って社労士試験に合格した人でも、その時かかった学習費用を簡単に賄うことができるでしょう。
また25年間勤めた場合、資格手当だけで600万円と軽い退職金レベルの収入になります。
このように、資格手当という経済的なインセンティブが期待できる点も社労士資格を取得するメリットです。
独立開業が狙える
社労士資格を取得すれば独立開業が狙えるため、独立志向が強い方にとっては取得メリットが大きいでしょう。
近年は経団連の会長も「終身雇用の継続は難しい」旨の発言をしていることから「自分の知識や腕だけで稼ぐスキル」を習得することの重要性は年々高まっています。
社労士資格を取得していれば登録の手続きを経ることでいつでも独立開業できるため、もし現在の勤務先が傾き存続が危ぶまれるような状況になっても慌てることはありません。
また独立開業することで下記のようなメリットも期待できることから、「自由度の高さ」「仕事の柔軟性」を求めている方は浪人してでも社労士試験の合格を目指す価値があります。
- 働く時間と場所を選べる
- 仕事量を自分で決められる
- 休もうと思えばいつでも休める
- 満員電車に乗る必要が無い
社労士試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!
社労士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。
合格者には受講費全額返金orお祝い金3万円の特典もあるのでモチベーションの維持も期待できます!
最短ルートで合格が目指せる!
アガルート公式HPはこちら
社労士試験合格をあきらめるべきタイミング
取得することで様々なメリットを得られる社労士資格ですが、だからといってズルズルといつまでも浪人生活を続けて良いわけではありません。
以下に該当する方は、社労士試験合格の諦めを検討するタイミングとみて良いでしょう。
- 60代、60代に近い50代
- 未就職で30歳を超えてしまった
理由を解説する前に、社労士試験過去10年の年代別合格者率を見てみましょう。
| 年度 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代~ |
|---|---|---|---|---|---|
| R5年度 | 11.8% | 32.6% | 29.2% | 18.9% | 7.5% |
| R4年度 | 10.7% | 30.4% | 31.7% | 20.1% | 7.1% |
| R3年度 | 12.8% | 35.6% | 28.5% | 16.9% | 6.2% |
| R2年度 | 12.3% | 30.1% | 30.1% | 18.7% | 8.8% |
| R1年度 | 8.2% | 33.1% | 31.5% | 18.8% | 8.4% |
| H30年度 | 9.2% | 29.5% | 32.8% | 19.2% | 9.3% |
| H29年度 | 10.0% | 30.7% | 31.2% | 19.6% | 8.5% |
| H28年度 | 9.1% | 31.4% | 32.3% | 18.8% | 8.4% |
| H27年度 | 9.6% | 32.5% | 30.9% | 18% | 9.0% |
| H26年度 | 11.1% | 35.8% | 28.5% | 17.9% | 6.7% |
上記のように60代の合格者数の割合が低いことから、60代にさしかかると合格するのが厳しくなることが分かります。
「60代は全員が厳しい」というわけではないものの、データ上はかなり難しいということは知っておくべきポイントです。
また繰り返しになりますが社労士試験は難関試験のため、浪人を繰り返している内に30歳を超えてしまった方も少なくありません。
30歳になって社会人経験が無いと社労士試験を取得するメリットよりも「社会人としての経験が無いことによる不安」というデメリットが上回るため、こちらも社労士試験合格の諦めを検討するタイミングと言えます。
未就職で30歳になりそうな方や既に30歳を超えてしまった方は、資格取得だけでなく就職も視野に入れることをおすすめします。
社労士試験に連続して落ちてしまう人の特徴
ここからは、社労士試験に連続して落ちてしまう人の特徴を解説します。
下記で解説する内容に気を付けると合格できる可能性は高まるため、ぜひ参考にしてみてください。
勉強時間不足
前述したように、社労士試験の合格には「1,000~1,200時間程度」の勉強が必要と言われています。
勉強時間が不足していると知識も不足してしまい、本試験で初見の問題に対応出来ない可能性が高くなります。
勉強時間を確保すれば必ず合格できるというわけではありませんが、勉強時間が不足していると合格できないのは当然と言えます。
そのため、在職中で勉強時間の確保が難しい方は移動時間や家事の合間など隙間時間を活用しコツコツと勉強する意識を持つと良いでしょう。
インプット・アウトプット不足
社労士試験では複雑な問題が出題されるため、インプット・アウトプットのどちらかが不足していると合格するのは難しいです。
社労士試験対策におけるインプットとは「基礎知識を覚える・法律の内容を理解する」ことで、実際に問題を解く際の根幹となるものです。
一方でアウトプットは「インプットで習得した知識を深める・問題を実際に解くコツを習得する」ことで、練習問題演習や過去問演習がそれに該当します。
「知識」「実際に問題を解く感覚」のいずれかが欠けていると何回受験しても難関の社労士試験には合格できないでしょう。
社労士試験に合格するためのコツ
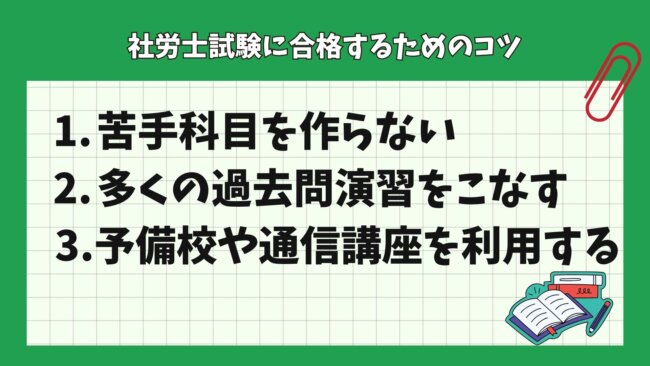
最後に、社労士試験に合格するためのコツについて解説していきます。
浪人してショックを受けている方でも、ここで解説する対策を実践すれば合格に近付くことができます。
下記を参考に、諦めずもう1年頑張ってみませんか?
苦手科目を作らない
社労士試験には科目ごとの「足切り基準」が設けられているため、苦手科目があると合格が遠のいてしまいます。
1科目でも足切りに引っかかってしまうとその他の科目が会心の出来だったとしても不合格になる「理不尽さ」があるのです。
苦手科目が多ければ多いほど足切りに引っかかるリスクが高くなるため、合格できる可能性は低くなります。
そのため苦手科目を作らないことを意識し、過去問演習でよく間違える分野や単元があれば徹底的に対策することを意識してみてください。
多くの過去問演習をこなす
多くの過去問演習をこなすことで問題慣れできるため、本試験でも冷静に対応できるようになります。
過去問演習を行い解説を読むことは知識を定着させる効果があるのはもちろん「これだけやったのだから大丈夫だろう」という自信が得られるメリットもあります。
また社労士試験は過去問と類似した問題も頻繁に出てくるため、問題慣れすることでスムーズに正誤判断できるようになるでしょう。
過去問を多くこなせば本試験でも対応できる知識と自身を習得できるため、浪人している方は過去問演習に割く時間を増やすことをおすすめします。
もちろん自分がミスしやすい部分はより深くインプットを行い、次の問題演習の際には完璧になっているようにしておきましょう。
予備校や通信講座を利用する
これまで独学で勉強してきたのであれば、予備校や通信講座の利用を検討することをおすすめします。
予備校や通信講座には、過去の頻出問題や狙われやすい論点など試験対策に役立つ多くのデータがあります。
また、合格のノウハウが詰め込まれたテキストを使いつつ指導経験豊富な講師から分かりやすい指導を受けられるため、効率良く合格を目指すことができます。
独学で浪人してしまっている方は、独学に見切りを付けて勉強方法を切り替えることも大切です。
社労士浪人のまとめ
社労士試験の合格率と難易度を考えると、浪人してしまうのはよくあることです。
しかし社労士資格には浪人して時間をかけてまで取得する価値があるため、合格を諦めていない方は受験を続けると良いでしょう。
ただし「60代・60代に近い50代」「未就職で30歳を超えてしまった方」は、合格の諦めを視野に入れるタイミングでもあります。
とは言え社労士を取得するメリットは大きいため、リスクとリターンのバランスを鑑みつつ自身で良きタイミングを判断することが大切です。