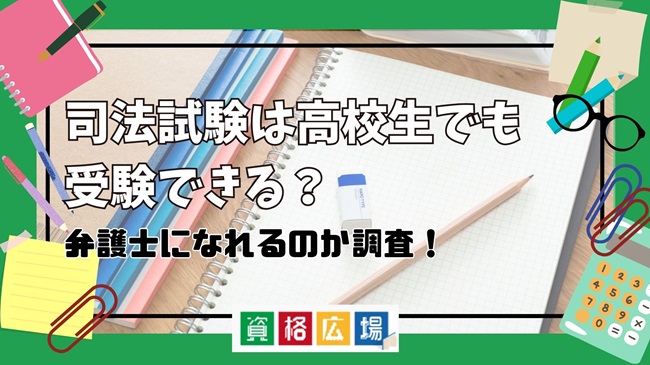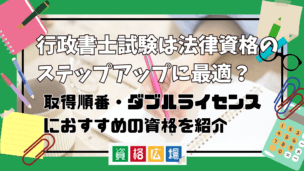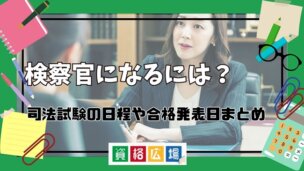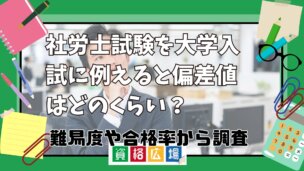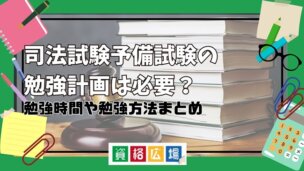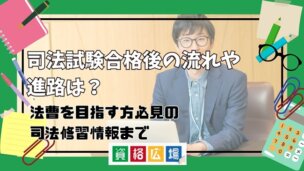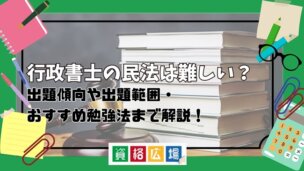ドラマやマンガなどでよく題材とされる弁護士ですが、弱い立場の人を守っている姿はとてもかっこいいですよね。
そんな弁護士に興味を持ち「弁護士になりたい」と、高校生のうちから将来の目標を定めている方もいるのではないでしょうか。
弁護士になるには「司法試験」という国家試験に合格する必要がありますが、高校生でも弁護士は目指せるでしょうか。
こちらの記事では、高校生でも司法試験を受験できるのか、弁護士になれるのかについて解説します。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
司法試験予備試験合格におすすめの通信講座
司法試験は高校生でも受験できる?
弁護士を目指す誰もが受験し、合格を目指す司法試験ですが、高校生でも受験できるのでしょうか。
司法試験には年齢制限がないため、高校生でも受験することは可能です。
しかし、司法試験は受験するための条件が定められているため、まずは受験資格を獲得する必要があります。
それでは、高校生が司法試験を受験するには何をすれば良いか解説します。
高校生でも受験できるが条件がある
司法試験の受験資格は以下の2つとされており、現状この2つの方法以外で受験資格を獲得する方法はありません。
司法試験の受験資格
- 法科大学院を修了する
- 予備試験に合格する
高校生が司法試験の受験資格を得るには?
高校生が司法試験の受験資格を得る方法は、「予備試験に合格する」ことです。
「法科大学院の修了」は、大学の卒業後に法科大学院に通う必要があるので、高校生では物理的に不可能な条件です。
予備試験は、合格することで法科大学院修了程度の知識・能力があると認められる国家試験です。
予備試験は、学歴・年齢は関係なく誰でも受験可能なので、高校生でも受験することができます。
予備試験は難易度が高い
予備試験の合格率は約4%と低く、非常に難易度の高い試験です。
受験者の多くは社会人・大学生・大学院生で、高校生の受験者はそもそも多くありません。
ただし、過去に予備試験に合格した高校生の前例があるため、挑戦する価値はあるでしょう。
| 科目 | 憲法・民法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法・商法・行政法+一般教養、選択科目、法律事務基礎科目 |
|---|---|
| 令和5年の試験日程 | ①答案式試験:令和6年7月14日(日) ・②論文式試験:令和6年9月7日(土)、8日(日) ・③口述試験:令和7年1月25日(土)、26日(日) |
予備試験の合格者の年齢について詳しく取りあげている記事もあるので、気になった方は以下の記事も参考にしてみてください!
⇒『予備試験・司法試験に年齢制限は無い?合格者の平均年齢や最年長・最年少は?』
高校生までの合格に拘らないなら進学する
今すぐに弁護士になりたい、司法試験を受験したいという高校生の方以外は、大学への進学をおすすめします。
進学する学部でも法律系の学部に進学することで、ゆっくり時間をかけて予備試験・司法試験の勉強を進められるだけでなく、法科大学院へ進む際にも卒業までの期間が短縮される等の恩恵があります。
また高校生が大学へ進学すると、将来の目標が弁護士から変わった時に対応しやすいメリットもあります。
法科大学院とは?
法科大学院とは、ロースクールとも呼ばれ、「法曹養成に特化した教育を行う専門職大学院」です。
法科大学院を修了することで、司法試験の受験資格を獲得できます。
以下の記事で法科大学院の学費など詳しくまとめているので、気になった方はぜひ参考にしてください!
⇒『法科大学院を卒業するメリットは?予備試験との違いもご紹介』
司法試験は高校生でも合格できる?
司法試験に受験年齢制限は設けられていないので、高校生でも受験できます。
高校生が司法試験に合格した前例もあるため、とにかく急いで弁護士になりたい方は目指す価値は十分あるでしょう。
司法試験の受験者情報
こちらでは、令和5年(2023年)の司法試験で、予備試験に合格し、司法試験を受験した方の情報を年齢別・職業別・最終学歴にご紹介します。
それぞれの合格者数も公表しているので、ぜひ参考にしてみてください。
| 年齢 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 19歳以下 | 1 | 1 |
| 20~24歳 | 159 | 155 |
| 25~29歳 | 70 | 70 |
| 30~34歳 | 32 | 31 |
| 35~39歳 | 30 | 25 |
| 40~44歳 | 29 | 27 |
| 45~49歳 | 9 | 7 |
| 50~54歳 | 10 | 5 |
| 55~59歳 | 8 | 4 |
| 60~64歳 | 3 | 1 |
| 65~69歳 | 2 | 1 |
| 合計 | 353 | 327 |
| 最終学歴 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 高校在籍中 | 0 | 0 |
| 高校卒 | 0 | 0 |
| 大学卒業 | 147 | 135 |
| 大学在籍中 | 38 | 37 |
| 大学中退 | 3 | 1 |
| 法科大学院修了 | 49 | 41 |
| 法科大学院在学中 | 49 | 41 |
| 法科大学院中退 | 16 | 16 |
| 法科大学院以外の大学院修了 | 14 | 12 |
| 法科大学院以外の大学院在学中 | 1 | 1 |
| その他 | 2 | 2 |
| 合計 | 353 | 327 |
残念ながら令和5年度試験では高校生の中には合格者がいませんでした。
しかし、令和4年度試験では1名の方が合格していました。
全体的に合格者の方が多く見てとれますが、司法試験・予備試験の試験内容・難易度・採点形式が類似している事が理由と言われています。
予備試験に合格すれば、法科大学院に進学せずに司法試験の受験ができるため、早めに受験する学生が多いです。
予備試験と司法試験の難易度の違いについて詳しく取りあげている記事もあるので、ぜひ参考にしてみてください。
⇒『司法試験と予備試験の難易度は?どちらの試験の方が難しい?』
高校生でも弁護士になれる?
司法試験合格後、弁護士など法曹になるためにほぼ必修の「司法修習」という研修制度があるため、高校生のまま弁護士になることはできません。
こちらでは、弁護士になるまでの流れや、高校生のまま弁護士になることが難しい理由について詳しく解説します。
弁護士になるまでの流れ
高校生のまま弁護士になることが難しい理由について解説する前に、弁護士になるまでの流れを簡単にご紹介します。
弁護士になるには、司法試験に合格するだけなく、合格後にもさまざまな過程があります。
弁護士になるための手順
- 司法試験の受験資格を獲得する
- 司法試験に合格する
- 司法修習生になる
- 司法修習生考試に合格する
- 弁護士登録をする
司法修習とは?
司法修習生は,司法試験に合格した人の中から,最高裁判所が命ずることになっており(裁判所法第66条),少なくとも1年間(旧司法試験合格者を対象とする司法修習については,少なくとも1年4か月間)の修習をした後,試験に合格すると司法修習を終え(裁判所法第67条第1項),裁判官,検察官,弁護士になる資格を得ることになります。
司法試験合格後、弁護士をはじめ法曹を目指すならほぼ必ず受けることが義務付けられているのが「司法修習」です。
司法修習は、司法試験合格者が受ける1年間の研修のようなもので、毎年約2,000名が司法修習生となっています。
兼業・兼職の禁止
司法修習生は,国家公務員ではありませんが,これに準じた身分にあるものとして取り扱われ,兼業・兼職が禁止され,修習に専念する義務(修習専念義務)や守秘義務などを負うこととされています。
司法修習生となると、兼業(アルバイトなど)・兼学(高校・大学など)・政治的なメッセージの発信が禁止され、海外旅行も制限されます。
これは、「修習期間中は修習に専念するように」という決まり事なので、高校と修習の両立はできないと考えて良いです。
もし高校生のうちに司法試験に合格し、すぐにでも弁護士になりたいのなら高校を退学する必要があります。
司法修習は自分のタイミングで受けられる
司法修習は、司法試験に合格した年に必ず受けるという決まりはありません。
すぐに司法修習を受けなければ、司法試験の合格が取り消しになるという事もないので、自分の好きなタイミングで受けられます。
高校生のまま弁護士になることはできませんが、高校を卒業してから司法修習を受け、弁護士活動を始めることは可能です。
司法試験に合格した後の流れについて以下の記事にて解説しているので、気になる方は合わせてお読みください!
⇒『司法試験合格後の流れや進路は?法曹を目指す方必見の司法修習情報まで』
司法試験・予備試験の勉強方法
高校生のまま弁護士として活動するのは司法修習の関係上難しいですが、司法試験・予備試験の受験は自由です。
最もお金がかからずコスパが良いのは独学ですが、司法試験・予備試験は論文式試験があり、採点には有識者による客観的な判断が必要なため、あまりおすすめできません。
こちらでは「今すぐにでも勉強を始めたい!」という方に向けて、司法試験・予備試験のおすすめの勉強方法についてご紹介します。
司法試験・予備試験の勉強方法
- 独学で勉強する
- 予備校に通う
- 通信講座を受講する
独学で勉強する
司法試験・予備試験に独学で合格することは可能ではありますが、非常に困難といわれています。
高校生が高校で学ぶ学習内容ではほとんど試験に対応できないため、膨大な範囲を1から独学で勉強するとなると、正直現実的ではありません。
また、司法試験・予備試験には毎年情報の更新や追加などされる科目があるため、合格には情報収集が肝になります。
周囲に司法試験・予備試験に詳しい方がいない限り、独学しつつ情報を集めるのは難しいと言わざる負えないでしょう。
予備校に通う
予備校は、司法試験・予備試験の勉強方法としてかなり一般的な手段です。
予備校に通えば、試験合格に必要な知識を絞ってくれるだけでなく、初学者でも分かりやすく法律の解説をしてくれます。
予備校は、独学でわかりずらい「どこから手を付けるか」優先度を示してくれるため、おすすめの勉強方法の一つです。
忙しい高校生には向かないこともある
高校生は、部活動や授業、アルバイトなど私生活が忙しい方も多いでしょう。
予備校には夜間のコースを開講していることもありますが、高校生は22:00以降外を出歩いていると補導されてしまう可能性もあるため、現実的ではありません。
これらの理由から、多忙な高校生にとって予備校は物理的に難しい可能性があるため注意してください。
通信講座の受講がおすすめ
司法試験・予備試験の勉強方法で、独学よりもおすすめなのが通信講座を受講する事です。
先ほど説明した論文式問題の添削や、疑問点、不明点の質問など、自分一人では解決が難しい内容も効率よく学習できるでしょう。
また、予備校のように優先度を示してくれるだけでなく、学習の場所を選ばない通信講座は、私生活との両立がしやすいため、高校生の方にもおすすめしたい勉強方法です。
短期合格も目指せる
予備校・通信講座は、試験対策のプロの講師が合格のための知識を教えてくれるため、短期間で合格を目指せます。
また、司法試験・予備試験で出題される法律は、毎年更新や新たな情報の追加があるため、情報収集が非常に大切です。
予備校・通信講座を受講すれば、これらの情報収集を自分で行う必要がなくなるため、そういった意味でも効率が良いです。
司法試験の受験資格となる予備試験の勉強方法について詳しく説明している記事もありますので、気になる方はこちらもチェックしてみてください!
⇒『司法試験予備試験の勉強方法!学ぶ科目の順番や事前準備まとめ』
通信講座ならアガルートがおすすめ!

司法試験・予備試験の対策をするなら、通信講座のアガルートがおすすめです。
アガルートは試験を徹底的に分析し、合格のための効率の良いカリキュラムが整備されています
また、高校生のように授業や部活動などで生活が忙しい方でもスキマ時間に学べる教材が用意されているため、学校と司法試験・予備試験の勉強の両立が出来るでしょう
個別指導・家庭教師のような特別なプランや科目ごとにフォーカスした講座など細かく授業が開講されているので、自分に必要な授業を選んで受講できます。
司法試験合格者の36%を占有

令和4年(前回)の司法試験の合格者数1,781名のうち、全体の36%の641名がアガルートの受講生でした。
司法試験に合格した方のおおよそ半数がアガルートの受講生という圧倒的な実績です。
また、予備試験対策講座の受講生も3年で約7倍となっており、アガルートの実績に多くの受講生が信頼を置いている事が分かります。
もし通信講座を受講するなら、他社を圧倒する合格実績を持つアガルートがおすすめです。
充実したカリキュラムとサポート体制
アガルートは、司法試験・予備試験の合格のために「段階式の正しい順序」で学習することを重要視しているため、段階を踏んで学習できるカリキュラムが整っています。
特に独学では対策が難しい「論文対策」が充実しているため、オンライン添削や質問対応などのサポート体制に力を入れています。
論文はもちろん、各科目の基礎から合格を目指せる初学者向けのコースもあるので、これから勉強を始める高校生の方にアガルートはおすすめです。
アガルートの予備試験講座について詳しく取りあげている記事もあるので、気になる方は以下の記事も合わせてチェックしてみてください!
⇒『アガルートの予備試験最短合格カリキュラムとは?特徴や評判を紹介』
高校生でも予備試験合格を目指せるプランがある

| 最短合格カリキュラム ライト | ・論文問題を中心に対策 ・法科大学院の入試対策 ・コンパクトなカリキュラム |
|---|---|
| 最短合格カリキュラム | ・自分のペースで勉強できる ・部活、学校が忙しい学生にぴったり ・社会人にもおすすめ |
アガルートの予備試験対策講座は、「最速合格カリキュラム」というプランが開設されており、受講することで試験合格に必要な知識が身に付きます。
高校生の方でも、予備試験を受験したいと考えているなら試験合格までの知識が身に付くためおすすめです。
自分のペースで受講できるのが通信講座の特徴なので、部活などで生活が忙しい高校生でも効率よく法律の勉強が出来るでしょう。
司法試験は高校生でも合格できる?弁護士になれるの?|まとめ
司法試験は高校生でも合格できる?弁護士になれるの?|まとめ
- 司法試験は高校生でも合格できる
- 司法試験は受験資格が必要
- 高校生のまま弁護士になることは難しい
- 司法試験合格を目指すなら予備校・通信講座がおすすめ
司法試験は受験するのに年齢制限がないため、高校生でも試験で基準点を採れれば合格できます。
しかし、司法試験には受験資格が存在するため、まずは受験資格を獲得できる予備試験の合格を目指す事から始めましょう。
もし高校生が司法試験に合格しても、弁護士になるために受けなければならない司法修習で兼業・兼学が原則禁止されています。
そのため、すぐにでも弁護士になりたい方は高校を退学、そうでない方は卒業後に司法修習を受ける事になるでしょう。
これらに情報を踏まえて司法試験の合格を目指したい!という高校生の方は、独学ではなく予備校・通信講座の受講をおすすめします!