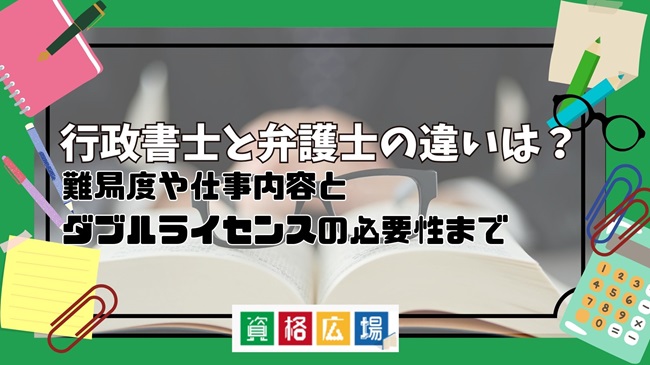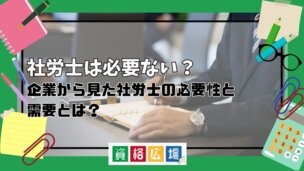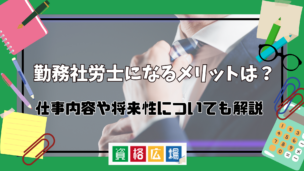行政書士や弁護士などの難関国家資格取得を目指そうと考えた際、「行政書士と弁護士の違いは?」「どっちを目指した方がいいの?」と気になる方もいるのではないでしょうか。
行政書士と弁護士は仕事内容の範囲が一部被っていることから同じような仕事と思われがちですが、実はそんなことはありません。
この記事では、行政書士と弁護士の違いを様々な観点から紹介していきたいと思います。
また、ダブルライセンスを取得することはできるのか、するべきなのかまで解説していきます。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
行政書士と弁護士の1番の違いは?
行政書士と弁護士の一番の違いは、行政書士は書類関係を扱うプロフェッショナルであり、一方で弁護士は法律や憲法を扱うプロフェッショナルということです。
1番の違いであるこの2点を頭の隅に残しつつ、この記事で解説している行政書士と弁護士について見ていくことで、それぞれの仕事について理解する手助けになると思います。
ここからは行政書士と弁護士の1番の違いを踏まえたうえで、行政書士と弁護士の仕事内容をそれぞれ解説していきたいと思います。
行政書士の仕事内容
行政書士は、行政書士法に基づいて行政機関に関する書類や法的書類を作成することに特化した職業です。
行政書士の仕事は大きく4つに分けることができます。
- 官公署に関する書類作成
- 相続関係や売買・贈与に関する権利義務に関する書類作成
- 客観的事実を担保できる事実証明に関する書類
- その他の業務
官公署に関する書類作成
「官公署に関する書類作成」では、様々な官公署に関わる書類の作成や、官公署に提出する書類についての相談業務、書類提出の代理作業をしています。
官公署に関する書類のほとんどは許認可に関するもので、その種類は1万以上あります。
官公署に関する書類の相談業務や、書類提出の代理を専門性がある行政書士が行うことによりユーザーの利便性の向上に貢献しています。
しかし、行政書士法以外の法律が関係する書類作成などの一部業務は行政書士資格では対応することができません。
相続関係や売買・贈与に関する権利義務に関する書類作成
「相続関係や売買・贈与に関する権利義務に関する書類作成」では、土地の売買や相続などの権利義務が発生する場合に必要な書類に関する業務で、代理人になることや相談業務もこれに含まれます。
この権利義務に関する書類は、先ほども挙げたような相続税や贈与税のような当人間で解決しづらいものから、申請書や訴訟などに必要な資料まで幅広く扱い、その書類の種類は数えきれないほど存在します。
客観的事実を担保できる事実証明に関する書類
「客観的事実を担保できる事実証明に関する書類」では、会社の階段や会計書類などを専門性の高く、第三者の立場である行政書士が引き受けることで書類の正当性を示せるというものです。
企業の専属顧問などで行われている作業は「客観的事実を担保できる事実証明に関する書類」の作業がほとんどになります。
行政書士ができる仕事内容は、紹介したもの以外にも存在しますが基本的にはここまで紹介した仕事内容が主になります。
その他の業務
上記の3つは行政書士法によって定められた独占業務の内容ですが、その他にも外国人が日本に出入国するときや、日本で働く際に必要な申請も一定の条件が満たされている状態であれば本人に代わって手続きをすることができます。
また、行政書士の中でも、「特別行政書士」の資格を取得することで弁護士と同じように作成した許認可申請ができるようになります。
特別行政書士を取得することで、自分一人でできる業務範囲を増やすことができ、同じ資格を持つライバルたちと差別化をすることもできるのではないでしょうか。
行政書士の仕事内容まとめ!・官公署に関する書類作成
・権利義務に対する書類作成
・事実証明に関する書類作成
・相談業務や代理業務
弁護士の仕事内容
弁護士は憲法や法律を使い基本的人権の擁護して、社会正義の実現という使命に基づいて仕事をします。
弁護士は法律専門の立場として、法律に関する書類をまとめたり事件や紛争に対して対応していくことが主な仕事内容になります。
弁護士の仕事内容は以下の通りです。
- 紛争性のある事件や事案の対応
- 法律に関する書面作成
- 裁判の代理手続きや弁護人
- 法律相談のアドバイス
- その他業務
紛争性のある事件や事案の対応
弁護士法第72条には弁護士でないものは、紛争に介入または交渉の代理を請け負うことはできないと定められています。
弁護士第72条から報酬を得る目的で「法律事件に関する事務」ということも規定されています。
このことから既に当人の間で発生してしまっている紛争性のある事件や事案は弁護士でないと対応することができません。
この問題に関しては弁護士以外では、書類を作成することはもちろん、相談なども受けることもできません。
法律に関する書面作成
法律に関する書類は日常でもよく目にする領収書からビジネスシーンで目にする報告書や契約書から注文書や委任状まで数えきれないほど存在しています。
上記で挙げたような書類はすべて法律に関わる書類であり、これらは自力でも対応することは可能ですが、法律トラブルを避けるために専門知識を持つ弁護士に依頼をする人や企業がほとんどです。
また、遺言書による相続問題や借用書の作成・対応も法律に関する書類であり、紛争が起きやすいことから弁護士がサポートするケースも多数存在します。
法律相談やアドバイス
何かトラブルが発生した際に弁護士に相談することで問題を解決できる可能性があります。
弁護士に相談できる内容は多くあり、身近な内容から自分たちでは解決しづらい内容まで相談をすることができます。
また、弁護士は犯罪の被害にあってしまった時や犯罪を起こしてしまった時など刑事関係の事案も対応することができます。
弁護士に相談することで、法律に関する問題を解決したり、裁判を起こすこともできます。
裁判の代理手続きや弁護人
弁護士の仕事として一番イメージしやすいのが裁判に関する業務ではないでしょうか。
弁護士の仕事は民事事件の対応が一番多くなり、民事事件には借金に関する問題や労働問題、離婚などの日常生活で起きる紛争があります。
基本的には何かトラブルが発生した際に一度弁護士に相談し裁判を起こすか決めていきますが、弁護士は民事裁判の際、訴訟代理人になることで依頼者の代わりに裁判に出廷することもあります。
行政書士と弁護士の仕事内容まとめ
行政書士と弁護士の仕事内容を簡潔にまとめると行政書士は書類作成のプロであり、弁護士は法律を取り扱うプロであるというような違いがあります。
弁護士は行政書士の独占業務以外は同じような仕事をすることができるが、行政書士では対応できないような範囲まで対応できるのが弁護士になります。
しかし、そんな弁護士も行政書士の独占業務には対応することができないので、可能であればどちらの資格も取得することをおすすめします。
行政書士と弁護士を比較
同じ法律系の資格とは言え、行政書士と弁護士にはそれぞれ独占業務があることから仕事内容は大きく違います。
続いては、行政書士と弁護士の資格取得の難易度や、年収の違いまで比較していきます。
まずは、行政書士と弁護士の基本情報を下の表にまとめてみました。
| 行政書士 | 弁護士 | |
|---|---|---|
| 年収 | 約580万円 | 約950万円 |
| 推奨勉強時間 | 約3,000~5,000時間 | 約3,000~5,000時間 |
| 合格率 | 35%前後 | 10%前後 |
| 資格取得人数 | 約42,000人 | 約50,000人 |
この表にあるように行政書士と弁護士は年収から推奨勉強時間まで、様々な点で大きく異なっていることが分かると思います。
行政書士と弁護士|年収の比較
厚生労働省の調査によると令和4年の平均年収は、行政書士の平均年収は約580万円で、弁護士の平均年収が約970万円という結果が出ています。
行政書士と弁護士は似て非なる仕事ですが、資格取得の難易度や取得した際にできる仕事内容の量から年収は弁護士の方が高い設定になっています。
しかし、その分弁護士はテストの難易度が高いだけでなく、取得までに時間や金額・労力が圧倒的にかかることから、行政書士のほうが目指しやすい資格と言えるのではないでしょうか。
【弁護士・行政書士の年収についてもっと詳しく知りたい方はコチラ!】
行政書士と弁護士|資格取得の難易度の違い
行政書士と弁護士はどちらも難関資格と言われています。
この記事を読んでいる人の中には「どっちの資格の方が難しい?」時になる方もいると思いますので、合格難易度の側面で行政書士と弁護士を比較していきます。
行政書士の難易度
行政書士は合格率が10%前後であることから難関資格と言われています。
令和5年では総受験者数が約59,460人中、合格者は6,571人と、合格率が13.98%となっています。
受験はだれでも受けることができますが、その難易度から、合格までに2~3年かかる人も多く、制度の高い知識が問われるため、独学で合格を目指すのは難しいと言われています。
行政書士の資格取得を目指している方で勉強方法に迷っている方は初めに独学で勉強を始めて、少し難しいと感じてから予備校に通うといったようにしてみるのはいかがでしょうか。
アガルートアカデミーなら行政書士試験の出題カバー率は驚異の97,8%!
弁護士の難易度
弁護士になるために必要な司法試験の合格率は近年上がってきていると言われており、現在の合格率は35%前後となっています。
司法試験自体の難易度は、勉強時間が約3,000~5,000時間ほど必要と言われています。
一見すると合格率は高いように思えますが、司法試験を受けるためには、例年合格率5%以下の予備試験に合格するか、法科大学院を修了していないと司法試験を受験することができません。
つまり、司法試験の合格率が35%前後と難関資格の中でも合格率が高いのは、予備試験や法科大学院という厳しい壁を乗り越えた人たちが受験しているからです。
裏を返すと、司法試験は合格率が5%と難しさを誇る予備試験を合格できた人たちや法科大学院を修了した人の中から、3割ほどしか合格できないという超難関資格である、ということになります。
弁護士になるために必要な段階をまとめたので詳しくは下記をご覧ください。
~弁護士になるまで~
- ➀予備試験合格or法科大学院の修了
- 司法試験を受験するためには、司法試験並みの何度と言われる予備試験を合格する必要があります。法科大学院を修了していれば予備試験をスキップすることができます。
- ➁司法試験の受験
- 国家試験にあたる司法試験を合格すればすぐ弁護士になれるわけではありません。弁護士になるためには資格の
- ➂司法修習を修了
- 約1年間の間、実務スキルから職業意識を徹底的に学びます。実際の現場を学ぶことで、1年目からプロとしてしっかり働き始めることができます。
- ④司法修習生孝試(二回試験)
- 司法修習を修了したのちに通称2回試験に受験します。合格率は約90%と非常に高いことから司法修習をしっかり学んでいれば問題なく合格できるのではないでしょうか。
- ⑤法曹資格取得
- 2回試験を合格することで初めて弁護士になる資格を得ることができます。日本弁護士連合会の登録することができれば弁護士として活動を始めることができます。
弁護士になるまでには予備試験や法科大学院が前にあるだけでなく、司法試験を合格してからも約1年間の研修と2回試験という最終テストが待ち受けています。
何度も試験があり、研修期間もあることから弁護士を目指すには長い期間、勉強を続ける精神力と合格への高い意識が必要になります。
司法試験は独学でも目指すことは可能ですが、非効率で現実的ではないため、司法試験を受験したいと考えている方は効率的に勉強ができる、予備校に通ってみるのはいかがでしょうか。
行政書士と弁護士の難易度まとめ
上記でそれぞれの合格率などの点から難易度を解説してきました。
行政書士と弁護士は合格率や試験内容の点からどちらも難関資格ではありますが、難易度で言ったら間違いなく弁護士の資格の方が取得するのが難しいと言えます。
行政書士と弁護士のどちらを目指すべきか迷っている方は、難易度や仕事内容が一部同じであることからも行政書士から目指してみるのはいかがでしょうか。
行政書士と弁護士の資格を取得したいと考えている方は、本当に自分がやりたい仕事を今一度考えてから目標を立ててみてはいかがでしょうか。
行政書士と弁護士|試験内容の違い
行政書士と弁護士の試験内容は一部類似している点があるものの、基本的な構成やテスト期間は大きく異なります。
行政書士と弁護士の司法試験を表にまとめてみたのでまずはそちらをご覧ください。
| 行政書士 | 弁護士の司法試験 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受験資格 | ・特になし | ・法科大学院の修了or予備試験の合格 | ||
| 試験範囲 | 【法令科目】 ・基礎法学 ・憲法 ・行政法 ・民法 ・商法 |
【出題数】 46問/60問 【配点】 244点/300点 |
【短答式試験】 ➀民法 75分 ➁憲法 50分 ➂刑法 50分 |
【出題数】 ➀約35問 ➁約25問 ➂約25問【配点】 ➀75点/175点 ➁50点/175点 ➂50点/175点 |
| 【一般知識】 ・政治 ・経済 ・情報通信 ・個人情報保護 ・文章理解 |
【出題数】 14問/60問 【配点】 56点/300点 |
【論文式試験】 ➀憲法 120分 ➁行政法 120分 ➂民法 120分 ➃商法 120分 ➄事訴訟法 120分 ➅刑法 120分 ➆刑事訴訟法 120分 ➇*選択科目180分 |
【配点】 各100点満点/800 【配点】 ➀~➆は不明 ➇では50点の問題が2つ出題 |
|
| 合格率 | ・5%以下 | ・35%前後 | ||
| 試験評価方法 | ・絶対評価 | ・相対評価 | ||
| 合格条件 | ・一般知識問題で24点以上獲得すること ・法令科目で122点以上以上獲得すること ・合計で180点以上獲得すること |
・短答式試験では各科目の点数がすべて4割を超していること。 (一つでも4割を超えないものがあった場合、どんな点数でも不合格) |
||
*選択科目の種類は、租税法・倒産法・経済法・労働法・環境法・知的財産法・国際関係(公法系)・国際関係法(私法系)の8つの中から選ぶことができます。
行政書士の試験は3時間ほどで終了しますが、司法試験ではその試験範囲の広さから合計で4日間も試験が行われます。
司法試験の短答式試験では、各科目で点数が4割に満たないものが1つでもあった場合、全体の合格点を超えていても“不合格”になってしまいます。
また、行政書士試験は絶対評価ですが、司法試験は相対評価で合格者が決まるのも違いの1つです。
ダブルライセンスする必要性はある?
結果からお伝えすると行政書士と弁護士のダブルライセンスは必要ありません。
どちらも独占業務があり、仕事量も多いため、ダブルライセンスを取って両方の仕事を行うというのは至難の業でしょう。
また、片方の資格さえ持っていれば十分に稼ぐ事ができますし、わざわざダブルライセンスを取らなければいけないという事は全くありません。
ダブルライセンスを持つメリット
ただし、キャリアアップやスキルアップを目指してダブルライセンスを取る事はおすすめできます。
行政書士と弁護士のダブルライセンスをすることで、どちらの独占業務もできるようになるため、対応できる幅が大きく広げることができるからです。
既に弁護士の資格を取得していて、行政書士の資格を取得してない方は協会に申請することで試験を受けずに資格取得ができるので、すでに弁護士の資格を取得している方の中で行政書士の資格が必要だと感じた方は申請してみてはいかがでしょうか。
既に行政書士の資格を取得していてこれから弁護士の資格を取得したいと考えている方は、行政書士は弁護士の仕事範囲と一部被っている箇所があるのため比較的に勉強が始めやすいと思います。
行政書士と弁護士の仕事内容で一部重なる点があることからも、行政書士と弁護士の資格で迷っている方は2つを比較して難易度が低い行政書士の資格に向けての勉強を最初にすることで、弁護士の資格取得にも繋げることができるのではないでしょうか。
行政書士と弁護士の資格のダブルライセンスは仕事で対応できる幅が広がることで、キャリアアップにも繋げることができるためダブルライセンスは有意義であるといえるでしょう。。
行政書士と弁護士の仕事内容や年収・難易度の違いまとめ
行政書士は書類関係を取り扱うプロフェッショナルであり、弁護士は法律や憲法を取り扱うプロフェッショナルであることからも分かるように、業務内容は大きく異なります。
しかし、行政書士と弁護士には一部、業務内容が似ている点があるためどちらを目指すべきか迷っている方はまず行政書士の資格を目指してみるのはいかがでしょうか。
また、行政書士と弁護士のダブルライセンスをすることで、顧客の相談に対応できる幅が広がるため無駄になることはなく、むしろ大きな強みとして将来の仕事に生かしていくことができるのではないでしょうか。
もちろん、片方の資格で十分稼ぐ事もできますので、自分がどんな仕事をしたいのか、自分の希望する働き方等と比較して検討してみてください。