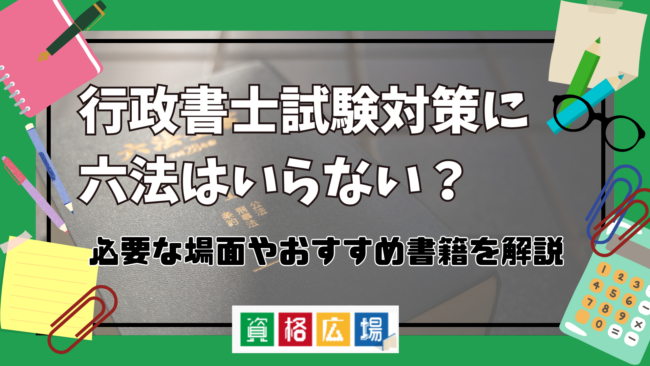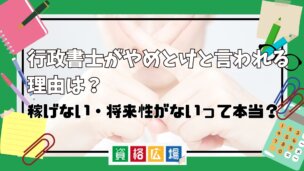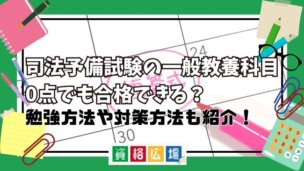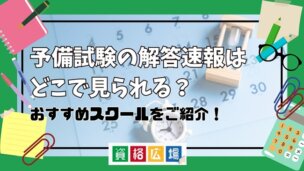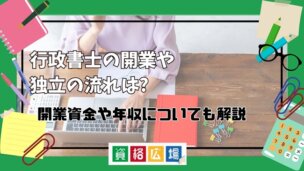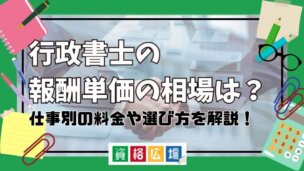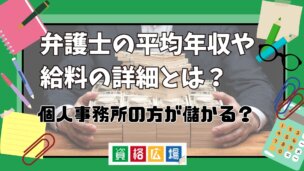行政書士試験の勉強をしていて、「六法は必要なの?いらないの?」という疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
結論から述べると、「行政書士試験に合格する」という点にフォーカスした時六法は必要ありません。
しかし、条文の理解を深めたい方や行政書士として開業することを考えている方は六法を持っておくと便利です。
こちらの記事では、行政書士試験対策で六法が「いらない」と言われる理由・六法のおすすめの使い方・おすすめの六法などを解説していきます。
行政書士試験の合格を目指している方に役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
行政書士講座ならアガルート!

行政書士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
令和5年度は全国平均の4.01倍の56.11%と高い合格率が出ています。
通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。
行政書士試験に合格するだけなら六法はいらない
冒頭でも述べたように、「行政書士試験に合格するだけ」であれば六法はいらないと言えます。
行政書士試験では条文の読解と理解が重要ですが、重要な条文はテキストや参考書にも掲載されているためわざわざ六法で確認する必要はありません。
テキストや参考書で強調されている条文を読み込んで内容を理解すれば、本試験には概ね対応できるでしょう。
実際六法を全く読まずに行政書士試験に合格している人も多いため、巷で見かける「六法はいらない」という意見は間違っていません。
行政書士試験の勉強をしている人の中には「六法を読むのは大変」と感じている人もいますが、行政書士試験に合格するために六法が必須ということはないため、「無理に六法を読まなくてもいいんだ」と心にゆとりを持って試験勉強を進めていきましょう。
行政書士試験合格後の実務まで見据える場合は六法は必要
繰り返しになりますが、「行政書士試験に合格するだけ」であれば六法は必要ありません。
しかし、条文の理解を深めたい方やテキストの勉強だけでは不安な方は六法を用意することをおすすめします。
ここでは、六法が必要になる場合や六法で勉強するメリットについてご紹介します。
条文に慣れ親しむことができる
六法を読むことで、各法律の条文に慣れ親しみ実質的意義を学ぶことが可能です。
行政書士試験に合格したあとに開業を検討している場合、仕事を受けるために「実務的な知識」まで有している必要があります。
六法の読解を通じて行政書士の仕事で使う法律知識を幅広く習得できるため、行政書士の実務をこなす際に非常に役立つでしょう。
そのため開業を検討している方にとって「六法はいらない」という情報は当てはまらず、六法を読み込むことが重要となります。
結果的に条文を理解して得点力アップにつながる
六法を読むことで、実務的な知識を習得できるだけでなく条文の理解を深めることにも繋がります。
行政書士の試験問題では条文の理解や結論を問う問題が多く出題されるため、六法を読むことで得点力をアップさせることができます。
市販のテキストや参考書にも重要な条文は掲載されていますが、より多くの条文に目を通すためには六法が必要です。
六法を読むことは結果的に行政書士試験の得点力アップに繋がるため、1冊手元に置いておくと役立つでしょう。
行政書士試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!
行政書士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。
合格者には受講費全額返金orお祝い金5万円の特典もあるのでモチベーションの維持も期待できます!
最短ルートで合格が目指せる!
アガルート公式HPはこちら
行政書士試験対策における六法のおすすめの使い方
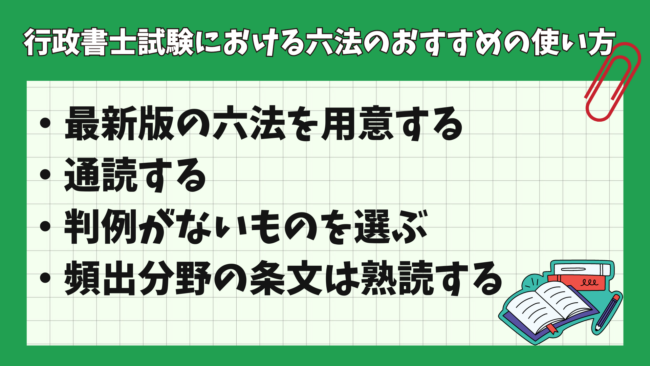
六法は使い方次第で行政書士試験対策の勉強を効率化してくれる存在です。
しかし、普段六法を見る機会がないと「六法の使い方がわからない」という悩みを抱えてしまうこともあるでしょう。
以下では、行政書士試験対策におすすめの六法の使い方を解説します。
最新版の六法を用意する
六法を用意して勉強する際には、最新版の六法を用意することが大切です。
法律は時代背景やニーズに合わせて改正されるため、毎年のように法改正が行われます。
古い条文を読んでも試験に役立たないばかりか実務でも使えないため、最新の六法は不可欠です。
本試験や実務で使える知識を得るためにも、購入する際には必ず最新版の六法かどうかを確認してみてください。
通読する
六法は「通読する」という使い方が非常に効果的です。
六法を通読することで法律の全体像を把握でき、出題範囲の法令を体系的に理解できます。
特に法律を初めて本格的に勉強する人の場合、法律の全体像を把握することで「勉強内容をイメージする」ことができます。
過去問を見ても本試験で法律の条文がそのまま出題されることが多くあるため、通読していれば難なく対応できるでしょう。
なお六法を通読するのは時間がかかってしまうため、1〜2回で十分です。
判例がないものを選ぶ
六法には、条文のあとに判例がついているものとついていないものがあります。
「勉強のしやすさ」を重視する場合、判例がない六法で十分です。
「判例あり」の六法は判例を調べる際に便利ですが、情報量が多く肝心の条文を調べたいときに不便です。
「判例なし」は判例を調べることはできないもののスムーズに条文を調べることができるメリットがあります。
行政書士試験に合格し、実務的な知識を習得するタイミングで判例付きの六法を通読すれば良いでしょう。
頻出分野の条文は熟読する
行政書士試験では、ほぼ毎年のように出題される頻出分野・重要論点があります。
そのため六法を読む際は頻出分野の条文は特に意識して熟読することをおすすめします。
狙われやすい条文を完璧に理解していれば、応用レベルの問題が出てきても対応することが可能です。
また頻出分野の条文を読むことは得点力アップにも繋がるため、非常に有意義な勉強となります。
六法の種類
一口に六法と言っても、種類は1つだけではありません。
六法の種類ごとに特徴があり、おすすめの使い方も異なります。
ここからは六法の種類について見ていきます。
自身のがイメージしている使い方に合った六法を用意すると良いでしょう。
判例の有無
前述したように、六法の中には判例が載っているものと載っていないものがあります。
条文の理解に加えて判例の確認も行いたい場合は判例有りの六法を準備すると良いでしょう。
しかし判例があると全体的に分厚くなってしまい持ち運びの際に不便になってしまう可能性がある点に注意が必要です。
「条文の確認だけできれば良い」という方であれば判例無しの六法で十分です。
サイズの違い
六法には、持ち運びに便利なコンパクトサイズの六法や判例なども載っている大きいサイズの六法もあります。
「とりあえず六法を読んでおきたい」という方は、コンパクトな六法を使うのがおすすめです。
具体的には、有斐閣『ポケット六法』や三省堂『デイリー六法』が代表的で、手軽な上に値段も安くなっています。
とりあえず六法を読んでおきたい方や外出先で勉強する時間が長い方は、コンパクトサイズの六法を用意しておくと良いでしょう。
行政書士試験対策に特化しているか
三省堂『行政書士合格六法』のように、行政書士試験対策に特化した六法もあります。
試験で出題されやすい法令のみを収録している点が特徴で、コンパクトで持ち運びやすいものが多いです。
本試験の問題を解く上で役立つアドバイスが載っているものもあり、得点力アップにも繋がるでしょう。
テキストを読んだだけでは理解が不十分のときに役立つため、条文理解を深めたい方におすすめです。
行政書士試験対策におすすめの六法
それでは最後に、行政書士試験対策におすすめの六法を具体的に紹介していきます。
各六法に特徴があるため、使い方などをイメージしながら必要な六法を用意してみてください。
行政書士受験必携六法(東京法経学院)

引用:東京法経学院公式サイト
『行政書士受験必携六法』は試験に合格するために必要な法令を収録しており、重要法令の条文には「判例要旨」も収録されています。
本試験でも狙われやすい重要条文には「ワンポイントアドバイス」が付されているため、効果的な試験対策を行うことができます。
1,000ページ程度の六法でボリュームも重すぎないため、テキストや参考書だけでは不安な方におすすめです。
行政書士 試験六法 2022年度(W(WASEDA)セミナー)

引用:TAC出版
『行政書士 試験六法 2022年度』は、条文だけでなく判例も収録されているため「判例を理解するのが苦手」という方におすすめできます。
さらに五肢択一式・多肢選択式・記述式の本試験の過去問を該当する条文ごとに掲載しているため、多角的に学習することも可能です。
条文と択一式問題が2色分けされており、視覚的にも理解しやすいメリットもあります。
デイリー六法 三省堂

引用:三省堂
『デイリー六法』は2,000ページほどのボリュームがある六法です。
条文中にかっこ書きで条文内容が説明されているため、スムーズに条文の内容を理解できます。
またカッコ書きアミ掛けで条文の骨格や定義・除外規定を明確化する工夫が施されており、勉強しやすい設計になっています。
「読みやすい六法が欲しい」という方は、デイリー六法が好相性である可能性が高いでしょう。
ケータイ行政書士 ミニマム六法(三省堂)
引用:販売サイト
『ケータイ行政書士 ミニマム六法』は「行政書士受験六法のトップブランド」とも言われており、試験合格に必要な条文が厳選されています。
また重要キーワードは2色刷りされているため、重要なポイントも分かりやすくまとめられている点が特徴です。
「ケータイ」とある通り300ページで持ち運びにも便利なため、通読したい方におすすめの六法です。
行政書士合格六法(三省堂)

引用:三省堂
『行政書士合格六法』は、合格に必要な法令を厳選して収録した試験対策向けの六法です。
重要条文はマーカーで表わされており、広い行間で2色刷りとなっているため視覚的にわかりやすい特徴があります。
また重要ではない箇所は「飛ばし読み」と記載されているため、重要な箇所のみ勉強できる設計となっており非常に便利です。
また必要に応じてメモを取れる「Notes」欄も備えており、ノートを取りながら条文理解を深めることができます。
また555ページにまとまったコンパクトな六法となっているため持ち運びにも便利です。
行政書士試験の六法まとめ
「行政書士に六法はいらない」と言われることがありますが、行政書士試験に合格するだけであれば確かに六法は必要ないと言えます。
しかし、行政書士として勤務する予定・希望があり実務での活躍を見据えている場合は六法があったほうが良いでしょう。
こちらの記事で紹介した六法はいずれもおすすめできますが、特徴が異なるため自身のニーズに合っている六法を選ぶことが大切です。
「自分に六法は必要なのか、いらないのか」を判断したうえで、「必要」と判断した場合は自分に最適な六法を用意すると良いでしょう。