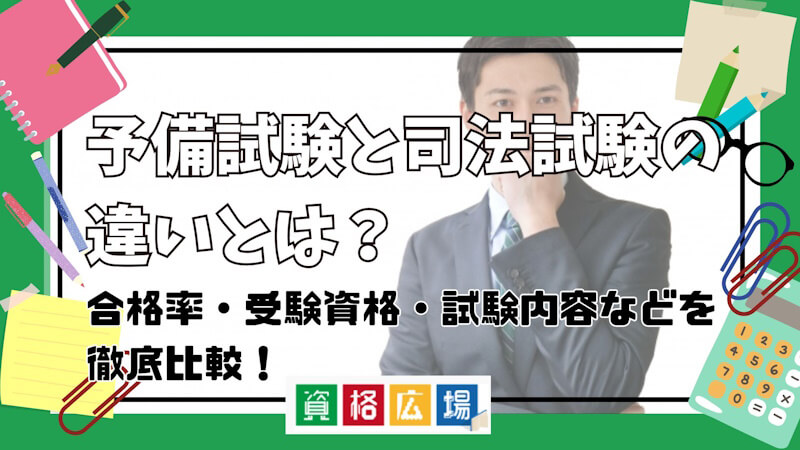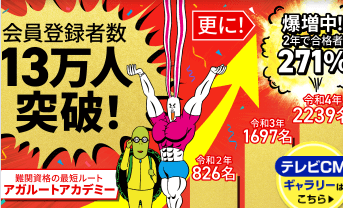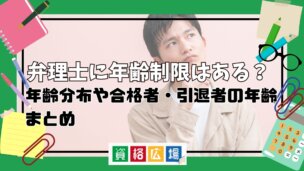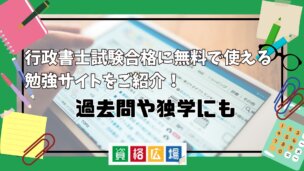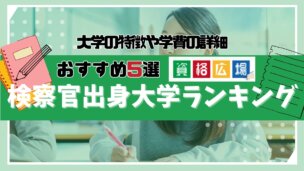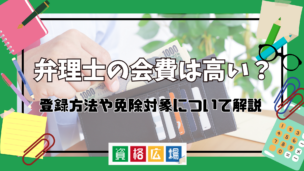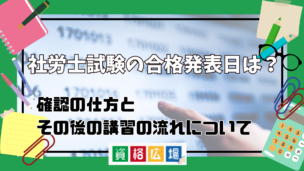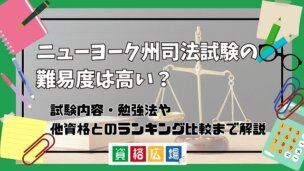予備試験と司法試験の違いは以下の通りです。
- 予備試験・・・司法試験の受験資格を取るための試験
- 司法試験・・・弁護士や検察官、裁判官になるための国家資格試験
予備試験に合格することで、司法試験の受験ラインに立てます。
また、司法試験は予備試験ルートの他、法科大学院ルートもある点が特徴です。
この記事では、予備試験と司法試験の受験資格・合格率・試験内容・難易度の違いを詳しく紹介します。
予備試験ルートのメリット・デメリット、司法試験に合格するポイントもあわせて解説します。
記事後半では、予備試験ルートと法科大学院ルート、どちらを選ぶべきかも解説しているので、ぜひ最後まで読んでください。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
予備試験とは司法試験の受験資格取得ルートの一つ
予備試験(司法試験予備試験)は、法科大学院を経ずに司法試験の受験資格を得るための重要な試験です。
法学に関する基礎的な知識から応用力までを問われます。
一方で司法試験は、弁護士、検察官、裁判官といった法曹資格を得るための国家試験です。
予備試験合格者または法科大学院修了者が受験できるものであり、法律実務に関する深い知識と応用力が求められます。
以下に、予備試験と司法試験の違いをまとめました。
- 予備試験・・・司法試験の受験資格を得るための試験
- 司法試験・・・弁護士、検察官、裁判官になるための国家試験
予備試験に合格することで、法科大学院修了者と同等の資格を取得し、司法試験への挑戦が可能となります。
予備試験の合格率は3~4%程度と低いですが、予備試験ルートの司法試験受験者の合格率は、なんと90%前後と高い点が特徴です。
また、法科大学院ルートとは異なり、予備試験ルートだと受験資格がなく、誰でも受験できます。
予備試験の難易度が高いと言われる理由とは?司法試験とも比較して解説
予備試験と司法試験の違い
予備試験と司法試験の違いの主な違いを、以下にまとめました。
- 予備試験と司法試験の違い①合格率
- 予備試験と司法試験の違い②受験資格
- 予備試験と司法試験の違い③試験内容
- 予備試験と司法試験の違い④難易度
それぞれの違いを詳しく見てみましょう。
予備試験合格後から司法試験までに勉強すべきことや就職活動について紹介
予備試験と司法試験の違い①受験資格
| 試験 | 受験資格 |
|---|---|
| 予備試験 | 受験資格がなく、誰でも受験できる |
| 司法試験 | 予備試験に合格する、または法科大学院を修了する |
予備試験は、学歴や実務経験を問わず、誰でも受験可能です。
これに対し、司法試験は予備試験に合格するか、法科大学院を修了することで初めて受験資格を得ることができます。
予備試験に合格すれば、法科大学院を経ずに司法試験を受けられるため、時間と費用の節約が可能です。
予備試験と司法試験の違い②合格率
| 試験 | 合格率 |
|---|---|
| 予備試験 | 3~4% |
| 司法試験 | 40%前後 |
引用元:法務省『司法試験予備試験の結果について』、『司法試験の結果について』
予備試験の合格率は非常に低く、例年3~4%程度です。
一方、司法試験の合格率は40%前後であり、決して容易な試験ではありませんが、予備試験に比べると高い数字です。
しかし、予備試験ルートの受験者は以下の通り90%前後と、司法試験で安定して高い合格率を誇ります。
| 年度 | 受験者数 | 最終合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度(2024年) | 475 | 441 | 92.8% |
| 令和5年度(2023年) | 353 | 327 | 92.6% |
| 令和4年度(2022年) | 405 | 395 | 97.5% |
| 令和3年度(2021年) | 400 | 374 | 93.5% |
| 令和2年度(2020年) | 423 | 378 | 89.4% |
| 令和元年度(2019年) | 385 | 315 | 81.8% |
引用元:法務省『司法試験の結果について』
【最新】予備試験の合格率は?合格者数・合格ラインの状況や大学別・社会人合格の割合を紹介
予備試験と司法試験の違い③試験内容
| 試験 | 試験内容 | 試験科目 |
|---|---|---|
| 予備試験 | 短答式試験 | 憲法 行政法 民法 商法 民事訴訟法 刑法 刑事訴訟法 一般教養科目 |
| 論文式試験 | 憲法 行政法 民法 商法 民事訴訟法 刑法 刑事訴訟法 民事実務基礎 刑事実務基礎 選択科目 |
|
| 口述試験 | 民事実務基礎 刑事実務基礎 |
|
| 司法試験 | 短答式試験 | 民法 憲法 刑法 |
| 論文式試験 | 憲法 行政法 民法 商法 民事訴訟法 刑法 刑事訴訟法 選択科目 |
予備試験は短答式試験、論文式試験、口述式試験の3段階で構成されており、幅広い法律知識を問います。
司法試験は短答式試験、論文式試験のみです。
口述試験はありません。
上記表の通り、予備試験と司法試験は共通する試験科目が多いです。
予備試験の口述試験で必要な知識は、司法試験の論文式試験で活用できます。
予備試験対策を徹底することで、司法試験対策も同時にできるので効率的です。
司法試験短答式と論文式試験には足切りがある?試験内容や対策を徹底解説!
予備試験と司法試験の違い④難易度
予備試験の合格率は3~4%、司法試験の合格率は40%前後で、合格率は予備試験の方が圧倒的に低いです。
しかし、合格率が難易度に比例するとは一概には言えません。
誰でも受験できる予備試験はその分受験者数も多く、相対的に合格率が下がりやすいです。
一方、司法試験は一定の受験資格を満たす必要があることが、合格率の高さに影響していると考えられます。
なお、予備試験と司法試験の試験内容は共通点が多く、予備試験の合格者の90%前後は司法試験に合格しています。
そのため、予備試験を攻略すれば、司法試験に合格する確率を高められるでしょう。
予備試験ルートで司法試験を受けるメリット
司法試験を受験するには、予備試験ルートと法科大学院ルートがありますが、予備試験ルートの主なメリットを紹介します。
- 法科大学院の学費がかからない
- 在学中から試験対策ができる
- 早期に司法試験を受験できる
法科大学院の学費がかからない
予備試験ルートの最大のメリットの一つは、法科大学院に通う必要がないため学費がかからない点です。
法科大学院では、通常2~3年間の在学期間中に数百万円の学費が必要です。
一方で予備試験ルートでは、独学や通信講座を利用することで、学費を大幅に抑えることができます。
経済的な負担を軽減できるため、特に学費を負担に感じる方にとっては魅力的な選択肢となるでしょう。
司法試験・予備試験の受験にかかる費用は平均いくら?予備校講座の受講料金や学習費用・受験費用の内訳まで解説
在学中から試験対策ができる
予備試験ルートでは、大学在学中から司法試験に向けた試験対策を進めることができます。
法科大学院で学ぶ必要がなく、効率的に司法試験の準備を進めることが可能です。
予備試験に向けての勉強を早めに開始することで、試験範囲の理解を深めることができ、合格への道を確実にします。
予備試験合格者の中には10代の方もいます。
早期に司法試験を受験できる
予備試験に合格すれば、法科大学院を経ずに早期に司法試験を受験できる点も大きなメリットです。
法科大学院修了者が司法試験を受ける場合、通常3年ほどの学習期間が必要ですが、予備試験ルートならばその期間を短縮できます。
これにより、法曹界でのキャリアを他のルートよりも早くスタートさせることが可能となります。
司法試験予備試験の効果的な勉強法とは?最短スケジュールで合格するための方法を解説
予備試験ルートで司法試験を受けるデメリット
予備試験ルートにはメリットが多い一方で、いくつかのデメリットも存在します。
- 予備試験の合格率が低い
- 学習スケジュールの管理が難しい
メリットどデメリットどちらも把握しておきましょう。
予備試験の合格率が低い
| 試験 | 合格率 |
|---|---|
| 予備試験 | 3~4% |
| 司法試験 | 40%前後 |
予備試験は、司法試験の受験資格を得るための難関試験であり、その合格率は約3~4%程度と低いです。
司法試験の合格率は40%前後で、合格率の差は大きいことが分かります。
ただし、予備試験の合格者の司法試験合格率は90%前後と高いです。
予備試験対策を徹底することで、司法試験に合格する可能性を高められます。
予備試験の論文の書き方や模範解答例を解説!答案構成の書き方や目安時間・初めてでも書けるコツを紹介
学習スケジュールの管理が難しい
予備試験ルートでは、学習スケジュールの管理が自己責任である点もデメリットとして挙げられます。
法科大学院では、体系的なカリキュラムが提供され、教授陣やクラスメートからのサポートが受けられます。
しかし予備試験ルートでは独学が主となるため、自分で計画を立て、学習を進める必要があります。
独学だとスケジュール管理が難しく感じたり、挫折する人も多いです。
効果的な学習を進めるためには、自己管理能力が重要となります。
予備試験ルートで司法試験に合格するポイント
予備試験ルートで司法試験に合格するためには、以下の重要なポイントを押さえておきましょう。
- 過去問題を徹底分析する
- 論文対策の徹底強化をする
- 短答式で確実に点を取る
- 予備校・通信講座を利用する
司法試験予備試験の勉強時間は?合格までの勉強計画・1日の勉強スケジュールを社会人・大学生向けに解説
過去問題を徹底分析する
予備試験ルート司法試験に合格するためには、過去問題の徹底分析が不可欠です。
過去問題を解くことで、出題傾向や試験の難易度を把握し、自分の弱点を発見することができます。
また、頻出問題を把握しておくことで、効率的に学習を進めることができます。
徹底的な分析を行い、自分の学習計画に反映させることが、合格への近道となるでしょう。
司法試験予備試験の出題趣旨はいつ読むべき?見方や活用方法まとめ
論文対策の徹底強化をする
司法試験において、論文式試験は合否を左右する重要な試験です。
論文対策を徹底的に行い、論理的な思考力や文章力を磨くことが求められます。
このため、模擬試験や過去の論文問題を解くことが効果的です。
予備校や通信講座の指導を活用して、論文の書き方や構成のポイントを学んで試験本番に備えてください。
司法試験・予備試験の民法が難しい理由は?論文式試験の勉強法と学習スケジュール・おすすめ参考書を紹介
短答式で確実に点を取る
短答式試験は、司法試験における基礎知識を問われる部分であり、ここで確実に点を取ることが重要です。
解答の正確さとスピードが求められるため、日頃から反復学習を行い、知識を定着させましょう。
また、模擬試験を利用して、試験時間内に解答できるように練習を重ねることをおすすめします。
予備試験の短答試験の時間配分はどうする?配点や問題数から考えてみる
予備校・通信講座を利用する
予備試験や司法試験に向けた学習では、予備校や通信講座を利用することも大いに役立ちます。
効率的な学習方法や試験のコツが学べるため、試験本番までに自信が自然と身に付きます。
独学では難しいと感じる部分を補完し、試験に向けた総合的な対策を行える点も予備校や通信講座のメリットです。
令和6年(2024年)予備試験・司法試験の試験日程
以下の通り、予備試験および司法試験の最新の日程を紹介します。
- 令和6年(2024年)予備試験の日程
- 令和7年(2025年)予備試験の日程
- 令和6年(2024年)司法試験の日程
- 令和7年(2025年)司法試験の日程
しっかりとスケジュールを把握し、計画的に準備を進めることが合格への第一歩です。
令和6年(2024年)予備試験の日程
令和6年(2024年)予備試験の日程は以下の通りです。
| 試験日 | 試験内容 | 試験科目 |
|---|---|---|
| 7月14日(日) | 短答式試験 | 民法・商法・民事訴訟法 憲法・行政法 刑法・刑事訴訟法 一般教養科目 |
| 9月7日(土)、8日(日) | 論文式試験 | 憲法・行政法 刑法・刑事訴訟法 選択科目 法律実務基礎科目(民事・刑事) 民法・商法・民事訴訟法 |
| 令和7年1月25日(土)、26日(日) | 口述試験 | 法律実務基礎科目(民事) 法律実務基礎科目(刑事) |
合格発表は以下になります。
| 試験 | 合格発表 |
|---|---|
| 短答式試験 | 8月1日(木) |
| 論文式試験 | 12月19日(木) |
| 口述試験 | 令和7年2月6日(木) |
令和7年(2025年)予備試験の日程
令和7年(2025年)の予備試験の日程も押さえておきましょう。
| 試験日 | 試験内容 | 試験科目 |
|---|---|---|
| 7月20日(日) | 短答式試験 | 民法・商法・民事訴訟法 憲法・行政法 刑法・刑事訴訟法 一般教養科目 |
| 9月6日(土)、7日(日) | 論文式試験 | 憲法・行政法 刑法・刑事訴訟法 選択科目 法律実務基礎科目(民事・刑事) 民法・商法・民事訴訟法 |
| 令和7年1月24日(土)、25日(日) | 口述試験 | 法律実務基礎科目(民事) 法律実務基礎科目(刑事) |
合格発表は以下の通りです。
| 試験 | 合格発表 |
|---|---|
| 短答式試験 | 8月7日(木) |
| 論文式試験 | 12月18日(木) |
| 口述試験 | 令和7年2月5日(木) |
司法試験予備試験の持ち物とは?短答式論文式で異なる?試験前に準備するもの
令和6年(2024年)司法試験の日程
令和6年司法試験の日程を以下にまとめました。
| 試験日 | 試験内容 | 試験科目/時間 |
|---|---|---|
| 7月10日(水) | 論文式試験 | 選択科目(3時間) 公法系科目第1問(2時間) 公法系科目第2問(2時間) |
| 7月11日(木) | 民事系科目第1問(2時間) 民事系科目第1問(2時間) 民事系科目第1問(2時間) |
|
| 7月13日(土) | 刑事系科目第1問(2時間) 刑事系科目第1問(2時間) |
|
| 7月14日(日) | 短答式試験 | 憲法(50分) 民法(75分) 刑法(50分) |
令和7年(2025年)司法試験の日程
令和7年(2025年)の司法試験の日程もすでに公示されているので紹介します。
| 試験日 | 試験内容 | 試験科目/時間 |
|---|---|---|
| 7月16日(水) | 論文式試験 | 選択科目(3時間) 公法系科目第1問(2時間) 公法系科目第2問(2時間) |
| 7月17日(木) | 民事系科目第1問(2時間) 民事系科目第1問(2時間) 民事系科目第1問(2時間) |
|
| 7月19日(土) | 刑事系科目第1問(2時間) 刑事系科目第1問(2時間) |
|
| 7月20日(日) | 短答式試験 | 憲法(50分) 民法(75分) 刑法(50分) |
令和7年(2025年)に司法試験受験を検討している方は、試験日から逆算して長期的な学習計画を立てましょう。
予備試験ルートの方が法科大学院ルートより司法試験の合格率が高い
予備試験ルートを選ぶことで、法科大学院ルートよりも司法試験の合格率が高くなる傾向があります。
以下に、予備試験ルートと法科大学院ルートで、直近の合格率の違いをまとめました。
| 年度 | 予備試験ルート | 法科大学院ルート |
|---|---|---|
| 令和6年(2024年) | 92.8% | 34.8% |
| 令和5年(2023年) | 92.6% | 40.7% |
| 令和4年(2022年) | 97.5% | 37.7% |
| 令和3年(2021年) | 93.5% | 34.6% |
| 令和2年(2020年) | 89.4% | 32.7% |
| 令和元年(2019年) | 81.8% | 29.1% |
引用元:法務省『司法試験の結果について』
上記の通り、法科大学院ルートに比べて、予備試験ルートの方が司法試験の合格率が圧倒的に高いです。
ただし、予備試験自体の合格率は3~4%と非常に低いです。
また、予備試験の受験者数は400人前後が一般的ですが、法科大学院ルートの受験者数は4,000人前後と10倍近い差があります。
合格率=難易度とは限りません。
予備試験ルートと法科大学院ルートのどちらが自分にとって最適なのか、勉強方法・費用・時間などをしっかり比較したうえで受験資格を取得しましょう。
予備試験ルートで司法試験を受験するのが向いている人
予備試験ルートで司法試験を受験するのが向いている人には、以下のような特徴があります。
- 独学でも効率よく学べる人
- 法科大学院に通うのが難しい人
- 法曹を目指す強い意志がある人
- 経済的な負担を抑えたい人
国家資格年収ランキングTOP10!年収の高い理由や取得する方法を解説
独学でも効率よく学べる人
予備試験ルートでは、独学での学習が主となります。
そのため、自己管理能力が高く、効率的に学習を進められる人に向いています。
計画的に勉強を進めることができる人は、予備試験ルートで独学でも合格する可能性が高いです。
法科大学院に通うのが難しい人
仕事や家庭の事情で法科大学院に通うことが難しい場合でも、予備試験ルートならば司法試験を目指すことができます。
通学の必要がなく、時間を自由に使えるため、自分のペースで学習を進められます。
法曹を目指す強い意志がある人
予備試験ルートで成功するためには、法曹を目指す強い意志が求められます。
独学での学習には困難が伴うこともありますが、目標に向かって努力を続けることができる人には適しています。
経済的な負担を抑えたい人
学費を抑えたい人にとって、予備試験ルートは大変魅力的です。
法科大学院に通わずに司法試験を目指せるため、経済的な負担が少なくなります。
ただし、予備校や通信講座に通う場合は、受講料やテキスト代等が必要です。
アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座を受講しよう
アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座は、過去の出題傾向を徹底的に分析し、重要なポイントを押さえたカリキュラムが特徴です。
特に、初心者から経験者まで幅広い受験者が利用できるよう、基礎から応用まで網羅しています。
初学者・学習経験者要はもちろん、予備試験ルート・法科大学院ルートなど、受講者の状況や希望に応じたカリキュラムを柔軟に組める点も魅力です。
自分に合った方法で最短で予備試験・司法試験合格を目指せます。
オンライン講座なので、自分のペースで学習を進めることができ、働きながら勉強したい社会人や主婦(夫)の方にもぴったりです。
アガルートでは経験豊富な講師陣が丁寧に指導し、疑問点があればすぐに解消できる環境が整っています。
受講者の声からも高い合格率が実証されており、多くの受験者が合格を勝ち取っています。
また、受講料が最大30%OFFの割引制度があるのでお得です。
効率的に合格を目指すならアガルートの講座を活用し、確実な知識と実力を身につけましょう。
【最新】アガルートの司法試験・予備試験講座の口コミ・評判は?費用や合格率・受講生からの評価を解説
元プロ野球選手もアガルートで受講していた!
元プロ野球選手の宮台選手はアガルートで受講されて東京大学法科大学院に合格!
現在は司法試験の合格を目指されています。
以下のインタビュー動画では司法試験を目指すにあたってのポイントも話していますので、ぜひご覧になって参考にしてください。
予備試験ルートで司法試験を受験するか検討しよう
予備試験は司法試験の受験資格取得のための試験です。
司法試験は裁判官・検察官・弁護士になるための国家資格試験で、予備試験に合格する他、法科大学院を修了するかの2パターンで受験資格を取得できます。
予備試験は非常に難関ですが、その分、法科大学院の学費が不要になったり、早期に司法試験に挑戦できる点がメリットです。
ただし、合格率が低く、独学で学習管理するのは難しいというデメリットがあります。
予備試験ルートで司法試験を受験するかどうかは、個々の状況や目標に応じて慎重に検討する必要があります。
どちらのルートが自分に適しているのかをよく考え、将来のキャリアに最も有利な選択をしましょう。
独学が不安な方は、予備校や通信講座を利用するのも選択肢の一つです。