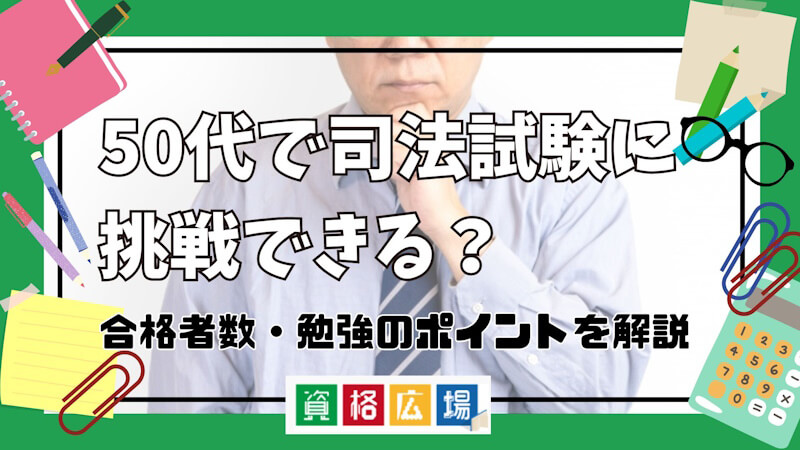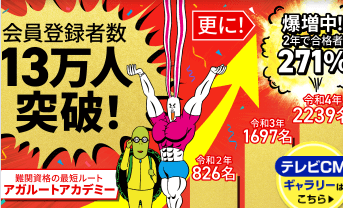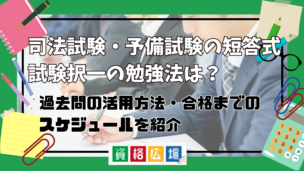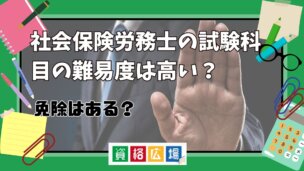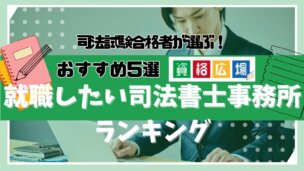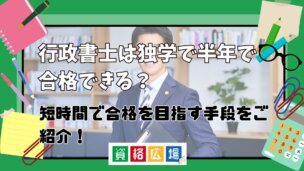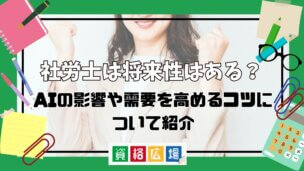「50代で司法試験は厳しい?」
「司法試験の50代の合格率はどれくらい?」
50代で司法試験を挑戦するか検討している方の中には、上記の疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
結論、50代でも司法試験の合格は目指せますが、若い世代と比べると難しい側面があります。
しかし、50代で司法試験に合格する方は毎年ゼロではありません。
この記事では、50代の司法試験の合格者や合格率の推移、50代で司法試験を受験するメリット・デメリットを解説します。
50代ならではの合格のポイントや、おすすめの勉強方法も紹介しているので、ぜひ最後まで読んでください。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
50代でも司法試験に挑戦できる!
50代でも司法試験に挑戦することは十分に可能であり、大きな価値を持つ挑戦です。
司法試験は年齢に関係なく受験可能で、50代という豊富な社会経験を持つ世代にとっては、法律の知識を深め、キャリアの新たな一歩を踏み出すチャンスとなります。
50代だからこそ得られる視点や経験は、法曹の世界で大いに活かされることでしょう。
また、司法試験を通じて自己成長を図り、人生の後半において新たな挑戦を成功させることができます。
ただし、時間・体力などの面から、若い世代と比べて50代で司法試験に挑戦するのは過酷だと言う意見もあります。
現在のライフスタイルや将来のキャリアなど、様々なことを考慮したうえで、50代で司法試験に挑戦するべきか、慎重に検討しましょう。
【最新】司法試験・予備試験の大学別合格者数や合格率ランキング!合格者数の推移は?
50代の司法試験の合格者数・合格率の推移
司法試験に合格する50代の方のデータをまとめました。
なお、司法試験の合格者に関する年齢別の公式データはありません。
そのため、予備試験の年齢別のデータをもとに、50代の司法試験の合格者数・合格率の推移を紹介します。
予備試験の合格者の約90%は司法試験に合格実績があります。
実際の数値と多少の誤差はありますが、参考にしてください。
| 年度 | 50~54歳 | 55~59歳 | 全体 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
| 令和5年(2023年) | 1,065名 | 10名 | 0.9% | 862名 | 5名 | 0.6% | 13,372名 | 479名 | 3.6% |
| 令和4年(2022年) | 946名 | 7名 | 0.7% | 766名 | 7名 | 0.9% | 13,004名 | 472名 | 3.6% |
| 令和3年(2021年) | 844名 | 8名 | 0.9% | 638名 | 4名 | 0.6% | 11,717名 | 467名 | 4.0% |
| 令和2年(2020年) | 769名 | 9名 | 1.2% | 616名 | 3名 | 0.5% | 10,608名 | 442名 | 4.2% |
| 令和元年(2019年) | 817名 | 2名 | 0.2% | 692名 | 4名 | 0.6% | 11,780名 | 476名 | 4.0% |
参照元:法務省『司法試験予備試験の結果について』
50代前半の予備試験の合格率は1%前後、50代後半の合格率は0.5~1.0%程度です。
また、予備試験の合格者の90%程度が司法試験に受かることから、50代前半の司法試験の合格者は約6名、50代後半は約4人と考えられます。
なお、上記はあくまで参考データになりますので、実際の数値とは異なる可能性があります。
【最新】予備試験の合格率は?合格者数・合格ラインの状況や大学別・社会人合格の割合を紹介
50代で司法試験を受験するデメリット
50代で司法試験に挑戦する際、以下のデメリットを考慮しましょう。
- 勉強できる時間に制限がある
- 記憶力が低下している
勉強できる時間に制限がある
一般的に50代はキャリアのピークを迎える年代です。
仕事での責任が重くなり、勉強に充てる時間を確保するのが難しい場合があります。
社会人としてフルタイムで働いている場合、司法試験の勉強時間を確保するためには、スケジュールを工夫し、無駄のない時間管理が必要です。
限られた時間の中で効率的に勉強を進めるため、短い時間でも集中して取り組むよう意識しましょう。
ただし、50代の多くは子育てが一段落している年代でもあるため、40代に比べて時間的な余裕があるかもしれません。
40代で司法試験に挑戦できる?合格者数・勉強のポイントを解説
記憶力が低下している
50代になると、若い頃に比べて記憶力が低下し、新しい知識を吸収するスピードが遅くなることがあります。
記憶力の低下を補うためには、反復学習や視覚的な教材を活用することが有効です。
法律の条文や判例など覚えるべきことが多い司法試験では、記憶力の低下をカバーするための工夫をしましょう。
司法試験の勉強時間はどれくらい?社会人の1日のスケジュールや合格まで何年かかるか解説
50代で司法試験を受験するメリット
一方で、50代で司法試験に挑戦することには、以下のメリットもあります。
- 老後の安定収入に期待できる
- 安定した精神力で挫折しにくい
- 豊富な社会経験から理解を深められる
予備試験・司法試験に年齢制限は無い?合格者の平均年齢や最年長・最年少は?
老後の安定収入に期待できる
司法試験に合格すれば、定年後の安定した収入源として弁護士や司法書士などの職業に就くことが可能です。
法曹の道は需要が高く、安定した職業として知られています。
50代で司法試験に合格することで、老後における経済的な不安を軽減することができるでしょう。
安定した精神力で挫折しにくい
50代は精神的に成熟しており、困難に直面しても挫折しにくい特徴があります。
司法試験は通常、長期間にわたる学習が必要な難関国家資格試験で、精神的なプレッシャーも大きいです。
しかしこれまでの人生経験を活かし、困難を乗り越える力を持っている50代の方は、司法試験のような厳しい長期戦でもしっかりと対応できます。
豊富な社会経験から理解を深められる
50年の人生で培った豊富な社会経験は、法律の学習においても大きな強みとなります。
例えば企業の法務部で長年働いていた経験など、実際の経験に基づいて学ぶことで理解を深めやすくなり、実務に即した知識を習得できるでしょう。
50代で司法試験を受験する方法2ルート
50代で司法試験に挑戦する際には、2つの主要なルートがあります。
それぞれ異なる特徴があり、自分の状況や学習スタイルに合ったものを選ぶことが重要です。
以下、それぞれのルートを詳しく解説します。
- 予備試験ルート
- 法科大学院ルート
予備試験ルート
予備試験ルートは、法科大学院に通わずに、予備試験を経て司法試験に挑戦するルートです。
50代の多くは自分のペースで学べる予備試験ルートを選びます。
予備試験ルートのメリットは、時間と費用を節約できる点です。
ただし独学の要素が強く、自己管理が非常に重要となります。
また、予備試験の合格率は3~4%と低く、上述の通り50代の予備試験の合格率は0.5~1.0%程度です。
50代で予備試験ルートを選択する場合、仕事や家庭と両立しつつ、試験突破に向けて効率的に学習を進める必要があるでしょう。
予備試験の個別指導が受けられる予備校・通信講座10選!特徴や料金比較
法科大学院ルート
法科大学院ルートとは、法科大学院に進学して法律を体系的に学び、その後に司法試験を受験するルートです。
専門的な知識をしっかりと身につけることができるため、合格後の実務にも直結する力を養うことができます。
50代で法科大学院に通うことは、学費や時間の負担が大きいものの、深い理解を得るためには非常に有効な方法です。
ただし通信制コースはないため、自宅から通学できない方にはおすすめしません。
また、法科大学院によって夜間コースがありますが、フルタイム勤務後に夜間コースで勉強するのは、体力・精神的に非常にハードであることを覚悟しておきましょう。
【最新】おすすめの法科大学院(ロースクール)ランキング!それぞれの合格率や学費を徹底比較【選び方も解説】
50代で司法試験に合格するためのポイント
50代で司法試験に合格するためには、特に周囲のサポートしてもらいながら、無理のない範囲で学習を進めることが大切です。
効率的な学習を進めるためのポイントを以下に挙げます。
- 周囲のサポートを得る
- こまめに休憩する
- 無理をしない
- 勉強仲間を見つける
周囲のサポートを得る
50代で司法試験に挑戦するには、家族や職場の理解とサポートが不可欠です。
勉強に集中するためには、家族との協力体制を整え、家事やその他の家庭内の責任を分担すると良いでしょう。
また、職場でも上司や同僚に理解を得て、勉強時間を確保するために柔軟な働き方を相談することが有効です。
周囲の支援があることで、精神的にも安定し、長期間にわたる勉強を続けるためのモチベーションを保つことができます。
さらに、勉強に対する意欲を高めるために、家族と目標を共有し、進捗を報告することも効果的です。
これにより、家族との絆も深まり、試験に向けた意識を高めることができるでしょう。
こまめに休憩する
50代での勉強は、若い頃と比べて集中力が続かないことが多いため、こまめに休憩を取ることが重要です。
長時間集中して勉強を続けると、疲労が蓄積し、効率が落ちるばかりか、健康を害するリスクもあります。
短時間の勉強を区切り、定期的に休憩を挟むことで、リフレッシュしながら効率的に学習を進めることができます。
休憩中には、軽いストレッチや散歩をすることで血流を促進し、体と脳をリフレッシュさせることが大切です。
また、適度な休息を取ることで、次の勉強セッションに対する集中力も向上します。
50代だからこそ、無理のないペースで持続可能な学習習慣を身につけることが、合格への鍵となります。
無理をしない
睡眠時間を削って長時間勉強するなど、無理をして勉強を続けることは、長期的に見て逆効果になることがあります。
50代は体力が衰えていることが多く、過度な負担をかけると健康を損なうかねません。
そのため、無理をせず、自分のペースで勉強を進めることが大切です。
例えば、疲れたと感じたら思い切って休みましょう。
健康を維持しながら勉強を進めることが、50代での司法試験合格を目指す上で欠かせません。
バランスの取れた食事や適度な運動など、体調管理に気を遣うと良いでしょう。
勉強仲間を見つける
勉強を一人で進めるのは、モチベーションが下がりやすく、孤独感を感じることがあるかもしれません。
50代では、同年代の仲間と励まし合いながら勉強を進めることが、精神的な支えとなり、勉強の継続に繋がります。
勉強仲間を見つけることで、お互いの進捗を共有し、情報交換を行うこともできるでしょう。
さらに試験に関する疑問点を議論し合うことで、理解を深めることも可能です。
近年はSNSなどから同じように司法試験に臨む50代を見つけられます。
また、予備校や通信講座を受講することで、講師や他の生徒とコミュニケーションを取るのも選択肢の一つです。
司法試験・予備試験対策におすすめの参考書・テキスト人気本ランキング39選!基本書から応用まで科目別に紹介【最新】
50代で司法試験に合格するための勉強方法
50代で司法試験に合格するためには、効率的かつ効果的な勉強方法を取り入れることが重要です。
若い頃に比べて記憶力や集中力が低下している場合もありますが、それを補うための工夫をすることで、十分に合格を目指せます。
ここでは、50代に特化した勉強方法をいくつか紹介します。
- 基礎知識を徹底的に固める
- 過去問・答練を繰り返す
- 視覚的な教材を活用する
- 予備校・通信講座を利用する
基礎知識を徹底的に固める
50代で挑戦する際には、特に基礎知識を徹底的に固めましょう。
基礎がしっかりしていれば、応用力も自然と身につきます。
まずは、基本書や講義資料を使って、法律の基本的な概念や用語をしっかりと学び、理解を深めます。
基礎知識を確認するために、自分でまとめノートを作成することも効果的です。
基礎がしっかりしていると、試験本番でも冷静に問題に対応でき、結果として高得点を狙うことが可能になります。
司法試験・予備試験の短答式試験のおすすめ勉強法は?過去問・問題集を使った対策方法から合格までの勉強スケジュールまで解説
過去問・答練を繰り返す
50代で挑戦する際には、過去問や答練を繰り返し行うことで、試験形式に慣れ、解答速度を上げることが重要です。
答練(答案練習)は、本番に近い形式で実践力を鍛えることができ、試験当日の自信につながります。
また、過去問を解いた後は、必ず解説を読み、理解を深めるようにしましょう。
自分の弱点を克服するために、重点的に学習する範囲を決め、効率よく学習を進めることが合格への近道です。
司法試験論文式試験のおすすめの勉強法とは?科目別の対策でも解説
視覚的な教材を活用する
50代になると、記憶力が低下しやすいため、視覚的な教材を活用することが効果的です。
図表やフローチャートを使った教材は、複雑な法律の概念を整理しやすく、理解が深まります。
また、視覚的な情報は記憶に残りやすく、試験対策としても非常に有効です。
例えば、法律の流れや関係性を視覚的に示した図表を活用することで、頭の中で整理しやすくなり、問題解決のスピードも向上します。
また、カラフルなペンや付箋を使って、重要な部分を強調することで、記憶の定着を図れます。
視覚的なアプローチを取り入れることで、勉強の効率を大幅に向上させることが可能です。
予備校・通信講座を利用する
50代で挑戦する場合、効率的に知識を習得するためには、専門的な指導を受けることが有効です。
独学での学習が難しいと感じる場合、予備校や通信講座を検討してみましょう。
それぞれのメリット・デメリットを以下にまとめました。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 予備校 |
|
|
| 通信講座 |
|
|
自分のライフスタイル、学習ペースに合う方法を選びましょう。
おすすめの司法試験・予備試験の答練ランキング!人気予備校5校を徹底比較【最新】
50代で弁護士になるデメリット
ここでは、50代で弁護士に就職するデメリットやリスクについて紹介します。
- 前職よりも年収が下がる
- 年下の上司がつく可能性が高い
- そもそも就職のハードルが高い
前職よりも年収が下がる
50代で弁護士を目指す際のデメリットとして、年収が数年間低下する可能性が高いことが挙げられます。
司法試験に合格し弁護士としてのキャリアをスタートさせる場合、前職を退職する人がほとんど。
50代だと多くの企業で上級職に就いていることが一般的であり、弁護士に転職することで給与が減少するリスクがあります。
弁護士は比較的安定した収入を得られる職業ではありますが、実際には、一定の軌道に乗るまで前職の年収を上回ることは容易ではありません。
ただし、弁護士には定年が存在せず、働き続けることが可能であるため、数年間の収入減少があったとしても長期的には多くの収入をもたらす可能性が十分にあります。
年下の上司がつく可能性が高い
50代で新人弁護士として入所する際、上司が年下であることがあるため、人によってはやりづらさを感じる方もいるでしょう。
しかし、弁護士業界では司法試験に合格する年齢が多様であり、一般企業に比べて年齢に対する意識はそれほど強くない風潮にあります。
実際、司法修習でもあらゆるな年代の修習生が集まり、年齢に関係なく対等な立場で学ぶことになります。
ただしもし年齢が気になるのであれば、年齢層が高い事務所に就職するのもひとつです。
そもそも就職のハードルが高い
50代は30代や40代と比べて就職のハードルが高い傾向にあります。
特に法律事務所においては、年上の部下を雇うことに対して抵抗感を持つことがあるため、50代の弁護士を新たに採用することが難しいと判断されるケースも少なくありません。
一方個人事務所では、60代や70代の弁護士が上司となることが多く、採用される可能性が高いです。
さらに、修習を終えた後にすぐに独立する選択をする人もいるため、弁護士資格を取ってから即独立するのもひとつです。
50代で弁護士になるメリット・強み
ここでは、50代で弁護士になるメリットやアピールできる強みについて紹介します。
- これまでの社会人経験が活かせる
- 人脈の広さをアピールできる
- 判断力や人間力の高さを評価されやすい
これまでの社会人経験が活かせる
50代で弁護士になることのメリットとして、これまでの職業経験や知識を活かせることが挙げられます。
弁護士として活動するには基本的な法律知識が求められますが、それに加えて社会人としての基本的なマナーなど多様な分野に関する知識も求められます。
法律とは直接関係がないように見える分野でも50代まで社会人経験を積んだ経験やスキルは、実際の弁護士業務でも役立つでしょう。
人脈の広さをアピールできる
50代の方は、弁護士としてのキャリアを築く際に、これまでの人脈を活用することができる可能性があります。
弁護士業務において最も重要な要素は依頼者を獲得することで、実際、多くの弁護士は依頼者を増やすための営業活動に注力しています。
特に企業弁護士の場合、以前の職場での人脈が豊富であれば、大いに役立つことがあります。
また、50代の方ともなれば企業の重役などとのつながりを持っていることが多く、仕事に直結しやすいため、ぜひチャレンジしてみてください。
判断力や人間力の高さを評価されやすい
50代は20代の若者に比べて豊かな人生経験を持ていることから、判断力や人間力の高さを評価されやすいといったメリットがあります。
実際の弁護士業務でも法律知識以上に人間的な資質が重要視される傾向が強く、採用につながる可能性も高いでしょう。
また、年齢が高いことで就職後にクライアントからの信頼を得やすいといった強みもあります。
特に、同年代のシニアクライアントからの信頼を得やすいでしょう。
【最新】2025年(令和7年)司法試験の試験日程や時間割・合格発表日まとめ
50代で司法試験を受験するならアガルートを受講しよう
50代で司法試験に挑戦するなら、効率的な学習で最短合格をサポートするアガルートの受講がおすすめです。
アガルートでは、司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座を受講できます。
カリキュラムは多岐にわたり、自分の選ぶルート、弱点などに合わせて自由にカスタマイズできる点が魅力です。
講座の選び方に迷っている方は、事前に無料で何度でも受講相談できます。
フォロー制度が手厚いので、孤独感を感じにくい点もアガルートの魅力です。
オンライン学習に特化しているので、仕事や家庭の都合に合わせて学習計画を立てられるため、50代での挑戦にも最適です。
最大30%OFFになるので、お得に受講したい方にもおすすめします。
【最新】アガルートの司法試験・予備試験講座の口コミ・評判は?費用や合格率・受講生からの評価を解説
50代の合格者の声
50代でアガルートを受講し、司法試験に合格した方の声を一部紹介します。
初学者が試験対策としての情報を獲得するのには、困難な素材でした。
一定の学力を要するものと思います。
アガルートの講座については、司法試験論文過去問解析講座から受講させて頂きました。
過去問は繰り返し問われているから、予備試験及び司法試験に合格するには手っ取り早い方法だと思ったのです。
しかし、基礎力がありませんでした。
そこで、基礎力を獲得すべく総合講義100を受講させて頂きました。これは役に立ちました。
その上で、論文答案の「書き方」を聴かせて頂きました。こうした講座を受講したうえで、重要問題習得講座を受講しました。これは大変重宝致しました。
結局、予備試験合格発表から、司法試験受験日までが、三か月程しかなく、私は満足な対策をたてることなく受験に至りました。
それでも合格できたのは、ひとえにアガルートの講座のお陰です。
50代・社会人
出典:アガルート|司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座 合格者の声
予備試験・司法試験業界における論文試験教材の最高峰である、「司法試験 重要問題習得講座」、略して、「重問」の存在が貴社を選択させて頂いた決定的な理由です。
最も素晴らしいのは、工藤先生が判例、基本書、そして、最高裁調査官解説まで徹底的に調べて書かれている必要十分な解説とこれに基づく解答です。
安心して信用して、重問で勉強させて頂くことができました。
解説や解答で分からない箇所があった場合にも、これらを叩き台にして、基本書等で調べて納得しながら勉強することで効果は抜群です。
重問を使って、脳内答案構成を何度も何度も繰り返すことで、手で実際に書くという答練をしなくても、論文本試験では、全科目平均3頁を書くことが出来ました。 予備論文合格の「効果」を得るためには、重問を回すことが「要件」と言っても過言ではないと思います。
50代・社会人
出典:アガルート|司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座 合格者の声
アガルートを受講した元プロ野球選手にインタビュー!
アガルートを受講して東京大学法科大学院に合格、元プロ野球選手の宮台選手のインタビュー動画を紹介します。
宮台選手の勉強法や経済法を選択した理由など、司法試験を目指すにあたって有益な情報が満載ですので、ぜひ参考にしてください。
50代からでも司法試験合格を目指せる
50代からでも司法試験に挑戦できますし、実際に50代の合格者は毎年一定数います。
メリット・デメリットはもちろんありますが、50代だからこそ持っている豊富な経験や知識を活かし、効率的な学習方法を実践することで、年齢に関係なく司法試験合格を目指せるでしょう。
司法試験に合格することで、新たなキャリアを築くことができ、人生の後半において充実した日々を過ごすための大きな一歩となります。
50代で司法試験に合格することは、決して簡単ではありません。
しかし自分自身を信じ、しっかりと計画を立てて努力を続けること、周囲のサポートや体力・健康に配慮した学習計画を立てることで、50代でも司法試験に合格する道は開けています。
年齢を理由に諦めることなく、挑戦する気持ちを大切にし、一歩ずつ確実に進んでいきましょう。
50代から司法試験にチャレンジすることに不安がある方は、アガルートに無料で受講相談してみてください。