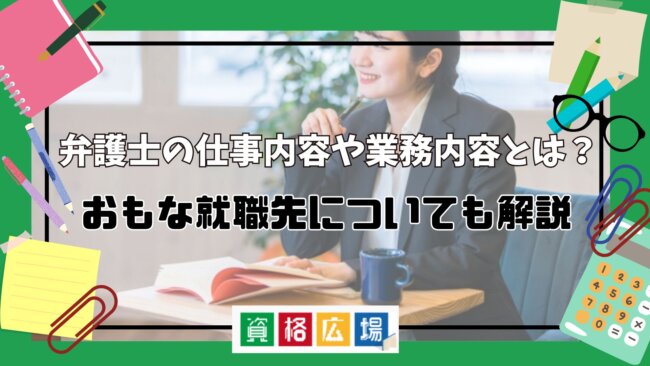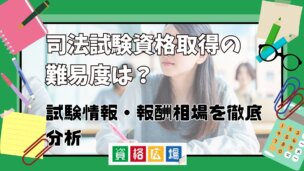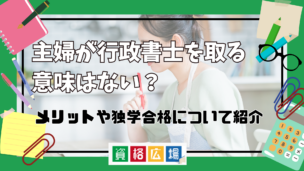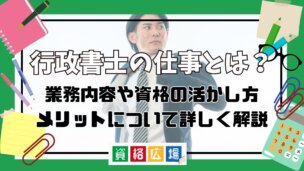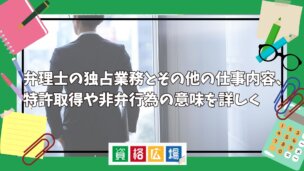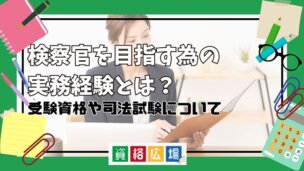「法律の専門家」である弁護士は、国民の基本的人権を守り、正義のために戦うことが仕事です。
弁護士は「民事事件」と呼ばれる、個人や企業のトラブルに関する法律相談を扱ったり、罪を犯した者と接する「刑事事件」を扱うなど、実に重要な仕事内容を担っています。
この記事では、弁護士の仕事内容や業務内容に焦点を当て、法律事務所以外の仕事も紹介していきます。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
司法試験予備試験合格におすすめの通信講座
弁護士の仕事内容とは
弁護士の仕事内容は、主に依頼人から受けた法律に関係する問題・相談を解決することです。トラブルの内容には大きく分けて「民事事件」と「刑事事件」の2種類があります。
基本的に弁護士の仕事は法律事務所で扱う法律相談から始まります。弁護士はその依頼者の利益を第一優先に考える必要があるため、不利にならないように話を進めなければなりません。
また、依頼人が裁判で有利になるように証拠を集めたり、書類を準備する必要があります。全ての問題解決は法律に基づき、弁護士は法律の専門家としての役割を果たすことが仕事です。
ここでは、弁護士の仕事内容について詳しくご紹介します。
民事事件について
「民事事件」とは、人対人であったり、企業同士であったりと日常生活や個人の間で生じた問題のことを指します。多くの弁護士は法律事務所に所属し「民事事件」を中心として扱っていることが大半です。
民事事件とは、「相続の件で親族が揉めている」「離婚したいのに話が進まない」「会社が残業代を支払ってくれない」などのケースが考えられます。
話し合いで解決できることであればそれに越したことはありませんが、個人の間で冷静に対処がしきれなくなった場合は弁護士に相談される方が多いです。
そのようなトラブルが発生した場合、弁護士は当事者の代理人となりそれぞれの主張や要望をまとめ解決への道を考えます。
最終的に当事者同士が納得できない場合や折り合いがつかない場合、さらに最初の法律相談の時点で裁判を起こすべきトラブルだった場合は「民事裁判」をすることになります。
刑事事件について
「刑事事件」は、主に犯罪の内容が対象となっており、警察が介入した事件のことを指します。犯罪が絡む「刑事事件」を扱っている弁護士は「民事事件」を扱う弁護士に比べてごく少数といわれています。
「刑事事件」を扱う弁護士は、犯罪行為の疑いをかけられた被疑者や被告人を「弁護人」として弁護しますが、ここで「なぜ犯罪者側に弁護士が必要なのか?」という声が上がることも多いです。
しかし、例え犯罪を犯した者であっても公平な裁判を受ける権利があります。そのため、犯罪者側にも弁護士がつき、検察官を相手にして裁判で争うことになります。
また、被告人である犯罪者が弁護士に対してお金を支払えない場合「国選弁護人」という裁判所が選定した弁護士が担当になります。
弁護士になるには、時として世間から「理解できない」と思われる仕事を引き受けることもあります。弁護士は、自分の感情に左右されることなく公正な目で物事を見る力が必要です。
弁護士の業務内容とは?
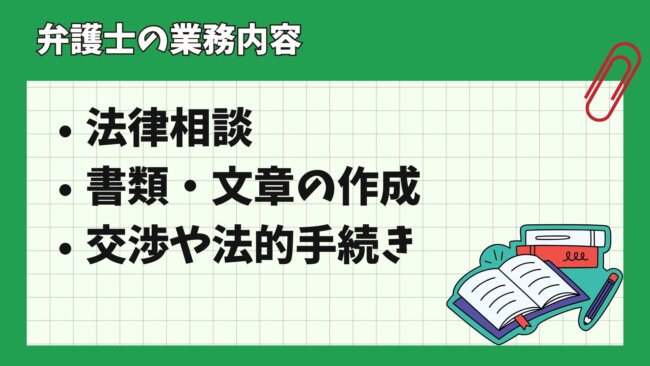
ここでは、法律事務所に所属する弁護士の仕事内容をさらに掘り下げて、業務内容を詳しく紹介していきます。
弁護士の業務内容も様々ですが、全てにおいて重要な役割を果たしています。そのため、弁護士の仕事内容や業務内容は責任が重いともいわれています。
法律相談
業務内容における法律相談は、依頼者と弁護士の信用・信頼関係を築いていく弁護士業務のスタート地点といえます。弁護士は依頼者の要望を1番に聞き入れる必要があり、依頼者の立場や利益を考えねばなりません。
法律相談では、依頼者の話を聞きだすコミュニケーション能力も重要になってきます。
また、多種多様な環境や境遇にある依頼者が法律相談に訪れるため、様々な法律の分野に精通するための知識やスキルも求められます。
書類・文書の作成
弁護士が作成する書類や文書には、裁判所への提出書類や交渉に使用する通知書、契約書や意見書など様々なものが挙げられます。
作成した書類や文書には、事件予防や事件交渉、事件解決するための非常に重要な役割を担ってる業務内容です。
そのため、依頼者や相談者からしっかりと話を聞きだし、主張や要望に応えられる書類や文書を作成しなければなりません。
交渉や法的手続き
弁護士は依頼者の許可なく交渉や話し合いを進めることができませんが、依頼者の承諾を得てから相手方と接触、交渉を行うことがあります。
弁護士は代理人という立場から、交渉を有利に進めるための条件を引き出したり、取引成立や事件解決、早期決着をつけるために示談や和解というケースに落ち着かせることも弁護士の業務内容の1つです。
しかし、交渉でも決着がつかない場合は調停・審判・起訴などという法的手段を取らなければならない場面も少なくありません。法的な手続き・申し立ての準備も重要な弁護士の仕事内容です。
司法試験・予備試験講座はアガルートアカデミーがおすすめ!

司法試験・予備試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめです。
フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、法律関係の勉強を初めてする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。
また、充実したカリキュラムや一人ひとりに合わせた手厚いサポートも魅力的です。
司法試験合格者の講師が指導!
アガルート公式HPはこちら
弁護士の主な就職先
ここでは、様々な場で活躍する弁護士の仕事先を紹介していきます。
法律事務所
司法修習を修了し、弁護士登録を果たしたほとんどの弁護士は法律事務所に所属することとなります。
法律事務所で先輩弁護士から書面の添削を受けたり、尋問技術を学ぶことで、独り立ちした弁護士としてのスキルを上げてくのが一般的です。
法律事務所の規模は多様で、海外に多数の拠点を持つ事務所も少なくありません。
たとえば個人経営の事務所では、所属弁護士が1人または数人で、一般民事を含む多様な業務を行っていることが多いといった特徴があるので幅広い経験を積みたい人におすすめです。
一方で、日本最大級の法律事務所には500人以上の弁護士が在籍しており、大手企業に関する企業法務など、専門的な法律知識が求められる分野で業務を分担しています。
弁護士事務所への就職活動を行う際には、各事務所の特徴や働き方について事前に情報を収集することが重要です。
サマークラークや説明会を実施している事務所も多く、インターネットでの情報発信に注目し、自分に適した事務所を見つけるようにしましょう。
一般企業で企業内弁護士として働く
最近では一般企業で企業内弁護士として働く人も増えてきています。
企業内弁護士としてのキャリアパスは、法務部や総務部などの部門での勤務となります。
具体的には企業の取引に関連する契約書の作成や知的財産の管理、紛争の予防や不祥事への対応といった業務を担当します。
法律事務所ではクライアントが常に変わるのに対し、企業内弁護士は特定の企業に専属して働くといった違いがあるので専門性を高めたい人におすすめです。
また、法律事務所では業務委託契約が一般的ですが、企業に勤務する場合は雇用契約を結ぶことが多く、会社員としての福利厚生を享受できる点が大きなメリットだといえるでしょう。
近年、企業内弁護士の数は急激に増加しており、ここ10年程度で2倍以上となっています。
行政内弁護士・自治体内弁護士
国の中央官庁や地方公共団体、国際機関、各自治体などの行政庁で働く行政庁内弁護士という弁護士も存在します。行政に関わる仕事であるため、公務員という扱いをうけます。
活躍の場としては「金融庁」「外務省」「公正取引委員会」「法務省」などに所属している弁護士が多いです。
業務内容は初速場所によって異なりますが、金融機関への検査業務や条約締結交渉、審判、民商法改正などが挙げられます。
また都道府県や市区町村などの自治体に勤務する職員として、主に法務部や労働委員会において活動する自治体内弁護士として活躍する人もいます。
業務内容には、規則や条例の策定、各種法律相談、住民への対応など、自治体職員ならではの法律業務が挙げられます。
自治体内の弁護士は公務員であるため、兼業は禁止されており、原則として自治体の職務以外での弁護士活動は行えません。
ただし、自治体によっては特別な許可を得ることで兼任が可能な場合もあるため、就職を考える際には各種条件を十分に確認するようにしましょう。
公設事務所弁護士
公設事務所とは、公益的な課題に対応することを目的として、日弁連や弁護士会の支援を受けて設立される法律事務所を指します。
大きく分けて過疎地型公設事務所と都市型公設事務所の二種類に分類されます。
過疎地型公設事務所は弁護士がほとんど存在しない地域に設立されるものであり、都市型公設事務所は都市部に設置され、過疎地型公設事務所への弁護士派遣やその他の公益的な課題に対応するために作られた違いがあります。
公設事務所では、都市部の法律事務所では扱われにくい案件に関与することが多く、弁護士過疎地特有の案件に関わる機会を得ることができるというメリットがあります。
独立開業
弁護士は通常、法律事務所に勤務して経験を積んだ後に独立することが一般的でが、法律事務所での経験を経ずにすぐに独立する弁護士も増えてきています、
ほかにも短期間で法律事務所を退職し、自らの事務所を設立するケースも見受けられます。
特に前者は「即独」と呼ばれる形態であり、 先輩弁護士からの指導を受けられないというデメリットはあるものの、弁護士会などの支援を受けることができ、自由な働き方が可能であるというメリットもあります。
実際には、司法修習時の人脈を活用して紹介を受けたり、インターネットを通じて集客を行うことで、即独で成功を収めている弁護士もいます。
開業した弁護士は案件数を増やすことで収入アップを実現できるため、年収アップを目指す方はぜひ挑戦してみてください。
弁護士の一日の流れ
弁護士事務所の規模や案件によっても異なりますが、一般的な弁護士の一日の過ごし方は以下の通りとなります。
- 午前9時頃~…出勤、業務開始
- 午後6時頃まで…依頼者との打合せや裁判への出廷、メールや電話の対応など
依頼者との打合せには新たな法律相談だけでなく、進行中の裁判や交渉に関する打合せも含まれますが、ときには出勤後すぐに法律相談で1日が埋まることもあります。
また裁判期日が設定されている場合、弁護士は裁判所に出廷します。調停や証人尋問の手続きがない限り、1回の期日は通常15分から30分程度で終わるのがほとんどです。
しかし、大規模な事件の証人尋問は、数日にわたって朝から夕方まで続くこともあるので注意が必要です。
弁護士の業務の中で最も時間を要するのは書面作成です。
しかし、午前9時から午後6時の間では、書面作成に十分な時間を確保できないことが多く、多くの弁護士は遅くまで事務所に残り、書面作成に取り組むことが一般的です。
さらに繁忙期や扱う事件が増えてくると、休日も書面作成に充てなければいけなくなったり、依頼者とのメールや電話のやり取りも増え勤務時間が長くなります。
特に弁護士としてのキャリアをスタートし、多くの経験を積む必要がある段階では、休むことなく働き続ける体力が必要だといえます。
弁護士になるには
弁護士になるためには司法試験に合格しなければいけません。
また司法試験を受験するのにも資格が必要であり、法科大学院(ロースクール)を修了した者、または司法試験予備試験に合格した人でないと受けられません。
もし学生時代から弁護士になりたいと考えているのであれば、まず大学の法学部に進学することがおすすめです。
さらに司法試験に合格した後は、1年間の司法修習を受け、司法研修所で専門的な知識を習得する必要があります。
そこから司法修習生考試および採用審査に合格することではれて弁護士押して活躍できます。
ちなみに司法試験の合格率は例年40%程度といわれています。
2014年10月に司法試験法の一部が改正されたことにより、法科大学院を修了するか予備試験に合格した後は、5年間の間に毎回受験することができるようになりましたが5回以上は受験資格がなくなるので注意なければいけません。
弁護士になるには費用がいくらかかる?司法試験・予備試験の費用や勉強代は総額いくらか解説
弁護士の仕事内容は法律相談だけではない!法律事務所以外の業務内容まとめ
弁護士の仕事内容や業務内容は様々であり、それぞれが得意としている分野があります。
基本的には、法律に関する相談から弁護士の仕事が始まりますので、どのような働き方であっても共通する事柄といえるでしょう。
近年様々な業界で需要がある弁護士は、法律事務所以外にも活躍の場を広げています。このことから、今後も弁護士に対する期待は高まっていくといえるでしょう。