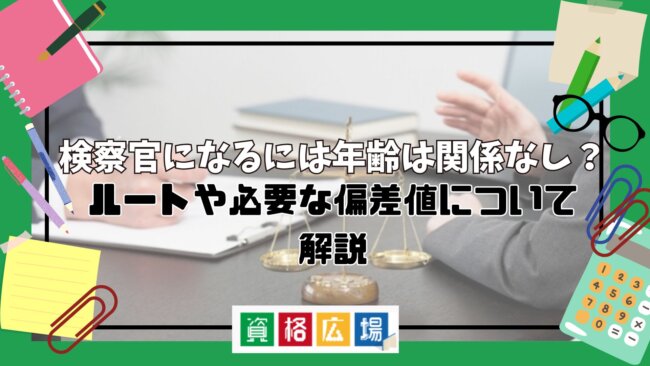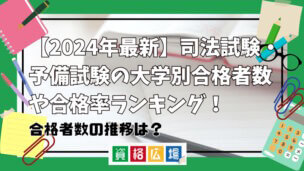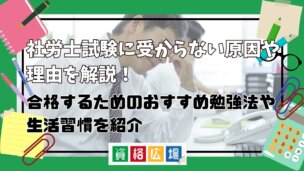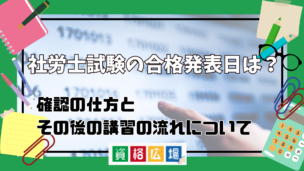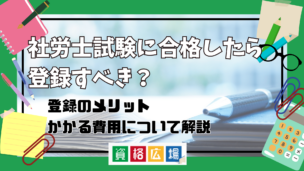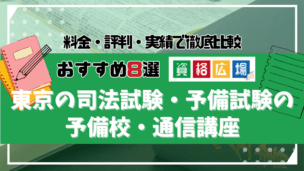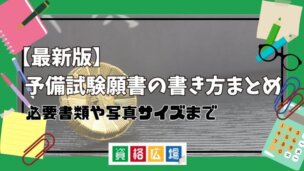検察官になるには法律の専門家としての役割を果たす為に、様々な試験をクリアしていかなければなりません。
しかし、それは簡単ではなく人並み以上の努力が必要となってきます。
今回はどういった方法で検察官となれるのか具体的にまとめました。
検察官になる為の必要な受験資格・年齢や法科大学などの偏差値など、検察官になるにはどういったルートがあるのかをご紹介していきます。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
司法試験予備試験合格におすすめの通信講座
検察官とは
検察官とは検事や副検事を指し、公益の代表として刑事事件に関して裁判所に公訴を提起する権限を有する国家公務員です。
法務省に所属しており、 起訴は検察官に特有の権限であり、検察官は裁判所に対して起訴し、被告に対する処罰を求める責任を担っています。
主な仕事内容としては警察からの捜査記録の確認や被疑者の取調べ、被害者・目撃者などの関係者からの事情聴取、証拠品の捜索・押収、さらにはその分析や検討を自ら積極的に行い、事件の真相を解明する役割を果たしています。
ほかにも、起訴後には被疑者が有罪であることを法廷で主張し、適切な刑罰の適用を求めることも検察官の重要な職務の一つです。
適正な刑罰権を行使することによって健全な社会を築くためには、検察官の存在が不可欠でしょう。
検察官の種類
検察官といってもさまざまな種類の役職があり、それぞれの業務が異なります。
| 名称 | 業務内容 |
| 検事総長 | 最高検察庁の長として庁務をおこない、全ての検察庁の職員を指揮・監督する。 |
| 次長検事 | 最高検察庁に所属し、検事総長を補佐する仕事。検事総長に事故があった際に代わりに職務をおこなう。 |
| 検事長 | 高等検察庁の長として庁務をおこなう。地方検察庁や区検察庁の職員を指揮・監督する。 |
| 検事正 | 地方検察庁の庁務をおこない、かつその庁 及びその庁の対応する裁判所の管轄区域内にある区検察庁の職員を指揮・監督する。 |
| 検事 | 最高検察庁・高等検察庁及び地方検察庁などに所属しており、捜査・公判及び裁判の執行の指揮・監督を行う。 |
| 副検事 | 区検察庁に所属しており、捜査・公判及び裁判の執行の指揮監督を行っている。 |
上記の表からわかるように、検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事という階層に分かれており、それぞれの役割は異なります。
検事総長は全ての検察官の最高責任者であり、高等検察庁の長としての役割を担っています。
検事は最高検察庁や地方検察庁、高等検察庁などに配属され、各種業務を遂行し、副検事は副検事選考試験に合格した者が就くことができる役職です。
検事は地方裁判所に所属し、副検事は簡易裁判所に所属しますが、業務内容には大きな違いはありません。
検事になるためには、司法試験に合格し、司法修習を受ける必要がありますが、最終的には検察の上層部に認められた者のみが検事として任命されます。
また、副検事として3年以上の経験を積み、検察官特別考試に合格することで検事になる道も開かれています。
検事胃に慣れなかった人が副検事選考試験を受け、副検事としての職務に就くケースもあります。
役職によって業務内容は若干異なりますが、全体としては検察官と呼ぶことができるでしょう。
検察官になるには司法試験が必須!検察官の年収や仕事内容まとめ
検察官の平均年収
検察官の年収は1,000万程度と言われていますが、検察官の等級によって月収が異なるため、平均年収の幅が600万~3,000万円程度等広がることによります。
国家公務員に該当する検察官の給与やボーナス、その他の手当は法律に基づいて定められています。
一般的に軽微な刑事事件を扱う区検察庁で勤務する副検事の場合、1号の等級であれば月給は574,000円で、これは検事7号と同額であり、年収は688万円を超える計算になります。
どの検察庁に配属されても初任給は同じであるため、検察庁の種類によって年収が異なることはありません。
また、検察官の俸給に関する法律では、勤務超過手当、休日手当、夜勤手当、宿日直手当は支給されないことが定められています。
理由としては事件の適正かつ迅速な処理を行うために、勤務時間外に対応することがあるため、時間外勤務を計測することが難しいからです。
検察官として年収を向上させるためには、勤続年数を重ね、昇進のための一定の受験資格を得る必要があります。
検察官としての初任給は検事20号から始まり、237,700円スタート、仮に毎年1回昇進できるとすれば、20年後の46歳頃には検事1号になり、月収は100万円を超える見込みとなっています。
検察官になるには?
検察官は国や国民を法律に沿って守り、保護する責任があるので、決して検察官になるのは容易ではありません。
検察官を目指す為には様々な知識や能力が求められます。
検察官になるには幾つか道順がありますが、主な前段階として必要になってくるのが以下になります。
法科大学院
法科大学院とは法曹三者(弁護士・検察官・裁判官)を目指す専門の大学院で、新司法試験の実施に伴い新設された教育機関です。
2002年に「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」が制定され、設置が認められました。
法科大学院を修了すると司法試験の受験が可能になります。
大学での在籍が法学部でない場合にも法科大学院への入学は可能で「既修コース」「未修コース」が開設されています。
| コース | 1年 | 2年 | 3年 | ||||||
| 既修コース | 法科大学院入学 | 実務法律科目 | |||||||
| 未修コース | 基礎法律科目 | 実務法律科目 | |||||||
法科大学院の受験資格と年齢について
法科大学院の受験資格は大学卒業者とされていますが、飛び級制度を認可している法科大学も存在します。
法科大学院にも特に年齢制限はありませんが、平均年齢として30歳前後となっていて、各大学院で最高齢の平均年齢は47歳前後となっています。
法科大学院:既修コース
既修コースは大学で法学部に在籍していた人の為のコースで、大学で法律に関して勉強してきた生徒が既修コースへ進みます。
法律の基礎知識を前提としたコースで2年間法律に関して学びます。
既修コースの入試試験は主に基礎的な法律に関しての問題となっていて、各法科大学院によって難易度はバラつきがあります。
法科大学院:未修コース
未修コースは大学で法学部に在籍していなかった人や社会人の為のコースで、法律に関して未修の人を対象にした学習コースです。
入学後から法律の最低限の基礎から学んでいく為、学習期間は3年間になります。
未修コースの入試試験は法律に関する知識は必要ありません。
司法試験
司法試験は法務省が管轄する法曹資格を取得する為の能力を評価する国家試験です。
検察官になるには司法試験が最難関の試験となり、この試験に合格しなければ法曹三者を目指す事はできません。
大学から法曹三者を目指す人は、司法に関する学業と同時に、司法試験の為の勉強を長時間費やしています。
司法試験を受験する為の受験資格は「法科大学院修了者」「法科大学院在学生」「司法試験予備試験合格者」のいずれかに該当しなければ受験できません。
司法試験は毎年7月に4日間行われます。
司法試験の受験資格と年齢について
司法試験の受験資格は法科大学院在籍または法科大学院修了者か使用試験予備試験合格者となります。
法科大学院ではコースにより、年数が決まっているので、既修コースであれば2年、未修コースであれば3年間の過程を修了しなければならないので、司法試験の受験資格を法科大学院から受験するのであれば、最短年齢は24~25歳となります。
司法試験自体に年齢制限は無く、平均的な合格者の年齢は予備試験者も含む為、28.8歳となっています。
司法試験の流れ
司法試験のスケジュールは以下の様になります。
31年度試験日程
| 2024年3月19日(火)~4月2日(火) | 2024年7月10日(水)~7月14日(日) | 2024年8月1日(木) | 2024年11月6日(水) | |||
| 願書受付 |
|
短答式試験 成績発表 | 合格発表 | |||
司法修習
司法修習は司法試験合格者が法曹資格を取得する為に定められた法曹の教育制度です。
法律に関する知識や実技を学び、法律専門家としての意識や倫理の教育を受けます。
司法修習修了前に二回試験と呼ばれる司法修習生孝試が行われ、それに合格すれば法曹資格を得る事ができます。
司法修習は法曹三者共同じ過程で行われ、それぞれに関連する職業として三者の視点・立場も学び、相互理解を深めます。
10ヵ月の実務研修に2ヵ月の習合修習を行い、実務修習は「民事裁判」「刑事裁判」「検察」「弁護」「選択」のそれぞれを2ヵ月程度行います。
司法修習生の年齢について
司法修習では、司法試験に合格した人が1年間司法に関する知識を習得しますが、司法修習を受ける年齢は幅広く法科大学院が年齢制限など無い為、社会人も多くなっています。
ただし、司法修習は30歳以上になると検察官として働くには非常に難しく、出来る限り20代のうちに修了しておきたい所です。
しかし、35歳で検事に任官された人もいるので、成績次第でその結果にも変化があります。
司法試験予備試験
司法試験予備試験は2011年に開始した、法科大学院修了程度の専門的知識や能力について判定する為の試験です。
受験条件はなく誰でも受験する事が可能で、司法試験予備試験に合格すれば、司法試験が受験できるようになります。
経済的理由や環境によって法科大学院に進学できなくても、この司法試験予備試験で十分検察官を目指す事が可能なのです。
予備試験予備試験の受験者は年々増加傾向にあり、試験に合格するだけでも就職に有利な場合が多く、予備試験合格者の司法試験の合格率は約72%と、司法試験受験者の合格率が最も高くなっています。
司法試験予備試験の受験資格と年齢について
予備試験に年齢制限は無く、誰でも受験が可能ですが、司法試験予備試験は難関の資格となっているので、最年少での合格は難しいと言われています。
司法試験と予備試験の難易度について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください!
司法試験予備試験に合格するには
難関資格である司法試験予備試験に合格するには、予備試験専門の予備校に通うと効率的に学習ができます。
数ある予備校の中でも特に合格実績が高いのがアガルートアカデミーです。
令和4年度の司法試験合格者1,781人中641人がアガルートアカデミーの受講生という結果でした。
最短1年で合格を目指せるカリキュラムになっているので、予備試験合格を目指される方には非常におすすめです。

検察官になる為のルートは
検察官になるには様々な条件が前提として存在し、多くの試験や勉強が必要となってきます。
検察官を目指す人のルートは環境によって様々ですが、勉強量などにも大きな変化が伴います。
検察官を目指す為のルートは以下の3ルートとなります。
ルート①法科大学院への進学
- 各大学法学部から法科大学院へ進学
- 法科大学院を修了する
- 司法試験に合格する
- 1年間の司法修習を習得
- 二回試験に合格する
検察官を目指す人が選択する最も多いルートで、このルートが最も安定的で検察官になるには最も近道のルートとなります。
大学時点で法学部に在籍していた割合が高く、最も法律に関する勉強量を確保する事ができ、またそれに関する専門分野のカリキュラムが組まれているので、法曹三者になる為の王道ルートとなります。
独学と違い、周囲の学生も職種は異なっても学ぶ事は同じなので、それぞれの視点から物事を考える事もでき、勉強しやすい環境が準備されています。
ルート②司法試験予備試験
- 司法試験予備試験に合格する
- 司法試験に合格する
- 1年間の司法修習を受ける
- 二回試験に合格する
司法試験予備試験の受験者は非常に多く、司法試験に合格するだけでも他業種にも大きなメリットとなります。
司法試験予備試験での司法試験の合格者は非常に多い傾向にありますが、その後の通過点で司法試験予備試験合格者の通過率は極端に減少傾向にあります。
司法試験予備試験からの検察官ルートは検察官になるまでに、法科大学院修了者の半分しか勉強する期間がないので、自分自身での勉強時間の確保や多くの法律に関する知識を習得する努力が必要となります。
ルート③検察庁に事務で就職
- 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験か高卒者試験)に合格する
- 検察庁に検察事務官として採用される
- 一定の等級以上での検察事務官として3年以上勤務する(受験資格)
- 副検事の試験に合格する
- 3年以上副検事を務め、検察官特別考試に合格する
検察事務官のメリットとしては、法律に関して未経験でも勤務する事が可能で、受験条件さえ達成できれば司法試験をパスする事ができるのです。
検察官特別考試について
検察官特別考試は筆記と口述があります。
筆記:「憲法」「民法」「商法」「刑法」「刑事訴訟法」「検察」
実務6科目が必修となり、選択科目は「民事訴訟法」「法医学」「刑事政策」から1つ選択します。
口述試験:「憲法」「刑法」「刑事訴訟法」「検察」
口述試験は、実務4科目になります。
検察官になる為に必要な偏差値とは?
検察官の職業を選択する場合に必要となる条件は法科大学や司法試験合格、二回試験の合格または司法試験予備試験の合格などを通過しなければなりません。
検察官になるには法科大学院を目指す方も多くいますが、検察官になるにはどの程度の学力が必要となってくるのでしょうか?
大学(法学部)・大学院の偏差値や現役検察官に多い出身大学をまとめました。
各大学法学部の偏差値
検察官としての目標を早い段階で決断している人の多くは、各大学の法学部に進学します。
法学部は法律に関する基礎知識を学ぶ事ができ、検察官を目指す為の法科大学院への対策講座や司法試験対策など、目的に沿ったバックアップをしてくれるコースがあり、現役検察官や弁護士などから直接指導を受けたりと、法曹三者を目指す人に最適の学習環境を望む事ができます。
司法試験の合格率の高い大学法学部の平均偏差値は66.79となります。
司法試験合格者の多い上位5つの大学:法学部と偏差値
- 京都大学(67.5)
- 東京大学(70.0)
- 慶應義塾大学(70.0)
- 早稲田大学(67.5)
- 中央大学(60.0-62.5)
法科大学院
法律の知識を更に深め検察官になるには、各大学法学部から法科大学院に進学します。
法曹を養成する為に司法試験制度の見直しを図り、2006年に新司法試験を実施するにあたって開設された教育機関です。
司法試験と法科大学院は密接な関係にあり、さまざまな実務に基づいた教育など、実践的なものも多く組み込まれたカリキュラムです。
司法試験を受験する為には、法科大学院を修了しなければなりませんが、在学中に司法試験に挑戦し合格する人もいます。
司法試験の合格率の高い法科大学院の平均偏差値は66.25となります。
司法試験合格者の多い上位5つの法科大学院と偏差値
司法試験を受験した大学院の中でも合格者の多い法科大学院では、どの法科大学院も司法試験合格率40%以上となっています。
- 京都大学(67.5)
- 一橋大学(67.5)
- 東京大学(70.0)
- 慶應義塾大学(70.0)
- 大阪大学(65)
検察官に多い出身大学
検察官として検察庁に勤務した人の平均的な偏差値は68と言われています。
検察庁で検察官として現役で働いている人の多い出身大学は以下の5大学になります。
やはり司法試験に強い大学・大学院の出身者が多く偏差値も高い傾向にあり、大学院も検察官になる為の教育環境が整っているので、現時点で大学選びを考えている方は参考にして下さい。
(2018年1月)
- 東京大学:23人
- 中央大学:9人
- 早稲田大学:7人
- 慶應義塾大学:4人
- 一橋大学:3人
検察官に必要な能力・向いている人の特徴
検察官は試験が難しいだけではなく、合格後も努力が必要でハードな仕事だと言われています。
ここでは、検察官に必要な能力や向いている人の特徴について紹介します。
正義感や責任感が強い
検察官は公益の代弁者として犯罪を犯した者を法廷に引き出し、適切な刑罰の適用を求める職務を担っています。
そのため検察官は社会の不正を許さない強い正義感が求められます。
個人の人生に大きな影響を与える可能性があるため、自らの判断に対する重い責任を常に意識しなければいけません。
犯罪を恐れない安全な社会を実現するための強い意志を持つことが、検察官にとって重要な資質となるでしょう。
組織的な行動をとれる人
検察官は公務員であることから弁護士とは異なり、刑事事件の捜査においては原則として組織的に行動することが求められます。
個人の独断行動は、刑事手続きに悪影響を及ぼし、被害者の権利を侵害する可能性があります。
したがって、組織の一員としての自覚を持ち、状況に応じて柔軟かつ迅速に行動しなければいけません。
また、検察官の職務は常に人との関わりを伴うため、優れたコミュニケーション能力が不可欠です。
被疑者の取り調べにおいても、コミュニケーション能力がなければ効果的に進めることができず、裁判においても不利な状況に陥ることがあります。
さらに、チームで事件に取り組むこともあるため、社会人としての基本的な協調性や倫理観も求められます。
探求心がある
検事は法律の専門家として、特に刑事訴訟法や刑法に関する深い知識が求められます。
犯罪に対する適切な刑罰を判断するためには、これらの知識は必須のスキルといえるでしょう。
検察官を目指すのであれば、学生時代から相当な学習を重ねる必要があります。
また検察官が人を裁く際には、法律が基準となり、私的な感情を持ち込むことは許されません。
真実を追求するためには、法律、判例、捜査手法などを熱心に学び続けることが不可欠。
検察官は真実を探求し、周囲の影響を受けずに、確固たる法律に基づいて適切な処分を下す使命を担っています。
必要な知識を常に吸収し、アップデートし続けることが重要であると言えるでしょう。
冷静な判断ができる人
検事の職務は非常に過酷であり、個々の事件に対しては最大で23日間の期限が設けられています。
期間内に起訴の是非を判断しなければならず、複数の事件を担当している場合は、事務作業を含めて膨大な業務を遂行しなければいけません。
限られた期間だとしても 決して表面的な仕事をしてはならず、迅速かつ正確な判断力が求められる重要な要素となります。
検察権を行使する際には、常に中立性と公正さを重視し、人権の尊重が基本とされています。
検事は必要に応じてためらうことなく起訴し、刑罰を求める責任がありますが、どのような状況においても感情に流されて判断を下してはなりません。
冷静さを保ち、自身の感情を適切にコントロールできる人であれば検事として活躍できるはずです。
検察官のやりがい
検察官は刑事事件に関与する職業であり、事件の真実を明らかにし、加害者に適切な処罰を課すことで、被害者やその家族の心情を少しでも和らげようとする正義感が必要です。
そのため、被害者の意向を法廷で代弁し、彼らの苦痛や悲しみを軽減することは大きなやりがいを感じる要素となるでしょう。
また、検察官は弁護士や裁判官と共に法曹三者の一員であり、法律を駆使して適正な処罰を求めることに対しても充実感を得ることができるでしょう。
法律の趣旨や解釈、判例など、日常的に学んできた知識や経験を最大限に活かせる点も検事の魅力のひとつです。
被害者、加害者、その他の関係者の人生に影響を与える判断を日々求められるため、事件が無事に解決した際の達成感は非常に大きなものとなるでしょう。
検察官になるには年齢制限はある?大学の偏差値まとめ
検察官になるにはどのような選択があるのか、またその受験資格や年齢についてのまとめと、検察官になるには必要となる大学・大学院の偏差値をご紹介しました。
検察官になるルートはいくつか存在し、いずれも大変な努力が必要となります。
しかし、検察官の職業は使命感を強く持たなければならないので、立派な検察官として職務を遂行する為には必要な難関なのだと言えますね。
検察官を目指す方はこの記事を参考に受験計画を立ててください。