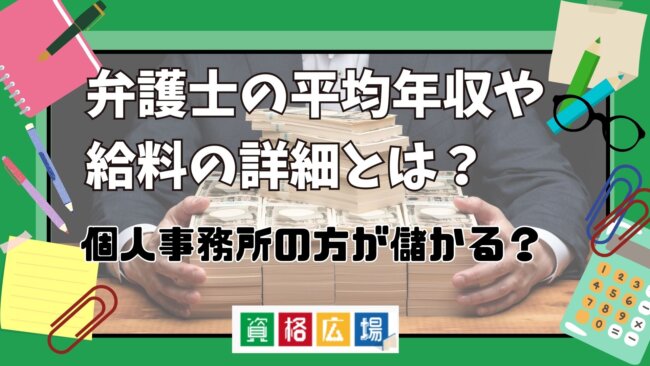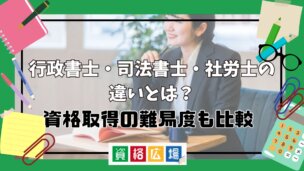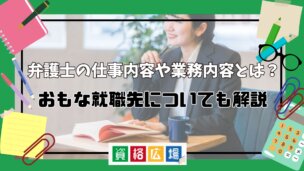昔から弁護士は高収入な職業として知られていますが、実際のところどのくらい稼いでいるかご存知ですか?
この記事では、気になる弁護士の平均年収や給料について詳しく解説していきます。
また、個人事務所など、働き方による平均年収の違いについても紹介していますので、弁護士の平均年収や給料を知りたい方はぜひチェックしてみてくださいね。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
司法試験予備試験合格におすすめの通信講座
弁護士の平均年収や給与事情
それではさっそく、弁護士の平均年収と給料について詳しく紹介していきます。
本当に弁護士が高収入な職業なのかどうか、その真相を解明していきましょう。
弁護士の平均年収
弁護士全体の平均年収は約1,000万円を超えるといわれており、給与にするとおおよそ40~60万円程度であり、ボーナスは約270万円程度であるとされています。
一般的な会社員の平均年収は約430万円という結果が出ていますので、一般の会社員と比べても弁護士の年収は非常に高いといえますね。
しかし、弁護士の平均年収や給与は年齢や性別、勤務先や勤続年数によっても左右されるともされています。
一般的に弁護士の年収は年齢とともに上がっていく傾向があり、60代以降も高年収を得られる可能性のある稀有な職種です。
反対に弁護士になって間もないころは実績や経験がないことや就職先が限られることで低くなります。
生涯年収は青天井
一般企業において定年まで勤務する場合、50代から役職定年が始まり、給与が減少することが一般的です。
一方で、弁護士の年収は年齢が上がるにつれて増加し、生涯年収は無限の可能性を秘めているとされています。
大手法律事務所でパートナーを目指す場合や独立して案件を獲得する場合でも、弁護士は自身の努力によって生涯年収を増やすことができる職業です。
弁護士は年齢とともに経験や実績が評価されるため、給与も無限の可能性を持っているので安泰だといえるでしょう。
地方や小規模事務所だと低め
弁護士の中には高収入を得ている者もいますが、世の中のニーズを捉えられず、十分な評価を受けていない弁護士も少なくあり、給与に格差が生じるのは避けられない状況です。
例えば、地方の法律事務所や小規模な事務所での勤務だけでは、年収や給与の向上は難しいと言えるでしょう。
しかしながら、弁護士の活動領域は伝統的な訴訟や交渉業務から企業法務にまで広がっており、インハウス弁護士という選択肢も徐々に普及しています。
弁護士として年収を向上させるためには、専門性に加えて、自身の能力や適性を正確に理解しておくことが大事です。
弁護士の働き方による平均年収
次に、弁護士の働き方による平均年収を見ていきましょう。
弁護士は働き方や雇われ方によって年収は大きく変動するといわれていますが、実際はどうなのでしょうか?
大手法律事務所に所属した場合や、独立し個人事務所を持つ場合など、弁護士の働き方で年収をまとめてみました。
大手法律事務所の平均年収
規模の大きい大手の法律事務所で働く場合、平均年収は約5,000万~1億円にものぼるといわれています。
大手の法律相談所の特徴としては、企業を顧客としているため年収にも関係してくるのかもしれません。
大手法律事務所で働くアソシエイト
部下の立場で働く弁護士のことを「アソシエイト」と呼び、大手法律事務所で働く弁護士はランクに分けられています。また、新人弁護士はアソシエイトからのスタートになります。
一般的な大手法律事務所のアソシエイトは、初年度から年収1,000万円を超えているといわれています。
大手法律事務所で働くパートナー
「パートナー」とは、法律事務所の経営にも関わっている役職の高い弁護士を指します。アソシエイトで実績を上げ、昇格を認められればパートナーになることができます。
法律事務所の売り上げにより報酬が変わるので、高収入が見込めます。そんなパートナーの年収は約1億円を超えることもあるようです。
中小法律事務所の平均年収
地方などで見られる小さな規模の法律事務所で働く場合、平均年収は約300~1,500万円と大きく差が開きます。
小さい法律事務所では、主に個人や中小企業を顧客としている場合が大半です。
中小法律事務所で働くノキ弁
「ノキ弁」とは、法律事務所の軒先だけを借りている軒先弁護士のことを指します。
ノキ弁は事務所の一角を借りて弁護士業を行うので給料は支給されず、自分で営業などを行う必要があります。
そんなノキ弁の年収は約300万、弁護士の平均年収を大きく下回っているのが現状のようです。
中小法律事務所で働くイソ弁
「イソ弁」とは、弁護士事務所に雇われて働く居候弁護士のことを指します。大半の新人弁護士はイソ弁からスタートする方が多いです。
扱う案件が多いほど、雇われている立場に関わらず年収約1,500万円以上稼げるといわれています。
企業内弁護士の平均年収
大手の企業や外資系企業の法務部で企業内弁護士として働く場合、平均年収は約1,500万円といわれています。企業によっては資格手当がつくことも。
法務部にて法務業務を中心に業務を行いますが、一般の弁護士と仕事内容とは異なる場合が多いようです。
個人事務所の平均年収
独立開業し、個人事務所で働いている場合は、年収数億円になる可能性も。
実際に個人事務所で1億円以上稼がれている方も少なからず存在します。しかし一方で、年収200万円以下の個人事務所を経営する弁護士がいるのも事実です。
独立開業し個人事務所で働いている方の年収にはかなり差がみられるようです。
弁護士の年齢による平均年収
最後に、弁護士の年齢による平均年収を確認していきましょう。
やはり、経験・勤続年数が長いとされる40~50代は、弁護士の中でも最も年収が高い年齢といえそうな結果になっています。
20代の弁護士の平均年収
20代の弁護士の平均年収は約580~730万円といわれており、平均給料は35~45万円といわれています。また、ボーナスは約140~180万円程度です。
20代の弁護士は、まだ新人弁護士と呼ばれる時期なので、弁護士全体の平均年収に比べても年収は低いといえます。
30代の弁護士の平均年収
30代の弁護士の平均年収は約800~910万円といわれており、平均給料は50~60万円といわれています。また、ボーナスは約200~230万円程度です。
弁護士は30代を超えてくると、高収入といってもいいほど稼いでいるといえます。それでも弁護士全体の年収には及びませんが、一般的な会社員の平均年収の倍は儲けていますよね。
40代の弁護士の平均年収
40代の弁護士の平均年収は約1,000~1,100万円といわれており、平均給料は65~70万円といわれています。また、ボーナスは約260~290万円程度です。
40代でようやく弁護士全体の平均年収と同額になってきました。役職がついたり、独立し成功する方が多い年代であることからこの額の年収をたたき出しているのかもしれません。
50代の弁護士の平均年収
50代の弁護士の平均年収は約1,200万円といわれており、平均給料は75~80万円といわれています。また、ボーナスは約300万円程度です。
弁護士も50代になってくると、ベテラン弁護士と呼ばれるようになってきます。そのため年収が他の年代と比べ高収入であることにも頷けますね。
男女別の弁護士の平均年収
厚生労働省の令和3年賃金構造基本統計調査によれば、男性弁護士の平均年収は約970万円であり、女性弁護士は約879万円といったデータがあります。
一般的な会社員の平均年収と比べると高いものの、女性弁護士の平均年収は男性に比べて低い状況です。
年収差の要因としては近年女性弁護士の数が増加している一方で、年収が最も高い40代から50代の女性弁護士がほとんど存在しないことが挙げられます。
しかし、実際には近年の弁護士の年収における男女差はそれほど大きくなく、20代から30代の弁護士の年収は男女ともにほぼ同等の水準に達しています。
弁護士として年収を上げる方法
ここでは、弁護士として年収をあげる方法についてご紹介します。
専門性を身に付ける
弁護士として年収をあげるにはまず専門的な知識を習得することがおすすめです。
特定の法律分野や業界において専門性を高めることで、その領域の専門家としての地位を確立することができます。
例えば、知的財産権、M&A、国際取引などの特定の分野における専門的な知識や技術は高く評価され、報酬の増加につながることが一般的です。
また、一般的な法律分野よりも競争が少ないニッチな領域を選び、その分野での先駆者となることで、独自の価値を上げるのもいいでしょう。
最近では、所属事務所の方針や契約内容によりますが、個人受任が可能な法律事務所も増えてきています。
大手・外資系の法律事務所に転職する
年収を向上させるためには、今より良い条件の職場に転職するのもおすすめです。
一般的に、大手法律事務所や外資系法律事務所は、高い報酬を提供することが多いです。
大規模な案件に関与する機会が増えることで、年収も上昇する傾向があります。
また転職によって年収を増やすためには、前述の専門性の習得や、徹底した企業研究が不可欠です。
転職を検討する際には、弁護士の転職に特化したエージェントを利用することで、自身のスキルや経験を最大限に活かせる職場を見つけやすくなるでしょう。
最近では、弁護士向けの転職サイトやエージェントも充実してきているため、積極的に利用してみて下さい。
独立・開業する
弁護士として年収アップを目指すために独立や開業を目指す方もたくさんいます。
実際、10年以上の経験を持つ弁護士の70%以上が経営者として活動しているといわれており、独立弁護士の平均年収は1,000万~3,000万円程度だといわれています。
ただし年収が無限大になる一方で、事務所や企業に所属していた時期と比べて年収が不安定になることも覚悟しなければなりません。
依頼を安定的に獲得できれば年収の向上も期待できますが、逆に苦戦すれば年収が減少し、事務所運営にかかるコストによって赤字になるリスクもあるため注意が必要です。
独立後に成功を収め続けるためには、事前の準備や継続的な努力、情報の更新が不可欠であり、常に弁護士業務や経営について考える必要があるでしょう。
企業内弁護士になるには?仕事内容や年収とデメリットはあるのか調査
弁護士になるには
弁護士は、幅はあれど平均年収は非常に高く、とても魅力的な職業であると言えます。
しかし、弁護士になるためにはいくつかの試験に合格しなければなりません。
弁護士になるまでのルートについて、簡単にみていきましょう。
司法試験に合格しなければならない
弁護士になるためには、司法試験に合格しなければなることができません。
司法試験は文系国家資格の中でも最高レベルであり、司法試験に合格することができれば、弁護士・検察官・裁判官になることができます。
しかし、この司法試験も受けるまでがかなり厳しくなっており、受験資格を得るのも困難となっています。
司法試験の受験資格を得るためには法科大学院コースと司法予備試験コースが存在するので後に詳しく紹介します。
法科大学院コース
次に法科大学院コースですが、名前の通り法科大学院を卒業することで司法試験の受験資格を得ることができます。
法科大学院コースを選択したからといって司法予備試験コースがなくなるわけではないので、法科大学院で勉強しながら司法予備試験に挑戦することもできます。
法科大学院は法学既習者は2年間、未習者は3年間かけて学習を行っていくので、日中働いている社会人には向いていないコースです。
司法予備試験コース
司法試験の受験資格を得るもう一つの方法が、司法予備試験に合格することで受験資格を得る方法です。
司法予備試験を受けるには受験資格などは年齢関係なく誰でも受験することができます。
また、司法予備試験コースからの司法試験した方の合格率は90%近くで司法予備試験合格=司法試験と考えても大袈裟ではありません。
自分がどちらのコースがあってるのか吟味して選択するようにしましょう。
司法予備試験コースを目指すならアガルート

弁護士は給料は平均と比べるとかなり高く、弁護士になることができれば将来は安泰と言えますが、司法試験は難易度のかなり高い試験となっています。
法科大学院を卒業していない方は司法予備試験コースとなりますが、司法予備試験も司法試験と同じくらいの難易度で独学では厳しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方は通信講座を利用することをおすすめします。
アガルート通信講座は難関国家資格を専門に扱う通信講座となっており、様々な魅力があるので特徴や特色について紹介していきます。
業界でもトップクラスの合格率
アガルート通信講座では業界でもトップクラスを誇っていることが特徴の1つとして挙げられます。
司法予備試験の合格率は公開されていませんが、司法試験では合格した人の45.3%がアガルート受講者となっており、アガルート通信講座の充実さが分かります。
このような合格実績を残している要因として、司法試験に深く精通したプロ講師の講義と、プロ講師達が監修したテキストが使われているなど様々な魅力があります。
【2024年・2025年合格目標】司法試験|予備試験最短合格カリキュラム
司法試験|予備試験最短合格カリキュラムは今から学習を始める方を対象したカリキュラムとなっています。
こちらのカリキュラムでは合格に必要な情報や知識が詰められており、最短(1年)での合格を目指すことができます。
また、司法予備試験コースも法科大学院コースのどちらも狙うことできるこちらのカリキュラムは初学者や法科大学院コースか司法予備試験コースで迷っている方に非常におすすめとなっています。
【2024年4月入学目標】法科大学院入試(ロースクール入試)専願カリキュラム
アガルートでは司法予備試験対策も行うことができますが、法科大学院コースにも対応しています。
2024年4月入学目標のカリキュラムでは約1年間の学習を通して難関法科大学院入試を突破できるような講座が展開されています。
難関法科大学院では司法試験の合格率が高くなり、より司法試験合格に向けて近づくことができます。
弁護士の給料や平均年収は?個人事務所は儲かる?
いかがでしたか?
弁護士の気になる給料や平均年収を紹介してみました。弁護士は意外にも、年齢や働き方によって大きく収入が異なります。
独立し成功を収めた個人事務所を持っている弁護士が高収入を得ている一方で、低所得な稼げない弁護士もいることも事実です。
最近では安定した収入を得ることができる企業内弁護士として働く弁護士も多く、弁護士の収入や働き方が昔とは変わってきているのかもしれませんね。