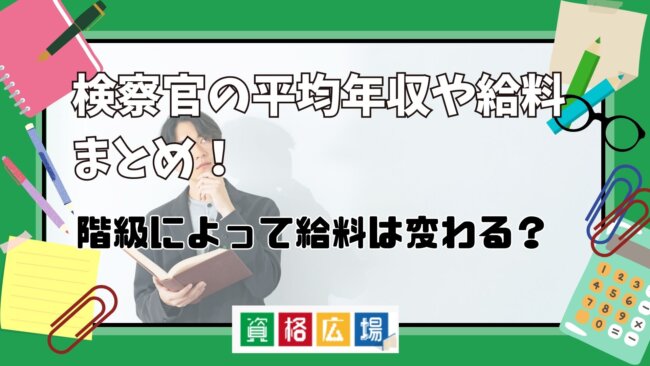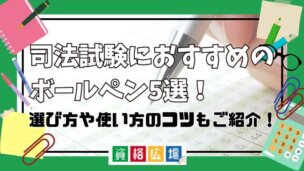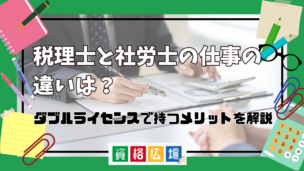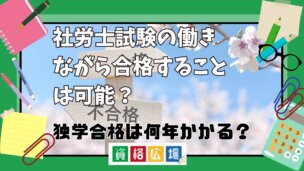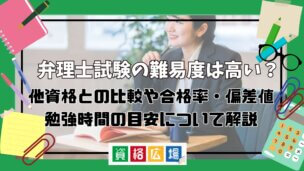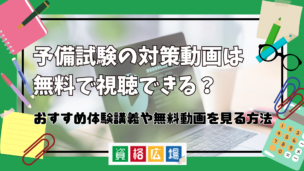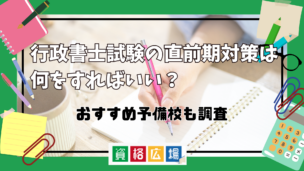検察官は法曹三者と呼ばれているうちの1つで、裁判官・弁護士・検察官の職業を指しますが、法曹三者は給料が高いのはご存知ですよね。
しかし具体的にはどれくらいの年収なのでしょうか?
検察官の業務が大変だという事はよく耳にしますが、国家公務員の中でも給料に関してトップクラスと呼ばれています。
今回は検察官の平均年収や階級によって変わるのか?など収入の疑問についてご紹介していきます。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
司法試験予備試験合格におすすめの通信講座
検察官の給料について
検察官の給料は「検察官の俸給等に関する法律」という法律で定められていて、独自の給与形態となっています。
また検察官は身分を保障されていて、待遇面で第三者が介入できない仕組みになっています。
法律で定められている給与形態とはどういったものなのでしょうか?
検察官の給料の仕組みについて見ていきましょう。
検察官の給料システム
検察官の給料形態は一般の国家公務員とは違い、検察官は法律で階級によって支払われる給料額が変化します。
検察官は一定の受験資格を認められれば試験を受け、合格すれば等級が上がります。
20代で検事として任官された場合には20等級となり、およそ10年程度勤務すれば8号程度です。
1号を目指すには30年以上の勤続年数とそれまでの功績があり、試験に合格しなければなりません。
検察官の初任給は月額23万円で、最も等級の高い1号の検察官では、月額117万円になります。
検察官の給料は一般のサラリーマン平均よりも全体的に多くなっています。
検察官の給料事情
検察庁は行政機関であり、検察庁に所属する検察官のトップは検事総長です。
法務省の職員の内訳に133人の検事を充てると定められていて、法務省での主要ポストの多くを検事が占めている状態です。
つまり法務省の上部機関は検察が指揮を取っているのです。
検事総長の年収は他の大臣と同額となっていて、約2,900万円で、東京高検検事長は副大臣などと同額の約2,800万円となっていて、各都道府県の地方検察庁の検事正、次席検事は次官と同額の約2,300万円と言われています。
ちなみに検事正の給料はエリート警察官僚の約2倍であると言われています。
検察官の給料は高いと言われていますが、狭き門を通過してきただけの給料であると言えますね。
検察官の平均年収は?
検察官は国家公務員で、高収入と言われていますが、具体的にはどの位の年収なのでしょうか?
検察官の平均年収は一般の国家公務員よりも少し多いとされています。
検察官の給与形態は特殊なものとなっているので、ここでは平均年収や年齢別の平均年収はどのように違ってくるのかをご紹介していきます。
検察官の平均年収
検察官は階級により給料額に変化がありますが、検事全体での平均年収は以下の通りとなります。
- 平均的年収:613万円
- 平均年収推移:272万円~1,453万円
- 月額:約39万円
一般の国家公務員の平均年収は600万円~800万円です。
階級によって変化するので給料幅が非常に大きくなっていて、また初任給では月額23万円ですが、十分に昇給アップが望める職業なのです。
これにボーナスや手当が支給されるので、検事総長の等級まで上がれば、年収が2,300万円程度になります。
残業代
検事は過酷な職種だと言われ残業も多いと言われていますが、残業代はつかず、みなし残業として給料はみなし労働時間を想定した上で支払われています。
検察官の初任給は?
検事と副検事では年収の差は大きく、検事20号としての初任給は23万円となっていて、一般の国家公務員の行政よりも高い金額になっています。
それに付け加え、様々な手当て等が支給されます。
一般的な職種での平均初任給では大卒で約20.6万円となっていて、検事の初任給は一般の大卒の同世代よりも多くなっています。
しかし、検事になるまでの試験や修習期間などを考えると、初任給を貰う年齢は高くなっています。
副検事について
副検事とは主に勤務経験3年以上の検察事務官が特別孝試という試験に合格し、副検事となります。
副検事は検察庁内でも、比較的軽微な事案を担当する事が主な業務です。
副検事は17号からのスタートとなり、支給額は21万円となり、検察官の中では最も低くなっています。
検察官の年齢別平均年収
検事の年齢別の平均年収は以下のようになります。
| 年齢 | 平均年収 |
| 20~29歳 | 349.4万円~435.2万円 |
| 30~39歳 | 478.1万円~545.6万円 |
| 40~49歳 | 613.0万円~686.6万円 |
| 50~59歳 | 735.6万円~705.0万円 |
年齢別で見ていっても年齢と共に年収が上がっていて、どの年齢でも平均的な同世代の年収よりは多い傾向にあります。
司法試験・予備試験講座はアガルートアカデミーがおすすめ!

司法試験・予備試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめです。
フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、法律関係の勉強を初めてする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。
また、充実したカリキュラムや一人ひとりに合わせた手厚いサポートも魅力的です。
司法試験合格者の講師が指導!
アガルート公式HPはこちら
検察官の階級と給料の関係
検察官の給与は階級に応じて変化していて、毎年国会において審議が行われていて給与は法律で定められていますが、勤務年数を重ね試験を合格すれば昇進する事が可能になります。
具体的には一般の公務員と同じで昇進する為の試験を受け、棒給を月収で割る年棒制度が採用されています。
階級別給与額と年齢によって変化するボーナス額を見ていきましょう。
階級と給料
検察官の給与幅は非常に多いですが、階級で見る給与ではどの程度上がっていくのでしょうか。
階級で定められている給料額は以下のようになります。
以下の給与額に加えて、ボーナス・扶養手当てや通勤手当などが更に支給されます。
| 職階 | 検事 | ||||
| 検事総長 | 1,470,000円 | 1号 | 1,178,000円 | 11号 | 367,100円 |
| 2号 | 1,038,000円 | 12号 | 343,800円 | ||
| 次長検事 | 1,203,000円 | 3号 | 968,000円 | 13号 | 322,400円 |
| 4号 | 820,000円 | 14号 | 307,900円 | ||
| 東京高等検察庁検事長 | 1,306,000円 | 5号 | 708,000円 | 15号 | 291,400円 |
| 6号 | 636,000円 | 16号 | 282,200円 | ||
| その他の検事長 | 1,203,000円 | 7号 | 576,000円 | 17号 | 253,500円 |
| 8号 | 518,000円 | 18号 | 254,800円 | ||
| 9号 | 423,000円 | 19号 | 249,400円 | ||
| 10号 | 389,300円 | 20号 | 244,000円 | ||
年齢で変わる検察官のボーナス
検事のボーナスは年齢によって以下のように定められていて、ボーナス支給額は50代が最も多くなっています。
| 年齢 | 支給額(月額) |
| 20~29歳 | 87.4万円~108.8万円 |
| 30~39歳 | 119.5万円~136.4万円 |
| 40~49歳 | 153.3万円~171.6万円 |
| 50~59歳 | 183.9万円~176.2万円 |
| 60~64歳 | 124.1万円 |
検察官のボーナス額は基本給の3ヵ月分程度が目安となっていて、平均月収50万円であれば、ボーナス支給額は約150万円となります。
ボーナス支給は夏と冬の2回となっていて、4ヵ月分で算出し、勤務年数に伴って支給額が値上がっていきます。
検察官が年収を上げる方法
先にも述べたように検察官の給与は号俸によって決まるので、年収を上げるには号俸を上げる必要があります。
具体的には勤続年数を重ね、昇進のための一定の受験資格が認められた後、試験に合格することで昇給ができるようになります。
検察官としての初任給は誰でも検事20号から始まり、月給は237,700円となります。
仮に毎年1回の昇進が可能であれば、20年後の46歳頃には検事1号に昇進し、月収は100万円以上も期待できるといわれています。
ただし昇進が順調に進むとは限らないので。日常的に真摯に仕事に向き合うことが大切です。
検察官になるには
検察官になるには司法試験に合格しなければならず、弁護士や裁判官から転身する人もいます。
ここでは、司法試験を受験し検察官になるルートについていくつかご紹介します。
予備試験ルート
検察官になるためには司法試験に合格しなければなりませんが、司法試験を受験するには司法試験予備試験に合格するか、法科大学院を修了して受験資格を得る必要があります。
予備試験の場合、毎年実施される司法試験予備試験に合格することで、司法試験の受験資格を得ることができます。
予備試験の合格率は例年約4%と、他の資格試験と比較して非常に低いため、検察官を目指す際の最初の難関は予備試験に合格することだと言えるでしょう。
法科大学院ルート
法科大学院のルートでは、各大学院が独自に設定したカリキュラムを修了することで、司法試験の受験資格を取得できるルートとなっています。
これまでは未修者コースでは3年間、既修者コースでは2年間のカリキュラムを履修する必要がありましたが、法曹コースでは法学部と法科大学院を最短5年で修了できるようになりました。
さらに、2023年からは特定の要件を満たすことで法科大学院在学中に司法試験を受験できるようになり、早期に受験ができるようになりました。
また司法試験に合格すると、法曹になるための研修である司法修習を受けることになります。
研修は1年間の期間で、司法試験では不足している実務に関する知識を学ぶことが求められます。
修習の最終段階では、通称二回試験と呼ばれる卒業試験に合格することで、正式に法曹としての資格が与えられます。
司法修習は検察官のリクルートも兼ねており、各試験の成績だけでなく、受験者の人柄や検察官を目指す動機、仕事に対する熱意なども評価の対象となります。
検察官になれるルートは?大学や予備試験・司法試験についての詳細
検察官の平均年収や給料事情!階級で年収は変わる?まとめ
検察官の平均年収や給料についての事情や、階級・年齢などの給料の変化をご紹介しました。
階級や年齢によって支給額が変化し、検察官は勤務年数に応じて昇給試験を受けている事が分かりました。
検察官の給与形態は法律によって定められていて、それ以上の給料を望む事はできなくなっていますが、検察官の職業は福利厚生が手厚く、様々な手当てなど給料以外の支給もあるので、比較的高額です。
国家公務員の中でもトップクラスの給料だと言われていますが、難しい試験を何度も通過し、狭き門を潜り抜けてきた検察官の職業は過酷で、残業が常態化しているとも言われているのでプライベートな時間よりも仕事に注ぐ時間や労力が多い事を考えるとその収入も納得です。