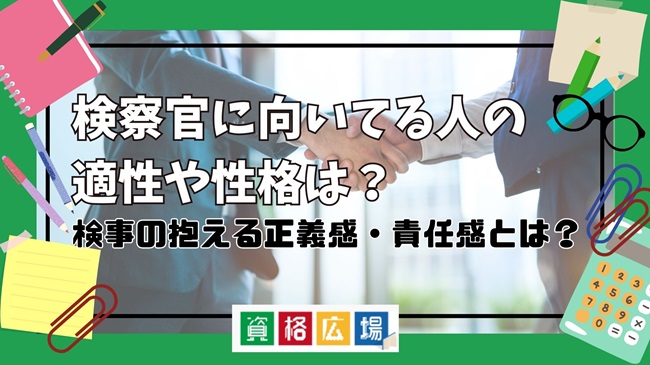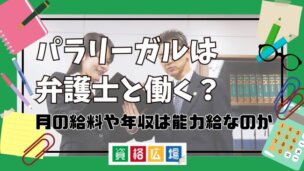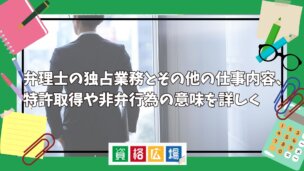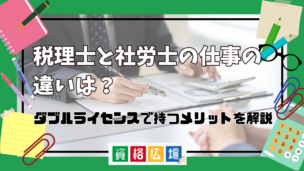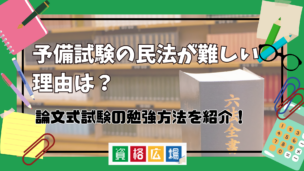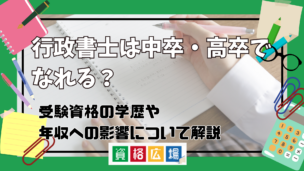検察官の仕事は「責任感」と「正義感」を基本とした、多くの判断が求められ、誰でも試験さえ通過できればという訳にはいきません。
検察官に向いてる人はどんな性格で、どういった適性が必要となってくるのでしょうか?
今回はそんな検察官が抱える責任感・正義感とはどんな事か、検察官に向いてる人の適性や性格など、検察官になる為に必要な資質について、ご紹介していきます。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
司法試験予備試験合格におすすめの通信講座
検察官の正義感・責任感とは
検察官という職業に関して向いているのはどんな人なんでしょうか?
警察への指揮や聞き取り、組織との関わり、裁判での業務など様々ありますが、それぞれに対応できる資質が必要となってきます。
まず検察官に向いてる人とは、正義感と責任感に関してどんな価値観で、どういう性格や適性を必要としているのかを見ていきましょう。
検察官の存在
検察官は法律の専門家として刑事事件を主に担当し、捜査の為に被疑者や被害者に聞き取り調査を行います。
事件によって被疑者や被害者にも様々な思いがあり、話したくない内容も聞かなければならない状況も多くあり、その場合の心のケアも必要となってくるのです。
検察官は事件の真相が解明するまで被疑者も被害者も公平に対応する事を意識していて、被害者の傷や被疑者の孤独感なども敏感に察知し、柔軟な姿勢で少しでも早く真相解明の為に正しい判断を目指して働いている頼もしい存在です。
検察官の役割
検察官の役割は正しい判断で処分を決断する事です。
その為にはどんな罪であっても、悪は許さないという正義感が必要となり、自分の判断で人の人生を大きく左右させる役割である為、常に責任感を持って冷静な判断を下さなければなりません。
そのために、誰にも影響されず自分の判断に自信を持って「この判断は間違っていない」と胸を張って主張できるよう努めなければならないのです。
検察官の仕事は個人的な感情で判断に影響するような事があってはなりません。
検察官の立場
検察官は弁護士と違い、組織で活動する職業となります。
その為、個人で業務する印象も強いですが、検察官の業務は人と関わる事が多く、個人の業務で軸となるのは個々の「判断力」であるという事で、被疑者や被害者の取り調べ、その家族などへの説明やケア、事件によっては警察や弁護士と協力したり、事件ごとの上司への相談や認可の申請など、常に組織や事件関係者などの多くの人の中で働いているという意識を強く持って業務を行わなければなりません。
検察官は独任官庁と呼ばれますが、上からの指令は絶対であり、何もかも自分の判断だけでスムーズに行われる訳ではありません。
検察官のなり方
検察官になるには予備試験・司法試験に合格し、1年間の司法修習を受講する必要があります。
予備試験・司法試験は難関国家資格試験の1つとして挙げられるほど難しい資格試験なので、独学ではなく予備校や通信講座の利用がおすすめです。
大手通信講座のアガルートアカデミーは、合格率が全国平均の4.9倍の合格実績を誇り、最短合格も目指せる通信講座となっています。
検察官の適性
検察官に求められる事柄は多くあり、複数の業務での適性が求められ、それはその人がそれまでに培ってきた資質であり、ある意味才能と呼べるものだとも言えます。
適性のある検察官に向いてる人は被疑者や被告人を守る為の正義感や責任感が強く、常にそれを意識して行動しています。
検察官の適性として重要になってくるのは以下のようなものがあります。
人に従う従順さ
検察官という職業は組織で働き、それぞれの刑事事件を処理していく上で、様々な許可を取らなければなりません。
検察官には個々で多くの権利がありますが、上から許可されなければ通らず、裁判においても例え異議申し立てを行っても却下される場合もあります。
その場合の臨機応変な対応や、上からの指示に従える柔軟さも必要です。
そして、検察官は事件に関して新たに判明した事があれば、どんな些細な事でも上に報告を行わなければなりません。
じっくり考え込み、後でまとめて報告しようというタイプは検察官に向かず、検察官に向いてる人は常に迅速な行動を行う事を心掛けています。
公平な判断ができる冷静な心
検察官が刑事事件を処理していく上で必要となるのは、冷静な判断力や即時の決断です。
検察官の業務は判断力が軸となり、証拠や聞き取りでの確信や被疑者や被害者と自身の距離感、警察への指揮、起訴するかしないかなど多くの判断が必要となる職業です。
被疑者や被害者どちらが正しいかは法律に沿って判断しなければならず、個人的な私情を持ち込む事は許されないのです。
日本では起訴する事ができるのは検察官のみとなっていて、それによって結果が大きく変わってくるので、責任感も大きいものとなります。
探求心の強さ
検察官は常に法律の知識を使って、事件を正しい方向へ導き、真実を明らかにしなければなりません。
あくまで、周囲が納得しているような状況であっても、法律に則って自分の納得がいくまで追求する探求心が大切なのです。
検察官に向いてる人は周囲に流されず、はっきりとした根拠を持って適切な処分を決断する使命を持っています。
その為には、事件には一切妥協が許されず、しっかりとした意思を持ち、何度も調書や証拠を見たり、聞き取りを行ったりという真相究明をしたい、という強い自主性と責任感の強さが必要となります。
検察官に向いてる人の性格
司法修習を受けているとそれぞれの個性や資質が垣間見え、検察官・裁判官・弁護士それぞれに向いてる性格・向いていない性格があります。
検察官を目指している場合にも、教官に弁護士に誘われて弁護士になったという声もありました。
その前例でもそれぞれ性格の向き不向きがあり、検察官に向いてる人の性格はどういったものがあるのか見ていきましょう。
検察官に向いてる人の性格:思考編
検察官に向いてる人の性格として思考力があります。
検察官は組織の中で活動をし、業務でも多くの人が関与してきます。
お互いに協力し合い、組織の中で活動しているんだという意識を持った協調性が必要となります。
そして、事件の処理に関しても、調査を行った上で出た結論に対して、責任感を持ち説明しなければなりません。
そのためには自信を持って、法律に沿った正しい判断ができる事、決して不正を許さず、事件をしっかり公平に処理するという正義感が必要になります。
- 協調性
- 正義感
- 根気強さ
- 自信
検察官に向いてる人の性格:体力編
検察官の業務には体力・精神力も重要となってきます。
基本的に検察官の日々の業務はめまぐるしく変化し、行う業務も多岐にわたります。
その為、残業や深夜・休日の呼び出しなどにも対応できすぐに行動できる強い精神力と、業務を繰り返し様々な事件について考える事が多いので、自分自身の精神が弱らないように、業務の合間を見つけ休暇を取得するなど、心身や健康面で自分を客観視した自己管理ができなければなりません。
また、検察官は担当する事件に関して被害者やその家族に強く責められる場合もあります。
その場合にも、確証を持った正しい説明を行う必要があり、責任感が伴う業務の為、業務上でもそれに対応できる強い心が必要です。
- 打たれ強い精神力
- 行動力
- 自己管理ができる
検察官に向いてる人の性格:社会性編
検察官として職務をしっかり遂行する為、常に勉強をし続けなければなりません。
そして、日々の業務でも熱心に事件に関して妥協を許さず、納得のいく答えが見えるまで諦めない情熱が必要不可欠です。
検察官の業務は慌ただしく、時間も限られているので仕事に関しての業務計画をしっかり立て、決まった時間に徹底的に調査するという姿勢が必要となります。
そして、団体行動の輪を乱さず、協力し合うという意識を持って職務を遂行する為にも、真面目さと柔軟さのバランスが必要になってきます。
- 仕事への情熱
- 真面目である
- 柔軟な対応力
検察官に向いてる人の適性や性格とは?責任感・正義感の必要性まとめ
検察官に向いてる人の適性や性格についてと、検察官が抱える責任感や正義感についてご紹介しました。
検察官の仕事は様々なシーンでそれぞれに合った対応が求められる為、全体的な能力バランスが重要です。
適性や性格から見ても検察官は適応能力が高く、何でも卒なくこなせる印象ですね。
そして人の人生を大きく変化させてしまう責任感や被疑者や被告を守る正義感の為に日々努力する精神力が必要となります。
いつどんな刑事事件が来ても対応し、限られた時間で解決に導いていく検察官の仕事はまさに大きな責任感と正義感を胸に忠実な心を自主的に感じ、持つ事をできる人こそが、検察官に向いてる人で検察官の使命だと言えますね。