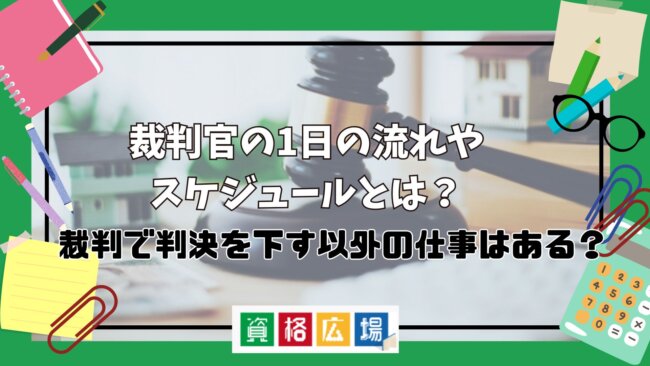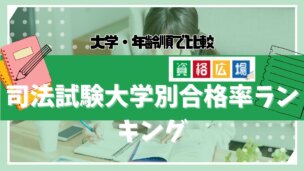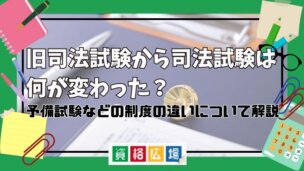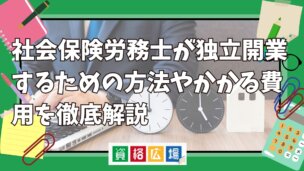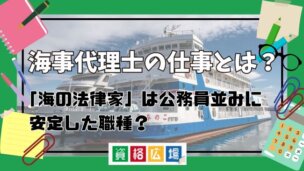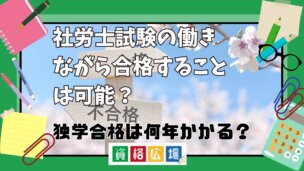裁判官の仕事は裁判の終わりに判決を下すだけではありません。
判決を決める前に裁判に向けた資料や証拠について読み調べたり、新しい起訴状について調べたり、終わった裁判資料を整理したりと仕事が満載なんです。
裁判所の種類によっても異なりますが、ある裁判官が朝起きてから夜寝るまで、どんなサイクルで1日のスケジュールを組むのか、1日の流れをご紹介していきます。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
司法試験予備試験合格におすすめの通信講座
裁判官とは
裁判官は全国の裁判所において中立的な立場から法律に基づく判断を行う職務を担う仕事です。
憲法第76条第3項には、「裁判官は、憲法及び法律に従う限り、良心に基づいて独立して各事件を判断する」と明記されており、具体的には、提出された資料を精査し、当事者や弁護士、検察官の主張や証拠を照らし合わせて法に基づく判断を下したりします。
内閣府男女共同参画局の発表によれば、2021年12月時点での裁判官数は3,441名(男性76.3%、女性23.7%)在籍しているといわれています。
また裁判は大きく分けて刑事裁判と民事裁判に分類され、それぞれの業務内容は異なります。
刑事裁判では、被告が罪を犯したかどうかを判断し、罪が認められた場合には適切な刑罰を決定し、裁判員制度が導入されている場合には、裁判員と共に判断を行います。
民事裁判は個人の生活に関する訴訟を扱い、裁判官は当事者双方の意見を聴取し、証拠を調査して判決を下しますが、調停者としての役割も重要です。
さらに、家庭内や親族間の問題が調停で解決しなかった場合に行われる家事審判や、非行の恐れがある少年に対して教育的な処遇を決定する少年審判も担当します。
裁判官の職務は刑事裁判や民事裁判の審判にとどまらず、逮捕令状や捜索差押令状の許可も重要な業務です。
不当な逮捕や捜索が行われないよう、法律に基づいて判断し、相当な理由が認められれば令状に押印します。
このように、裁判官の職務は多岐にわたることが理解できます。
裁判官の1日の流れ
6種類ある裁判所の全てに該当するわけではありませんが、裁判官の1日の流れとして基本的に裁判所の一般職員が出勤した後で裁判官が出勤します。
裁判官に渡さなくてはならない資料の用意や裁判官の部屋の掃除等で、裁判官が居ない時にしておかなくてはいけない事があり、それを邪魔しないようにとの判断から出勤時間に決まりのない裁判官は少し遅めに出勤します。
そして資料に目を通し、当日に裁判が無ければ後日の裁判に向けた準備の為、資料を読み調べ、弁護士や検事とのやり取りをし、判決文を作成していくというようなスケジュールを組むことが多いです。
裁判所の大きさや裁判官の人数にもよりますが、忙しい裁判所だと一人の裁判官が抱える件数は年間で250~300件となり、毎日新しく事件が割り振られる為、最低でも1日20件以上の判決を作成しなくてはなりません。
民事事件担当の裁判官
民事事件を担当する裁判官は、訴えた人が加害者に向けて訴えた理由が正当かどうかの判断をします。
そして民事裁判では有罪か無罪かの他に「和解」という第3の解決方法を取ることが少なくありません。和解した方がお互いの為になる裁判がそれだけ多いと言う事なのでしょう。
民事裁判の特徴としては裁判になる前に訴えられた側の話を聞くことが無いので、裁判になって初めて相手の言い分を理解する事が多くあります。
近年民事事件が増えてきて1件1件が長引くことも多いので、民事事件を担当する裁判官はスケジュールを立てる事がとても難しくなっています。
刑事裁判担当の裁判官
刑事事件を担当する裁判官は、警察や検事が集めた証拠が刑事訴訟の証拠になるかどうかの判断もします。
そして裁判中には有罪であると訴える検事と、有罪ではない若しくは有罪であっても量刑が軽くなるようにとする弁護人に、どちらに発言させ、どう進めていくのかという司会のようなことをするのです。
その他には犯罪を犯した人が心の病で訴えられない時に強制的に治療させるかどうかの判断をするのも刑事裁判担当者の仕事です。
裁判官の勤務形態
裁判官は基本的には勤務時間に決まりはなく、法廷が開かれない土日祝日は休みとされていますが、忙しい裁判所に任官されていると土日祝日関係なく自宅や裁判所に出向いて仕事をします。
下級裁判所の裁判官の評価は高等裁判所長官が地方・家庭裁判所所長により作成された評価書を基にして決定して、人事異動を決めていくのです。
判事補から判事、判事の中から裁判長や各裁判所所長を決めて、さらに全国への転勤が決まっていきます。
裁判官は数年で転勤する!
裁判官は3年ごとに転勤する事が決められています。全国各地にある裁判所を転々とする事もありますが、一応毎年8月に希望地の調査票を提出します。
その希望地が通ることは少なく、親の介護や子どもの学校等の理由で転勤を拒否する方もいます。
しかし、拒否した場合は同期より出世が遅れたり裁判所の裁判長になれない等の弊害が起こる可能性や、次の任地が条件が低いところになる事があるのです。
裁判官には夜勤がある?
地方裁判所では裁判官が宿直する事があります。これは刑事事件で令状が必要になった時に地方裁判所で発付するために、24時間365日刑事裁判官が泊まり込みで夜間・休日に当番制で夜勤や休日出勤しているんです。
裁判官が少ない地域では民事裁判担当の裁判官が請け負う事もあり、受付は裁判所職員がするので裁判官は裁判所もしくは近くの家か宿泊施設で待機しています。
令状が必要な時以外には刑事事件での身柄拘束に対し、不服申し立てがあった際に違法かどうかの判断を裁判所にしてもらう手続きがあり、これは裁判官3名での判断が必要なため、夜中でも休日でも裁判官は呼び出されて審議します。
司法試験・予備試験講座はアガルートアカデミーがおすすめ!

司法試験・予備試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめです。
フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、法律関係の勉強を初めてする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。
また、充実したカリキュラムや一人ひとりに合わせた手厚いサポートも魅力的です。
司法試験合格者の講師が指導!
アガルート公式HPはこちら
地方裁判所判事補の1日
大抵の地方裁判所職員が朝8時半には出勤し、裁判所自体が8時45分に開館します。裁判官は出勤時間を決められていませんが、大体が9時頃に出勤する事が多いです。
もちろん裁判があるときはその時間までに出勤しておく必要がありますが、勤務時間に規定が無いので裁判所に居なくても事件の処理さえ適切に行っていれば自宅や図書館で仕事をすることも出来ます。
1日に数件の法廷と証人尋問をする事もあるので、資料整理や判決文作成もこなしていく量を考えてスケジュールを決めていかなくてはなりません。
実際の裁判官がどのようなスケジュールで1日の流れを作っているのか、とある地方裁判所刑事部判事補を例にしてみました。
裁判のない1日
午前9時~ 出勤すると決裁書の入ったケースから資料を取り出し、新しい起訴状や継続中の事件の資料を読み込みます。そして1日のスケジュールを組み、それに沿って仕事をこなしていきます。
その後昼休憩までを資料読みや書記官が作成した調書に目を通したり、事件の打ち合わせをしていきます。
午後12時~ 昼休憩の時間も決められていない為、自由にお弁当や外に出てお店で食べたり、家が近い方であれば自宅で食べる方もいるそうです。
午後1時~ 朝にチェックした決裁書のケースに書類が増えている為、また資料を取り出して目を通していきます。
書記官が作成した以前の公判の記録や次の裁判の資料のチェックをし、資料化へ必要な資料を借りに行く事も。
翌日に裁判と証人尋問があるので事件の記録に目を通し、裁判の準備をして、判決文の作成をするところまで進めておいて、夕方6時ごろに帰宅します。
業務が滞っている時には家に仕事を持ち帰り、夜寝る前や朝早く起きて出勤前に作業する事もあります。
裁判がある1日
午前9時~ 裁判が10時からあるので、それまでに決裁書の入ったケースの中の資料をチェックします。そして1日のスケジュールを組み、それに沿って仕事をこなしていきます。
午前10時~ 本日1件目の裁判。先輩裁判官と共に3人で公判にあたります。起訴状朗読から始まって、検事の論告・求刑、弁護人の弁論したところで判決期日を定めて1時間足らずで修了。
午前11時~ 2件目の裁判も先輩裁判官と共に3人で公判へ。起訴状朗読をし、論告・求刑、弁論の後に判決期日を指定して40分ほどで修了。
午後12時~ お昼休憩は近くのお店で食事をして、裁判官室へ戻って書記官が作成した公判調書や次の裁判に向けた資料に目を通します。
午後1時~ 証人尋問があるので、午後1時過ぎから書記官と共に尋問にあたります。
午後4時半~ 以前にした証人尋問の調書の確認や判決文の作成。検事と事件の打ち合わせ、書記官からの相談に応えたりします。
午後6時~ 翌日の準備をして帰宅します。業務が滞っている時は自宅や、そのまま裁判所で事務作業や起案作成等の仕事をする事もあります。
裁判官の平均年収とは
裁判官の給与は役職や階級によっても異なります。
裁判官の月収については以下の通りとなります。
| 区分 | 報酬月額 |
|---|---|
| 最高裁判所長官 | 2,038,000円 |
| 最高裁判所判事 | 1,486,000円 |
| 東京高等裁判所長官 | 1,426,000円 |
| その他の高等裁判所長官 | 1,321,000円 |
| 判事 | 526,000円~1,191,000円 |
| 判事補 | 263,600円~426,600円 |
| 簡易裁判所判事 | 263,600円~829,000円 |
裁判官としてのキャリアを始めたばかりの方は、月収234,000円からスタートします。
上記の金額は一見、一般企業と同様に感じるかもしれませんが、実際には初任給調整手当、地域手当、勤勉手当が支給され、さらに1年目からは4.4ヵ月分のボーナスも加わります。
ただし、裁判官は一般職の職員と同じ勤務時間を維持することが難しいため、残業手当や休日・夜間の報酬は支給されません。
裁判官の推定年収は5,030,368円(平成30年時点)であり、一般企業の新入社員と比較してもかなり高い水準といえるでしょう。
また、検事に昇進すると、推定年収は約1,900万円から約800万円に達し、最高裁判所の判事は約3,000万円、最高裁判所長官は約4,000万円という高額な収入が見込まれます。
裁判官になるには司法試験合格が必須
裁判官になるには司法試験への合格が必須となります。
しかし、司法試験を受験するには条件が必要です。
ここでは、司法試験合格へのルートについて紹介します。
予備試験ルート
裁判官になるためには先にも述べたように、司法試験に合格すしなければいけません。
司法試験は誰もが自由に受験できるわけではなく、司法試験予備試験に合格するか、法科大学院を修了して受験資格を得る必要があります。
予備試験を経る場合、毎年実施される司法試験予備試験に合格することで、司法試験の受験資格を得ることができます。
予備試験の合格率は例年約4%前後であり、他の資格試験と比較しても非常に低いため、予備校や通信講座などを利用して対策するのが有効でしょう。
法科大学院ルート
法科大学院ルートでは各大学院が独自に設定したカリキュラムを修了することで、司法試験の受験資格を得ることが求められます。
これまでは未修者コースで3年間、既習者コースで2年間のカリキュラムを履修する必要がありましたが、2023年からは、両コースともに所定の単位を取得すれば、大学院在学中の最終年次に司法試験を受験できるようになりました。
法学部と法科大学院を最短5年で修了する「法曹コース」を選択することで、法科大学院在学中に司法試験を受験し、最短5年で合格することができます。
さらに司法試験に合格すると、法曹になるための研修である司法修習を受けることになり、期間は1年間で司法試験だけでは不足している実務に関する知識を習得します。
修習の最終段階である通称「二回試験」と呼ばれる卒業試験に合格することで、正式に法曹となる資格が与えられます。
また、裁判官は多くの場合、司法試験に一発で合格している優秀な人材が選ばれていますが、合格順位が最低位であった者が裁判官になった例もあるため、順位だけが全てではないことも留意すべきです。
裁判官を目指せる大学ランキング!各大学の特徴や裁判官の出身人数・学費を比較【2025年】
裁判官の年齢制限
裁判官の定年は法律によって規定されており、最高裁判所の判事は70歳、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所の裁判官は65歳、簡易裁判所の裁判官は70歳で定年を迎えます。
しかし、裁判官に就任する際の年齢制限については、法律上の規定は存在しません。
司法においては年齢に関係なく、経験豊富で見識のある優れた人材を広く求めることが望ましいとされているためです。
裁判官の仕事は判決を下すだけじゃない?1日の流れやスケジュールは?まとめ
裁判官の1日の流れやスケジュールは裁判の有無でも変わってきますが、毎日忙しく資料や証拠調査等をこなしている事が分かっていただけたでしょうか。
公判で判決を下す為の準備には時間がかかり、その為のスケジュールを組む事がかなり大切なのです。
休日やプライベートの時間も裁判準備や判決文の作成に使っている裁判官は全国にたくさんいて、持ち帰りの仕事をこなすだけで休日が終わるなんて方もいるのです。
日本の裁判官は人数も少なく、1日のスケジュールに余裕が少ない程忙しい裁判所もたくさんあります。