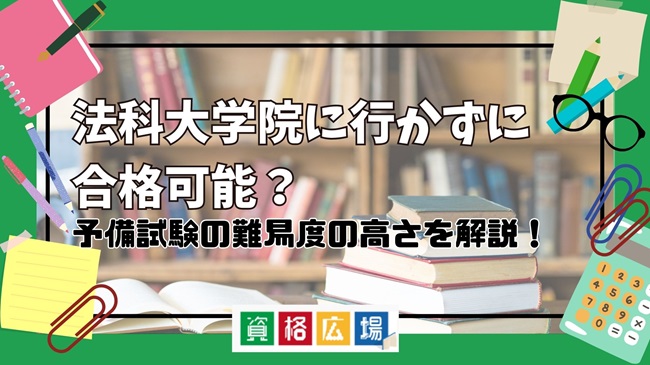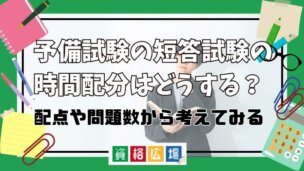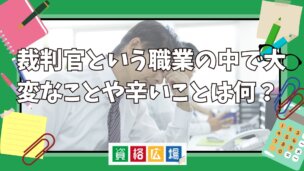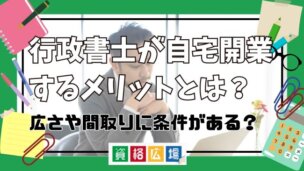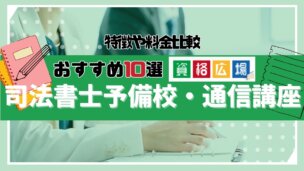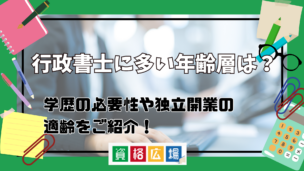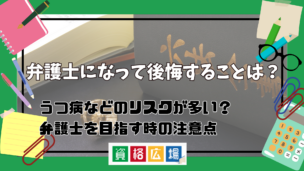弁護士を含む法曹三者を目指す方は司法試験予備試験に合格するか法科大学院を修了する事で司法試験を受験する資格を得られます。
法科大学院に進学するとなると時間もお金もかかるので、近年は法科大学院に行かなくても司法試験の受験資格が得られる予備試験の合格を目指す方が増えてます。
法科大学院に進まなくても司法試験に合格する事は出来るのか?今回は予備試験の難易度と合格するための学習法について解説していきます。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
司法試験予備試験合格におすすめの通信講座
最短ルートで予備試験に合格する学習法

司法試験に合格したいけれど、法科大学院に通うための費用や時間がない!
できるだけ早く予備試験に合格して司法試験に挑む方法はないのかな?
そんな悩みを解決できるのが、アガルートの予備試験最短合格カリキュラムです!
- 法律初学者でも予備試験合格を目指すための充実したカリキュラムがある
- 講義映像はブラウザ・OSを選ばず8段階の再生速度調整、音声ダウンロードが可能
- 受講中は何度でも無料で講師に相談できる
- インターネット環境があればいつでもどこでも講義が受講可能で、テキストを持ち歩く必要もなし!
アガルートの詳細については下記の記事をご覧ください。
他予備校と比較するならコチラ!
法科大学院のメリット/デメリット
法科大学院に行けば司法試験の受験資格が得られるため、大学院に通おうと考えている人も多いと思います。
その一方で、「通学する時間がない」「あまり費用をかけたくない」という方もいるはず。「法科大学院に行かずに司法試験に合格したいけど可能なの?」と悩んでいませんか?
法科大学院と予備試験のメリット・デメリットを比較し、司法試験合格に法科大学院は必要かどうか見ていきましょう!
メリット│自主ゼミでモチベーションを維持しやすい
法科大学院に通うのと予備試験用の通信講座で学習するのとで大きく違う点は、周りに同じ目標を持った人がいるかどうかです。
法科大学院で、大半が法曹を志望しているため、助け合ったり励ましあったりすることで精神的に不安定になりがちな試験勉強も乗り切れたという意見も多いです。
また法科大学院には「自主ゼミ」という制度があり、学生が自主的に集まって答案を添削しあったり、分からない点を教えあったりします。
切磋琢磨できるためモチベーションを保ちやすいのが、法科大学院に通う大きなメリットになります。
デメリット│費用と時間がかかる
法科大学院の1年間あたりの授業料の目安は下記のようになります。
既修者コースは2年間、未修者コースは3年間分の学費を払わなければなりません。
| 法科大学院/入学金・授業料 | 入学金 | 授業料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国公立 | 一律 28万2000円 |
80万4000円 | 108万6000円 |
| 私立 | 15万~30万円 | 約100万円 | 約140万円 |
つまり、国公立の法科大学院に通う場合は
既修者コースで28万2000円+80万4000円×2=189万円
未修者コースで28万2000円+80万4000円×3=269万4000円
がトータルでかかることになります。
私立の法科大学院は学校にもよりますが、おおむね既修者コースで合計300万円前後、未修者コースで合計400万円前後かかります。
また、法科大学院の授業は1コマ90分で週8コマ程度受講する必要があります。
夜間コースがある法科大学院(日本大学、筑波大学、福岡大学etc…)もありますが、社会人の場合働きながらの通学は体力面や精神面でもかなり大変と言えます。
予備試験のメリット/デメリット
続いて、予備試験のメリット・デメリットについて見ていきましょう。
法科大学院に進むとなると、大学の4年間+法科大学院で2年、法学未修者なら3年を過ごす事になり、早くても6年間という時間がかかります。
法科大学院に行かずに司法試験を受験するために必須な予備試験。予備試験を受けることで得られるメリットには一体どんなものがあるのでしょうか。
メリット│時間とお金の節約
一番大きいメリットは時間とお金の節約です。時間とお金を節約しながら予備試験に合格する事が出来るのか?と思われそうですが、通信講座なら出来るんです!
通信講座で学び、2017年に18歳という最年少で予備試験に合格し、2018年に司法試験に合格した大学1年生がいますが、彼のように最短で進める方法を取れば、法科大学院に進む費用を抑える事が出来るんです。
彼は大学に進学しましたが、予備試験合格後そのまま司法修習に進めば大学進学の費用も必要ありませんよね。
予備試験の予備校や通信講座の平均費用は、60万円~100万円です。
大手予備校では大学院と同等程度の学費がかかることもありますが、通信講座を選べば20万円~高くても80万円で受講することが出来ます。
メリット│司法試験の合格率が高い
| 司法試験 実施年度 |
1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 予備試験合格者 | 京都大法科大学院 | 一橋大法科大学院 |
| 2022年 | 予備試験合格者 | 京都大法科大学院 | 慶応義塾大法科大学院 |
| 2021年 | 予備試験合格者 | 京都大法科大学院 | 慶應義塾大法科大学院 |
| 2020年 | 予備試験合格者 | 東京大法科大学院 | 慶應義塾大法科大学院 |
| 2019年 | 予備試験合格者 | 慶應義塾大法科大学院 | 東京大法科大学院 |
ここ数年のデータを見ると、司法試験合格者のうち予備試験合格者の合格率がかなり高いものとなっています。
理由として多く挙げられている意見が、司法試験と予備試験の短答式試験の内容が共通している事が多く、予備試験が司法試験の対策になっているというものです。
他にも予備試験の難易度が高く、司法試験合格のための能力が確保されている、若年層の20歳代の合格率が高い事から受験勉強等で学習に慣れている為に吸収率が高いという意見がありました。
メリット│社会人が働きながら合格を目指せる
決まった時間に通学することができない方でも、通信講座であれば自分の好きな時間に何度でも授業を見ることができるため、忙しい社会人でも働きながら合格が目指せることも利点の1つです。
また地方に住んでいる場合、大学院に通うために引っ越さなければならないという方もいると思いますが、通信講座では居住地を変える必要がないのもメリットです。
デメリット│確実に司法試験を受験できるとは限らない
予備試験のデメリットは、確実に司法試験を受験できるとは限らないということです。
しかし予備試験に万が一不合格だったとしても、弁護士への道を諦められないのなら法科大学院への入学という道があります。
もちろん金銭面で学費がかかるなどのデメリットはありますが、再度予備試験を受けながら法科大学院での勉強を進められるので、モチベーションの低下にはならないでしょう。
その他、国家公務員第一種の勉強とも内容が重複しているので、国家公務員として働きながら通信講座で予備試験の勉強を進めて、翌年以降再度予備試験を受験する事も可能です。
予備試験の難易度は?
弁護士を含む法曹を目指す方の必須試験である司法試験。法科大学院に行かずに司法試験を受ける為の第一関門である予備試験は3つの試験方式がありますが、それぞれの難易度はどれ程なのでしょうか。
1つ1つクリアして全て制覇しなくては予備試験合格とならないので、気になる方も多いはず。
直近3年の各試験の合格率をご紹介していきましょう。
| 実施年度/試験内容 | 短答式試験 | 論文式試験 | 口述試験 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 20% | 19.1% | 98.3% |
| 2022年 | 21.7% | 17.9% | 98.1% |
| 2021年 | 23.2% | 18.1% | 98.1% |
短答式試験の難易度
弁護士を目指す為の登竜門、予備試験の一歩目である短答式試験の難易度は高く、約20~23%程度で推移しています。
受験年度によって合格点も変わるのですが、160~170点は必要となっていて、全科目で平均して6割以上得点しなければならないことになります。弁護士を目指す方なら合格点より高い点数が必要になります。
司法試験よりも科目数が多く、覚える事も幅広いですし、短答式試験に合格しなければ論文式試験を受けられないので、確実に合格点以上を狙える知識が必要です。
論文式試験の難易度
短答式試験の合格者のみが受験できる論文式試験の難易度は短答式試験より高く、合格率は約18~20%程度です。
合格点も500点満点中235~245点で、論文式試験は独学で学びにくい事もあり通信講座や予備校で知識と理解力を付け、制限時間内に解答できる力をつける必要があります。
法律知識と応用力を鍛える為に、司法試験の過去問や通信講座の受講で何度も繰り返し問題を解いていくという勉強法を取っている方が多いです。
口述試験の難易度
予備試験の最終関門、口述試験の難易度は上記の一覧を見てわかるように、合格率はかなり高くなっています。
試験官の質問にその場で口頭で答えていくのが口述試験なのですが、短答式試験・論文式試験の合格者であれば基本的に答えられる問題であると言えるでしょう。
入室から退室までの姿勢や作法もチェックされていますので緊張しすぎないようにしましょう。合格率が高いとはいえ、落ちる事もあるので、気を抜かずに試験に向かう事が大切です。
予備試験の合格を目指すためには
予備試験を合格するためには、非常に膨大な学習量が必要になります。
法律の知識を1から身につけるのは並大抵の努力では叶わないので、かなりの覚悟と自分に合った勉強法が必要だと言えるでしょう。
予備試験の勉強方法には主に2つの方法があるため、それぞれの特徴やメリットをご紹介します。
通学式の予備校へ通う
まず挙げられる方法が予備校に通うことで、独学では怠けてしまいそう・モチベーションが保てないという方にはおすすめです。
日中コースだけでなく夜間コースがある予備校も多いので社会人でも通学できますし、同じように弁護士を含む法曹を目指す仲間がいることで精神的に支え合えるでしょう。
講師が生徒1人ひとりの苦手分野を丁寧に把握できるため、その場ですぐに効果的な勉強法を教えてもらえることが強みでしょう。
インターネットを駆使した通信講座で学ぶ
近くに予備校が無く通学できない・予備校に通う時間がないようなら、インターネットで通信講座を利用するという手もあります。
オンラインで講座を視聴したり、テキストを閲覧したり、添削指導を受けたりすることができるので、通学時間の節約につながります。
また、スマホでも動画を観られるため、学校や会社の昼休みや就寝前といったスキマ時間に勉強を進められることもメリットです。
一人でコツコツと勉強をしたい方や、勉強のためのまとまった時間が取れない方には通信講座が向いているでしょう。
インターネットで学ぶならアガルートがおすすめ!
もし通信講座で学習したいなら、アガルートの予備試験最短合格カリキュラムの受講をおすすめします。
予備試験最短合格カリキュラムは、法律の勉強を一切したことがないという初学者でも予備試験合格を目指せる講座です。
効率のいい学習ノウハウを有しているため、受講生にとって最短期間で予備試験を突破できるレベルにまで導いてくれます。
その他にも下記のようなおすすめポイントがあります。
- オリジナルのフルカラーテキストを使用!
法律の勉強は専門用語がずらりと並びとっつきにくいと思われがちですが、アガルートのオリジナルフルカラーテキストなら難解な法律の解説も視覚的に理解することができます。 - いつでもどこでも効率的に学習!
アガルートのオンライン講座は1chapterあたり10分~20分程度と短く、マルチデバイス対応で音声ダウンロードもできるので自宅でも外出先でもちょっとした時間に勉強ができます。 - 論文添削指導の回数が豊富!
論文式試験対策はどれだけやっても心配になるものですが、アガルートでは実際に受講生が書いた答案を徹底的に添削してくれます。
約100通もの論文添削を受けることができるので、合格するために必要なスキルを身に着けることができます。 - 講師は全員現行の(新)司法試験合格者!
選び抜かれた精鋭の講師陣は全員、現行の(新)司法試験に合格しています。
どの講師もただ単に現行の司法試験の出題傾向を把握しているだけでなく、予備試験の受験指導経験が豊富です。
法科大学院に行かずに予備試験に合格するための確実な学習をするなら、自分のレベルを確実にアップデートさせてくれるアガルートがおすすめ!
できる限り早い予備試験合格を目指したいという方は、今すぐアガルート公式サイトをチェックしましょう!
法科大学院に行かずに司法試験合格はできる?まとめ

法曹になろうと思っても、時間や学費が多くかかる法科大学院に行くほどの余裕が無い方は予備試験の合格を目指すことをおすすめします。
予備試験は難しい試験内容ですが、確実に身につく勉強法をしていれば合格を目指せるでしょう。
予備試験の勉強方法はいくつかありますが、スキマ時間を利用して効率的に学べる通信講座がおすすめです。
特にアガルートには司法試験に実際に合格したプロの講師陣による指導と充実した学習システムがあり、予備試験を最短で合格させるメソッドが導入されています。
スマホやタブレット、パソコンがあればどこでもいつでも学べて、自分のペースで進めることも可能ですし、細かく組まれた学習スケジュールに沿って学ぶこともできます。
アガルートで最短での予備試験に合格しましょう!