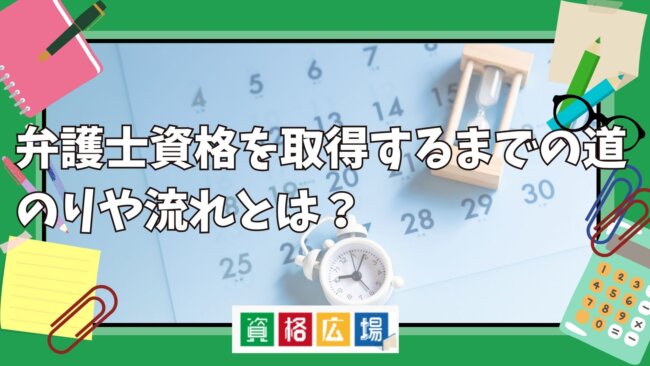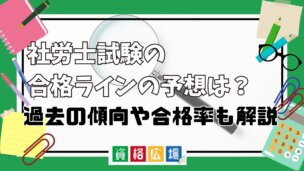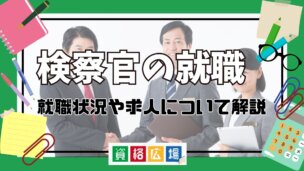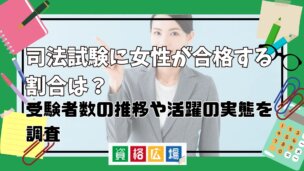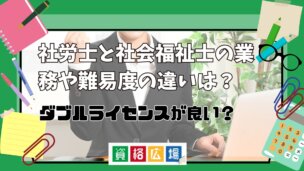弁護士の資格を取得するには、難関と呼ばれている「司法試験」に合格する必要がありますが、司法試験の受験資格には2通りの道のり・流れがあることをご存知ですか?
今回この記事では、弁護士資格を取得し弁護士になるまでの道のりと流れを詳しく紹介していきます。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
弁護士になるならアガルートアカデミー!

弁護士資格取得待っでの道のりは長いですが、初めの関門である予備試験を合格したいならアガルートアカデミーがおすすめです。
アガルートは高い合格率と豊富なサポートで講師と2人3脚で予備試験合格を目指せます。
短期学習で、弁護士になるまでの道のりを最短ルートで駆け抜けましょう!
弁護士資格を取得する道のり・流れとは?
まずは弁護士資格を取得するための大まかな流れを確認しましょう。
弁護士になるまでの道のりは決して簡単ではなく、長期的な計画が必要になります。
弁護士資格の道のりと流れ①:最難関国家試験を突破する
弁護士資格を取得し弁護士になるまでには、まず国家資格であり文系最難関と呼ばれている「司法試験」に合格しなければなりません。
司法試験とは、弁護士や裁判官、検察官と呼ばれる法曹を目指している方が受験する試験であり、法律家として必要な学識や応用能力を持っているかどうかの判定を行う国家試験です。
試験は年に1回、毎年5月中旬頃に4日間にわたり実施されています。
弁護士資格の道のりと流れ②:司法試験は受験資格がある
司法試験には受験資格が設けられており「法科大学院(ロー・スクール)を卒業する」か「予備試験に合格する」どちらかの条件を満たしていないと受験することができません。
この2つも簡単ではなく、法科大学院は最低2年の学習期間、予備試験が合格率4%の壁が立ちはだかっています。
司法試験自体の合格率も高くなく最難関試験として知られていますが、この受験資格を取得すること自体が第一関門でもあり、その難易度の高さが伺えます。
弁護士資格の道のりと流れ③:2通りの受験資格の流れ
司法試験の受験資格を得るまでの流れは2通り用意されており、法科大学院の道のりでは法律をすでに学んでいる方は「法学既修者コース」で2年間、そうでない方は「法学未修者コース」で3年間法律について学び、法科大学院修了後に受験資格が与えられます。
一方予備試験の道のりは、予備試験に合格すれば受験資格を取得することができます。
司法試験の受験回数には制限があり、法科大学院修了後および予備試験合格後5年以内に5回まで試験を受けることが可能です。
受験資格を取得する道のりと流れ
司法試験を受験するには受験資格を満たしていることが条件であり「法科大学院修了者」か「予備試験合格者」でなければならないことを確認しました。
ここからは、法科大学院と予備試験の各受験資格の特徴について、それぞれの道のりと流れを紹介していきます。
資格取得の流れと道のり①:法科大学院を卒業する
一般的な弁護士を目指す道のり・流れとしては「法科大学院」に進学し、修了後に受験資格を取得し司法試験合格を目指すことでしょう。
しかし、法科大学院に入学するにも受験資格が必要とされ、原則として4年制大学を卒業していなければなりません。
また、各大学で実施される入試では適性検査や自己評価書の提出、試験では小論文や面接なども実施されますので、法科大学院に入学することは容易ではありません。
法科大学院入学後は、2年ないし3年の学習期間を経ることで司法試験の受験資格を得られるようになります。
関連記事:法科大学院を卒業するメリットは?予備試験との違いもご紹介
資格取得の流れと道のり②:予備試験に合格する
「予備試験」は、年々受験者が増え、世間の関心を集めている資格取得の道のりです。
予備試験には受験資格が必要なく誰でも受験することが可能という点や、時間・経済的理由で法科大学院への進学が困難な方も弁護士を目指せる制度として注目されています。
また、予備試験合格者の司法試験合格率が非常に高い上、予備試験合格者のレベルの高さから就職活動にも有利に働くといわれています。
試験の対策においても、弁護士になってからの実務においても予備試験の道のりは人気になっています。
法科大学院と予備試験どちらが道のりがおすすめ?
弁護士資格を得て弁護士になるまでの道のり、流れとしては予備試験がおすすめです。
理由は先に述べた通り、予備試験合格者の司法試験合格率が高いこと、時間的・経済的拘束が法科大学院に比べて軽いことです。
加えて予備試験合格という実績は就職にもいい影響を与えることがあり、すべての方面で役に立ちます。
かつては法科大学院が正当な道のりとして評価されていましたが、昨今では予備試験から弁護士資格を取得する流れの方がメジャーであると言えます。
各試験の合格率
それでは、それぞれの試験の合格率を見てみましょう。
どちらの試験も文系国家資格としては最難関と言われ、合格率の低さからその難易度を測ることができます。
予備試験の合格率
予備試験は例年4%前後の合格率となっており、非常に難易度が高くなっています。
予備試験は受験資格がないことから合格レベルに満たない方や記念受験をする方も多く、受験者数が多いことも合格率が低い要因となっています。
予備試験の最難関は論文式試験と言われており、総受験者のうち短答式試験に合格した20%から、さらに上位20%に入った人しか合格できません。
予備試験は、まさに最難関国家資格に相応しい試験となっています。
| 試験年度 | 受験者数 | 最終合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 | 13,372人 | 479人 | 3.5% |
| 令和4年 | 13,004人 | 472人 | 3.6% |
| 令和3年 | 11,717人 | 467人 | 4.0% |
| 令和2年 | 10,608人 | 442人 | 4.2% |
| 令和元年 | 11,780人 | 476人 | 467人 |
司法試験の合格率
司法試験の合格率は毎年40%前後となっています。
予備試験と比べると合格率が高く、特に令和4年は45.5%という高い合格率になりました。
しかし司法試験は法科大学院の修了者か予備試験合格者しか受験できず、その中から4割程度しか合格しないため、非常に難易度が高いと言えます。
短答式試験合格率は70%前後と高いですが最終合格率は40%前後であるため、やはり鬼門は論文式試験と言えるでしょう。
| 試験年度 | 受験者数 | 合格者数 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 | 3,928人 | 1,781人 | 45.3% |
| 令和4年 | 3,082人 | 1,403人 | 45.5% |
| 令和3年 | 3,424人 | 1,421人 | 41.5% |
| 令和2年 | 3,703人 | 1,450人 | 39.2% |
| 令和元年 | 4,466人 | 1,502人 | 33.6% |
司法試験合格後すぐに弁護士資格を取得できる?
法科大学院の道のりでも予備試験の道のりでも、司法試験に合格するための通過点に過ぎません。
では、司法試験に合格さえすればすぐに弁護士資格を取得し、弁護士になることができるのでしょうか?
試験合格後の流れを解説していきます。
司法修習で1年間学ぶ
司法試験合格後にすぐ弁護士として活躍できるわけではなく、司法修習生として約1年間実務修習を行う必要があります。
司法修習は法曹として働くために必要な実務や法律についてさらに知識を深める期間であり、多くのプログラムが用意されています。
司法修習期間は兼業・副業が禁止されており拘束が多いですが、準公務員扱いで給与も出て、いずみ寮という寮も用意されています。
司法修習を修めることでようやく弁護士への道が拓けます。
司法修習では実務が行える
司法修習は「分野別実務修習」が大半を占めており「民事裁判修習」「刑事裁判修習」「検察修習」「弁護修習」の4科目、それぞれ2か月間実施します。
その後はインターンのような実務収集である「選択型実務修習」や二回試験対策の「集合修習」も行われ、弁護士として活躍していけるように実践を積むことになります。
実務修習は裁判所や弁護士事務所など希望する場所、地方の企業や法テラス、企業や官公庁など、目指す法曹や働き方によって多彩な実務修習が行えます。
ここで学んだことは弁護士として働く際も非常に役立つことでしょう。
司法修習後の「二回試験」とは一体なに?
全ての司法修習を終えた後、最後の難関である「二回試験」を受験することとなります。
試験科目は民事裁判・刑事裁判・検察・民事弁護・刑事弁護の5科目、1科目を9:30〜17:30行うという非常にハードな試験となっています。
ですが、二回試験は卒業試験のようなものであり、通年9割以上の受験者が合格を勝ち取っている試験でもあります。
この二回試験に合格することでようやく弁護士として活動することができるので、様々な難関試験を乗り越えなければならない弁護士の道のりは非常に長いといえます。
関連記事:
司法修習考試(二回試験)は不合格が当たり前?試験の詳細や日程は?
司法修習を免除して弁護士資格が得られる?弁護士法5条を徹底解説!
弁護士会に登録したら晴れて弁護士!
見事司法修習に合格したら、弁護士会に登録することで弁護士として活動できるようになります。
弁護士会登録は資格審査会の議決を経て登録できるか判断され、健康でない方や信用・適性を欠く方は登録できません。
日本弁護士連合会や入会する地域弁護会から登録が認められれば、晴れて弁護士を名乗れます。
弁護士資格取得し、弁護士になるまでの道のり・流れは非常に長いものですが弁護士として働く際に自分を支えてくれることでしょう。
弁護士資格の取得におすすめの道のりと流れ
それでは最後に、弁護士資格を取得するためにおすすめの道のりである予備試験について、おすすめポイントを改めて確認していきましょう。
予備試験日程の流れ、おすすめの予備試験対策通信講座も紹介します。
予備試験がおすすめである理由①:短答式試験合格率が高い
予備試験が法科大学院よりおすすめの道のりである大きな理由は、司法試験の短答式試験合格率が極めて高いことです。
令和3年度の司法試験において、予備試験合格者の短答式試験合格率はなんと100%でした。
司法試験は短答式試験に合格しないと論文式試験の採点が行われないため、確実に駒を進めたい方は予備試験がおすすめです。
予備試験がおすすめである理由②:司法試験合格率が高い
続いて、最終合格率が高いことも予備試験の道のりがおすすめの理由です。
令和5年は353名の予備試験合格者が駒を進めた司法試験ですが、そのうち327名が最終合格を果たしました。
予備試験と司法試験は試験内容・形態が似ていることから、そのままの流れで試験対策をすることができ、効率的な学習が可能です。
| 試験年度 | 予備試験の道のりの合格率 | 法科大学院の道のりの合格率 |
|---|---|---|
| 令和5年 | 92.6% | 40.6% |
| 令和4年 | 97.5% | 37.6% |
| 令和3年 | 93.5% | 34.6% |
| 令和2年 | 89.4% | 32.7% |
試験日程
令和5年の予備試験は既に始まっているため、令和6年の予備試験日程を確認していきましょう。
予備試験は短答式試験・論文式試験・口述試験の3つから構成され、それぞれの試験の間には時間があるため別々の対策を行うことができます。
後述するアガルートアカデミー通信講座のカリキュラムであれば短期間で予備試験合格を目指せるため、今からの学習でも令和6年の試験対策は間に合います!
| 令和6年予備試験の日程 | |
|---|---|
| 短答式試験 | 令和6年7月14日(日) |
| 論文式試験 | 令和6年9月7日(土)・8日(日) |
| 口述試験 | 令和7年1月25日(土)・26日(日) |
| 合格発表 | 令和7年2月6日(木) |
予備試験合格の流れを掴みたいならアガルートアカデミー!

弁護士資格を取得し弁護士になるまでにはいくつもの試験を超えなくてはなりませんが、まず最初に突破すべき試験は予備試験です。
予備試験合格にはアガルートアカデミーを利用した試験対策がおすすめです。
最後に、アガルートアカデミーのポイントを紹介します。
極めて高い合格率で弁護士資格取得を目指せる
アガルート最大の特徴は、試験合格率が非常に高いことです。
令和5年の司法試験合格者占有率は36%で、約4割がアガルートの受講生という実績です。
豊富なサポートで安心して学習できる
アガルートのカリキュラムは講師やスタッフによるサポートが手厚いことも評判です。
論文式試験対策に書かせない添削は約100通行い、学習中の質問は無料で無制限に行えます。
さらに最新の法改正情報やカリキュラムの進め方を解説するホームルームなど、学習を支えるサポートが豊富に用意されています。
予備試験はスケジューリングとモチベーションの維持が大切になるので、アガルートで講師と一緒に合格を目指しましょう。
多彩なキャンペーンでお得に受講できる
予備試験対策の予備校・通信講座は基本的に100万円程度の費用がかかります。
しかしアガルートはキャンペーンを頻繁に開催しており、タイミングが合えばかなりお得に講義を受講できます。
お得なキャンペーンを逃さずぜひアガルートで予備試験合格を目指してください!
弁護士になるには資格取得の道のりと流れ|まとめ
弁護士資格を取得し、弁護士になるまでの道のりと流れを紹介いたしました。
弁護士になるには、まず「法科大学院修了」か「予備試験合格」どちらかの資格を取得し、本試験である司法試験に合格する必要があります。
さらに、司法試験合格後には司法修習生として約1年間にわたり実務修習を経験し、修習後に実施される「二回試験」に合格して初めて弁護士と名乗ることができます。
弁護士になる道のり・流れは険しく長期戦になりますが、それだけ弁護士という職業は難易度が高く魅力的だといえそうです。