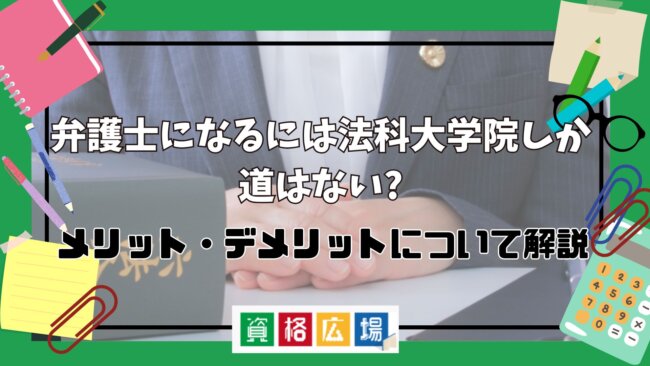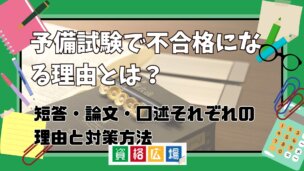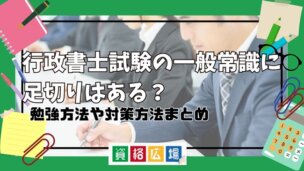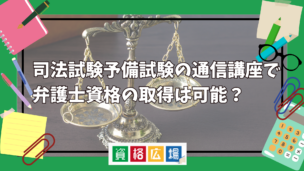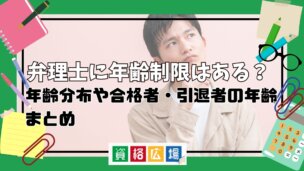弁護士になるには司法試験に合格する必要があり、司法試験を受験するには予備試験ルートか法科大学院を卒業するルートがあります。
予備試験はパスする難易度が高い試験ではありますが、最短のルートと言われています。
しかし、法科大学院ルートでは経済的なコストがかかるものの、実践的な実務研修などを経験できるメリットがあります。
そこで今回は法科大学院ルートについて、メリット・デメリット、予備試験ルートとの比較などをしていきたいと思います。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
法科大学院(ロースクール)とは
法科大学院(ロースクール)は、法曹(弁護士、検察官、裁判官)に必要な知識を育成することを目的とした専門職大学院です。
2004年4月に設立され、法科大学院では少人数制の教育を基本とし、双方向的かつ多様な授業、実務研修や体験学習を通じて、密度の高い教育が行われます。
さらに、法科大学院では研究者教員に加え、実務家教員も積極的に授業を担当するため、理論と実務のバランスを取った学びができるメリットがあります。
法科大学院のコースはさまざまあり、未修者向けの3年コースと法学既修者向けの2年コースのほかにも社会人向けの夜間コースや将来的に法科大学院に入学することを前提とした法曹コース(大学を3年間で卒業可能)。
学費については、国立大学で約80万4千円、私立大学では55万から170万円と幅がありますが、110万円前後の法科大学院がほとんどです。
なかには、奨学金制度や補助制度を利用することで、学費を軽減できる場合もあります。
法科大学院ルートのメリット・デメリット
弁護士を目指すために法科大学院を利用する場合、弁護士資格を取得するまでには、最短で6年(法曹コース3年、法科大学院2年、司法修習1年)が必要です。
法科大学院に入学するメリットとして修了または修了見込みであれば、司法試験の受験資格が確実に得られる点が挙げられます。
また、夜間部を設けている法科大学院もあるので、社会人でも働きながら通学できるのも利点だといえるでしょう。
一方で、学費が発生し、国立大学の場合でも入学金が約30万円、学費が約80万円かかります。
私立だとさらに費用が掛かり、仕事を一度休職もしくは辞職しなければいけないケースもあるので経済的リスクはデメリットといえます。
さらに、法科大学院を修了した際の司法試験合格率が予備試験ルートよりも低いのも考慮が必要です。
予備試験ルートのメリット・デメリット
短期間で予備試験に合格すれば法科大学院よりも短い期間で司法試験の受験資格を得ることができます。
法科大学院ルートでは大学入学から修了までに通常6年(学部4年+既修者コース2年)が必要ですが、年齢に関係なく受験できる予備試験ルートでは最短で合格を目指せます。
実際、大学1〜2年生で合格し、学部卒業前に司法試験に合格するひともいると言われています。
さらに、予備試験合格者は例年法科大学院出身者よりも司法試験の合格率が高い傾向があります。
2019年以降の司法試験の合格率を比較すると、法科大学院出身者は30〜40%程度であるのに対し、予備試験合格者は80%以上という顕著な差があります。
司法試験の合格率が高い理由には、予備試験の合格率が約4%とかなり難易度が高いことが関係しています。
予備試験に合格するまでに2年以上かかることがほとんどなので、結果的に法科大学院ルートと大差ない、あるいは長引くリスクも存在します。
高卒で司法試験の受験資格取るなら法科大学院と予備試験どっち?
法科大学院の選び方

法科大学院は100万円程度必要と言われており、自分の状況などに合わないと後悔することも少なくありません。
そこでここでは、後悔しない法科大学院の選び方について紹介します。
司法試験の合格率
司法試験の合格率は法科大学院を選ぶ際の基準となります。
合格率が高い大学院には優秀な成績を持つ学生が多く在籍している傾向があり、モチベーションが高いまま学習に集中できる可能性が高いです。
しかし、合格率のみを重視してしまうのもよくありません。
なぜなら、学生数が20人程度の小規模な学校から200人以上の大規模な学校まで様々であり、学生数の違いによって合格率は大きく変動することがあるからです。
したがって、合格率だけでなく、教育内容や教員の質、サポート体制など、複数の視点から総合的に大学院を評価することが重要となります。
留年率・修了率
留年率と修了率は、法科大学院を選ぶ際の重要名ポイントとなります。
留年率が高い、または修了率が低い大学院では、学生が授業についていくのに困難を感じている可能性が高いです。
特に法科大学院は学費が高いため、留年は経済的な負担を引き起こすことになります。
また修了率が低い場合は学生が途中で挫折したり、目標を達成できなかったりするケースが多いことを示しています。
合格率の高さや学習環境など、自分にあったところかどうかを多角的に見るようにしましょう。
学費
法科大学院の学費は、国立と私立で大きく異なり、国立大学院は比較的低価格である一方、私立大学院は各校によって学費が異なり、高額な場合も多く見受けられます。
学費は学生やその家族にとって重要な決定要因となるため、法科大学院を選ぶ際には、学費だけでなく、その教育の質や将来への影響など、コストパフォーマンスを総合的に見て判断することが大事です。
また、学費の負担を軽減するための奨学金制度の有無や内容も同時にチェックしておくことおおすすめします。
特に私立大学院では、卒業生に対して入学金を半額免除する特典を提供していることがあります。
奨学生として選ばれることで授業料が全額免除されたり、毎月奨学金が支給される大学院もあります。
少しでも費用を抑えたい方は学費とカリキュラム内容のバランスを見ながら判断してみてください。
アクセス・学習環境
法科大学院を選定する際には、学習支援の充実度や通いやすいアクセスにあるかどうかも大切な要素となります。
学習支援が充実していることで、学生は学習への意欲を持続しやすくなるでしょう。
また自宅から通いやすい場所にかるかどうかの通学の利便性や生活の質に影響を与え、学習効率にも大きく関わります。
自身のライフスタイルにあった場所や学習環境かどうかを見ておくようにしましょう。
授業スタイル
法科大学院における学習経験の質は授業内容や教授の指導方法によって大きく影響されます。
有名な教授が在籍している場合でも教授の授業スタイルが自分に適しているかどうかは別の問題であり、合わないところだと通い続けられなくなるおそれがあります。
法科大学院を選ぶ際には、できる限り多くの情報を集め、自分に合った教授がいるかどうかをよく吟味するようにしましょう。
たとえば先輩や在校生からの情報、またはオープンキャンパスでの体験を通じて、授業内容や教授の教え方について具体的なイメージを持つことがおすすめです。
夜間通学ができる法科大学院(ロースクール)一覧!社会人向けの大学や入学方法を徹底解説
司法試験合格率の高い法科大学院ランキング
ここでは、2024年度の司法試験合格率が高い法科大学院についてランキング形式で紹介します。
| 大学名 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 慶應義塾大法科大学院 | 59.35% | 246 | 146 |
| 愛知大法科大学院 | 55.56% | 9 | 5 |
| 京都大法科大学院 | 49.31% | 217 | 107 |
| 一橋大法科大学院 | 48.78% | 123 | 60 |
| 東京大法科大学院 | 47.45% | 255 | 121 |
| 中央大法科大学院 | 45.86% | 181 | 83 |
| 早稲田大法科大学院 | 42.12% | 330 | 139 |
| 大阪大法科大学院 | 40.68% | 177 | 72 |
| 神戸大法科大学院 | 37.50% | 136 | 51 |
| 同志社大法科大学院 | 36.94% | 111 | 41 |
参考:法務省
上記の表からも分かるように、偏差値の高い大学が司法試験に合格しやすい傾向となっています。
理由としては、そもそも入学時の学生のレベルが高いことが考えられます。
しかし、一般的に偏差値がそこまで高くないところでも合格する可能性はゼロではありません、
法科大学院は合格者数だけではなく、合格率や学費、学習環境などさまざまな条件から選ぶことが大事です。
なぜなら合格者数の多い大学院が直ちに実力があるとは限らず、合格率の高さも在籍者数に左右されることがあるためです。
在籍者数や長期的な実績を踏まえて評価する必要があります。
数年間にわたって安定した合格実績を保っている大学院であれば、カリキュラムやサポート体制が整っているといえるでしょう。
【2025年最新】おすすめの法科大学院(ロースクール)ランキング!それぞれの合格率や学費を徹底比較【選び方も解説】
法科大学院の入学条件とは
法科大学院に入学するためには各法科大学院が実施する試験に合格しなければいけません。
通常、既修者コースでは法律論文が、未修者コースでは小論文が課されます。
例外はあるものの一般的には私立大学の試験は8月頃、国立大学の試験は11月頃に行われることが多いです。
また既修者コースにおいては私立大学では短時間の試験で基本的な問題が出題されることが多く、国立大学では試験時間が長く、応用的な問題が出題される傾向があります。
科目や入学条件は各学校によって異なるため、詳細については各大学の法科大学院の公式ホームページをちぇっくするようにしてください。
弁護士とは

弁護士の仕事でイメージが付きやすいのは法律事務所に所属し、法律関係の相談を受ける仕事かもしれません。
しかし、働く場所は事務所に限らず、全国各地の弁護士会の事務所や市町村の役場などから依頼を受けて相談窓口を開設したりしています。
法律面でのアドバイスなどでトラブルが解決しない場合には、裁判へ移行することもあるので、適切な手配をしていくのも弁護士の仕事です。
弁護士の仕事は基本的な人権の保障や権利の保障など人々が不正に侵されたりしないように、また不正が起きても正しく罰せられる社会をつくる一翼を担っています。
司法試験の受験資格
司法試験は誰でも受験できるわけではありません。
最近では少しでも多くの人に受験してもらえるように様々な形で司法試験受験条件を得られるようになっています。
是非自分に合った条件の取り方を検討してみて下さいね。
①法科大学院に在学・卒業する
一番有名で多くの人が選択する最も確実性が高い方法は、法科大学院に在学、または修了する事です。
法科大学院に入る為には、学部は関係ありません。
法学部を卒業している場合でも学部期間4年、大学院期間2年と合計6年、更に法学部以外の学部を卒業している場合は更に1年必要となります。
この時点で金銭的に難しく司法試験を諦める人もいると思いますが、今は他にも選択肢があるので諦めるにはまだ早いです!
②予備試験に合格する

長い間、司法試験を受験できるのは法科大学院の修了生だけでした。
しかし、2011年までから、金銭的、時間的負担の軽減し、より幅広い人に司法試験の受験を受験してもらえるように予備試験制度が開始しました。
この試験は、誰でも受験する事ができ、合格すると法科大学院修了と同等の知識があるものとみなされ「司法試験受験資格を得る」ことができるのです。
法学部の学生達も在学中に予備試験を受け、1年でも早く司法試験を受験できるように勉強するようになりました。
ちなみに平成30年には19歳で司法試験に挑戦している人も居たそうです。
実際、大学院を卒業した方よりも、予備試験合格してからの合格者の方が多くなっているという結果もあります。
社会人なら夜間のある法科大学院がおすすめ
今回は法科大学院ルートについて、メリット・デメリット、予備試験ルートとの比較などをおこなってきました。
弁護士になるには法科大学院しかないんどえはないかと思っていた人も多いと思います。
法科大学院に行かなければいけないとなると、高校生を卒業してから最低でも6年は学生生活を続けなければならず時間的にも金銭的にも重い負担で諦める人も多かったと言います。
ですが年々司法試験の受験資格は取りやすくなるように制度が改革されてきています。
これからも制度の変更がある可能性が高いので興味のある方は情報更新にお気を付けください。
法科大学院と言っても様々なタイプがあり、もし社会人から司法試験合格を目指すのであれば夜間のあるものがおすすめです。
ほかにも、カリキュラムや司法試験合格率の高さ、通いやすさなどを総合的に見て判断するようにしてみてください。
また法科大学院合格に向けた予備試験や通信講座も普及しているので、ぜひチェックしてみてください。