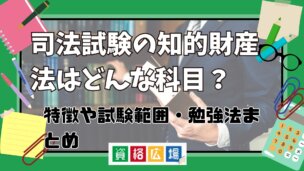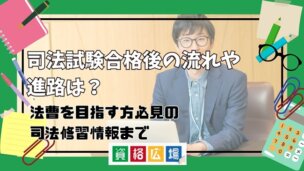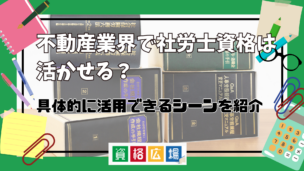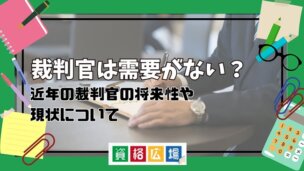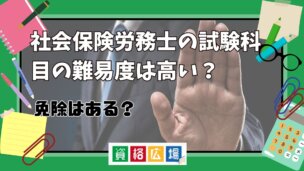裁判所事務官II種・裁判所事務官III種になる難易度は高いのでしょうか。
裁判所事務官は幅広い年齢層の男女が目指せる、法治国家における最重要機関の仕事です。
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種の資格は「国家資格」です。
資格広場は、裁判所事務官II種・裁判所事務官III種になりたい人を応援しております。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種採用試験の難易度
判所事務官試験は、どの区分も非常に高い倍率となっています。
一般職試験は、総合職試験よりも難易度は若干低めといえますが、それでもかなりの倍率だといえるでしょう。
試験本来の難易度、受験者数の多さもあり、難関試験になっていることは間違いないでしょう。
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種資格の倍率は3.6倍
令和5年度の裁判所事務官、大卒程度区分の倍率は3.6倍です。
令和5年度実施結果のすべての勤務地の採用倍率を平均したところ、3.6倍という結果になりました。
ただし、高松高等裁判所の管轄区域では6.2倍の高い倍率を誇っています。
裁判所事務官、大卒程度区分の採用倍率は地域によって上下することに注意しましょう。
参考:裁判所 試験の実施結果
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種合格に必要な勉強は1,000時間〜1,500時間
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種の合格のためには、1,000時間〜1,500時間の勉強が目安です。
試験範囲が広く、問題では専門的な知識も問われます。
ただし、学習効率や知識レベルによって必要な勉強時間は異なるでしょう。
試験対策に自信がない人は、1,500時間以上の勉強も視野に入れてください。
難易度の高い試験なので、早めからの対策が必須になります。
試験勉強の進め方としては、なるべく一次試験と二次試験の勉強を並行して行うことでしょう。
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種の試験概要
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種の試験概要をチェックしましょう。
受験資格、試験料、年間試験回数などをまとめました。
合格発表時期、年間試験回数などの試験概要は裁判所の管轄によって異なります。
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種の概要
裁判所にて各種の裁判事務や事務局の一般事務に従事する裁判所事務官。
採用されるには、裁判所職員採用総合職試験(院卒・大卒程度)または一般職試験(大卒程度・高卒者)のどちらかの試験に合格する必要があります。
採用後、一定の在職期間を経ると、裁判所書記官への試験を受けてステップアップを目指せます。
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種の試験料
試験料は無料となっています。
公務員試験で受験料が必要になることはありません。
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種試験の年間試験回数
各都道府県によって異なります。
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種を目指す人は、希望する裁判所の試験要項をチェックしましょう。
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種試験の合格発表時期
合格発表は各都道府県によって異なります。
裁判所事務官の試験日と結果発表日は、試験概要に記載があります。
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種の採用試験が難しいと言われる理由
- 裁判所事務官希望者が多い
- 試験範囲が広く深い
- 人物試験対策が難しい
以上のことからも、裁判所事務官の採用試験は難しい傾向です。
一般的な公務員試験と異なった問題が出題されるので注意しましょう。
理由①裁判所事務官希望者が多い
裁判所事務官は希望者が多い仕事です。
希望する人が多いほど、採用試験の難易度も上がってしまいます。
申し込み者数も1万人以上になることが多く、高い競争率が見込まれます。
例年の傾向から見ても、難易度が下がることはほとんどありません。
雇用や給料が安定している国家公務員は、希望者が多いのではないでしょうか。
理由②試験範囲が広く深い
試験範囲が広く深いことは、裁判所事務官採用試験の特徴です。
憲法や民法、経済原論などの理解は必須と考えてください。
基礎能力試験では大学卒業レベルの学力が試されます。
専門試験では法律に関わる問題が出題されるでしょう。
そのうち、専門試験は選択式と記述式に分かれています。
理由③人物試験対策が難しい
公務員試験の人物対策は、一般企業で言うところの採用面接です。
裁判所事務官採用試験では、人物試験が採用判断の10分の4を占めます。
試験官3名との個別面接が行われるので、失敗がないように十分に注意してください。
公務員採用試験の面接は、事前に面接カードを提出します。
面接カードの作成も、傾向を知って対策を練りましょう。
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種採用試験の難易度を他試験とランキングで比較
裁判所事務官の倍率はどれくらいか、他試験と比較しましょう。
| 区分 | 合格倍率 |
|---|---|
| 裁判所事務官 | 約3.6倍 |
| 弁護士 | 約2.55倍 |
| 検察官(大卒者程度試験) | 約3.4倍 |
裁判所事務官の倍率は検察官(大卒者程度試験)と同じくらいのレベルと判断できますね。
しかし、どちらも職務に就くためのプロセスに違いがあります。
国家公務員の合格倍率は採用試験の難易度とは別物と考えてください。
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種試験の内容・科目
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種の採用試験は、1次~3次に分かれています。
筆記試験や人物試験(面談)など、各試験のポイントをまとめました。
1次試験
公務員として必要な基礎的な能力(知能及び知識)についての筆記試験です。
基礎能力試験は問題数が多く、配点率が高い科目です。
| 試験 | 分野/区分 | 科目・内容 |
|---|---|---|
| 基礎能力試験 | 知能分野 24題 |
文章理解 判断推理 数的推理 資料解釈 |
| 知識分野 6題 |
化学・物理などの「自然科学」 政治・経済・法律などの「社会科学」 歴史・思想など「人文科学」 |
|
| 専門試験 多肢選択式 |
多肢選択式 30題 |
憲法7題、民法13題 (選択)刑法または経済理論10題 |
2次試験
課題に対する理解力などについての論文による筆記試験です。
裁判所によっては、人柄、資質、能力などについての個別面接もあります。
| 試験 | 問題数 | 科目・内容 |
|---|---|---|
| 論文試験(小論文) | 1題 | 表現力、課題に対する理解力などについての筆記試験 |
| 専門試験 記述式 |
1題 | 憲法について |
3次試験
3次試験は人物試験です。
人柄、資質、能力などについての集団討論及び個別面接となっています。
面接の配点比率が高いことは、裁判所事務官採用試験の特徴です。
難易度の高い裁判所事務官II種・裁判所事務官III種採用試験に合格するポイント
裁判所事務官の試験合格を目指して、勉強するポイントを確認しましょう。
- 過去問を活用して勉強する
- 配点が多い科目を積極的に解いていく
- 試験の時間配分に慣れておく
- 学習スケジュールは早めに立てる
- 人物試験対策は第三者に依頼する
以上のことに気をつけながら、勉強を進めてください。
学習計画を早めに立てることでスケジュール管理がしやすくなります。
ポイント①過去問を活用して勉強する
過去問を活用して試験対策をしましょう。
過去問題は過去5年までさかのぼってチェックしてください。
裁判所事務官の試験範囲は独特です。
試験では法律に関わる、広く深い範囲の理解が求められるでしょう。
他の公務員試験とは異なる要素の問題が出題されます。
ポイント②配点が多い科目を積極的に解いていく
配点が多い科目を積極的に勉強してください。
裁判所事務官の採用試験は、基礎能力試験のうち知能分野が24題を占めます。
文章理解、数的推理などを重点的に学習することをおすすめします。
効率的な勉強方法を見つけるためには、反復的な演習もいいでしょう。
インプットとアウトプットを繰り返すことで、頭に入りやすくなります。
ポイント③試験の時間配分に慣れておく
試験の時間配分に慣れておきましょう。
普段から時計を見て勉強を進め、時間の使い方を身につけてください。
試験は時間配分が決まっています。
試験の科目ごとに利用できる時間に限りがあるので注意してください。
解答がわからない場合、無理に時間をかけることは避けましょう。
ポイント④学習スケジュールは早めに立てる
学習スケジュールは早めに立てることが重要です。
早い段階で学習スケジュールを立てれば余裕を持って勉強できます。
学習に遅れてしまった場合も、別日で補填がしやすくなるでしょう。
裁判所事務官採用試験の日に向けて、早い段階でスケジュールを計画してください。
ポイント⑤人物試験対策は第三者に依頼する
人物試験いわゆる面接は、第三者からのアドバイスも重要です。
第三者からアドバイスを受けることで自分の改善点が見つかります。
印象や表情、服装のチェックも、大切な人物試験対策です。
人物試験対策に迷ったら、予備校や通信講座を活用することもおすすめです。
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種の仕事内容
判所での仕事というのは「法律」に関する仕事です。
法律が改正されれば、当然それに合わせて仕事内容も変えていかなければなりません。
毎年法律の改正をチェックしなければならないのです。
パソコンで資料を作るためには、「ワード」や「エクセル」などを覚えなければならないでしょう。
訴状の発送などでも、段取りを勉強していかなければなりません。
部署ごとに仕事が違うので、転勤の度に仕事を覚えていくことが必要となります。
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種に向いている人
裁判所事務官の仕事は、一般の事務職と同様、文書の作成が多くなります。
ただしその文書は、裁判に関わるものなので、ミスがゆるされない責任重大な文書です。
文書作成が得意で、かつ責任感をもって注意深く作業にあたれる人に向いています。
事務作業のみならず、裁判所の利用者や弁護士との応対も業務に含まれるので、コミュニケーションのスキルも求められます。
当然ながら、法律の知識も必要になりますので、その手の勉強が苦にならない人に向いています。
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種の年収・給料相場
勤務地によっても多少の差がありますが、年収は初年度で270万から390万円ほどとなっています。
総合職試験の院卒者試験では約24万円、大卒程度試験では約21万円、一般職試験の大卒程度試験では約20万円、高卒者試験では約16万円です。
裁判所事務官は国家公務員なので、法律によりさだめられた給与体系にもとづく安定収入が得られます。
採用試験には複数あり、それぞれ初任給の時点で差が生じます。
その後は公務員らしく勤続年数とともに昇給してゆきます。
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種の現状
裁判所事務官は国家公務員ということもあり採用の倍率は高いですが、公務員ならではの安定職と言えるでしょう。
現在の社会において裁判は欠かせないものであり、今後も裁判所事務官の仕事の重要性は変わらないと考えられます。
ですが、裁判所事務官の業務は、今後の環境により変わってくる可能性があります。
特に近年は裁判員制度の導入、ロースクールの設立による弁護士増加の可能性、司法のあり方を問うマスコミ報道など、裁判をめぐる環境が変化を続けています。
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種の将来性
日本が法治国家である限り、裁判所は不可欠な存在であり、そこに勤務する裁判所事務官も必要な存在であり続けるでしょう。
しかし業務の内容は、司法をめぐる改革やIT化などによって大きく変わってゆくかもしれません。
事務官個人の将来性を見た場合、国家公務員として安定した生活が見込めますが、裁判所書記官へとキャリアアップすることで、より責任ある立場となり、給与も増やすことができます。
積極的に書記官を目指すべきでしょう。
また、10年以上の勤務経験があれば、司法書士の資格も取得できます。
裁判所事務官II種・裁判所事務官III種採用試験の独学合格が難しい理由
裁判所事務官採用試験の独学合格は難しいのでしょうか。
- 法律の学習が難しい
- 記述式問題の対策ができない
- 学習教材が少ない
以上の理由から、とくに初学者には独学をおすすめできません。
効率的な勉強方法を身につけるまでに、時間がかかってしまうこともあるでしょう。
独学が難しい理由①法律の学習が難しい
裁判所事務官採用試験では、民事や憲法に関わる問題が多く出題されます。
法律の学習は独学では難しいでしょう。
独学は、疑問点や質問があっても、すぐに尋ねられる環境ではありません。
最悪の場合、問題や疑問を解消できないこともあります。
独学が難しい理由②記述式問題の対策ができない
独学では記述式問題の対策が難しいでしょう。
もし解答に読みにくい文章があっても、自分一人では気づきにくいものです。
記述式問題は、解答にベストとなる型があります。
問題によっては、解答のNG例もあるので注意しましょう。
独学が難しい理由③学習教材が少ない
裁判所事務官採用試験に特化している学習教材は少ないです。
市販のものを探すとなると、そろえるまでに時間がかかってしまうでしょう。
通信講座や予備校を受講すれば、採用試験対策の教材が一括で購入できます。
教材や学習動画探しの手間がかかりません。
勉強に時間をかけたい場合、学習教材探しに手間がかかりすぎることは避けたいですよね。
裁判所事務官採用試験対策におすすめの予備校・通信講座
裁判所事務官採用試験対策におすすめの予備校・通信講座を探すには、ベストな方法があります。
講座の一括資料請求なら、自分にぴったりの勉強法が見つけられるでしょう。
簡単な情報を登録するだけで、複数の講座の資料が簡単に手に入ります。
タイムパフォーマンスやコストパフォーマンスを重視する人にも、通信講座や予備校はおすすめです。
裁判所事務官採用試験対策に迷ったら講座を受講しよう
裁判所事務官採用試験は、事前の対策がとても重要です。
効率よく勉強を進めるためにも、予備校・通信講座の力を借りてもいいですね。
独学では、対応できる範囲に限りがあります。
自分のペースで進められますが、間違った勉強法で進めてしまう危険性に注意しましょう。