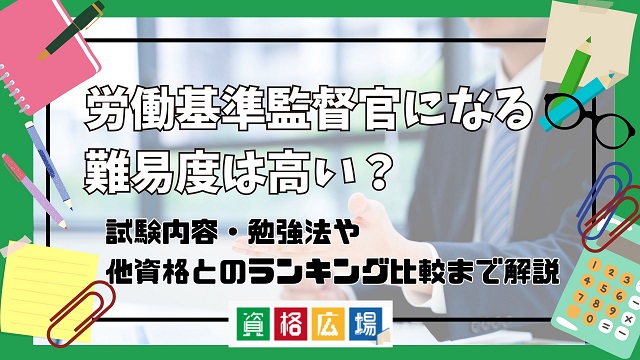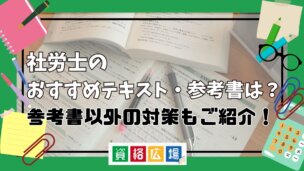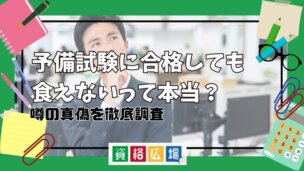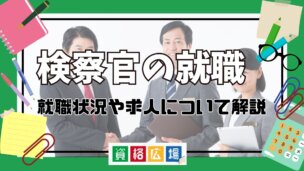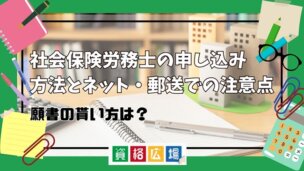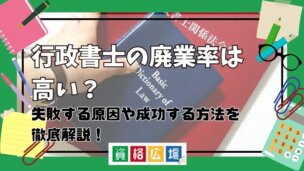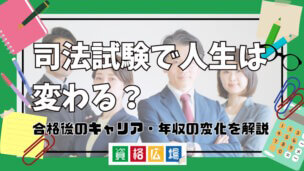労働基準監督官になる難易度は高いのでしょうか。
一般的な公務員試験と同様、一般教養・専門ともに幅広い知識が必要です。さらにこれらに加えて、身体的にも健康であることが求められます。
労働基準監督官の採用は「厚生労働省」が運営管理を行っております。
厚生労働省とは国家行政組織法が規定する「国の行政機関」である省の一つです。
健康・医療、子ども・子育て、福祉・介護、雇用・労働、年金に関する政策分野を主に所管しています。
労働基準監督官の資格は「国家資格」です。
資格広場は、労働基準監督官になりたい人を応援しております。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
労働基準監督官になる難易度
低い採用倍率からみても、労働基準監督官採用試験に合格するのは大変難しいです。
労働基準監督官は、国家公務員の中でも相当の難関試験だと言えるでしょう。
倍率や必要な勉強時間をまとめました。
労働基準監督官の倍率は5~10倍
労働基準監督官の倍率は、労働基準監督Aが10倍程度、労働基準監督Bが5~6倍程度です。
採用試験の合格に必要な勉強時間は1,200時間程度
労働基準監督官になるためには、1,200時間程度の勉強を計画しましょう。
7~12ヶ月の学習計画を立て、労働基準監督官採用試験へ挑戦することがおすすめです。
1,200時間の勉強は、最低ラインと考えてください。
試験範囲の学習は余裕を持った計画が必須です。
労働基準監督官の採用試験概要
労働基準監督官の試験概要を確認しましょう。
採用試験の受験料や、年間の試験回数をまとめました。
労働基準監督官採用試験の受験料
労働基準監督官の試験料は無料です。
ほかの公務員試験と同様に、試験にお金はかかりません。
2024年(令和6年度)の試験日程
試験は年に1回実施されています。
令和6年度試験の場合、第1次試験は5月26日(日)月に、第2次試験は7月9日(火)~7月12日(金)にそれぞれ実施されます。
労働基準監督官採用試験の合格発表
合格発表は、第1次試験が6月18日(火)に、第2次試験が8月13日(火)に行われます。
労働基準監督官採用試験の受験資格
労働基準監督官採用試験の受験資格は次の通りとなっています。
1.受験年度の4月1日の時点の年齢が21歳以上30歳未満の者。
2.受験年度の4月1日の時点の年齢が21歳未満の者で、次に掲げる者。
(1)大学を卒業した者および受験年度の3月までに卒業する見込みのある者。
(2)人事院が(1)と同等の資格があると認める者。
以上の男女が目指せる、労働者と事業者のトラブルの解決、労働災害の予防、労働災害の調査などを行います。
労働基準監督官採用試験が難しいと言われる理由
労働基準監督官採用試験が難しいと言われる理由には、以下があります。
- 労働法や労働事情への理解が必須
- 試験そのものの難易度が高い
- 採用倍率・競争率が高い
- 試験では専門性が問われる
労働基準監督A、Bともに、難易度が高い試験と考えましょう。
理由①労働法や労働事情への理解が必須
労働基準監督官採用試験に合格するためには、労働法や労働事情への理解が求められます。
法文系である「労働基準監督A」の試験の多くは、労働に関するものです。
ほかの公務員試験とは異なる、独自の問題が出題されるでしょう。
労働法や労働について、幅広い知識をつけなくてはなりません。
理由②試験そのものの難易度が高い
労働基準監督官の採用試験は、大学卒業程度です。
試験を受ける人は、国家公務員を目指すために日々努力している人が多いのではないでしょうか。
受験者のレベルが高いうえに、やさしい試験ではありません。
難易度がそもそも高いことに注意しましょう。
理由③採用倍率・競争率が高い
労働基準監督官の採用倍率は、例年のデータを見ると5~10倍です。
競争率が高いことで、試験の難易度が上がっています。
国家公務員を目指す学生や社会人は昨今も多いでしょう。
労働基準監督官は人気がある職種です。
採用されるためには、幅広い試験対策をしましょう。
理由④試験では専門性が問われる
「労働基準監督B」は、理工系の問題が出題されます。
労働事情だけでなく、工学に関する知識も必須と考えましょう。
専門性の高い知識をつけてください。
勉強方法にも工夫をし、採用試験合格を目指すことが重要です。
難易度の高い労働基準監督官採用試験に合格するポイント
労働基準監督官採用試験に合格するポイントは以下の通りです。
- 問題数の多い科目から取り組む
- 過去問から傾向を読み取る
- 学習計画は余裕をもって立てる
- 時間配分にも気をつける
難易度の高い試験では、より多くの点が取れるように時間配分にも気をつけましょう。
大学での履修内容を復習するとともに公務員試験の専門試験用テキスト、過去問題集などを使って対策できます。
ポイント①問題数の多い科目から取り組む
労働基準監督官採用試験は、問題数の多い科目が決まっています。
出題数が多い科目に優先度をつけて勉強を進めましょう。
基礎能力試験のうち知能分野は、27題を占めます。
文章理解や判断推理、数的推理といった、基本的な知識を磨いてもいいですね。
ポイント②過去問から傾向を読み取る
過去問から傾向を読み取りましょう。
最低でも直近5年の過去問題をチェックしてください。
どのような問題が多く出題されるのか、効率的に確認できます。
問題の文章やスタイルに慣れておくためにも、事前に過去問で演習しましょう。
過去問を活用することは、試験対策で有利な方法です。
ポイント③学習計画は余裕をもって立てる
学習計画は余裕を持って立ててください。
試験勉強に必要な時間を計算し、試験日から逆算をしましょう。
このとき、スケジュールに余裕を持たせることが重要です。
勉強に遅れが出てしまっても、カバーできる体制を整えると安心できますね。
ポイント④時間配分にも気をつける
試験の時間配分にも気をつけて対策をとりましょう。
時計を見ながら試験勉強をする癖をつけてください。
時間配分が間違っていないか、確認することが重要です。
どんな問題に時間がかかるのか分かりやすくなるので、勉強に時計を使うことはおすすめです。
労働基準監督官採用試験の難易度を他試験とランキングで比較
労働基準監督官採用試験の難易度を他試験と比べました。
| 区分 | 倍率 |
|---|---|
| 労働基準監督官 | 5~10倍 |
| 国家総合職 | 7.5〜8.7倍 |
| 国家一般職(行政職) | 2.5倍 |
| 国家一般職(行政職以外) | 1.5倍 |
| 社会保険労務士 | 10~20倍 |
労働基準監督官は、国家公務員の中でも高い採用倍率を誇る仕事です。
ただし、他の区分とは応募条件や仕事に就く手順が異なります。
採用倍率が低い=試験の難易度が易しい、というわけではありません。
2025年(令和7年度)国家公務員試験の日程・試験日最新情報
労働基準監督官採用試験の科目
共通試験は、公務員として必要な基礎的な能力(知識及び知能)についての筆記試験です。
出題数は30題です。
| 分野 | 出題数 | 科目 |
|---|---|---|
| 知能分野 | 24題 | 文章理解 判断推理 数的推理 資料解釈 |
| 知識分野 | 題 | 自然 人文 社会(時事を含む)情報 |
労働基準監督A
| 科目 | 出題数 | 分野 |
|---|---|---|
| 必須 | 12題 | 労働法
労働事情(就業構造、労働需給、労働時間・賃金、労使関係) |
| 選択 | 36題から28題選択 | 憲法、行政法、民法、刑法
経済学、労働経済・社会保障、社会学 |
| 記述式 | 2題 | 労働法
労働事情(就業構造、労働需給、労働時間・賃金、労使関係) |
法文系の専門試験は、就業構造や労働需給など広く深い知識が必要です。
労働基準監督B
| 科目 | 出題数 | 分野 |
|---|---|---|
| 必須 | 8題 | 労働事情(就業構造、労働需給、労働時間・賃金、労使関係、労働安全衛生) |
| 選択 | 38題から32題選択 | 工学に関する基礎(工学系に共通な基礎としての数学、物理、化学) |
| 記述式 | 4~6題出題、2題解答 |
|
労働基準監督Bでは、工学・化学・数学に関する知識が求められます。
労働基準監督A・B共通の2次試験
2次試験では、人物試験として、人柄・対人的能力などについての個別面接が実施されます。
身体検査として、胸部疾患(胸部エックス線撮影を含む。)、血圧、尿、その他一般内科系検査を受けましょう。
【2025年最新】公務員の人気が増加中?人気の公務員おすすめ資格の種類・職種を一覧で紹介
労働基準監督官の仕事内容
労働基準監督官は、厚生労働省に所属する国家公務員です。
労働基準法や労働安全衛生法に基づき労働者と事業者のトラブルの解決、労働災害の予防、労働災害の調査などを行うことが主な仕事です。
労働者が職場で安全に働けているかどうか労働環境(賃金、労働時間等)を調査します。
万が一、法律違反が見受けられれば指導や摘発を行うとともに、悪質な違反者に対しては司法警察員として犯罪捜査を行い、書類送検する権限も持っています
労働基準監督官の年収・給料相場
労働基準監督官は国家公務員のため、その給与額は法律により定められています。
「行政職俸給表(一)」が適用されます。年度によって若干変動する可能性がありますが、たとえば大卒で新卒採用された場合の初任給は約17万円(東京都特別区内勤務の場合は約20万円)となっています。
この金額をみると意外と低いと思われるかもしれませんが、この金額は基本給です。
その他超過勤務手当や期末・勤勉手当などの各種手当も支給されます。
公務員として安定した収入を得ることは期待できるでしょう。
労働基準監督官の現状
労働基準監督官は国家公務員であり、他の公務員と同様に比較的安定している職種です。
しかし、近年の経済不況の影響から、公務員数を削減すべきという流れの中に労働基準監督官も含まれており、若干ですが人数の削減も行われています。
基本的に労働基準監督官の業務量は安定しているため、残業が必要になることは少なく、働きやすい職場です。
一方で、経済不況時には、労働者と事業者間のトラブルは増加しがちであり、それらの紛争を解決しなければならないため、業務量も増える傾向にあります。
労働基準監督官の将来性
諸外国に比べるとまだまだ日本での労働者の権利は保護されておらず、労働者が安心安全に働ける労働社会をつくることは、やりがいの大きな仕事でもあり、今後も大いに必要とされる仕事といえるでしょう。
労働基準監督官は公務員のため、将来にわたって安定性を期待できる職種といえます。
一方で、労働関連の専門性の高い職種でもあるため、着実に多くの経験を積むことで、キャリアアップを望めるなど、将来性も期待できるでしょう。
労働基準監督官に向いている人
労働基準監督官は、事業主に労働関連法令を遵守させ、労働災害を未然に防ぐ役割を担っています。
長時間労働や安全対策のとられていない工事現場での労働など、過酷な環境を強いられ、苦しんでいる労働者を助けることが仕事です。
ときには協力的ではない事業主を相手にすることもありますし、膨大な処理業務で苦しい場面もあります。
そのような時でも、なんとか困っている人を助けたいという熱意をもって取り組める人が適しているでしょう。
労働基準監督官は個人に任せられる裁量は多いものの、仕事は多くの先輩や同僚と共に行います。
そのため、職場の人間関係を良好に築くことも必要でしょう。体力があることも必要です。
労働基準監督官採用試験の独学合格が難しい理由
労働基準監督官採用試験の独学合格は、ほとんどの受験にとって難しいです。
独学は人によって向き不向きがあるので注意しましょう。
自分一人での勉強に不安がある人は、早い段階で通信講座や予備校などの利用を考えてください。
独学が難しい理由①初学者には公務員試験の勉強が難しい
初学者には公務員試験の勉強は難しいです。
傾向と対策を練るためには、過去の資料や情報もチェックしなくてはなりません。
教材の準備や、勉強する環境を整えることも必要です。
準備段階で時間がかかってしまうことが考えられるでしょう。
独学が難しい理由②面談の対策が難しい
面談の対策は1人では難しいでしょう。
受け答えや服装のアドバイスが受けられないので、試験で不利になる可能性があります。
公務員の採用判断は、面談も多くの比重を占めます。
面談で失敗してしまうと、筆記試験で高得点をとっても採用されません。
独学では対策できる範囲に限りがあることに注意しましょう。
独学が難しい理由③記述式問題の添削ができない
独学では記述式問題の添削ができません。
自分の文章の癖や問題点も見つけにくいでしょう。
労働基準監督官採用試験では、記述式問題も出題されます。
採用につなげるためには記述式の対策も十分に取る必要があるでしょう。
不安があるのに、無理に独学にこだわることはおすすめできません。
労働基準監督官の専門学校・通信講座
労働基準監督官の専門学校・通信講座に迷ったら、複数の講座の資料請求がおすすめです。
一括で資料が手に入るので、手間がかかりません。
労働基準監督官を目指す人向けの専門学校・通信講座をチェックしましょう。
 労働基準監督官になる難易度は高め
労働基準監督官になる難易度は高め
労働基準監督官の採用試験は国家公務員の中でも、難易度が高めです。
毎年5倍以上の採用倍率ということに気を付けましょう。
労働基準監督官になった後も、常に努力できる人が採用されます。
労働基準監督官の業務のためには、学習する意欲は必須です。