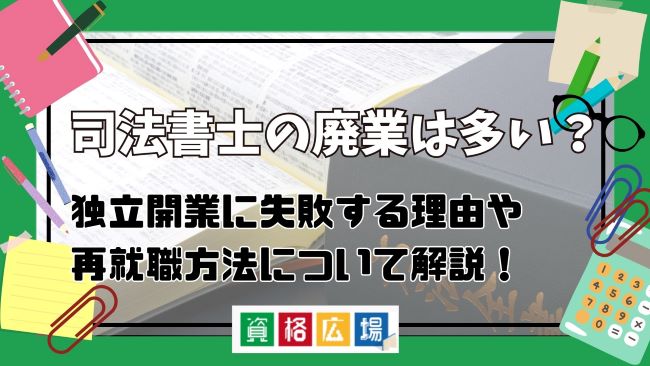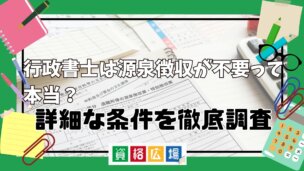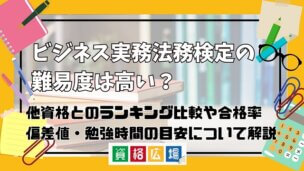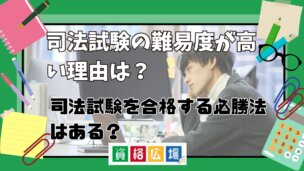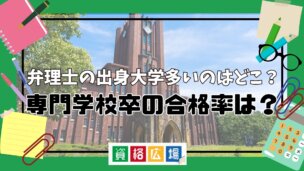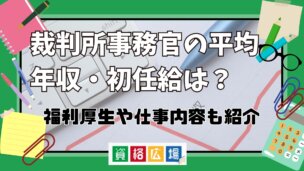司法書士は他の士業資格よりも独立開業しやすく廃業になりにくいという話を聞いたことはないでしょうか。
しかし、そんな司法書士でも廃業になってしまうケースは少なくありません。
廃業になってしまうのは一体どのような理由があるのでしょうか?
今回の記事では司法書士が廃業してしまう理由や廃業しないためのポイントについて解説します。
また、途中で進路変更したくなるなどもしもの場合に備えて司法書士の再就職方法についてもご紹介しています。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
司法書士は独立開業しやすい資格?
司法書士は弁護士や行政書士など他の士業と比べて、独立開業がしやすい資格という話をインターネットなどで見かけたことはないでしょうか?
いざ独立開業するとなると、事務所を契約したり必要な備品を揃えたり、経理の管理や新規案件の獲得もしなければなりませんので、独立開業することは決して簡単のことではありません。
司法書士は本当に独立開業しやすい資格なのか、以下では司法書士の実情を交えて解説していきます。
司法書士は独立開業しやすいといわれる理由
①少ない資金で開業できる
②司法書士試験の内容が実務に近い
③研修制度が充実している
④営業力次第で初年度から売上を作れる
①少ない資金で開業できる
司法書士の開業資金は比較的安価で大体50万円~150万円の資金があれば開業できます。
司法書士の業務は一般的な事務所設備があればできますので、商品の仕入れや大型設備などの設備投資をする必要がありません。
また、自宅を事務所として開業する場合には更に賃貸料を抑えれるため、他に用意するものはデスクや椅子、棚などの一般的なオフィス用品のみになります。
このように司法書士の開業資金は自己資金で用意できる範囲に収まるため比較的開業しやすくなっています。
②司法書士試験の内容が実務に近い
司法書士の試験内容は実際の業務内容に近いため、試験合格後にすぐ独立開業することもできます。中には試験合格から1年も経たずに独立開業する方もいます。
他の司法書士事務所に所属する形でも、2年~3年の実務経験を積めば十分に独立可能なスキルを身に付けられるため、他の士業資格と比べ独立開業する難易度は低いといえるでしょう。
ただし、司法書士の業務は法改正の影響を色濃く受けるため、試験合格後も最新の法改正情報を常に把握しておく必要があります。
③研修制度が充実している
司法書士には試験合格後に受けられる研修制度がいくつかあり、中でも中央新人研修(前期・後期)の研修単位の取得は司法書士として活動する上で必須とされています。
どの研修も参加することで実務に近い内容を学ぶことができ、他の司法書士と横のつながりもできるため、ほとんどの司法書士は全ての研修に参加しています。
研修中に他の司法書士と交流を図り、人脈を築ければ独立開業する前から案件の目途を立たせることも可能です。
新人研修は以下の4種類となっています。
・中央新人研修(前期、後期)
・ブロック研修
・各司法書士会新人研修
・特別研修
④営業力次第で初年度から売上を作れる
企業に勤務している司法書士の平均年収は250万円~400万円程度で、独立開業した司法書士の平均年収は500万円~600万円程度といわれています。
このように司法書士は独立開業することで高収入を目指すことができる資格のため、営業力次第では独立開業初年度から売り上げを作ることができます。
しかし、独立開業した司法書士の中には1,000万円~2,000万円程度の年収を得る方がいる一方で200万円~300万円程度の年収の方もいますので、年収に大きなバラつきがあり、独立開業したからといって必ずしも高収入を得られるわけではありません。
司法書士の廃業率について
司法書士は開業資金も少なく独立開業しやすい資格とご紹介しましたが、司法書士の廃業率は一体どのようになっているのでしょうか?
せっかく独立開業してもすぐに廃業になってしまっては元も子もありませんよね。
そこでこちらでは司法書士全体の人口や司法書士を廃業した人数についてご紹介し、近年の廃業率について解説していきます。
司法書士の廃業率は減少傾向
近年の司法書士の廃業率は年々減少傾向にあります。
「日本司法書士会連合会」が出している司法書士の人口と登録取り消し者の人数のデータから廃業率についてまとめました。
司法書士の廃業率の推移
| 年度 | 司法書士の人数 | 登録取消人数 | 廃業率 |
|---|---|---|---|
| 平成25年度 | 20,979名 | 629名 | 3.0% |
| 平成26年度 | 21,366名 | 657名 | 3.0% |
| 平成27年度 | 21,658名 | 605名 | 2.7% |
| 平成28年度 | 22,013名 | 613名 | 2.7% |
| 平成29年度 | 22,283名 | 569名 | 2.5% |
| 平成30年度 | 22,488名 | 642名 | 2.8% |
| 令和元年度 | 22,632名 | 628名 | 2.7% |
| 令和2年度 | 22,724名 | 585名 | 2.5% |
上記の表から令和2年度の司法書士の人数が22,724名に対して、登録取消者が585名で廃業率が2.5%とかなり低いことがわかります。
また、年々司法書士の人数が増加しているのに対して、登録取消者数は毎年600人前後であることから相対的に廃業率が減少しています。
司法書士の人数が年々増加している理由は、会社法の改正で法人設立が容易になり、司法書士の新設法人数が増加しているからだと考えられます。
司法書士の廃業率が低い理由
令和元年の廃業率は2.5%とほとんどの司法書士は廃業せずに活動を続けています。司法書士の廃業率が低い理由は以下のように考えられます。
司法書士の廃業率が低い理由
・毎月のランニングコスト(固定費)が安い
・経費の出費が少ない
司法書士が毎月支払う費用は、事務所の家賃とインターネット回線や固定電話などの通信費くらいですので、経営のランニングコストが比較的安いです。そのため多少売り上げが落ちても売り上げを回復させるまで持ちこたえやすいでしょう。
また、司法書士は商品の仕入れや他社への仕事の発注などの出費がほとんどないため、大きな失敗をしずらく経営が安定しやすい業種です。
このような経営コストの安さが廃業率の低さに繋がっていると考えられます。
司法書士が廃業してしまう理由
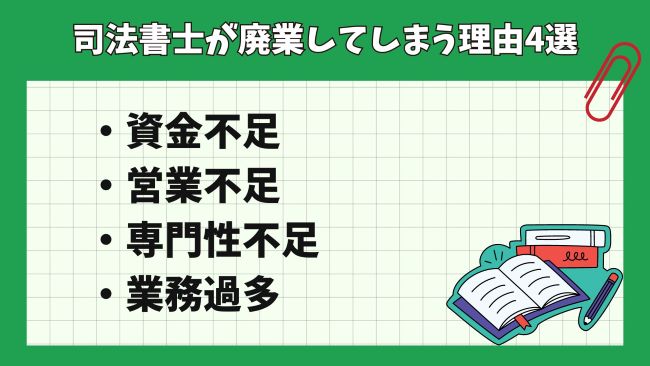
これまでに司法書士は比較的に独立開業しやすく廃業率の低い業種とお伝えしてきました。
しかし、そんな司法書士が廃業してしまう原因は準備不足や経営方法に問題があることが多いです。
以下では司法書士が廃業してしまう理由を大きく3つに分けて解説していきます。
資金不足による廃業
司法書士が廃業となってしまう理由の1つは資金不足によるものです。
開業当初は経営が安定するまで時間がかかりますので、毎月かかるランニングコストを計算せずに闇雲に開業してしまうと資金不足によりすぐに廃業となってしまいます。
そのため売り上げの目途が立つまでにどのくらいの期間と資金が必要なのかある程度把握しておく必要があります。
売り上げが立たない間の生活資金として少なくとも半年から1年は生活できるだけの資金を用意しておくといいでしょう。
営業不足による廃業
司法書士が廃業してしまうもう1つの原因は営業不足によるものです。
司法書士としての能力が高く優秀だとしても、案件を取ってくる力がないと能力を活かすことができません。
営業スキルが不足していると新規顧客やリピーター顧客の獲得ができずに廃業となってしまいます。
営業スキルはすぐに身に付くものではないので、他の事務所で働きながら営業スキルを磨いたり、ある程度人脈を築いてから独立すると売り上げが立ちやすくなるでしょう。
専門性不足による廃業
案件獲得の競争が激しい中、専門性やブランディング能力がなければ案件を獲得しずらくなります。
専門性がなく幅広い分野を取り扱う司法書士事務所は、競合との価格競争に巻き込まれやすく廃業になりやすいです。
業務過多による廃業
独立開業したあとしばらくは、司法書士の実務、経理管理、営業など全て1人で行うことになります。
早く経営を安定させたい気持ちから、多少無理をしてでも案件を受任してしまうケースも少なくありません。
その結果、業務過多となり身体を壊して事業が続けられなくなることもあります。
司法書士を廃業しないためには?
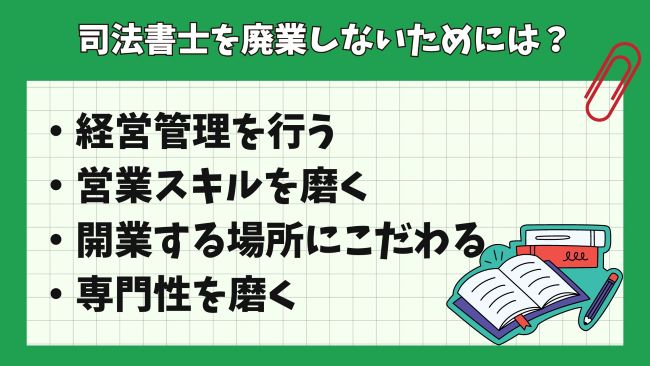
上記では司法書士が廃業してしまう理由を述べましたが、廃業してしまう司法書士の多くは廃業しないための対策を行っていません。
廃業しないためには事前に営業計画を立てたり営業スキルを身につけておくことが重要です。
以下では司法書士が廃業しないためのポイントについて詳しく解説していきます。
経営管理を行う
廃業しないためには開業費用や生活費、毎月のランニングコストを把握してしっかりとした経営管理を行うことが大切です。
上述した通り、開業資金と毎月のランニングコストは比較的安く済みますが、売り上げが立つまで想定以上に時間がかかったり、途中でホームページ作成費用など新たな必要経費が発生する場合もあります。
日ごろから経理状況や業務内容などを細かく記録し、安定した経営を行えるように努めましょう。
営業スキルを磨く
独立開業した司法書士は自分自身で案件を取ってくる必要があるため、営業スキルを磨くことが非常に重要になります。
営業スキルを磨くといってもただ顧客を集めれば良いというものではなく、人脈を広げることで顧客の紹介や新たな案件を獲得しやすくなります。
社労士や行政書士などの司法書士の業務に関わりのある士業とつながりを持てれば、そこから仕事の委託を受けることも可能です。
営業なくして経営は望めないので目の前の顧客は真摯に対応し、無料相談会の実施やセミナーなどは積極的に参加するようにしましょう。
専門性を磨く
独立開業している司法書士は多いため、依頼者は依頼する分野の専門性が高い司法書士事務所を選ぶことが多いです。
秀でた専門性がない司法書士は他の司法書士の中に埋もれてしまい案件を獲得するのも難しくなります。
そのため、専門性を持ちしっかりアピールすることで、その分野の集客がしやすくなり経営の安定性も増すでしょう。
専門性を高めるにはダブルライセンス
司法書士資格とは別にもう1つの資格を取得するダブルライセンス保持者になれば業務範囲が格段に広がり、案件を獲得しやすくなります。
例えば司法書士と行政書士のダブルライセンスを取得すればほとんどの公的書類を一度に扱えるようになり、本来なら別々で依頼される案件を1人で完結できるようになります。
一度の依頼で他の士業の業務もこなせる司法書士は貴重な存在のため、専門性を高めるにはダブルライセンスの取得が効果的です。
開業する場所にこだわる
廃業しないためには自分の営業戦略に合った地域・立地で事務所を構えることも大切です。
人口が多い都市部は顧客の母数が多く司法書士の需要も高いですが、既に大規模な法人事務所が台頭しており案件獲得の競争が激しいため、都市部で開業するのは必ずしも有利になるとはいえません。
都市部では、専門性を高めるなどして他社との差別化を図る戦略が重要になります。
一方、地方で開業する場合は都市部と比べて競争は少ないですが、その分顧客の母数も少ないので、幅広い業務範囲を持ち取りこぼしのないような戦略を取る必要があります。
地方では自分の事務所を根付かせるために親密な人間関係を保ち、顧客の紹介をしてもらうなどして仕事を回していくことが重要です。
司法書士が廃業した場合の再就職方法
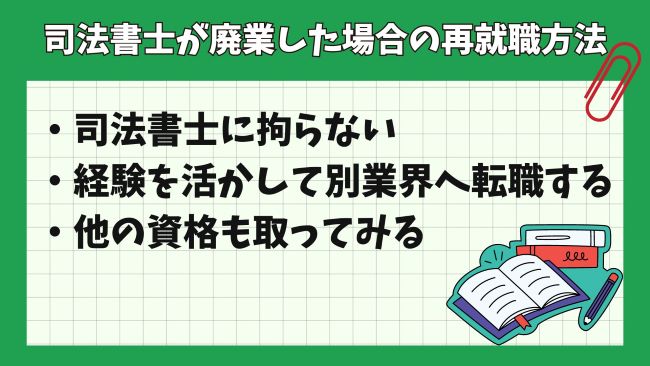
司法書士として独立開業に失敗して転職を余儀なくされる場合や、進路変更がしたくなった場合に備えて、こちらでは司法書士の再就職方法についてご紹介します。
司法書士の転職市場の現状や再就職のコツなどを解説していますので、是非確認してみてください。
独立開業に失敗した司法書士の再就職は難しい
一度独立開業して失敗した司法書士は自分の意志が強い傾向にあり、協調性に不安を感じる事務所が多いようです。
そのため人脈がない限り一度独立開業した司法書士が他の事務所で採用されるケースはほとんどないようです。
しかし、独立開業に失敗した経験や反省点を活かし、謙虚に就職活動に取り組めばもう一度司法書士として働くことも不可能ではないでしょう。
再就職のコツ①司法書士に拘らない
上述では再就職することは難しいとお伝えしましたが、司法書士の業種に拘らなければ再就職することは十分に可能です。
司法書士の業種に拘ると転職の選択肢を大きく減らす原因になります。
司法書士としての業務経験を評価する企業もありますので、幅広い転職先を検討できる柔軟な思考を持つことが再就職する際の大切なポイントになります。
再就職のコツ②経験を活かして別業界へ転職する
司法書士が転職する際は、司法書士としての実務経験を活かせる業種に転職するのが一般的でしょう。
例えば一般企業の法務部などは法律の知識が活かせるため、司法書士や行政書士資格の保有者は優遇されるケースが多いようです。
また、不動産業界も民法に関する法律知識を活かせる業種のため司法書士の転職先としてオススメです。司法書士試験で不動産業務に関する法律の内容を学習するので、不動産の事務作業では即戦力として活躍できるでしょう。
転職する際の注意点
司法書士から別業界へ転職する際の注意点として、自分の市場価値を高く設定しすぎないことです。
司法書士は他の行政書士や宅建士よりも企業からのニーズが低いため、司法書士の資格を全面的にアピールしても採用されないことがあります。
司法書士の資格だけに頼らず他の資格も取得したり、自分に出来ることや経験ベースの話をしてアピールするようにしましょう。
司法書士の廃業は多い?まとめ
司法書士の廃業は多い?まとめ・司法書士は独立開業しやすい資格
・廃業率は3%前後と低い
・廃業率は減少傾向にある
・廃業しないためには準備が大切
・実務経験を活かすと再就職しやすい
司法書士は少ない資金で開業できますので独立開業しやすく、営業力次第では高収入を目指すことができます。
また、司法書士の廃業率は3%前後とかなり低く廃業率は年々減少傾向にあります。
そんな司法書士が廃業してしまう原因は資金不足や営業不足によることが多いため、廃業にならないためにもしっかりと事前準備をしておきましょう。
また、司法書士が再就職する際は、実務経験を活かせる業種だと転職しやすくなるでしょう。