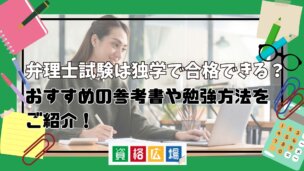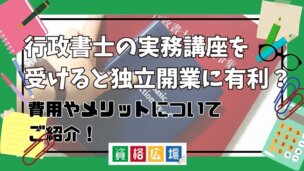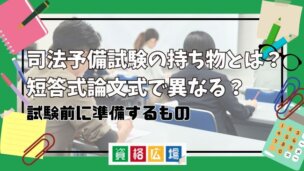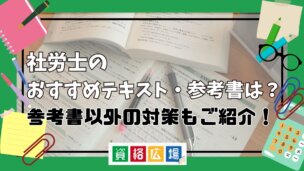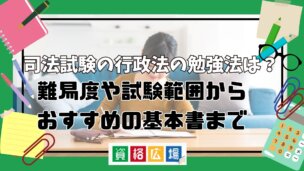「行政書士の資格に興味があるけど、難しそうだな」
「年齢制限や学歴は必要なのだろうか」
行政書士を目指そうと考えた時、そんな風に思ったことはありませんか。
この記事では、行政書士になるにはどのような方法があるのか、平均年齢、資格取得の際に必要な条件などを詳しく解説しています。
また、独立したい方向けに独立開業の適齢についても紹介するので、ぜひご覧ください。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
行政書士の仕事内容とは?
行政書士とは、書類作成などを通して民間と行政の橋渡しをする職業で、業務内容は多岐に渡りますが代表的なものは以下の2種類です。
1. 依頼主の代理として、官公署への書類を作成・提出する
2.法律に関する相談業務(離婚調停や遺言書の作成など)
行政書士の需要は昔から高く、最近では法律の知識を活かして企業へのコンサルティング業務を行う方も多いです。
では行政書士になるにはどうしたら良いのでしょうか?
下記では行政書士になる方法を紹介します。
行政書士になるには?
行政書士になるためには、以下の3つのうち1つを満たさなければいけません。
1.行政書士試験を受験し、合格する
2.弁護士、弁理士、公認会計士、税理士のいずれかの資格を持っている
3.公務員として一定年数働き「特認制度」を利用して行政書士になる
以下ではそれぞれについて詳しく解説していきます。
1.行政書士試験を受験し、合格する
行政書士になるうえで最もメジャーな方法が行政書士試験を受験することです。
以下は、行政書士試験の概要です。
行政書士試験の概要
| 実施日 | 毎年1回、11月第2週の日曜日 |
|---|---|
| 試験内容 | 行政書士の業務について(マークシート式) |
| 受験料 | 1回7,000円 |
| 会場 | 47都道府県それぞれの会場で受験が行われる |
| 受験資格 | 受験制限なし |
行政書士試験では、「行政書士の業務に関し必要な法令等」と「行政書士の業務に関連する一般知識等」に関する問題が出題されます。
国家資格の中でも難関と言われており、令和3年度の行政書士試験の合格率は10.7%でした。
狭き門ですが、傾向の把握と対策をしっかり行えば独学でも十分に合格の可能性があります。
1人では勉強に身が入るか不安な方、法律の幅広い知識を勉強したい方などは、大学の法学部や専門学校、試験対策の予備校などを活用してもよいでしょう。
2.弁護士、弁理士、公認会計士、税理士のいずれかの資格を持っている
弁護士、弁理士、公認会計士、税理士のいずれかの資格を持っている方は、手続きをすれば自動的に行政書士として活動することができます。
いずれも試験の難易度は行政書士より高く、1番易しいとされる税理士でも数年の腰を据えた勉強が必要です。
法律の世界で幅広く活動したい方にはおすすめですが、行政書士を本業としたい方には大変かつ現実味のない方法と言えます。
3.公務員として一定年数働き「特認制度」を利用して行政書士になる
公務員の特認制度とは、以下の条件を満たした公務員であれば行政書士試験を突破しなくても行政書士として活動できる制度のことです。
①国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員であること
②公務員として17年間(中卒の場合は20年間)勤務すること
役所で働く公務員の仕事は行政書士の業務内容と似ているため、経験があれば行政書士としても活躍できます。
ただし公務員と行政書士の仕事を掛け持ちすることはできません。
そのため公務員を定年退職した後に行政書士として開業し、社会で活躍し続ける方も多いです。
ただ、特認制度を利用できるまで最低でも17年がかかるので、行政書士として若い頃から働きたいと考えている方には不向きな方法になります。
行政書士に年齢制限はある?
まず気になるのは、行政書士になるための年齢制限についてです。
行政書士は国家資格のため、受験可能な年齢が制限されているイメージをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。
行政書士試験に年齢制限はない
結論からお伝えすると、行政書士に年齢制限がなく、行政書士試験は年齢に関係なくだれでも受験することができます。
したがって年齢によって受験を諦める必要はなく、何歳であっても挑戦できる国家資格と言えます。
実際に令和2年度の行政書士試験では、最年長で96歳、最年少で13歳が受験しており、最年長で76歳、最年少で15歳が合格しています。
未成年者は行政書士として働けない
行政書士法においては、未成年のみ受験資格はあるものの、行政書士としての登録が不可となっています。
未成年時に行政書士試験を受験し合格した場合は、成人した後に行政書士として登録することが可能なので実際に行政書士として働くことができるのは20歳以上からとなります。
行政書士に学歴は必要?
年齢制限はないことが分かりましたが、国家試験受験の際に大きな弊害となる要因のひとつに、学歴が挙げられます。
代表的な国家資格として知られる弁護士は、司法試験受験の際に法科大学院進学が必要とされています。一部、予備試験ルートでは学歴を必要としない場合がありますが、基本的に大学卒業の学歴が必須です。
行政書士に学歴は必要ない
一方行政書士は学歴に関係なく行政書士試験を受験することができ、日本国籍である必要もありません。未成年であっても受験自体は可能なので、受験したいタイミングで行政書士を目指すことができます。
このように学歴についても、特に定められた受験資格がない点は行政書士の大きな特徴です。
実際に高卒で受験している方もいる
大学卒業の資格が必須ではない行政書士は、高校卒業の学歴で資格取得をしている方も少なくありません。
行政書士試験は合格率が毎年10~15%と簡単な試験とは言えないものの、どのような学歴であっても努力次第で資格取得が可能となる資格です。
他の国家資格受験を検討する際、学歴が弊害となる場合には、行政書士試験の受験を検討してみるのも良いかもしれません。
行政書士の平均年齢
ここまでご紹介したように、行政書士の資格は非常に多くの方に門戸が開いた国家資格と言えます。
では、実際にはどのような年齢層の方が働かれているのでしょうか。
行政書士の平均年齢は58.6歳で、一定の要件を満たした公務員なら退職後に行政書士資格が与えられる制度もあるため、還暦を迎えてから開業する方も多いです。
行政書士は高齢化が進んでいる
国内の行政書士約5万人以上が登録する、日本行政書士連合会が2018年に発行した「月刊日本行政 10月号」によると、61歳~70歳をボリュームゾーンとし、60歳以上が回答数の約半数を占めていました。
調査の回収率は9.2%のため、全体感の把握とは言い難いものの、行政書士の高齢化が進んでいるのは明白であると言えます。
平均年齢が高い要因
行政書士の平均年齢が高い要因として、有効求人が少ないことや、行政書士の業務に従事する方は個人事務所を開業している場合が多く、どこかの事務所で働きたいと思っていても、働き先が少ないからです。
また、業務はデスクワークが中心ですし、近年はAI技術の拡大も進んでいるので高齢の方でもパソコンが使えれば無理なく仕事をすることができます。
一定の社会経験を積んだ方が個人事務所を開業し、行政書士としての業務に従事するケースが多くなっています。したがって、若い方の参入が少ない負の側面があるため、平均年齢が高くなっていると考えることができます。
将来性についても言及されている
AI技術の拡大により、現在行政書士が担当している業務はオンラインで自動化されていくという予想があります。
現在は紙の書類で手続きされている内容も、いずれはオンライン化することで、行政書士の存在が不要になると考える方は少なくありません。
人生100年時代と言われる現代社会において、AIに代替されてしまうという可能性も、若い方が少ない理由のひとつと言えるでしょう。
行政書士試験の受験者・合格者の年齢層
では、行政書士試験はだれでも受けられる試験ですが、実際に受験し合格する方はどのような方が多いのでしょうか。
行政書士試験の受験者や、合格者の年齢についてご紹介します。
受験者の年齢分布は下記の通りです。
受験者の年齢分布
| 年齢 | 受験者数 |
|---|---|
| 〜10代 | 573人 |
| 20代 | 7,599人 |
| 30代 | 9,491人 |
| 40代 | 11,954人 |
| 50代 | 11,311人 |
| 60代 | 6,063人 |
出典:一般財団法人行政書士試験センター「最近3年間における行政書士試験の受験者・合格者の属性」
一般財団法人行政書士試験センターが発行する、令和5年度試験結果分析内の「受験者・合格者の属性」によると、40歳代が11,954名と最も多くなっています。次いで50歳代が11,311名、30歳代が9,491名と、行政書士試験のボリュームゾーンであることが分かります。
いずれの年齢層も毎年大きな変化はなく、ほぼ同様の数字で推移していることが分かります。
20歳代の受験者の伸びが顕著
60歳代以上の受験者も毎年5,000〜6,000人台と大きな変化がない一方で、20歳代の受験者の伸びが顕著となっています。
この一因として、新型コロナウイルス感染症の影響があるとされていて、新型コロナウイルス感染症により所属企業の経営が安定的ではなくなった方は少なくありません。今後も起こり得るパンデミックに備え、安定志向の若い方が増えている傾向があります。
しかし行政書士は国家資格のため、保有することによる職業選択の自由が増えるので、資格を保有しておこうと考える方も増えているようです。
合格者の年齢の特徴
では、実際に行政書士試験を受験し、合格している方はどのような年齢なのでしょうか。
合格率に毎年大きな変化はなく、全世代平均10%前後を推移しているとされていて、受験者数が多い40歳代は14.5%、50歳代は11.4%となっており、ほぼ全世代平均と相違が無いと言えます。
一方60歳代の合格率は8.4%、10歳代は8.2%と、全世代平均よりも大きく下回る傾向があります。
30歳代の合格率が高い
年齢が高くなるほど合格率が低下する一方、年齢が若くなるほど合格率が高くなるという傾向があります。
令和5年度の30歳代の合格率は17.8%と、世代別の平均合格率の中では20歳代を抑えトップです。
SNSやYoutubeを使い勉強している
若年層の合格率の伸びが顕著な要因として、SNSやYouTubeなどで手軽に資格取得勉強ができるようになったことが挙げられます。最新のツールを上手く活用しながら勉強できるという点で、今後若年層が合格率をけん引していく可能性があります。
独学での合格難易度が高いとされていた行政書士資格は、予備校や通信講座を活用し、一定の金額を掛けて受験対策をすることが一般的でしたが、YouTubeなどで気軽に受験対策情報を集めることができるようになり、費用を掛けずに勉強し、資格取得を実現することが可能となっています。
開業する行政書士の年齢層
では無事に行政書士試験に合格したのち、どのような理由で独立や開業に至るのでしょうか。
独立開業の適齢は特にありませんが、ある程度の経験を積んだり、顧客を抱えてから独立する方が多いです。
下記では開業をする理由と共に、独立する行政書士の年齢層をご紹介します。
そもそも行政書士としての求人は少ない
上述でお伝えしたようにそもそも行政書士の求人が少ないです。
行政書士事務所を設立する場合、事務所としての拡大を狙うのではなく、あくまでも自身が食つなぐことができれば問題ない範囲で独立する方が多くなっています。したがって、求人を出すほどの余力がない場合がほとんどです。
行政書士の資格取得後は企業の法務部などで勤める方が多いです。企業で安定的に働きながら、独立を見据える場合は行政書士事務所の求人を定期的にチェックし、タイミングを見て転職の上、実務を通して経験を積んでいきます。
最も多いのは50歳代以上での開業
行政書士として独立するのは、50歳代以上が多くなっています。
行政書士には定年がないため、所属していた企業や事務所を早期退職しながら、それまでの社会経験で培ってきた人脈を活かし、業務にあたる方も少なくありません。
独立することによって、自分の好きなペースで働くことができるので定年後のライフワークとして、自身の事務所でゆっくり働くことを検討できるのも、国家資格ゆえの強みと言えます。
若くして独立という選択
社会経験を積み、老後を見据えて事務所を開業するという選択肢の一方で、若くして独立するという選択肢もあります。
行政書士の業界は平均年齢が高く、年齢が若い行政書士の割合が少なくなっているため、年齢が若いという事実が差別化に繋がり、お客様と継続的な関係性を構築できる可能性があります。
社会経験が少ないと感じる方がいらっしゃるかもしれませんが、20歳代のうちに行政書士事務所や企業法務で経験を積むことは可能ですし、20歳代でもネットで集客できれば十分に独立が可能です。
事務所開業後の差別化戦略として、ご自身の年齢が強みとなるうちの独立を検討してみても良いかもしれません。
年齢制限がない行政書士試験に合格するならアガルートがおすすめ
上述の通り、行政書士は受験に年齢制限などはなく、誰でも受験できる試験です。
また行政書士は年齢層が高い資格でもあり、一般的に社会を10~20年経験している30歳台・40歳台の方でも、行政書士の世界ではまだまだ若手という業界です。
行政書士としてキャリアアップをしたり、セカンドキャリアとして新しい仕事に従事したりなど、行政書士はかなり柔軟な働き方ができる仕事でもあります。
そんな魅力的な行政書士になるためにも、まずは合格率10%前後の行政書士試験に合格する必要があります。
行政書士試験はいくつかの通信講座や予備校が開設していますが、資格広場が最もオススメできる行政書士講座は「アガルートアカデミーの通信講座」です。
アガルート行政書士講座のオススメポイント
- 30歳代40歳代以降の合格者を多数輩出!
- 働きながらでも勉強出来るテキスト&講義動画のカリキュラム
- 全額返金制度がある手厚い合格特典
令和6年度は合格者数300名を輩出

2024年度の行政書士試験では合格者数300名と、アガルート受講生の合格率は全国平均の3.63倍の46.82%でした。
また過去4年間(令和2年~5年)の累計合格者数は889名となっているなど、確かな合格実績があります。
アガルートは安い費用で受講できるため内容に不安を感じる方もいますが、合格率や合格者数を公表している点から信頼できる講座となります。
中には働きながら合格した人もいるので、ぜひ合格者の声チェックしてみてください。
働きながらでも勉強出来るテキスト&講義動画のカリキュラム
アガルートの行政書士講座は社会人の方でも働きながら勉強ができるカリキュラムが組まれています。
アガルートはテキストと講義動画を並行して勉強していくスタイルで、講義動画はダウンロードして通勤時にも視聴することが可能です。
また8段階の倍速モードや講座の進捗率がわかる機能など、時間の無い社会人受験生にとって嬉しい工夫が講座に施されています。
行政書士講座のカリキュラムは「入門総合カリキュラム」「中上級総合カリキュラム」「上級総合カリキュラム」の3つに分かれており、自分の学習状況に合わせて講座を進められるので、実力に合わせて最短距離で行政書士合格を目指せます。
「合格したら受講料全額返金!」 嬉しい合格特典

アガルートでは行政書士試験に合格したら、受講料を「受講料全額返金」もしくは「お祝い金Amazonギフトコード5万円分」の合格特典があります。
合格したら実質アガルートの講座を無料で受講できるので、お財布にもかなり優しい通信講座です。
合格特典があることで勉強に本腰を入れて集中することができ、「行政書士試験に合格する」という目標を成し遂げるために最後まで努力を続けられます。
アガルートは合格すると全額返金という謎の制度があります。
ガチで返金されますよ。笑
— タジー(田島圭祐) (@tajimakeisuke) November 9, 2020
今のところ、コスパや全額返金等の取組みを見るとアガルートが優勢かなぁ。。
— 亀太郎 (@moriken315) September 19, 2021
行政書士講座、何となく下記で決めました。
・伊藤塾:平林さん〇バインダー式テキスト✕
・LEC:野畑さん、横溝さん〇割引△
・リーダーズ:山田さん〇講座の値段✕。別途本の購入要✕
・アガルート:割引〇。豊村さん〇合格すると全額返金◎— Lifetime Trip (by Musubi-goen) (@MusubiGoen) November 27, 2021
行政書士の仕事内容や年齢層まとめ
本記事のまとめ・書類作成などを通して民間と行政の橋渡しをする職業
・行政書士試験には年齢、国籍、学歴などは一切必要ない
・行政書士として活躍している方は50~60歳代が多い
・ネットなどを駆使して顧客を獲得できれば20代でも十分に独立開業できる
行政書士は、他の国家資格と比較しても平均年齢が高い資格と言えます。ご自身が受験したい、勉強したいと思ったタイミングに受験資格が存在するだけでなく、何歳になっても挑戦できるという点が強みの資格です。
平均年齢が高いからといって、ご自身の年齢を気にする必要はありません。平均年齢より若い場合には、年齢自体が強みとなって行政書士として活躍できる可能性があります。平均年齢に近い場合には、老後の仕事として検討してみるのも良いでしょう。
このように行政書士は働き方が多様な選択肢から選べること、自分の実力次第でいくらでも年収をあげられることが魅力的です。
自身が行政書士を目指したいと感じた年齢を「適齢」として、ぜひ社会生活における民間と行政のパイプである行政書士を目指してみてはいかがでしょうか。


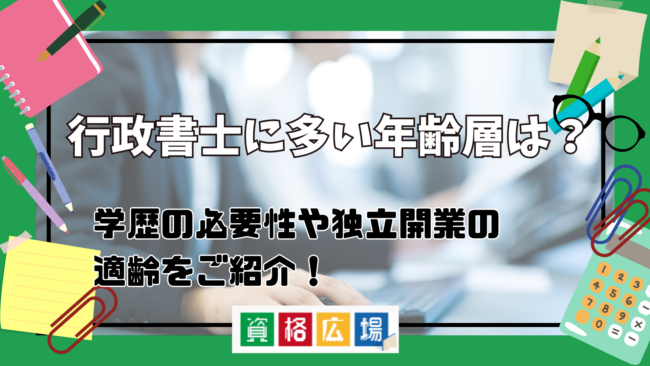

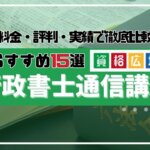

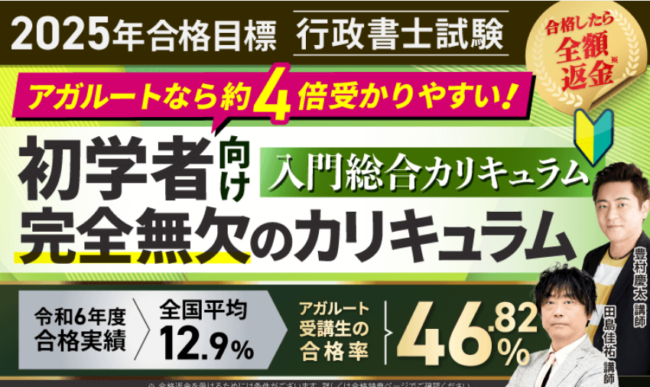 引用:
引用: