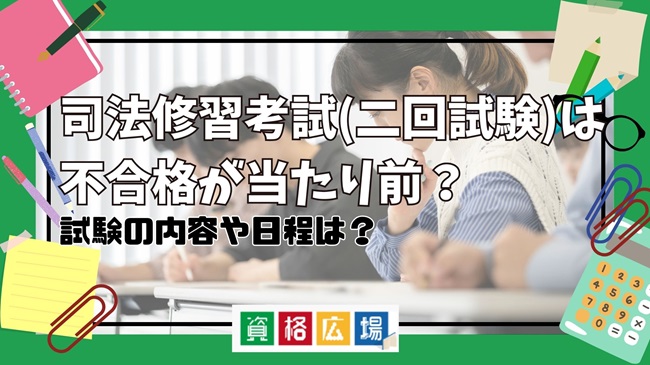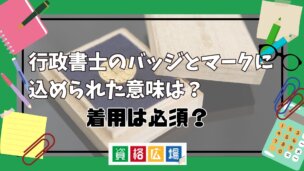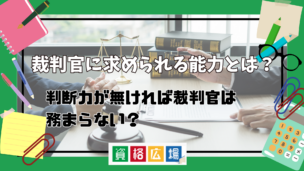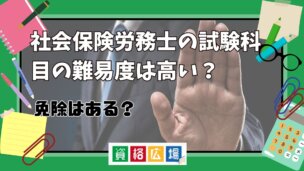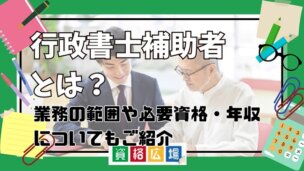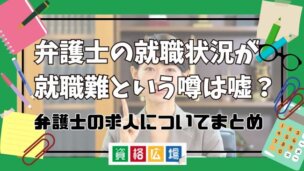法曹を目指し司法試験に合格すると、「司法修習生の修習」である司法修習を1年間受けることになります。
この司法修習の最後に待っているのが司法修習生考試、通称「二回試験」でありこの二回試験に合格することで弁護士や検事・裁判官になることができます。
この記事では司法修習生考試とは何か・試験内容や不合格にならないためのコツを紹介します!
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
司法試験予備試験合格におすすめの通信講座
司法修習生考試(二回試験)とは
司法修習生考試とは、1年間法律実務を学んだ司法修習生に対して行われる最後の試験です。
「司法修習生考試」が正式名称ですが司法試験に続いて2回目に行われる試験であるため「二回試験」とも呼ばれます。
司法修習生考試は法科大学院で学んだ法論理教育及び実務の基礎的素養を前提として出題されるためそのレベルは非常に高く、入念な対策が必要となります。
司法修習生考試(二回試験)の出題内容
司法修習生考試は「民事裁判」「刑事裁判」「検察」「民事弁護」「刑事弁護」の5科目から出題されます。
各科目100ページ程の事件記録を読み込み、事実認定、書面の作成といった起案やそれに関する設問を行います。
起案作業は司法修習中にもたびたび行うことになり、それがもとにテキスト作成が行われたり討論に使用されたりもします。
民事裁判科目
民事裁判科目では民事事件の事件記録を元にして民事判決の起案をします。
2つの記録のうち1つについては用件事実に関する起案を行い、もう1つの事件記録について事実認定に関する起案を行います。
刑事裁判科目
刑事裁判科目では与えられた刑事事件の事件記録を元に刑事判決を起案します。
事実認定のほか量刑判断についても起案する場合があり、刑事訴訟手続に関する小問が出題されることもあります。
検察科目
検察科目は、捜査記録を元にして終局処分を起案します。
この検察科目でも、刑事訴訟手続に関する小問が出題されることがあります。
民事弁護科目
民事弁護科目では民事事件の事件記録を元に最終準備書面を起案します。
民事執行・保全手続の小問が出題されることもあります。
刑事弁護科目
刑事弁護科目では刑事事件の事件記録を元に、弁論要旨を起案します。
司法修習生考試(二回試験)の日程
司法修習生考試は上記の5科目を1日1科目、計5日間に渡って行われます。
例年11月下旬に行われ1日の試験時間は10:20〜17:50、休憩時間も含めた7時間30分、5日間で合計37時間30分という長時間開催されるため高い集中力と体力が求められます。
起案の分量はA4・26行の罫紙に1行おきの手書きで記入し、枚数制限はありません。
成績は優・良・可・不可の4段階で判定され、一つでも不可判定があると不合格となります。
司法修習生考試(二回試験)までの道のり
司法修習生考試は司法修習の最後の研修ですが、二回試験に合格するためにはそれまでの研修をしっかりと行いつつ、試験の対策を立てていくことが非常に重要です。
司法修習は二回試験を含めた5段階に分けて研修が組まれています。
・修習生登録 9月
・導入修習 12月
・分野別実務修習 1月〜7月
・選択別実務修習 8月〜9月 or 10月〜11月
・集合修習 8月〜9月 or 10月〜11月
・司法修習生考試 11月
・合格発表 12月
修習生登録
司法試験の合格発表は例年9月にあり、見事合格を果たすと合格発表日〜約1週間の間に司法修習生の申し込みをします。
分野別実務修習は全国の地方裁判所所在地で行われるため、希望の勤務地の指定ができるほか「白表紙」という司法修習の教材と課題が配られるため12月の司法修習開始までに取り組む必要があります。
導入修習
導入修習は埼玉県和光市にある司法修習所で1ヶ月間、起案の初歩的な考え方や事前課題の解説といった講義、グループワークを行います。
修習のガイダンス的な役割ですが導入修習期間中は勉強時間の確保が難しいため、事前準備が大切です。
開始1週間目から「即日起案」が実施されます。
分野別実務修習
司法修習の大部分がこの分野別実務修習です。
全国の修習地で行われ、「民事裁判」「刑事裁判」「弁護」「検察」といった配属庁に4クールに分かれて2ヶ月ずつの研修を受けます。
実際の事件に取り組むこともあります。
選択型実務修習
選択型実務修習ではいくつかの収集プログラムのうち、興味のあるものを選んで修習します。
A班とB班に分かれ、各配属庁や全国様々な場所行われるプログラム、会社の法務部などの研修先を自分で見つけて参加します。
各プログラムは1週間〜2週間程度のものがほとんどであるため、多くの修習生はいくつかのプログラムを選択します。
集合修習
集合修習では民事裁判・刑事裁判・検察・民事弁護・刑事弁護の5科目を徹底的に講義します。
内容は起案と模擬裁判であり、起案は丸一日かけて行われる、非常にハードな期間です。
集合修習期間で、司法修習生考試に向けて学力をしっかりつけることになります。
各修習で起案の予行練習ができる
司法修習の各研修では起案の予行練習を行うことができ、導入修習で1回、実務修習で1回、集合修習で2回の機会が設けられています。
特に集合修習は5科目について起案と裁判をみっちり行い、起案は丸一日かけて行われます。
これら起案の機会を有効に使うことで司法修習生考試のための対策を取りましょう。
司法修習生考試(二回試験)は不合格になる?
司法修習生考試はほとんどの人が合格する試験です。
そのため試験結果は不合格者を公表する形で行われ、そこに掲載されていなければ合格ということになります。
ここ最近の不合格率はこのようになっています。
| 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 司法修習生採用者数 | 1,393 | 1,328 | 1,456 | 1473 | 1482 |
| 不合格者数 | ‐ | ‐ | 5 | 10 | 8 |
| 不合格率 | ‐ | ‐ | 0.34% | 0.7% | 0.5% |
出典:法務省 司法修習生採用者数・考試(二回試験)不合格者数
このように司法修習生考試に不合格となる人は全体の1%ほどであり、ほとんどの人が合格します。
司法修習はハードな期間であり、試験もボリュームが多く内容も決して簡単ではありませんが、普通に勉強をしていけば基本的に落ちることはないでしょう。
司法修習生考試(二回試験)に落ちてしまったら
もしも司法修習生考試に落ちてしまうと、翌年の試験をもう一度受けなくてはなりません。
また、司法修習生は司法修習生考試の前に検事・裁判官・弁護士のいずれかになることを決め、就職先からの内定を得ます。
内定先が決まっている状態で司法修習生考試を受けることになりますが、試験に落ちてしまうと内定取り消しとなることが多々あります。
特に五大法律事務所はどんな理由であっても司法修習生考試不合格者は内定が取り消されるといわれています。
想定していたキャリアが崩れてしまい、同期が先に活躍していくプレッシャーもあるため誰もが一回での合格を目指します。
司法修習生考試(二回試験)を突破するために
司法修習生考試は基本的落ちることのない試験ですが、それでも毎年10人前後の人は落ちてしまい、来年に再び試験を受けることになります。
司法修習生考試に合格するためにはいくつかのポイントがあり、これらを守れないとそれだけで不合格判定を受けるというものもあります。
以下のポイントには気をつけ、受かっていたはずの司法修習生考試が不合格になった……なんていうことがないようにしましょう
禁止事項を書かない
各科目では禁止事項とされるものがあり、これらを書いてしまうと一発で不合格となります。
◆民事弁護で・・・原告と被告を取り違える
◆刑事弁護で・・・無罪判決を書く
◆検察で・・・不起訴処分とする
◆刑事弁護で・・・被告人が無罪を主張しているのに有罪弁護を行う
◆民事裁判で・・・事実を4類型のどれに当たるか明示し、それに応じた論じ方をしなくてはいけないが、しない
ついつい間違えがちな内容ですが、正確性を求められるためこれらの内容を書くだけでアウトになります。しっかりと理解及び確認する時間が取れるように注意しましょう。
起案を紐で閉じる
司法修習生考試は答案用紙が散らばらないように綴り紐でしっかり結ぶ必要があります。
司法修習生考試終了時に起案が紐で閉じられていないと、それだけで不合格になってしまいます。
これは非常に有名なルールであり、多くの人が心から気をつけていることですが、それでも紐でしっかり綴られていないことで不合格になる修習生がゼロではありません。
時間に余裕を持って綴る、解けないようにしっかりと縛ることが大切です。
油断せずに取り組む
不合格者はほとんどいない司法修習生考試であっても、上記の理由などで落ちる可能性はあります。
司法修習生考試が司法修習最後の試練であり、これに合格できるかで法曹への道が拓かれるのか、1年延びるのか決まる為全ての司法修習生が全力で取り組みます。
起案の練習・復習を怠らないこと、試験では今までと同じように取り組むことを心がけ、普段通りのパフォーマンスを発揮できればまず合格できるでしょう。
とにかく普段せずに取り組むことが大切です。
司法修習のメリットと意外なデメリットについて
法曹になるにあたって必要になる司法修習ですが、司法修習生となることにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
また考試は絶対受けなければならないものなのか調査しました。
司法修習のメリットは?
こちらの記事でもご紹介しているように、もちろん司法修習にはいくつかのメリットが存在しています。
・自然と法曹コミュニティに参加できる
・実務的な学びを得ることが出来る
・給費(月額135,000円)をもらいながら勉強できる
修習生は未来の法曹であるため、経済的にもサポートを受けながら勉強を進めることが出来ます。
また法曹として働き始めた後にも自然を連絡を取り合える同期のような存在ができるため、精神的なメリットも大きいようです。
司法修習中に受けられる指導も非常に優れており、メリットとして挙げる方が多く見られました。
一方でこのようなデメリットも…
様々なメリットがある司法修習ですが、その一方で懐疑的な意見も見られました。
司法修習の意外なデメリットとして何が考えられるのでしょうか。
法律界に加わるのが遅れる
1年間で行われる司法修習では充実した学びが得られる一方で、実務に触れることが出来ない期間がもどかしいという方も多いようです。
司法修習では職業意識などを学習するという役割もあるのですが、野心家の方が早くデビューしたい気持ちも分かります。
また給費をもらうという立場として準公務員となるため、そういった社会的な重責や規則を重荷に感じることもあるようです。
欲を捨てきってとにかく勉強の期間となるため、最近では司法修習に参加しない方も増えつつあります。
経済的に苦しい
司法修習生として給費をもらえるわけですが、基本の生活費はそこから支払うことになる上に様々な費用もそこから捻出しなければなりません。
学習に必要な参考書代や移動用の宿泊費などを計上すると日々の生活は以外に苦しいものとなることが多く、貯蓄がなければきつい生活となることが予想できます。
準公務員の規則として一切の副業が禁止されるため、経済的な苦しさを自分で解決することもできません。
以前は給費自体もなかったためこれでも良くなりましたが、依然苦しい状況が続いています。
最近では司法修習を受けない方が増加中
こうした現状を受け、最近では言語氏資格認定制度を用いて司法修習に参加せずに法曹を目指す方が増えています。
下記の記事で詳しくご紹介しておりますが、一定期間以上の実務を民間企業や法律事務所で積むことで弁護士資格などを取得することができるのです。
司法修習生として考試から1年間勉強するよりもスピーディーに法曹になれるため、こちらのルートが市民権を得ていくかもしれません。
特に経済的に不安を感じている方は、司法修習ではなく制度利用をおすすめいたします!
これから司法試験を目指すなら

現在紹介している司法修習生考試は司法試験合格後の最終関門ですが、この記事を読んでいる方の中には司法試験合格を目指してこれから学習を始める方もいるかと思います。
司法試験合格にオススメなのは法科大学院より予備試験を利用したコースですが、予備試験学習にオススメなのは通信講座の「アガルートアカデミー」。
圧倒的な合格者数

初学者でも安定して法学を学ぶことが出来るアガルートの通信講座は、圧倒的な数の合格者を輩出しています。
令和5年度試験では全合格者1,781人中で36%にあたる641人がアガルートの受講生なのです。
これには司法試験合格の一流講師が直接監修した講座や教材の分かりやすさが寄与しており、受講生の満足度も非常に高いものとなっています。
講座に関する詳しい情報はこちらの記事でご紹介しているため、ぜひご覧ください!
合格までの最短ルートで進められる
アガルートのカリキュラムでは、一流講師が考案した合格までのロードマップが細かく提示されています。
また集中力が持続しやすい30分程度のコンパクトな講義をスマホやPCから場所・時間を選ばずに受講できるため、独学などとは一線を画す成果が期待できるのです。
フルカラーの教材は見やすいだけでなく、法律を図示して分かりやすく体系的に理解することができます。
回数制限なしでいつでも質問できる制度が完備されているため、学習する上でのモチベーションも高いまま進めることが可能です!!
気になった方は受講相談!
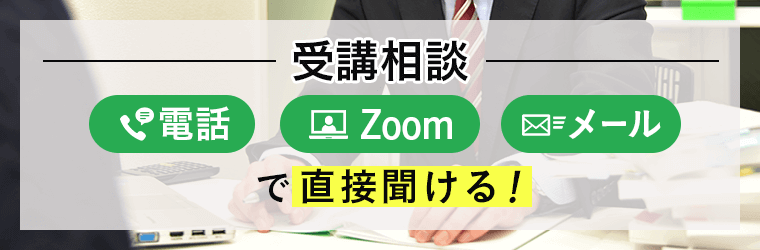
非常に魅力的なポイントが多いアガルートの通信講座ですが、いきなり受講を申し込むのは勇気のあることです。
誰しもが感じる学習上の不安を解決するために、アガルートでは無料の受講相談を受けることが出来ます!
試験に精通したアガルートのスタッフに「どうやって学習を続けていいかわからない」といった不安を伝えてみることで、受験への解像度がグッと上がるはずです!
少しでも気になった方は、ぜひこちらからアガルートの公式サイトをご確認ください!
司法修習生考試は不合格が当たり前?まとめ
司法修習生考試とは何か、試験の詳細や不合格にならないためのポイントなどを紹介しました。
予備試験・法科大学院から始まり司法試験・司法修習生を経て法曹になるための最後の関門が司法修習生考試です。
不合格率の低い試験であっても油断せず、今までの集大成として取り組むことが大切でしょう。
この記事を読んだ方は、以下の記事もチェックしてみてください!