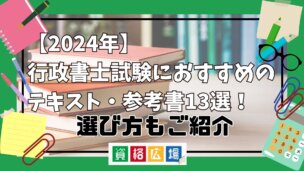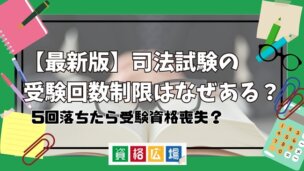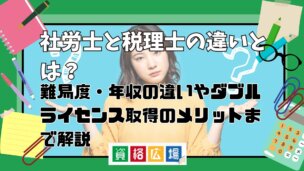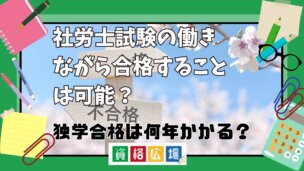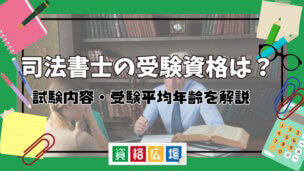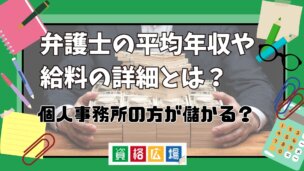毎年多くの方が合格を目指して勉強している司法試験は、国内でも最難関の難易度を誇る国家試験です。
中でも難所とされている論文式試験では選択式の科目が導入されており、受験戦略の中で何を選択すればいいか迷っている方も多くいらっしゃいます。
そこで今回は、司法試験における選択科目の詳細や選んだ科目によって生じる有利・不利について調査しました。
法曹を目指して勉強されている方にとっては必見の内容となっていますので、ぜひご覧ください!
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
司法試験予備試験合格におすすめの通信講座
司法試験の選択科目について
まずは司法試験における選択科目の概要についてご紹介します。
試験の仕組みなども振り返りたい方はぜひお読みください!
選択科目は論文式試験で課される
司法試験はおおまかに2つのステップに別れており、選択式の問いに答える短答式試験と法的な知識に則って応用的な知識が問われる論文式試験によって合否が決まります。
どちらもかなりの難易度を誇っており、ただ知識をインプットするだけでなくアウトプットする力を身につけていないと合格することは難しい試験です。
その中でも選択科目が課されているのが論文式試験で、これからご紹介するような科目から回答を書くことになります。
選べる出題科目の種類
論文式試験の選択科目として選択できるのは、8つの法律です。
- 労働法
- 経済法
- 倒産法
- 知的財産法
- 租税法
- 国際関係法(公法系)
- 国際関係法(私法系)
- 環境法
選択科目は他の科目と比べても解答時間が長く設定されており、ここの点数が取れるかどうかで合格率は大きく変わると言っても過言ではないでしょう。
選択科目の存在を知ると皆さんが疑問に感じるのが、「受ける科目によって有利や不利が発生するのでは…」という点です。
ここからは、実際に科目選びによって試験の結果を左右されるようなことは起こり得るのかどうかをご紹介します。
司法試験の選択科目で有利になる科目はある?
結論から言えば、下記のような点を重要視して科目選びをすることで試験勉強を優位に運ぶことが可能です。
【注目すべき点】
・教材が充実しているかどうか
・出題範囲と充てられる勉強量がマッチしているかどうか
・実務で使用するかどうか
今回の記事では、これらの観点からおすすめできる科目を3つほどご紹介します。
有利となり得る科目①:労働法
労働法は選択科目の中でも広めの範囲を対策しなければならないものの受験生の中でも選択者がかなり多いため教材等が充実していることから、かなり勉強しやすいという点でおすすめできます。
また必答科目である民法との親和性もあり、イメージしやすいという観点からも勉強は有利に進むのではないでしょうか。
加えて労働法は実務でも役立つ機会がとても多いことから、選択科目の中でもかなり実りの多い学習をすることが出来ます。
弁護士資格を取得すると試験なしで社労士としての登録も可能なため、活躍できる場が多いのは魅力的です。
有利となり得る科目②:倒産法
労働法に次いで毎年一定の方が選んでいるのが、破産法や民事再生法が主な学習範囲である倒産法です。
民法や民事訴訟法など民事系科目の知識を活かせるのが大きなポイントで、しっかりとした対策を行えれば十分な対策が可能な科目と言えます。
教材などもかなりの量が市場に流通しているため勉強しやすさも兼ね備えており、最近では倒産企業の増加によって需要も増加中です。
実務でもトップレベルに役立つ科目となっているため、有利な科目の1つとしてご紹介しました。
有利となり得る科目③:知的財産法
最後におすすめできる有利な選択科目が、著作物や商標といった無形の物の権利を取り扱う知的財産法です。
法律の改正されるスパンがかなり短いためこまめな対策が必要となるのが難点ですが、その分教材などが多いため勉強しやすいのではないでしょうか。
また知的財産法を扱える弁護士は企業法務での需要が急増しており、合格後は多少のアドバンテージがあると言えます。
最近では弁護士と知的財産のプロ資格である弁理士のダブルライセンスのメリットも高まっており、実務的なキャリア形成もスムーズに進むはずです。
選択科目の選び方やポイントは?
本題の選択科目の選び方について詳しく紹介していきます。
選択科目は8種類あり選び方がイマイチ分からない方や、自分はそれを選べばメリットが大きいのか気になる方は参考にしてみて下さい。
自分にとって選択科目の比重はどのくらいなのか
司法試験にはもちろん選択科目以外の科目も多数あり、どの科目にどのくらい時間を使うのか、どのくらい点数が欲しいのかの科目ごとの比重が大事になってきます。
受験者にとって選択科目で点数を稼ぐのか、もしくは他の教科で稼ぐため選択科目は最低限でいいのかによって選択科目の優先度は変化します。
自分にとって選択科目は稼ぐ教科なのか、及第点さえとれさえすればいいのか決める必要があります。
その選択科目の特徴は?
選択科目の特徴と自分の得意が一致していることも選択科目を選ぶ重要な要素となっています。
その科目が暗記することが多い暗記系の科目なのか、暗記よりも思考を試される論理系なのかなどの科目毎に特徴はあります。
自分の得意な分野や、それぞれの選択科目の特徴を吟味してから選ぶようにしましょう。
受験者数を注視する
司法試験の選択科目には受験者数の差が激しくなっているのが特徴となっています。
そこで、選択科目に特にこだわりが無い方は受験者数が多い科目を選ぶことをおすすめします。
受験者数科目が多いということは、その分参考書や対策本などが充実に揃っている可能性が高いからです。
以下が科目別の令和5年度の科目別の受験者数となっているので、参考にしてみて下さい。
| 科目名 | 人数 |
|---|---|
| 倒産法 | 569人 |
| 租税法 | 233人 |
| 経済法 | 787人 |
| 知的財産法 | 613人 |
| 労働法 | 1,127人 |
| 環境法 | 136人 |
| 国際関係法(公法系) | 54人 |
| 国際関係法(私法系) | 378人 |
上記を見てみると分かるように、人数のバラつき激しく多いところでは1,000人以上の科目、少ないところでは50人ほどとなっており、1,000人を越えるような科目は対策本などもしっかりして可能性が高いです。
それぞれの選択科目の合格率は次で詳しく紹介します。
選択科目別の合格率は?
選択科目毎の受験人数について先程は紹介しましたが、科目毎に合格率の差はでるのでしょうか?
以下の表は令和3年度の司法試験の選択科目別の合格率となっています。
| 科目名 | 人数 |
|---|---|
| 倒産法 | 292人(51.3%) |
| 租税法 | 80人(34.3%) |
| 経済法 | 371人(47.1%) |
| 知的財産法 | 277人(45.1%) |
| 労働法 | 538人(47.7%) |
| 環境法 | 41人(30.1%) |
| 国際関係法(公法系) | 18人(33.3%) |
| 国際関係法(私法系) | 164人(43.3%) |
上記の表を見てみると、選択科目の合格率に大きな差はないことが分かりますね。
どの科目を選んでも合格に左右するほど問題のレベルに差はないようになっていますね。
司法試験の選択科目で不利になる科目
受験勉強において有利になり得る科目があるというのは判明しましたが、一方で不利になってしまうような科目があるのでしょうか。
こちらでは様々な理由からおすすめできない2つの科目をご紹介します。
不利となり得る科目①:国際公法
論文式試験でもトップレベルに不利となり得るのが、選択科目の中でも最も回答者が少ない科目として知られている国際公法です。
例年では総受験者中でも1%~2%しか取っていない理由には、まず圧倒的な教材の少なさが考えられます。
また学習しても「どこで役に立つか分からない」や「他の科目の方が関連性が高い」といった声も多く、否定的な意見が多い印象です。
ただライバルが少ない分徹底的に学習すれば跳ねるはずですので、本気で合格したい方はあえてこの科目を受験するのも戦略としてあり得るかもしれません。
不利となり得る科目②:環境法
国際公法に次いで不人気とされているのが、環境を保全して維持するという環境法です。
学習範囲が狭いためコスパがいいと思われがちなものの、教材が少ないため学習に必要な時間が間延びしてしまう傾向から敬遠されています。
またSDGsなどが叫ばれているため注目されつつありますが、実社会で活躍できる場が少ないことからキャリア的にそこまでのメリットがないのです。
ここからは今まで登場したような選択科目の選び方に惑わされることなく、安定して合格をつかみ取るための手段をご紹介します!
結論:科目選びはかなり重要
これまでご紹介したように、司法試験における選択科目はかなりの重要性を持っているのです。
特に独学では自分に合わない科目を選んでしまったことで、「学習に時間がかかった」「合格後の活躍の幅が…」といった声も聞こえてきます。
独学などでは適切に選択科目を乗り越えることも難しいため、一度で合格を目指している方は下記の手段で突破を目指してみてはいかがでしょうか!
論文式試験で高得点を狙うなら通信講座
司法試験は日本で受けられる国家試験の中でも、司法試験はトップレベルに難しい難易度を誇っています。
合格するための戦略として公平性のある採点などが難しい独学などはあまり良い選択肢とは言えず、我々が最もおすすめしているのは通信講座を活用することです。
従来の資格予備校よりも安価な料金で受講できる上に、実績のある講師から質の高い受けられるなど魅力が非常に多くなっています。
司法試験合格を目指すならアガルート

様々な企業からリリースされている通信講座の中でも、資格広場が最もおすすめしているアガルートの司法試験対策講座をご紹介します。
他の講座と徹底比較した記事もあるため、少しでも気になる方はぜひこちらの記事もご覧ください!
全ての選択科目に対応したカリキュラム
この司法試験対策講座を担当しているのは、アガルートの代表かつ新司法試験を57位で合格した経歴を持つ工藤北斗講師です。
司法試験に合格しているだけではなく公務員試験にも合格しており、蓄積された圧倒的な学習ノウハウが全て落とし込まれたテキストは多くのファンを獲得しています。
カリキュラム内では論文式試験の全科目も十分に対策しており試験に精通した講師による添削・無制限の質問対応が受けられるため、試験勉強を有利に進められるはずです!
また他にも過去問解析等も万全に育てられるため、なんと司法試験の最終合格者の内およそ2人に1人がアガルートの講座を受講しています!
まずは無料の受講相談を
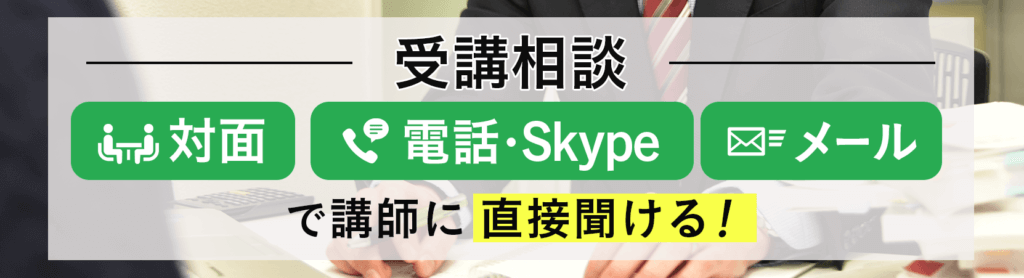
アガルートは受験者が試験や講座に対して感じる疑問や心配を取り除くために、いつでも無料の受講相談を開催しています。
手段は電話、Zoom、メールの三種類があり、資格の知識に長けたアガルートのスタッフから自分にフィットする学習方法や資格にまつわる情報を聞くことが可能です。
司法試験を受けることや通信講座を受講することを少しでも迷っている方は、ぜひこちらから参加してみることをおすすめします!
まとめ|司法試験の選択科目について
今回は司法試験の中でも特に難関とされている論文式試験の選択科目について、対象となっている科目や受験に有利となるような科目をご紹介しました。
選択科目を選ぶポイントは、自分が選択科目でどのくらいの点数が欲しいのかや、受験者数を多いもので選ぶことをおすすめします。
様々な視点から分析した結果、教材の充実度合いと実務で活かせるかどうかに重点をおいて考えるといくつかおすすめの科目があるようです。
ただもし論文式試験で本気の高得点を狙うのであれば、充実した講座や添削指導、質問がすぐに解消できる通信講座がおすすめとなっています。
資格広場は司法試験や勉強法に関する様々な記事を投稿しているため、気になった方はぜひ他の記事もご覧ください!